私は此の世に生まれたからには、何を遺して死んで行くのか…。
私の命は自分自身の持ちものでは無く、創造主のもの。私の人生は自分自身のものでは無く、創造主のもの。私の命・人生は創造主の為のもの。
「後世への最大遺物・デンマルク国の話」(著者:内村鑑三氏、出版社:岩波書店、出版日:1946/10/10、改版2011/9/16)
本書を読みました。
キリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者である著者・内村鑑三氏は、帰国後の宣教師達との対立、「不敬事件」を起こして世間・社会やキリスト教会から排除され、再婚相手との死別等があり、アルバイト的に流浪の教師、英訳、聖書講義等をして不安定な貧困生活を送る中で、日清戦争の有った明治27年(1894年、内村氏34歳時)に箱根で行なわれた第6回基督教青年会・夏季学校に於いての講演「後世への最大遺物」(刊行は3年後)。因みに前年には「基督信徒の慰」を刊行。
失敗の連続から得た内村鑑三氏の「思想」は、同様に失敗と後悔の連続であった私自身にとって共感するものであります。そして別著の「基督信徒の慰」と共に本書から、私自身が慰められ、励みとなり、希望を持ち、一個人として独立した私としての自信や誇りの維持に繋がる影響を与えられています。
キリスト者としては功名心を持つ事はあまり好ましいと思わないのは私自身も40代半ばとなった現在においては同感で、以前の若い頃に比べて欲望も少なくなり、その頃の自身の持っていた欲心が虚しく感じられます。
それ故に私自身も今日においては、俗世間・社会に対して厭世的に思い、此の世の様々な物事があまり価値が無く、無意味で虚しいものばかりの様に感じてしまいます。
しかしキリスト者にとっては此の世の世俗を軽く見て、次の天における生を重視する思想があり、その事が此の世において感じられる「絶望」からの救いとなる「希望」に繋がっています。
「絶望」とは自分自身が勝手に持った欲望・目標から来るもので、元々創造主である神がその人に求める望みとは別の方向にあった事から生まれるものであり、神に託し委ねる事で絶望とは無縁となり希望を持つ事が出来る訳です。
しかしこの世に生を受けた以上、何かを遺して行く必要があるのか。神の御心に適う様にする事が人の為の偽りでは無く神の為となって本当の意味での意味の有る人生となるのでしょうが、具体的にどうすれば良いのか。そしてさほど取り得も無く才能も無い場合に何が出来るのか。
まず内村氏は「お金」を取り上げます。遺族に遺産を残す、施設や貧困者に寄付をする等。
その次に「事業」を起こす事。社会、経済、自然環境、福祉等、起業して社会の発展に貢献する事。
しかしその「お金」や「事業」には、お金を貯めたり企業・組織を起こす事が出来る才能が必要になります。
そこで次に「思想」を取り上げます。独立した一個人の「思想」を基に、学問や哲学等の教育・啓蒙する教師やものを書く文学に繋がり、一つの小さな書物が社会改革・革命に繋がった事は歴史的事実を見ても解ります。地位・身分も低く名も無き小さな存在の人達によって書かれた聖書が、その後の世界において最大のベストセラーとなって多大な影響を与えている事からも解ります。しかし、「思想」も知識や学問がベースとなって生まれるものである為に、それらが必要となります。
「お金」より優る「事業」、それに優る「思想」、そしてその「思想」をも上回る最大遺物として一個人の「生涯」、それも「勇ましい高尚なる生涯」、「真面目なる生涯」であると言います。
職業に貴賤は無く、自分の仕事を真面目に真剣に取り組む事。正義を実行する事。義侠心を持って少数派や弱者の側に立つ事。そして、信仰によって此の世での不幸・反対・艱難・不足・情実・邪魔に打ち勝つと言う「大事業」を行なうと言う事。これらが「勇ましい高尚なる生涯」、「真面目なる生涯」と言う「後世への最大遺物」となると言います。これは元手が要らず、大した才能も必要とせず、誰にでも、私自身にも実行出来る事です。
お金や人、俗世間、社会等の外に求めるのでは無く、自分自身の内に求める事の必要性。それは、信仰の有する心に存在する聖霊に求める事からの、その「勇ましい高尚なる生涯」、「真面目なる生涯」に繋がるものと思います。
次に併著「デンマルク国の話」について。
1864年のオーストリアとプロイセンとの第2次シュレースヴィヒ戦争での敗戦によって元々が小さな国土しか持たない上に肥沃な領土を奪われたデンマークに於いて、ユグノー(フランスのプロテスタントであるカルヴァン派)の血を引く軍人エンリコ・ダルガス氏が、「外に失いしところのものを、内にありて償わん」とし、ヒース(荒地)で覆われた国土を開墾・植樹して、日本よりも人口も国土も小さなデンマークが豊かな富を抱える事となった事を、明治44年(1911年、同氏51歳時)の聖書研究会で「デンマルク国の話~信仰と樹木とをもって国を救いし話」と題し講演(刊行は2年後)。
敗戦国の経営の難しさの中、戦いに敗れても精神に於いて敗れない民が真に偉大な民であるとし、ダルガス氏の植林成功によってデンマーク市民の精神が一変し、国内も善く変革されたと述べています。
そしてそのデンマークからは、敗戦が必ずしも不幸では無いと言う事と、天然の無限的生産力によってもたらされる多大な富と、信仰の実力を学ぶ事が出来ると述べます。国の実力は軍隊では無く、金や銀でも無く、「辛種のごとき信仰」であると言います。
新約聖書・マタイの福音書17章20節「イエスは言われた。『あなたがたの信仰が薄いからです。まことに、あなたがたに告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、『ここからあそこへ移れ。』と言えば移るのです。どんなことでも、あなたがたにできないことはありません。」。
明治34年(1901年、同氏41歳時)、「無教会」を創刊。また足尾銅山鉱毒地を視察して、その後、幸徳秋水らと社会改良団体理想団を設立した内村氏。内村氏は生前にデンマークでキリスト教思想家・哲学者セーレン・オービエ・キェルケゴール氏(1813年~1855年)が当時のデンマークのキリスト教会が形式主義に陥っている事を批判していた事に共感し、「その単独者として絶対者の前に立つ人間観、教会的キリスト教に対する批判に共鳴、同じ無教会的キリスト教の『先導者』として紹介」(解説・鈴木範久氏)。
最後に内村氏は、「私が今日ここにお話しいたしましたデンマークとダルガスにかんする事柄は大いに軽佻浮薄のわが国今日の経世家を警しむべきであります。」。
 | 後世への最大遺物・デンマルク国の話 (岩波文庫)価格:¥ 583(税込)発売日:2011-09-17 |










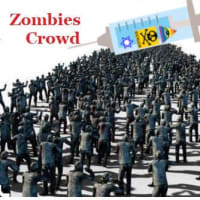
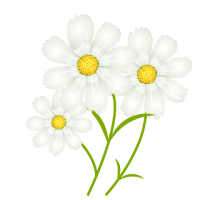
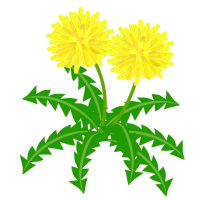
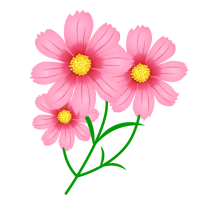
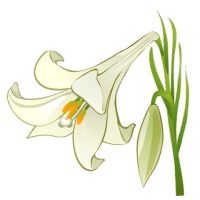
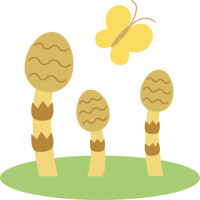
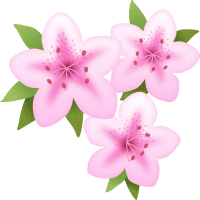

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます