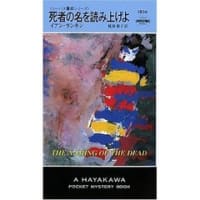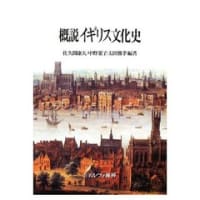このところ、どうもかったるい。
そうだ、こういうときこそミステリーだ。
あの本が溜まっている一画のどこかに、古本屋で買った古い早川ポケミスがあるはず。
ガサッ ドサッ
あった、あったぞ!
「幻の女」「妄執の影」
よし、有名な「幻の女」からいこう。
そんなわけで、購入してからはや一年が経過していたアイリッシュを読むこととなりました。
「幻の女 」は、アイリッシュの代表作としても、古典ミステリの名作としても有名で、私の持っているポケミスは昭和42年10月に発行、8版目のものです。
」は、アイリッシュの代表作としても、古典ミステリの名作としても有名で、私の持っているポケミスは昭和42年10月に発行、8版目のものです。
私の年齢と大差ない、古書の薫り高い一冊であります。
その頃の印刷は、わりあいいい加減で、時折、文字が半分消えていたり、吃驚するほど薄い印刷のページがあるかと思えば、急に濃くなったりして、明らかに今使われていないような難しい漢字のところでそういうことになると推測するしかない場合もあるわけで、読みにくいことこの上ないんですが、古い言い回しなども奥ゆかしく、それが古書を読む面白さであったりするんですね。
そのポケミス「幻の女」を読んでいると、何度読み直しても、
理解に苦しむところが出てくるんです。
これは、アイリッシュ独特の文章に原因があります。
アイリッシュは、普通の作家なら一行で済むような場面を長々とこと細かく描き、さらに比喩や暗喩を使って、直接的な表現方法をあくまで避けるという傾向があります。
ですから、現在では普段使われていないような言葉はこういう意味かなと思いながら読むにしても、意味がよく分からない言い回しとなると推測するのさえ難しく、しかも、そこが分からなければ、暗喩の意味がつかめないということになるんですね。
古書に限らず、そこがアイリッシュの優れている点でもあり、また、欠点にもなりえるわけです。
私のようなひねくれ者は、こういう表現方法を面白いと思うし畏敬の念を抱くわけですが、ストレートな文章表現に慣れている読者にとっては、古くさくてわかり難く、まどろっこしいと感じてしまうんじゃないでしょうか。
まあ、最近の若者がアイリッシュやウールリッチを好んで読むとは思えませんが。
「幻の女」は、ある男性が妻を殺害した容疑で逮捕され、死刑執行までに身の潔白を証明しなければならない羽目に陥るというもので、その証明には、殺害時間に派手なオレンジ色の帽子をかぶっていた女性と一緒にいたことを立証しなければならないのですが、女性とはそれまで一面識さえなく、その場限りの関係で名前もわからず、2人が一緒にいたことを証明できる人々が口をそろえて、彼が1人だったと証言するという不可解さ、あらたな証人となりうる人々が次々と死んでいくという謎、彼の死刑執行の期日が着実に迫ってくるというしかけが、はらはらするサスペンスとなって読むものをひきつけます。
多分、勘のいい人は途中で犯人に気づくんじゃないかな。
私は、やっぱりねと思いました。
「幻の女」が名作たりえるのは、オレンジ色の帽子という小道具が、あまりにも強烈であるために、平凡で特徴のない彼女自身の存在を隠してしまうことと、幻の女が最後まで幻であるというところにあると思います。
アイリッシュは女性を描くのが非常に巧みであるのは定評がありますが、「幻の女」のなかで、私がもっとも印象深いと思ったのは、殺される彼の妻でした。
「黒衣の花嫁」のヒロインにしても、女性の描き方がとても素敵でしたから、彼の妻は清廉潔白で罪のない奥様だろうとついつい思い込んでしまいがちです。
そこに疑問を持つか否かが犯人に迫る第一歩でもあるわけですが、妻の女性像が明らかにされたとき、やはりショックを受けずにはいられません。
「幻の女」をとっても楽しく読んだので、いい気になった私は、以前「黒衣の花嫁」を記事にしたときにコメントで話題にのぼった長編を読んでみようと、図書館で「暁の死線」「喪服のランデヴー」、そして、なんとなくもう一冊と思って「恐怖の冥路」を借りてきました。
 暁の死線 (創元推理文庫 120-2)
暁の死線 (創元推理文庫 120-2)
無茶苦茶強引な設定だという前評判にたがわず、無茶苦茶強引でした。
物語は深夜1時からから始まり、早朝6時までに男の身の潔白を証明し、田舎に帰るバスに乗り込まなければならないという「幻の女」によく似た設定ですが、時間的な余裕がまったくないなかで、よくもまあこんなにいろいろ盛り込むことが出来たなぁと感心するばかりです。
「暁の死線」で特徴的なのは、文章から漂い出る暗さで、その暗さが明るい日差しとともに消えていくところが爽快です。
「喪服のランデヴー 」は「黒衣の花嫁」の男性版と聞いていましたが、
」は「黒衣の花嫁」の男性版と聞いていましたが、
確かにその通りでありました。
犯人が全てを成し遂げるのか、警察がそれを阻止できるのかというスリルは同じでも、「黒衣の花嫁」のヒロインがミステリアスな魅力を持っていたのに対し、「喪服のランデヴー」の犯人である彼は際立った美男ではありませんが、普通ではない精神状態が哀愁を誘い、直接的には関係ない人物を殺害するというかなり酷な復讐劇を切なく美しく仕上げています。
ここまでお付き合いいただいている人のなかに、アイリッシュとウールリッチが同一の作家であるという基本原則を知らない人はいないでしょうけれど、「喪服のランデヴー」と「恐怖の冥路 」はウールリッチ名義で書かれています。
」はウールリッチ名義で書かれています。
ウールリッチという名は「黒衣の花嫁(The Bride Wore Biack)」
「喪服のランデヴー(Rendezvous in Black)」「恐怖の冥路(The Black Path of Fear)」というようにタイトルにブラックという単語が冠されているブラックシリーズに使われているようですが、あまり名義の使い分けは厳密ではないようです。
「恐怖の冥路」はそのブラックシリーズなかでも、異質な部類に入るのではないかと思いますが、私としては今回読んだなかではNO1ですね。
同じようなエピソードを手を変え品を変えて、いろいろな趣向で楽しませてくれるのがアイリッシュでありウールリッチであって、「恐怖の冥路」はその多彩さの極みといっても過言ではありません。
「幻の女」「暁の死線」の身の潔白の証明と「黒衣の花嫁」「喪服のランデヴー」の復讐劇を同時に併せ持ち、尚且つ舞台はキューバであって、そのまま映画になってもおかしくないぐらいの設定と活劇があります。
この大掛かりな設定が、あまりにも嘘くさくてご都合主義的なのですが、
そういうところがまたいいんですねぇ。
「恐怖の冥路」の一番の読みどころは、復讐の場面の主人公の心理状態の描写でしょう。
背筋が寒くなりました。
また、主人公を取り巻く人物達のキャラクターも際立っていて、
キューバで彼を手助けする女性は大変魅力的です。
隠れた存在ですが、執事のジョブも気になります。
最後に短編集「妄執の影 」について、少し触れておきましょう。
」について、少し触れておきましょう。
アイリッシュは長編よりも数多くの短篇小説を発表していて、評価も高いのです。
「裏窓」「ダイヤルMを廻せ」はヒッチコックにより映画化されていますし、本書の表題作「妄執の影」もフランス映画になっているようです。
本書の短編集は表題作のほか「さらばニューヨーク」「ガラスの目玉」「影絵」「義足をつけた犬」「爪」が所収されています。
「妄執の影」は追い詰められていく女性の心理を描いたもので、
フランス映画となったのも頷けるものです。
「さらばニューヨーク」はラストの一行が素晴らしい。
「影絵」では女性の観察眼の鋭さに驚き、「義足をつけた犬」では長編を思わせる構成で
読ませます。
「爪」では昔読んだ夢野久作をチラリと思い浮かべてゾッとしました。
「ガラスの目玉」は、主人公の少年が、ハラハラドキドキの冒険を繰り広げていますので、児童向けに書かれたものなんじゃないでしょうか。
緊張感高まる場面でのユーモアが光る、わたし一押しの短篇です。
アイリッシュの短編集は創元推理文庫から6巻ほど出版されていて、「影絵」はアイリッシュ短編集の4巻目の表紙を飾っている「シルエット」だろうと思います。
興味をもたれた方は、是非、探してみてください。

そうだ、こういうときこそミステリーだ。
あの本が溜まっている一画のどこかに、古本屋で買った古い早川ポケミスがあるはず。
ガサッ ドサッ
あった、あったぞ!
「幻の女」「妄執の影」
よし、有名な「幻の女」からいこう。
そんなわけで、購入してからはや一年が経過していたアイリッシュを読むこととなりました。
「幻の女
私の年齢と大差ない、古書の薫り高い一冊であります。
その頃の印刷は、わりあいいい加減で、時折、文字が半分消えていたり、吃驚するほど薄い印刷のページがあるかと思えば、急に濃くなったりして、明らかに今使われていないような難しい漢字のところでそういうことになると推測するしかない場合もあるわけで、読みにくいことこの上ないんですが、古い言い回しなども奥ゆかしく、それが古書を読む面白さであったりするんですね。
そのポケミス「幻の女」を読んでいると、何度読み直しても、
理解に苦しむところが出てくるんです。
これは、アイリッシュ独特の文章に原因があります。
アイリッシュは、普通の作家なら一行で済むような場面を長々とこと細かく描き、さらに比喩や暗喩を使って、直接的な表現方法をあくまで避けるという傾向があります。
ですから、現在では普段使われていないような言葉はこういう意味かなと思いながら読むにしても、意味がよく分からない言い回しとなると推測するのさえ難しく、しかも、そこが分からなければ、暗喩の意味がつかめないということになるんですね。
古書に限らず、そこがアイリッシュの優れている点でもあり、また、欠点にもなりえるわけです。
私のようなひねくれ者は、こういう表現方法を面白いと思うし畏敬の念を抱くわけですが、ストレートな文章表現に慣れている読者にとっては、古くさくてわかり難く、まどろっこしいと感じてしまうんじゃないでしょうか。
まあ、最近の若者がアイリッシュやウールリッチを好んで読むとは思えませんが。
「幻の女」は、ある男性が妻を殺害した容疑で逮捕され、死刑執行までに身の潔白を証明しなければならない羽目に陥るというもので、その証明には、殺害時間に派手なオレンジ色の帽子をかぶっていた女性と一緒にいたことを立証しなければならないのですが、女性とはそれまで一面識さえなく、その場限りの関係で名前もわからず、2人が一緒にいたことを証明できる人々が口をそろえて、彼が1人だったと証言するという不可解さ、あらたな証人となりうる人々が次々と死んでいくという謎、彼の死刑執行の期日が着実に迫ってくるというしかけが、はらはらするサスペンスとなって読むものをひきつけます。
多分、勘のいい人は途中で犯人に気づくんじゃないかな。
私は、やっぱりねと思いました。
「幻の女」が名作たりえるのは、オレンジ色の帽子という小道具が、あまりにも強烈であるために、平凡で特徴のない彼女自身の存在を隠してしまうことと、幻の女が最後まで幻であるというところにあると思います。
アイリッシュは女性を描くのが非常に巧みであるのは定評がありますが、「幻の女」のなかで、私がもっとも印象深いと思ったのは、殺される彼の妻でした。
「黒衣の花嫁」のヒロインにしても、女性の描き方がとても素敵でしたから、彼の妻は清廉潔白で罪のない奥様だろうとついつい思い込んでしまいがちです。
そこに疑問を持つか否かが犯人に迫る第一歩でもあるわけですが、妻の女性像が明らかにされたとき、やはりショックを受けずにはいられません。
「幻の女」をとっても楽しく読んだので、いい気になった私は、以前「黒衣の花嫁」を記事にしたときにコメントで話題にのぼった長編を読んでみようと、図書館で「暁の死線」「喪服のランデヴー」、そして、なんとなくもう一冊と思って「恐怖の冥路」を借りてきました。
 暁の死線 (創元推理文庫 120-2)
暁の死線 (創元推理文庫 120-2)無茶苦茶強引な設定だという前評判にたがわず、無茶苦茶強引でした。
物語は深夜1時からから始まり、早朝6時までに男の身の潔白を証明し、田舎に帰るバスに乗り込まなければならないという「幻の女」によく似た設定ですが、時間的な余裕がまったくないなかで、よくもまあこんなにいろいろ盛り込むことが出来たなぁと感心するばかりです。
「暁の死線」で特徴的なのは、文章から漂い出る暗さで、その暗さが明るい日差しとともに消えていくところが爽快です。
「喪服のランデヴー
確かにその通りでありました。
犯人が全てを成し遂げるのか、警察がそれを阻止できるのかというスリルは同じでも、「黒衣の花嫁」のヒロインがミステリアスな魅力を持っていたのに対し、「喪服のランデヴー」の犯人である彼は際立った美男ではありませんが、普通ではない精神状態が哀愁を誘い、直接的には関係ない人物を殺害するというかなり酷な復讐劇を切なく美しく仕上げています。
ここまでお付き合いいただいている人のなかに、アイリッシュとウールリッチが同一の作家であるという基本原則を知らない人はいないでしょうけれど、「喪服のランデヴー」と「恐怖の冥路
ウールリッチという名は「黒衣の花嫁(The Bride Wore Biack)」
「喪服のランデヴー(Rendezvous in Black)」「恐怖の冥路(The Black Path of Fear)」というようにタイトルにブラックという単語が冠されているブラックシリーズに使われているようですが、あまり名義の使い分けは厳密ではないようです。
「恐怖の冥路」はそのブラックシリーズなかでも、異質な部類に入るのではないかと思いますが、私としては今回読んだなかではNO1ですね。
同じようなエピソードを手を変え品を変えて、いろいろな趣向で楽しませてくれるのがアイリッシュでありウールリッチであって、「恐怖の冥路」はその多彩さの極みといっても過言ではありません。
「幻の女」「暁の死線」の身の潔白の証明と「黒衣の花嫁」「喪服のランデヴー」の復讐劇を同時に併せ持ち、尚且つ舞台はキューバであって、そのまま映画になってもおかしくないぐらいの設定と活劇があります。
この大掛かりな設定が、あまりにも嘘くさくてご都合主義的なのですが、
そういうところがまたいいんですねぇ。
「恐怖の冥路」の一番の読みどころは、復讐の場面の主人公の心理状態の描写でしょう。
背筋が寒くなりました。
また、主人公を取り巻く人物達のキャラクターも際立っていて、
キューバで彼を手助けする女性は大変魅力的です。
隠れた存在ですが、執事のジョブも気になります。
最後に短編集「妄執の影
アイリッシュは長編よりも数多くの短篇小説を発表していて、評価も高いのです。
「裏窓」「ダイヤルMを廻せ」はヒッチコックにより映画化されていますし、本書の表題作「妄執の影」もフランス映画になっているようです。
本書の短編集は表題作のほか「さらばニューヨーク」「ガラスの目玉」「影絵」「義足をつけた犬」「爪」が所収されています。
「妄執の影」は追い詰められていく女性の心理を描いたもので、
フランス映画となったのも頷けるものです。
「さらばニューヨーク」はラストの一行が素晴らしい。
「影絵」では女性の観察眼の鋭さに驚き、「義足をつけた犬」では長編を思わせる構成で
読ませます。
「爪」では昔読んだ夢野久作をチラリと思い浮かべてゾッとしました。
「ガラスの目玉」は、主人公の少年が、ハラハラドキドキの冒険を繰り広げていますので、児童向けに書かれたものなんじゃないでしょうか。
緊張感高まる場面でのユーモアが光る、わたし一押しの短篇です。
アイリッシュの短編集は創元推理文庫から6巻ほど出版されていて、「影絵」はアイリッシュ短編集の4巻目の表紙を飾っている「シルエット」だろうと思います。
興味をもたれた方は、是非、探してみてください。