大学病院以外の病院・診療所の産婦人科医数は、昨年7月現在で、1施設当たり平均1.74人であった。1人勤務の産科施設が非常に多い。しかも、全国の産婦人科医の4分の1は60歳以上である。
毎年4月に全国の大学病院産婦人科に入局する新人医師数は、3年前までは350人前後だったが、新臨床研修制度への移行期(一昨年、昨年)の2年間は新人医師の入局はなく、今年の新規入局者は213人(従来に比べて4割減!)だった。大学病院の産婦人科は自らの診療態勢の維持が精いっぱいで、従来通りの地域への医師派遣は非常に困難な状況に陥っている。
福島県立大野病院での「癒着胎盤による患者死亡事例」において、担当医師が逮捕、起訴された事件は、現役の産婦人科医達にも非常に大きな衝撃を与えた。予後不良の疾患に対して、患者救命のために治療に最善を尽くした医師が、治療の結果次第で、凶悪事件の犯人と全く同じに扱われるようになってしまえば、救急医療や産科医療に従事しようとする者など、この世の中からすぐに消えていなくなってしまうのは当然だ。「犯罪者」扱いされてまでも医療を続けたいとは誰も思わない。
この事件の影響もあって、1人勤務の産婦人科では分娩取り扱いの継続は非常に困難な状況にある。1人勤務の産科施設のほとんどは、今後数年以内に分娩取り扱いが中止されるだろう。また、現在60歳以上の産婦人科医のほとんど全員が10年後には現役を引退していることも間違いないだろう。
このままでは、10年後には、日本中で、妊娠しても分娩を受け入れてくれる産科施設がどこにもみつからないような事態となっていることが危惧される。国、自治体、医療界、医学教育界、市民が、挙げて、この問題の解決に真剣に取り組んでゆく必要があると思う。










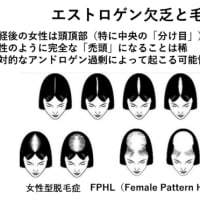


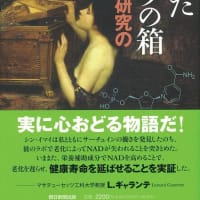
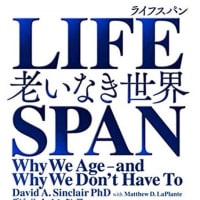
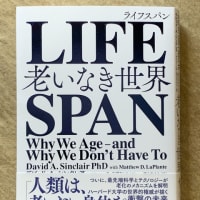
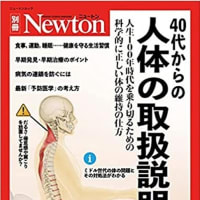
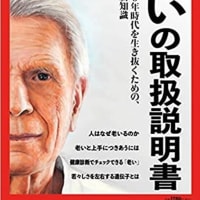
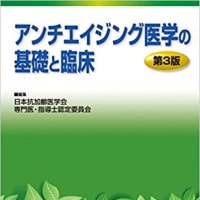

ニュースで、少子化対策に、経済的な問題はあるとしても お金だけでは解決できない という話題がありました。
医者の働き手の問題も 金さえ出せば いくらでも働き手は現れる わけではないように思います。たしかに報酬が低い とか 損害賠償保険のカバーの金額が低い のは論外ですけどね。
単純な過失ならよいのですが、「重大な過失」があったとされたら・・・
新破産法第253条(免責許可の決定の効力等) 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
↓
横浜市に1億円賠償命令 出産時ミスによる障害認定
横浜市立市民病院で帝王切開が遅れたため脳に重い障害が残ったとして、市立養護学校3年渡辺りさ子(わたなべ・りさこ)さん(8)と両親が市に計約2億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は6日、市に計約1億700万円の支払いを命じた。
判決によると、りさ子さんの母親(39)は陣痛があり1997年10月24日午前10時ごろ入院。胎児が低酸素状態となったことをモニターが示していたが、医師は午後1時すぎまで帝王切開を決断せず、出産は午後3時半ごろにずれ込んだ。りさ子さんは脳性まひで四肢が不自由になった。
判決理由で小林正(こばやし・ただし)裁判長は「医師はりさ子さんの仮死状態が疑われた同日午前11時5分ごろまでに帝王切開を決め、遅くとも1時間以内に出産させる義務があった」と指摘。入院前に障害が生じていたとの市側の主張を退け、診療ミスと障害との因果関係を認めた。
[共同通信]
カイザー決断のタイム・ラグと障害発生との間に、明らかな因果関係があるのでしょうか?1時間以内というのは、確かな医学的根拠があるのでしょうか?これで1億払わされていれば、産科医の多くは自己破産するのでは?と思ってしまいます。
産科医療のための今後の大きな目標としては無過失保証制度の創設や医療裁判制度の見直しといったことが必要なのでしょうが、産科医不足解消に対する成果を早期に確実に出したいというのでしたらやはり産婦人科医の報酬をそのリスクに見合ったものに上げてやるのが一番手っ取り早い方法でしょう。
たとえば先頃話題になった某病院の年収5500万とまでは言わずとも3000万以上は保証するとなれば産婦人科医の希望者は必ず増えます。
私は一応順調な経営状況にある外科開業医ですが産科の報酬形態がそのようになるのでしたらこれからでも産婦人科の研修をうけても良いと思いますし、同様に勤務医として復帰してもよいと思うベテラン産婦人科医師も大勢出てくるでしょう。
まずは隗より始めよです。
診療の忙しさを軽減できないのでしたら、せめて現在の産婦人科医の報酬を現状に即して現在の数倍以上に上げる必要があるかと思います。
もちろん医療機関の集約化、無過失保証制度の確立、裁判制度の見直し、誤ったマスコミ報道の規制等は同時に行われるべきです。新人が増えるのはその状況を見てからになるでしょう。
他科のDr.と多少の齟齬が生じるかもしれませんが、その勤務状態に応じた産婦人科医師の報酬のupは絶対に必要だと思いますし、それだけの給料が出せる診療報酬改正が必要だと思います。