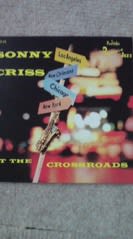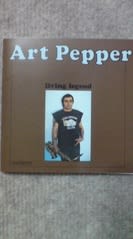私の住んでいる神奈川県では、今日の天気もとても蒸し暑い「残暑」でしたが、夜吹いてくる風などは、大分秋の様相をしてきました。
私、変わり者かもしれませんが、ぎらぎらと「クソ暑い」、所謂、「真夏」が大好きなんです。
冷夏なんてもっての他、太陽さんが「ウルトラ元気」じゃないと、すごーく嫌なんですよ。
何で「真夏」が好きだと言うと、答えは単純明快で、太陽光線は人間が作り出せないからです。
まぁ、セレブみたいにお金があれば、冬になったら南半球にいけば良いんだけど、私には勿論、そんなお金は有りません。
ちなみに、ガキの頃は「夏」は一番嫌いな季節でした。
これも理由はしごく簡単、エアコンなんて完備な世の中じゃなかったので、冬は寒くても服を多く着るか、沢山動けば(運動等)暖かくなるが、夏は服を脱いでも、ちっとも涼しくなんかならないからでした。
おまけに夜は超寝苦しいしねぇ。
しかし、そんな悲喜こもごもの「夏」ですが、確実にその真夏は過ぎ去り、一寸寂しい今日この頃です。
さて、季節の話(特に夏)が多くなってしまいましたが、それにも理由が有るんです。
私はこのブログで色々なジャンルの曲を紹介していますが、大まかに言って、「ジャズ」が大黒柱(横綱)で、太刀持ち、露払いを「クラシック」と「ラテン」が受け持っています。
その中の「ラテン」ですが、「ラテン」は「絶対」に真夏に聴かなきゃ駄目な曲だと持論が有ります。
まぁ、実際は私は冬でも聴いてはいますが、「真夏」こそ「相応しい」と言った方が正確でしょうか?
そんな訳で、前置きが長くなりましたが、過ぎ去る「夏」に一抹の寂しさを感じつつ、今日は渋めの「ボサノヴァ・ジャズ」を紹介します。
アルバムタイトル…ボッサ・アンティグア
パーソネル…リーダー;ポール・デスモンド(as)
ジム・ホール(g)
ジーン・ライト(b)
コニー・ケイ(ds)
曲目…1.ボッサ・アンティグア、2.夜は千の眼をもつ、3.オー・ガトー、4.サンバ・カンティーナ、5.悲しみのキュラソー、6.ア・シップ・ウィザウト・ア・セイル、7.アリアンサ、8.東9丁目の女
1964年7月28日、29日、8月20日、9月8日
原盤…RCA 発売…BMGビクター
CD番号…BVCJ-7340
演奏について…まず全編に渡って、「デスモンド」のクールなアルトと、「ホール」のほのぼの系ウォームなギターで、対照的な音色による絡みと、対比が趣深い演奏に仕上がっている。
リズムバックは名人「ケイ」と、渋い「ライト」が完全脇役に徹して、このフロント二人を見事にサポートしている。
さて、それぞれの曲の聴き所だが、印象的なギターのイントロと、上品なラテンリズムに乗って「デスモント」がメロディアスに吹き通す、オープニングの表題曲「ボッサ・アンティグア」は絶対聴かなきゃ損の1曲です。
スティックを敲いて、ラテンの香りを漂わせる「コニー・ケイ」のリズムの作り方は、すごくソフィストケイトされた、大人のドラム(スティック)ワークです。
勿論、「ジム・ホール」のソフトな口当たりのギターも行けてますよ。
2曲目の通称「夜千」…「デスモンド」の、とてもリラックスした大人の脱力感的演奏が、大いに曲の格調を上げていて、「ホール」の、でしゃばらないギター伴奏と、センス抜群のアドリブソロが、この演奏に更に高級感をもたらしている。
「コルトレーン」の「夜千」等とは対極にある名演奏です。
3曲目「オー・ガトー」は、「コニー・ケイ」の間を極限まで活かしたドラミングが最大の聴き所。
「デスモンド」と「ホール」は、輪唱的な演奏で、お互いのソロを競い合い、伴奏でサポートし合う、スポーツのダブルス見たいな演奏です。
個人的には、この寛ぎの演奏は、とても気に入ったよ!
4曲目「サンバ・カンティーナ」…リズムはハッキリと良く分かるサンバで、「ケイ」と「ライト」によって淡々と刻まれる。
ここでは「デスモンド」「ホール」とも、原曲のマイナー調で哀愁たっぷりのメロディーを活かしたアドリブソロが、とにかくお見事!!
曲の美しさも相成って、私が選ぶこのアルバムのベスト1演奏はこれでしょう。
5曲目の「悲しみのキュラソー」は「デスモンド」のオリジナル曲だが、流石に良く考えられた演奏で、二人の「癒し音楽」は、そろそろ頂点に達してきたようです。
特に「ホール」が堂に入ったアドリブソロを奏でています。
6曲目「ア・シップ~」は、ミディアム・スローテンポの、とても甘美なメロディ曲で、こう言った曲は「デスモンド」の十八番です。
寛ぎと余裕たっぷりの吹きっぷりは、素晴らしいの一言、一方「ホール」はマイナーフレーズを多めに使用して、曲に隠し味的なスパイスを効かす。
7曲目「アリアンサ」、8曲目「東9丁目~」も、ボサノヴァ・リズムで心が晴れ晴れする様な、明るくライトなサウンドで、「デスモンド」「ホール」とも快演をします。
全8曲とも、肩の凝らない「寛ぎ」&「癒し」演奏ですが、決して軟派な音楽では無く、軟らかさの中にピシッっと一本芯の通った、そうだなぁ、食べ物で言うと高級イタリアンの〆に出てくる、完全アルデンテのペペロンチーノみたいな演奏かな?
かえって、例えが分かり難いかな?
私、変わり者かもしれませんが、ぎらぎらと「クソ暑い」、所謂、「真夏」が大好きなんです。
冷夏なんてもっての他、太陽さんが「ウルトラ元気」じゃないと、すごーく嫌なんですよ。
何で「真夏」が好きだと言うと、答えは単純明快で、太陽光線は人間が作り出せないからです。
まぁ、セレブみたいにお金があれば、冬になったら南半球にいけば良いんだけど、私には勿論、そんなお金は有りません。
ちなみに、ガキの頃は「夏」は一番嫌いな季節でした。
これも理由はしごく簡単、エアコンなんて完備な世の中じゃなかったので、冬は寒くても服を多く着るか、沢山動けば(運動等)暖かくなるが、夏は服を脱いでも、ちっとも涼しくなんかならないからでした。
おまけに夜は超寝苦しいしねぇ。
しかし、そんな悲喜こもごもの「夏」ですが、確実にその真夏は過ぎ去り、一寸寂しい今日この頃です。
さて、季節の話(特に夏)が多くなってしまいましたが、それにも理由が有るんです。
私はこのブログで色々なジャンルの曲を紹介していますが、大まかに言って、「ジャズ」が大黒柱(横綱)で、太刀持ち、露払いを「クラシック」と「ラテン」が受け持っています。
その中の「ラテン」ですが、「ラテン」は「絶対」に真夏に聴かなきゃ駄目な曲だと持論が有ります。
まぁ、実際は私は冬でも聴いてはいますが、「真夏」こそ「相応しい」と言った方が正確でしょうか?
そんな訳で、前置きが長くなりましたが、過ぎ去る「夏」に一抹の寂しさを感じつつ、今日は渋めの「ボサノヴァ・ジャズ」を紹介します。
アルバムタイトル…ボッサ・アンティグア
パーソネル…リーダー;ポール・デスモンド(as)
ジム・ホール(g)
ジーン・ライト(b)
コニー・ケイ(ds)
曲目…1.ボッサ・アンティグア、2.夜は千の眼をもつ、3.オー・ガトー、4.サンバ・カンティーナ、5.悲しみのキュラソー、6.ア・シップ・ウィザウト・ア・セイル、7.アリアンサ、8.東9丁目の女
1964年7月28日、29日、8月20日、9月8日
原盤…RCA 発売…BMGビクター
CD番号…BVCJ-7340
演奏について…まず全編に渡って、「デスモンド」のクールなアルトと、「ホール」のほのぼの系ウォームなギターで、対照的な音色による絡みと、対比が趣深い演奏に仕上がっている。
リズムバックは名人「ケイ」と、渋い「ライト」が完全脇役に徹して、このフロント二人を見事にサポートしている。
さて、それぞれの曲の聴き所だが、印象的なギターのイントロと、上品なラテンリズムに乗って「デスモント」がメロディアスに吹き通す、オープニングの表題曲「ボッサ・アンティグア」は絶対聴かなきゃ損の1曲です。
スティックを敲いて、ラテンの香りを漂わせる「コニー・ケイ」のリズムの作り方は、すごくソフィストケイトされた、大人のドラム(スティック)ワークです。
勿論、「ジム・ホール」のソフトな口当たりのギターも行けてますよ。
2曲目の通称「夜千」…「デスモンド」の、とてもリラックスした大人の脱力感的演奏が、大いに曲の格調を上げていて、「ホール」の、でしゃばらないギター伴奏と、センス抜群のアドリブソロが、この演奏に更に高級感をもたらしている。
「コルトレーン」の「夜千」等とは対極にある名演奏です。
3曲目「オー・ガトー」は、「コニー・ケイ」の間を極限まで活かしたドラミングが最大の聴き所。
「デスモンド」と「ホール」は、輪唱的な演奏で、お互いのソロを競い合い、伴奏でサポートし合う、スポーツのダブルス見たいな演奏です。
個人的には、この寛ぎの演奏は、とても気に入ったよ!
4曲目「サンバ・カンティーナ」…リズムはハッキリと良く分かるサンバで、「ケイ」と「ライト」によって淡々と刻まれる。
ここでは「デスモンド」「ホール」とも、原曲のマイナー調で哀愁たっぷりのメロディーを活かしたアドリブソロが、とにかくお見事!!
曲の美しさも相成って、私が選ぶこのアルバムのベスト1演奏はこれでしょう。
5曲目の「悲しみのキュラソー」は「デスモンド」のオリジナル曲だが、流石に良く考えられた演奏で、二人の「癒し音楽」は、そろそろ頂点に達してきたようです。
特に「ホール」が堂に入ったアドリブソロを奏でています。
6曲目「ア・シップ~」は、ミディアム・スローテンポの、とても甘美なメロディ曲で、こう言った曲は「デスモンド」の十八番です。
寛ぎと余裕たっぷりの吹きっぷりは、素晴らしいの一言、一方「ホール」はマイナーフレーズを多めに使用して、曲に隠し味的なスパイスを効かす。
7曲目「アリアンサ」、8曲目「東9丁目~」も、ボサノヴァ・リズムで心が晴れ晴れする様な、明るくライトなサウンドで、「デスモンド」「ホール」とも快演をします。
全8曲とも、肩の凝らない「寛ぎ」&「癒し」演奏ですが、決して軟派な音楽では無く、軟らかさの中にピシッっと一本芯の通った、そうだなぁ、食べ物で言うと高級イタリアンの〆に出てくる、完全アルデンテのペペロンチーノみたいな演奏かな?
かえって、例えが分かり難いかな?