今回の尖閣国有化を機に、両国メディアで尖閣問題を巡る報道がヒートアップしていった。
日本では、中国各地で発生した反日デモの様子が繰り返し放映され、一部暴徒化した民衆の過激な行動の数々は、日本の市民に恐怖感を植え付ける結果となった。
とりわけ、反日デモがピークを迎えた9月18日などは、どのチャンネルを選択しても同じような光景が映し出され、まるで中国全土が戦争状態にあるかのような錯覚を引き起こさせるような取り上げ方だった。
他方、中国では情報統制されたメディア社会で、政府見解に沿った政府や各種団体の代表者、日中関係研究の専門家が連日のように出演し、「日本政府による尖閣国有化は誤りだ」と繰り返すばかりだった。
しかも、時折、人民解放軍の映像なども交え、「いざとなれば、交戦状態になることも辞さない」といった雰囲気も醸し出し、見方によっては日中戦争の再来を想起させるような内容のものも見受けられた。
こうした外交問題が先鋭化した局面においては、両国のメディアが互いの主張を批判し合うのは珍しいことではなく、ある意味では当然のこととも言える。
ただ、筆者はこの局面で、どうしても両国の「報道」をめぐって違和感を感じずにいられなかった。
報道の違いというものが、端的に言って、全く正反対の性質だったからだ。
日本は、日本国民の誰もが知るとおり、「言論の自由」が確立された民主主義国家。
各種メディアを通じて、政府の方針と異なる見解を展開しても、その行為自体で罰せられるというようなことはない。
しかし、近年の各メディアの報道を見ていると、あまりにも短絡的で目立つ映像ばかりを採用し、真実を伝えようとする努力が不足しているように思えてならない。
勿論、高度情報化社会を迎え、各社が情報伝達スピードを速める必要があるのは分かるが、情報番組すらワイドショー化の道を辿るようでは日本の未来は明るくないだろう。
一方、中国はご存知のとおり、情報統制の行き届いた国。
あまり知られていないが、中国は国土が広大なこともあって、地方のTV局も合わせるともの凄い数のTV局が存在しており、これまたデジタル放送の普及によって、各家庭で視聴できる局数も60近いチャンネル数となっている。
各TV局は、独自性のある番組なども放映しているが、基本的にはメディア各社は何らかの形で政府の関与を受けている。CCTV(中国中央テレビ)は中央政府の管轄化におかれているし、有事においては政府広報の役割も果たす。地方TV局もそれぞれの本拠地の地方政府が所管する形となっている。
【上海関連の情報が満載の「にほんブログ村 上海情報」はコチラ】
しかも、中国のTV局で日中戦争を題材としたドラマが放映されない日はないと言っていいくらい、どこかの時間帯で必ず戦争モノの映像が流されている。
勿論、視聴率がそんなに高いとは思えないが、繰り返しというのは怖いもので、中国人民の深層心理から「日本の侵略行為」という残像が消える日は近くないと感じざるを得ない。
こうした両国のメディアの特性は、今に始まったことではなく、これまでも両国間で何か問題が発生するたびに、自国メディアの影響を受けた民衆が何らかの行動に出るという場面もしばしば見受けられた。
ただ、いまは両国ともにネット社会が急速に発達。
中国では微博(マイクロブログ)が爆発的に普及し、TVのニュース番組は見ないが、微博関連のサイトでニュース等を仕入れるという若者は少なくない。
微博は基本的に個人が開設したものであるため、情報の即時性が高く、ネット社会の中で拡散するスピードも速い。その半面、個人的な行動ゆえに信憑性に疑問が付くこともあるワケだが、ここはフォロワー数の大きさや通常の記事内容などから自然と信憑性の確度が判断できるようになっている。
あわせて、フォロワーがコメントすることもできるため、一方通行で政府見解ばかりのTVニュースよりも遥かに現実的だということもあるのだろう。
翻って、日本はどうだろうか・・・?
日本という国に住んでいると気付かないと思うが、日本では政府広報というものに出会う回数が異常に少ない。
厳密に言うと、NHKは純粋な国営放送ではないし、紙媒体に至っては、政府見解をそのまま掲載した日刊のものは存在しない(と思うが、あるのだろうか・・・)。
日本の市民は、これまで朝日、読売、毎日といった大手新聞社の発行する新聞の情報があたかも真実を伝えるニュースペーパーだと信じきっていたが、各種記事が実社会の状況にマッチしていないことが多く見受けられるようになるにつれ、情報感度の高い知識層を中心に新聞離れが進むようになってきた。
情報の即時性という観点からも、いまではインターネットやスマホで情報をチェックする方々が増えているのは自然な流れというもの。
こういった環境の中、日本の市民は既存のメディアを信頼しない傾向が強まっているようで、物事の真相を知りたいときほど、よりディープなメディアであるオンライン専門記事(ダイヤモンドオンラインなど)や個人開設のブログ記事等へと検索を進める傾向が強まっている。
【中国関連の話題が満載の「にほんブログ村 中国情報(チャイナ)」はコチラ】
日中両国の現状、なぜか似ていますよね。
中国の場合、表の情報が統制されているが故に非公式の情報へと駆り立てられる。
日本の場合、ニュース提供が自由すぎるが故に、これまた非公式の情報へと向かっていく。
つまり、どちらのメディアも心のどこかで信用されていないってコトなのかな?
だから、置かれている状況は180度異なると言ってもいいのに、人々の行動のベクトルは何故か同じ方向に向かっていくのだろう。
あの反日デモがピークを迎えたとき、筆者のブログでも象徴的なことが起きた。
私が開設しているgooブログは、総数175万を超える大所帯。
そこで、筆者ごときの記事が第43位を獲得した日があったのである。
ハッキリ言って、あり得ないこと。
書いている本人としては、勿論嬉しいという気持ちもあったが、これは裏返すと既存メディアに満足していない人々の数が累積されたものの表れとも言えるので、ちょっと複雑な気持ちになったのを今でも覚えている。
日本は、中国に対して「もっと言論の自由を担保しろ!」と主張することが多い。
でも、日本を反対側から見ると、政府見解がどこでタイムリーに発表されているかさえ分からない状態なので、「日本はもっとハッキリ自国の見解を示せ!」となるわけである。
でも、やっぱり分からないでは済まされないので、結果的に大手メディアの報道から日本の考えを探ろうとする。
ただ、各メディアが政府見解だけを掲載するなんてことは極めて稀なわけで、どうしてもそこには記者や新聞社としての主観が介在することになるから話がややこしくなる。
こうした記事を巡って、中国側メディアから批判が出たりする状況・・・、あまり好ましくないと思うんですが。。。
筆者は以前から主張しているとおり、日本政府はもっと政府広報を充実させるべきだと思っている。政府の人間がTVのインタビューに答えたり、記者会見を開いたりするだけで、その国の方針が正しく伝達されるはずと思うのは、あまりにも自己中心的な考えに過ぎない。
もっと丁寧に説明を尽くせば、少なくとも現在よりは状況が改善されるはずだし、そうした行動を積み重ねていけば、より良い情報伝達の仕組みが出来上がっていくはず。
要は、積極的に情報提供していく姿勢、その背景に持つべきは情報戦略ではないか・・・と。
この点、中国は本当にしたたかである。
人民日報は政府広報の役割を果たしているワケだが、同社のHPは既に多言語化されており、主要な記事はタイムリーに多言語で配信される仕組みが整えられている。
他国の人々は、重要な案件にかかる中国政府の方針等をタイムリーに知ることができるのだ。(無論、それが正しい情報か、操作された情報かは自己判断する必要あり)
恥ずかしながら筆者もそうだが、日本人は他言語に対するアレルギーが強く、日本語に頼ろうとする傾向が強い。
日本全体がこのアレルギーを克服して、高度情報化社会に対応した情報伝達の仕組みを築くことこそ、日本の国益に沿うものではないか・・・と、筆者は強く感じている。
↓ご愛読ありがとうございます。よければ応援クリックをポチっとお願いします。(ブログランキングに参戦中)












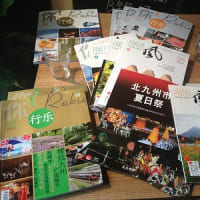


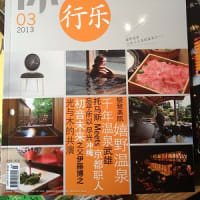




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます