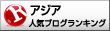本日、NYダウと日経平均が大幅安となったので、今日はシリーズ編をお休みして世界経済の先行きをテーマに。
またしても、完全な思いつきではありますが。
昨日、「為替」をテーマに記事を書いたら、いきなり「円高・株安」の方向に向かっていますね。まあ、金融市場は難しいもんです。
ただ、言い訳をするワケではないが、こうした展開はある程度想定していた。
だって、NYダウにしても史上最高値を続々と更新、日経平均も民主党政権時と比べると倍近くまで急騰していますからね。そろそろ下げが始まってもおかしくない状況にあったワケです。
それ以上に、あまり注目されていないが、欧州の主要株価指数は普通じゃないペースで上昇を続けていた。ドイツ、フランスなんかがまさしく典型ですね。
両国の株価指数は少しばかり早めに下落傾向を見せていましたから、振り返るとこれも一つの兆候だったと言えます。欧州の株価指数が下がっているのは、ここまでハイペースで上がってきたのと同時に、欧州経済の先行き不透明感が漂ってきたことも背景にありそうだ。
とりわけ、トルコリラの急落などはその象徴。トルコ政府は大幅な利上げを実施して沈静化を図ろうとしているが、経済成長が鈍化するのでは・・・との懸念を完全に払拭するには至っていない。
もっとも、ギリシャ危機、欧州経済危機と言われた政府債務問題は本質的に解消されていない。仮に世界経済が低迷するような事態になれば、こうした問題が再燃しかねないワケで、今後しばらくは神経質な展開が続くことが予想される。
【上海関連の情報が満載の「にほんブログ村 上海情報」はコチラ】
トルコ以外の新興国においても、通貨安・株安という状況に陥っている国が少なくないが、これは米国の金融緩和縮小政策の開始がきっかけとなった可能性が指摘されている。米国は量的緩和の縮小を緩やかに慎重に進めていくことになるだろうが、今のところ他国の通貨のことまで考えるような姿勢は見せていない。
米国ほどの経済大国といえども、第一に考えるのは自国の経済のことなのだ。
米国にしてみれば、リーマンショックから立ち直るため、かなり大胆に量的緩和策を行ってきたワケで、経済が上向いてきたこの機会に元の水準に戻しておかないと、いつまで経っても正常な金融政策(金利の上げ下げ等)を実施できないドコかの国(日本のことです・・・)のようになるワケにはいかないのだ。
そこで、いよいよ日本と中国の状況に目を転じてみたい。
日本はこの一年、アベノミクスで盛り上がってきましたよね。
以前も記事に書いたとおり、この経済政策自体は時機を得たものだったと言えます。まあ厳密に言うと、民主党政権時代に金融政策は無策に近い状態だったので、日本経済という観点からは遅きに失した感もあり、その反動高の要素も多分にあると思うのですが。。。
このアベノミクスのうち、第一、第二の矢である大胆な金融緩和、財政政策が一定の効果を発揮したことになるが、問題は第三の矢である「成長戦略」。
これについては、いささか小粒と言わざるを得ない。
既に市場の関心は、この成長戦略の成否にシフトしているのだが、成長戦略という耳障りのよい言葉だけが独り歩きし、「肝心の中身は一体何なの?」という状況がずっと続いているように思えてならない。
実際、新聞報道で挙がっている特区の概要を見ても、日本経済の浮揚に大きなインパクトを与えるようなものではなさそうだ。
こうなってくると、日本経済の先行きはすこぶる怪しい。
金融緩和に関しては、日銀が国債などの資産買入れを増やせば増やすほど中央銀行としての独立性を失っていくことに繋がるし、景気対策を目的とした財政出動は歯止めがかからない財政赤字を雪だるま式に増やしていくばかりで、とても持続可能な対策とは言い難い。
まして、日本は少子高齢化が急速に進んでいる。今年4月には遂に消費税が8%に増税されるが、筆者は巷で言われている以上に駆け込み需要、増税後の買い控えが起こると予想している。日本人の消費行動は緻密ですからね、短期的にだけど。個人消費のカギを握るのは、何と言っても家庭の奥様方。
後世に巨大な借金というツケを回さずに済むよう、そろそろ現実的な対策を真剣に検討すべきだろう。
そんなこんなで結果的には、日本円は外的要因に大きく左右されると考えたほうがよさそうだ。
今回の円高・株安も世界的な金融市場の動揺による影響が極めて大きく、この数週間で円高or円安のどちらに振れるかも金融市場の沈静化が図られるかにかかっているだろう。
【中国関連の話題が満載の「にほんブログ村 中国情報(チャイナ)」はコチラ】
次に、中国経済について考察を進めたい。
日本に住んでいると、中国経済の実質的な状況というのを肌感覚で感じることが難しいが、いまも中国で生活している方々の話を総合すると、「中国国内の景気は統計指標が示すほど良くない」というのが共通認識のようだ。
まあ、中国では統計数値もコントロールされているという根強い噂がありますからね。もしコレが事実だとしたら、過去何年にも亘って操作が行われている可能性が高いワケで、ホントの数字は中国政府しか知らないってことになるかも。。。
もっとも、うまく凸凹を修正しながら全体としては調和がとれるように調整してるんでしょうけど。
余談はさておき、いまの中国は様々な問題を抱えつつも、巨大な国土と労働力、成長する消費力を背景に突進を続けているといった印象か・・・と。まあ、例えがいいかは分かりませんが、相撲の力士のようなイメージですね。
悪く言うと、相撲取りと同様、足下が弱く、持久力に不安がある。汚職などの故障も抱えているといったイメージか。
不動産バブルや環境問題、役人の腐敗や貧富の差の拡大など、ある意味では国全体が「難題のデパート」とも言えなくもない。
でも、この国は当分の間、成長率こそ緩やかに鈍化するものの、成長を維持するだろう。なぜって、そういう国だからだ(答えになってない?)。中国はご承知のとおり共産党一党独裁の国。よって、計画を達成できないというのは、それ自体が「悪」であり、許されないことなのだ。だから、役人が総力戦でもって、血眼で計画達成を目指して突っ走る。元々は役人だった国有企業の幹部も同様。こと中国国内にあっては、WTOルールや世界経済の一般常識など通用しないことはザラにある。その他、諸々・・・だから、よほどの理由がない限り、経済成長を成し遂げていくだろう。
もっとも、そんな中国であっても勿論、どうしようもない事態が発生する可能性は否定できない。不動産バブルの崩壊、経済格差に対する民衆の不満の爆発、大規模災害など・・・。ただ、国土が想像を絶するほど広いですからねぇ。国全体のムーブメントを起こすというのは至難の業に違いない。
中国は折しも春節(旧正月)の真っ只中。
香港の株式市場は一足早く休場明けとなったが、米国をはじめとする各国の株式市場と同様、大幅安の展開となった。
中国本土市場が再開するのが2月7日。
この日まで各国の市場が弱含みで推移するとなると、最悪のケースでは中国本土市場が1週間分の下落を1日で消化(つまり大暴落)、その結果が更に他国の下落を招くという負の連鎖が始まる可能性もゼロではない。
米国の経済指標改善が呼び水となって、一両日中に市場が落ち着きを取り戻すことを今はただ祈るばかりだ。
↓ご愛読ありがとうございます。よければ応援クリックをポチっとお願いします。(ブログランキングに参戦中)
 にほんブログ村
にほんブログ村