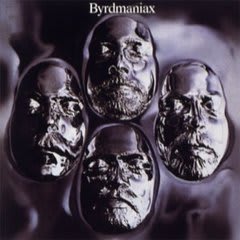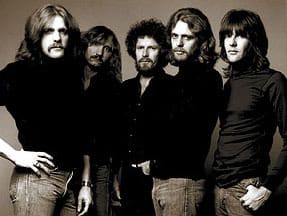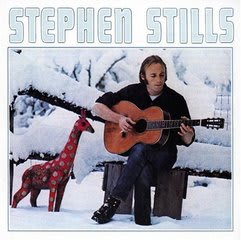『アサイラム・レコードとその時代』(音楽出版社)
今時、こんな本を出して売れるのでしょうか。
ターゲットは、団塊から10歳くらい若い世代?
ちなみに、ワタシは団塊から20歳くらい若い世代(つまり、既に若くナイ)ですが、少々心配です。
しかも、この本、雑誌コードでの流通のようですから、店頭には長いコトは置かれないに違ェねぇ。
速攻でゲトだ!
と、思ってから、数日迷って買いました。
まだ、キチンと読んではおりませんが、アサイラムだけでアルバム・ガイド173枚というのは、中々のヴォリューム。快挙です。
サウザー=ヒルマン=フューレイ・バンドがカラー写真で載る本なんて、二度と出版されないでしょう。快挙です。
できれば、20年前に出版して欲しかった。
アサイラム・レコードを知らない方に、ちょいと解説すると、アサイラムというのは、1970年代のアメリカを代表するLAの新興レーベル(当時)で、イワユル、ウェスト・コースト・ロックを象徴するレーベル。所属アーティストは、ジャクソン・ブラウン、イーグルス、リンダ・ロンシュタッド、ジョニ・ミッチェル、などなど、などなど。
コレを読むと、ジャクソン・ブラウンも、キチンと聴かないとイカンねえ~、と言う気になってしまって、今、『Late For The Sky』(1974)を聴いております。
チキショー、沁みるゼい。
経済の倒壊を恐れず、未着手の、ジュディ・シル、それから、あんまり着手していなかったリンダに、ジャクソン・ブラウンに、そんでJDにも、もっと行っとくぅ?な、気分にナリカネない、危険なムックですね。
岸辺も一徳ぅ?
今時、こんな本を出して売れるのでしょうか。
ターゲットは、団塊から10歳くらい若い世代?
ちなみに、ワタシは団塊から20歳くらい若い世代(つまり、既に若くナイ)ですが、少々心配です。
しかも、この本、雑誌コードでの流通のようですから、店頭には長いコトは置かれないに違ェねぇ。
速攻でゲトだ!
と、思ってから、数日迷って買いました。
まだ、キチンと読んではおりませんが、アサイラムだけでアルバム・ガイド173枚というのは、中々のヴォリューム。快挙です。
サウザー=ヒルマン=フューレイ・バンドがカラー写真で載る本なんて、二度と出版されないでしょう。快挙です。
できれば、20年前に出版して欲しかった。
アサイラム・レコードを知らない方に、ちょいと解説すると、アサイラムというのは、1970年代のアメリカを代表するLAの新興レーベル(当時)で、イワユル、ウェスト・コースト・ロックを象徴するレーベル。所属アーティストは、ジャクソン・ブラウン、イーグルス、リンダ・ロンシュタッド、ジョニ・ミッチェル、などなど、などなど。
コレを読むと、ジャクソン・ブラウンも、キチンと聴かないとイカンねえ~、と言う気になってしまって、今、『Late For The Sky』(1974)を聴いております。
チキショー、沁みるゼい。
経済の倒壊を恐れず、未着手の、ジュディ・シル、それから、あんまり着手していなかったリンダに、ジャクソン・ブラウンに、そんでJDにも、もっと行っとくぅ?な、気分にナリカネない、危険なムックですね。
岸辺も一徳ぅ?