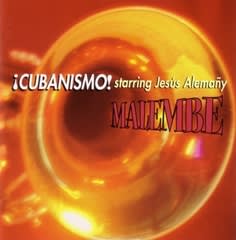NICA'S DREAM MAMBO - SONORA PONCEÑA
そうです。
ホレス・シルバーの「ニカズ・ドリーム」ですよ。
それを、マンボジャズに仕立てたって事ですがね。
あぁ、揺れるココロが切なくて。
みたいな、感じの仕上がりデスね。
で、この曲は、元々、メロドラマのテーマ曲みたいな、
ベタベタでメロメロなメロディですが、パポ・ルッカ師匠は、
これを、シャープで繊細でしなやかに揺れるピアノで、
すっかり、腰からシュビドゥバに砕いてしまう訳ですよ。
師匠は、ラインとタッチを、思いのまま微妙に揺らしてるんデス。
発音タイミングを前後にズラし、ヴェロシティも微妙に揺らす。
んで、それは、高音成分がシャープに伝わるからこそ、
よりシュビドゥバに、聴き手の腰に伝わるんだと思いますが、
リズムの揺れを繊細に意識的にコントロール出来るプレイヤーには、
アタック音がシャープに聴き取れるサウンドが合うと思うんデス。
これが、50年代風のブルーノートなピアノの音だったとしたら、
聴き手の脳は、きっと勝手に、揺れないスクエアなパルスに合わせて、
クォンタイズしてしまうんデスよ。
パポ・ルッカ師匠の才能のスーパーな開花が70年代半ばだったのは、
レコーディング技術の進化と言う時代の状況に、
スカっとマッチしたってぇ背景もあるんだと思うんスよね。
 にほんブログ村
にほんブログ村
そうです。
ホレス・シルバーの「ニカズ・ドリーム」ですよ。
それを、マンボジャズに仕立てたって事ですがね。
あぁ、揺れるココロが切なくて。
みたいな、感じの仕上がりデスね。
で、この曲は、元々、メロドラマのテーマ曲みたいな、
ベタベタでメロメロなメロディですが、パポ・ルッカ師匠は、
これを、シャープで繊細でしなやかに揺れるピアノで、
すっかり、腰からシュビドゥバに砕いてしまう訳ですよ。
師匠は、ラインとタッチを、思いのまま微妙に揺らしてるんデス。
発音タイミングを前後にズラし、ヴェロシティも微妙に揺らす。
んで、それは、高音成分がシャープに伝わるからこそ、
よりシュビドゥバに、聴き手の腰に伝わるんだと思いますが、
リズムの揺れを繊細に意識的にコントロール出来るプレイヤーには、
アタック音がシャープに聴き取れるサウンドが合うと思うんデス。
これが、50年代風のブルーノートなピアノの音だったとしたら、
聴き手の脳は、きっと勝手に、揺れないスクエアなパルスに合わせて、
クォンタイズしてしまうんデスよ。
パポ・ルッカ師匠の才能のスーパーな開花が70年代半ばだったのは、
レコーディング技術の進化と言う時代の状況に、
スカっとマッチしたってぇ背景もあるんだと思うんスよね。