(昨日ご紹介したウィンドカーの作り方補足を末尾に掲載しました)
高専の文化祭を回りながら、卒業研究その他を見せてもらいながら、いろいろつっこんだ質問をしていくなかで、ちょっと気になることがあった。
つまり、「それでこれは、従来技術と違う、どういう特長があるんですか??」「どういう点で得になることを狙っているのですか??」という質問をすると、まったく答えられないことがけっこう多かったのだ。
卒業研究は、先生に提案やアドバイスをもらいながらなんかいっしょうけんめい作っていって、でもそれだけではなくて、爪の先くらいの「何か新しいこと(技術の改善や新しい知見)」を狙って…その結果やっぱりうまくいきませんでした、でも全然かまわないから、ともかく何か、1ミクロンのオリジナリティー(を目指す心)がほしいと思う。
どのみちたいしたことができるわけではないんだけど、その中で、全体を「研究」としてまとめるポーズの付け方みたいなものを学んでほしい。
この考え方はおかしいだろうか?? 私の知っている卒業研究は大学のそれであって、高専のものではない。大学と高専では「二歳」ずれている。だから求められるものが違っても不思議はないのだけれど、高専は一般教養的な無駄(?)を省いて、専門科目の面では同じくらいの高さを目指しているのではないだろうか。と、とりあえずは贅沢をいってみる。
もちろん、並んでいる「作品」の数々を見ると、ほとんどの理系大学生にはマネができない工作技術に支えられて、「ごりっ」とした機械が出来上がっている。そこは魅力だと思う。けれども、そういう「手に職」の部分だけでは一生食っていくことはできない。
またろうが高専志望を決めたころ、会社で技術者研修みたいなのがあって、そこに講師に来た「社内ですごい高いところまで出世した技術者」がいた。その人のスピーチの中で、その人が高専出身であることがわかったので、後のパーティーでつかまえて話を聞いてみた。
すると、その人は高専を出てから大学編入したので、会社から見た扱いは大卒(あるいは院卒)。「通信」が専門だったので、高専卒で就職した友だちの多くは船に通信士として乗り込むなどの道に進んだそうだ。就職の際には「引く手あまた」な状態だったが、その後、船で使う通信の方法に技術革新があり、職を失った人も多いとか。
「ある技術分野を極めることは、それだけでも大きな価値がある。しかしそれは一生ものではなく、必ずその技術は陳腐化するので、いつも新しいところに進んでいける力を持っていなくてはいけない」「新しいところでも、ある技術分野を極めた経験はきっと役に立つ。また、そのように別の分野に行ってからも役に立つような方法で極めておく必要がある」「あなたの息子さんが高専を目指したい気持ちはよくわかるし、私も高専に行ってよかったと思っているが、親として心配になる気持ちもよくわかる」というようなことをその人は言っていた。
私なりに解釈すると、その「いつも新しいところに進んでいける力」というのは、例えば、自分が今作っているものを一歩引いて見て、位置づけについて把握でき、それをまた説得力を持って語れる力ではないかと思うのだ。作るだけで終わってしまうのは危険である。
ウィンドカーを作りながら話をした彼は、「組み込み」技術を学ぶためのシステムを作っていると言っていた。学ぶためのシステムってところがおもしろい。「そのシステムを作って、学習効果がどれくらい上がるかの測定までいけそうですか??」と聞いてみたら「いや全然、作るだけでめいっぱい終わってしまいそうですね。でも僕は専攻科に行くのでまだ続きができますよ」とのこと。がんばってね!!
ウィンドカーの作り方:
作り方がわかるように後ろから撮ってみました。

車輪と車体の間や、風車と車体の間には、短く切ったストローを通してすべりをよくしています。
作り方のツボは、ゴムのかけ方です。風車は、速く回るけど力弱く、車輪はもっとずっとゆっくり回ればいいんだけどある程度パワーがないと進めません。なので、風車側は竹ひごに直接ゴムをかけ(直径を小さく)、車軸の側は、写真でいうと赤い丸いのをつけてその上にかけています(直径を大きく)。
この赤いパーツは、竹ひごがしっかり通って固定でき、輪ゴムがずれずにかかるように溝がついているすぐれものです。車輪も竹ひごに差し込んだだけで固定できるつくりになっています。
こういう、すぐれもののパーツが揃っていて寸法も決まっているキットでしたら、作るのは「あっという間」で、逆にいえばおもしろいところもたいしてありません(遊ぶのはおもしろいけど)。材料や寸法を試行錯誤して作るなら、もっとずっと時間がかかるけどプロセス自体がおもしろいでしょう。
でも、手軽に楽しめるほうがいいな、という方には、今回ゲットしたパーツをばらして郵送します。先着二名まで。メールまたは旧ブログの非公開コメントを使ってご連絡ください。
高専の文化祭を回りながら、卒業研究その他を見せてもらいながら、いろいろつっこんだ質問をしていくなかで、ちょっと気になることがあった。
つまり、「それでこれは、従来技術と違う、どういう特長があるんですか??」「どういう点で得になることを狙っているのですか??」という質問をすると、まったく答えられないことがけっこう多かったのだ。
卒業研究は、先生に提案やアドバイスをもらいながらなんかいっしょうけんめい作っていって、でもそれだけではなくて、爪の先くらいの「何か新しいこと(技術の改善や新しい知見)」を狙って…その結果やっぱりうまくいきませんでした、でも全然かまわないから、ともかく何か、1ミクロンのオリジナリティー(を目指す心)がほしいと思う。
どのみちたいしたことができるわけではないんだけど、その中で、全体を「研究」としてまとめるポーズの付け方みたいなものを学んでほしい。
この考え方はおかしいだろうか?? 私の知っている卒業研究は大学のそれであって、高専のものではない。大学と高専では「二歳」ずれている。だから求められるものが違っても不思議はないのだけれど、高専は一般教養的な無駄(?)を省いて、専門科目の面では同じくらいの高さを目指しているのではないだろうか。と、とりあえずは贅沢をいってみる。
もちろん、並んでいる「作品」の数々を見ると、ほとんどの理系大学生にはマネができない工作技術に支えられて、「ごりっ」とした機械が出来上がっている。そこは魅力だと思う。けれども、そういう「手に職」の部分だけでは一生食っていくことはできない。
またろうが高専志望を決めたころ、会社で技術者研修みたいなのがあって、そこに講師に来た「社内ですごい高いところまで出世した技術者」がいた。その人のスピーチの中で、その人が高専出身であることがわかったので、後のパーティーでつかまえて話を聞いてみた。
すると、その人は高専を出てから大学編入したので、会社から見た扱いは大卒(あるいは院卒)。「通信」が専門だったので、高専卒で就職した友だちの多くは船に通信士として乗り込むなどの道に進んだそうだ。就職の際には「引く手あまた」な状態だったが、その後、船で使う通信の方法に技術革新があり、職を失った人も多いとか。
「ある技術分野を極めることは、それだけでも大きな価値がある。しかしそれは一生ものではなく、必ずその技術は陳腐化するので、いつも新しいところに進んでいける力を持っていなくてはいけない」「新しいところでも、ある技術分野を極めた経験はきっと役に立つ。また、そのように別の分野に行ってからも役に立つような方法で極めておく必要がある」「あなたの息子さんが高専を目指したい気持ちはよくわかるし、私も高専に行ってよかったと思っているが、親として心配になる気持ちもよくわかる」というようなことをその人は言っていた。
私なりに解釈すると、その「いつも新しいところに進んでいける力」というのは、例えば、自分が今作っているものを一歩引いて見て、位置づけについて把握でき、それをまた説得力を持って語れる力ではないかと思うのだ。作るだけで終わってしまうのは危険である。
ウィンドカーを作りながら話をした彼は、「組み込み」技術を学ぶためのシステムを作っていると言っていた。学ぶためのシステムってところがおもしろい。「そのシステムを作って、学習効果がどれくらい上がるかの測定までいけそうですか??」と聞いてみたら「いや全然、作るだけでめいっぱい終わってしまいそうですね。でも僕は専攻科に行くのでまだ続きができますよ」とのこと。がんばってね!!
ウィンドカーの作り方:
作り方がわかるように後ろから撮ってみました。

車輪と車体の間や、風車と車体の間には、短く切ったストローを通してすべりをよくしています。
作り方のツボは、ゴムのかけ方です。風車は、速く回るけど力弱く、車輪はもっとずっとゆっくり回ればいいんだけどある程度パワーがないと進めません。なので、風車側は竹ひごに直接ゴムをかけ(直径を小さく)、車軸の側は、写真でいうと赤い丸いのをつけてその上にかけています(直径を大きく)。
この赤いパーツは、竹ひごがしっかり通って固定でき、輪ゴムがずれずにかかるように溝がついているすぐれものです。車輪も竹ひごに差し込んだだけで固定できるつくりになっています。
こういう、すぐれもののパーツが揃っていて寸法も決まっているキットでしたら、作るのは「あっという間」で、逆にいえばおもしろいところもたいしてありません(遊ぶのはおもしろいけど)。材料や寸法を試行錯誤して作るなら、もっとずっと時間がかかるけどプロセス自体がおもしろいでしょう。
でも、手軽に楽しめるほうがいいな、という方には、今回ゲットしたパーツをばらして郵送します。先着二名まで。メールまたは旧ブログの非公開コメントを使ってご連絡ください。










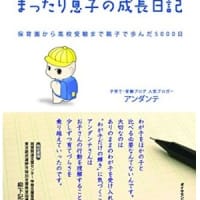



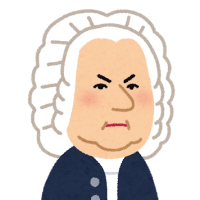






おかしくはないんだけど……高い要求ではあると思います。
>> 私の知っている卒業研究は大学のそれであって
大学の卒論だって、いろいろ、ですからね。アンダンテさんが知ってる卒業研究は、そらまあ、そういうものだっただろうとは思いますけど(と、ヒトゴトのように言ってみる^^;)。
大学教授から論文の英語チェックを頼まれ、「新しく分かったこと、何か少しでもあるんですか? ないなら論文なんて書かない方がいいと思いますけど」とのどまで出かかっておさえたなんて経験があります。あの教授が指導する卒業研究とか、どういうレベルなんだろうって思ってしまいました。
会社に入って、与えられた仕事の目的や手法を考え、終わった後こそ思う「こうすればよかった。この次は!」を逃さないこと。このあたりはノートにメモする習慣がついてます。自分のためにも機会を見てまとめてあり、何年か後に役に立つこと「も」ある。
毎回同じように見える仕事を嫌がる若者が多いのですが、必ず新しい何かがあって調べたり、新しい何かを組み込んだりして変化させているので私は面白いと思うんだけどそういうの理解されないなぁ。
OJTなどを通して思うのは難しかったり面倒そうなことでも前向きに対処する個人の資質の方が「つぶしがきく」ように感じています。
本日も続きなので、未知の分野のお話かな、とざくっと読み始めて、この言葉で釘付けになってしまいました。
この方のような高みには至っておりませんが、幾つか専門に近いものを持ちながらでないと、平成不況下に働き続けるのは困難だな、と思っておりましたので、読ませて頂いて幸運でした。
孫またろうを生む時に会社に母親の立場の社員が居ず、会社&社会の体制も法制も話にならないレベルでしたので、それまでの(大して輝かしくも無い)経歴を投げ捨てました。
しかーし。とりあえず産後プライドというものを捨て、働いてみた。そこから何とか細い道が続いた次第です。でもまだまだ勉強し続けないと、ですね。
これ、分かります。
「技能」と「技術」とは違う。
(もちろん技能を磨くこと高めることはすばらしいことです、とお断りをして。)
技術的なオリジナリティーを出そうとすると、センスというか総合力が必要になってきて、それって技能をぎゅーっと高めることとはちょっと違うと思います。
(余力と言うかムダというかノイズの部分というか...へんなたとえですが、それが必要かと。)
私の場合ですが。
ここ高専にいれば、あるテーマについて技能的なトレースはできるかもしれないけれど、
何を研究対象とするか、とか、不思議に思うことを発見するといった、
何もないところから自分で方向性を決める力をつける時間としては足らないかも~と感じました(あくまでも私の場合です)。一般教養ってムダかもしれないけど、物事をいろんな角度で見る力を貯める時間でもあると思います。
でも私のまわりでも優秀な高専「卒」の優秀な技術者たくさんいますし、
高専も、卒後や途中からの選択肢も多いですよね。
高専のその辺りのことについてはブログに書いてみようと思います。
ただもう一つ気になる点もあって、ここ数年入社して来る院卒の子たちですらも同様な傾向があると私は感じています。
そつなくはこなせるのですが、オリジナリティを生み出す力、突発に対する対応力、チャレンジ精神がやや劣る、これらをどうしようかというのが会社内の育成関連でよく議論されています。
> 新しく分かったこと、何か少しでもあるんですか?
はは(^^;;
英語直してっていっただけなのに、ココ突っ込まれたら立つ瀬ないよね~
とにかく実地に頭つかってやってみたらば、発見がないなんてことはないですもんね。一発思いつきなんてのは天才に任せておくとして、やっぱり凡人は日々改善というか、それができればいちおう仕事になりますね。
メタレベルの知恵をどれだけ抽出できているか、というのが能力の部分だとしたら、メンタルの部分も半分以上は効きそうですけどね…
我々まだここから、安穏としていられる年じゃないからあれこれやっていかないとね。
まず手を動かしてモノをつくれる高専という環境はそれはそれですばらしいし、とりわけまたろうにはぴったり合っていると思うんです。
でも、そこで終わるとなかなか一生の仕事とするのはつらいかも、というのもやや感じたので、やはり専攻科または大学への進学、さらには修士課程への進学なども考えてみてほしいと思いました。
aniaさんが辿ったのはなかなかユニークで実り多いコースでしたね(^^)
ただ、そこでとりあえず「手に職」就職しちゃうのはどうだろうか、ということを感じたわけなんです。その先はまたろう次第だけれども、やはり進学を考えてみてほしいと思ってます。
> 高専のその辺りのことについてはブログに書いてみようと思います。
ぜひ!! お願いします。
モチロン、院を出ればいいってもんじゃないですよね(笑)