オシアンOssian - ロマン主義に多大な影響を与えた叙事詩 -
たまたま、スコットランド国立美術館展の解説で、オシアンという言葉を発見した。この言葉は、昨年末にルーブル美術館で見たジロデ展でもキーワードで、オシアンを主題としたテーマの絵画も展示されていた(Fig.1)。「西洋美術史ハンドブック」のロマン主義の項でも、とオシアンとロマン主義の関係は指摘されていたので気になっていた。ちょっと調べると、「スコットランド 歴史を歩く」にオシアンが論じられていた。(手元にあった本だが、内容は全く覚えていなかったとは情けない。)第四章に一章にわたりオシアン事件として論じられている。引用要約すると、
かなり端折って引用要約してあるが、時代背景、どうしてマクファースンが「オシアン」を創作したかなど、詳しく説明し論じてある。岩波新書なので簡単に手に入る。興味をもたれたならば、読んでいただければと思う。
西洋絵画史では、新古典主義の時代の次に、ロマン主義の時代がある。しかし、ロマン主義は、そもそも古代への想いの発露が別の表現形式で現れたもののようである。新古典主義の契機となったのは、18世紀はじめのポンペイの遺跡の発掘である。その結果、ギリシア・ローマ時代への懐古が新古典主義になったわけであるが、その流れが、自国を失ったスコットランドがアイデンティティを求めて、さらに遠い古代に思いを馳せるロマンティシズムとして、「オシアン」は創作されたようである。そのとき歴史は変わった、という話。
追伸:オスカルの語源はここでした。
氏族の誇りを示すタータン柄のキルトや民族の英雄叙事詩「オシアン」など、古代に遡る「伝統」とされていたものの思いがけない起源。それは英・仏という大国の間に挟まれ、内部には分裂を抱えたこの小国の複雑な軌跡と深くかかわりを持っていた。聖堂や古城、渓谷などをめぐる旅から浮かび上がる、スコットランド国民再生の歴史。
目次
はじめに 風景のなかのスコットランド史
第1章 二つの国―ハイランドとロウランド
第2章 聖人の国から聖書の国へ
第3章 合邦あとさき―悲しい結婚式の日
第4章 オシアン事件
第5章 キルトとタータンの国
第6章 “知”に生きる人びと―「スコットランド啓蒙」の内側
第7章 “実”の世界をつくる人びと
たまたま、スコットランド国立美術館展の解説で、オシアンという言葉を発見した。この言葉は、昨年末にルーブル美術館で見たジロデ展でもキーワードで、オシアンを主題としたテーマの絵画も展示されていた(Fig.1)。「西洋美術史ハンドブック」のロマン主義の項でも、とオシアンとロマン主義の関係は指摘されていたので気になっていた。ちょっと調べると、「スコットランド 歴史を歩く」にオシアンが論じられていた。(手元にあった本だが、内容は全く覚えていなかったとは情けない。)第四章に一章にわたりオシアン事件として論じられている。引用要約すると、
「オシアン」とは。1762年、スコットランドのマクファースンがスコットランドのハイランドのゲール語の古代長編叙事詩を発見したとして、英訳を叙事詩「フィンガル」を、1年後には「テモラ」を刊行した。それらは、語り手である英雄の名をとって「オシアン」Ossianと呼ばれる。
これらの歌は、3世紀ごろスコットランド北部で活躍したフィンガル一族の物語詩。勇敢で気高い戦士は、ローマ人やスカンディナヴィアの異民族と次々戦い、最後に残った王子オシアンが高齢で失明した後も、息子のオスカルの許婚で竪琴の名手マルヴィーナに語り聞かせた回想の形をとる。雄大な自然、武装して男たちのあとを追う娘たち、闇の世界を漂う亡霊など新しいロマンティシズムの精神に満ちる。敵に対して寛容で高貴で、古代ケルト人の心性はかくやと思わせる長編叙事詩。
各国でセンセーションなる反響を巻き起こし、18世紀のうちにドイツ語、フランス語など9ヶ国語に翻訳された。子供にオスカルやマルヴィーナと名づけるのがはやり、その一人がスエーデンのオスカル1世。その名づけ親はナポレオンで、「オシアン」の熱狂的なファン。ジロデAnne-Louis Girodet-Triosonに「天国でナポレオンの将軍たちを迎えるオシアン」(Fig.1)、アングルに「オシアンの夢」(Fig.3)を描かせた。ナポレオンが英雄熱にうかされていなかったら、エジプト遠征も実現しなかったという想像する作家もいる。オスカー・ワイルドもオスカー・フィンガル・ワイルドと名づけられた。ゲーテは「若きヴェルテルの悩み」で、「オシアン」の詩を使っている。
Fig.3
INGRES, Jean-Auguste-Dominique
(b. 1780, Montauban, d. 1867, Paris)
The Dream of Ossian
1813
Oil on canvas, 348 x 275 cm
Musée Ingres, Montauban
(図面は、http://www.wga.hu/へのリンク、クリックすると絵の解説有り)
イギリスでは、「オシアン」が本物の古詩か、とりわけ長編の叙事詩であるか、それともマクファースンの創作か、それとも断片的な古詩をつなぎ合わせたものではないかと当初より疑われており、1775年にイングランド文壇の大御所サミュエル・ジョンソン博士により、贋作だと断定された。いまでも、スコットランドでもあまり好意的には評価されていない。
現在の研究では、2つの主な物語をプロットに、別の3つのエピソードを利用し、その上にロマンティックな挿話でみたした、よくいっても「編訳」といったところ。
1707年にイングランドに合邦したスコットランドのアイデンティティの発揮という社会的背景でオシアンの物語は「編訳」されたようである。
かなり端折って引用要約してあるが、時代背景、どうしてマクファースンが「オシアン」を創作したかなど、詳しく説明し論じてある。岩波新書なので簡単に手に入る。興味をもたれたならば、読んでいただければと思う。
西洋絵画史では、新古典主義の時代の次に、ロマン主義の時代がある。しかし、ロマン主義は、そもそも古代への想いの発露が別の表現形式で現れたもののようである。新古典主義の契機となったのは、18世紀はじめのポンペイの遺跡の発掘である。その結果、ギリシア・ローマ時代への懐古が新古典主義になったわけであるが、その流れが、自国を失ったスコットランドがアイデンティティを求めて、さらに遠い古代に思いを馳せるロマンティシズムとして、「オシアン」は創作されたようである。そのとき歴史は変わった、という話。
追伸:オスカルの語源はここでした。
 | スコットランド 歴史を歩く岩波書店このアイテムの詳細を見る |
氏族の誇りを示すタータン柄のキルトや民族の英雄叙事詩「オシアン」など、古代に遡る「伝統」とされていたものの思いがけない起源。それは英・仏という大国の間に挟まれ、内部には分裂を抱えたこの小国の複雑な軌跡と深くかかわりを持っていた。聖堂や古城、渓谷などをめぐる旅から浮かび上がる、スコットランド国民再生の歴史。
目次
はじめに 風景のなかのスコットランド史
第1章 二つの国―ハイランドとロウランド
第2章 聖人の国から聖書の国へ
第3章 合邦あとさき―悲しい結婚式の日
第4章 オシアン事件
第5章 キルトとタータンの国
第6章 “知”に生きる人びと―「スコットランド啓蒙」の内側
第7章 “実”の世界をつくる人びと
 | 西洋美術史ハンドブック新書館このアイテムの詳細を見る |


















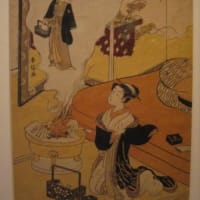
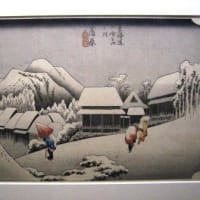


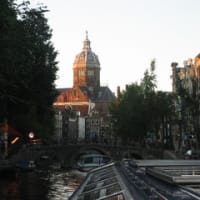




この話題に付いて、貴サイトの当該の頁を読むだけで要点が摑めてしまいそう。
「オシアン」は贋作なのだとしても、この叙事詩がある時期まで相当程度に影響を持ったという事実は重いような気がします。
しかも、見方によっては世界史(ヨーロッパ史)にも影響を与えた…あるいは、情熱や意思に裏打ちを与えていたとも言えるようで、世界史の舞台裏の深さを感じます。
逆TB、ありがとう。