◎青木茂雄氏評『日本人はいつから働きすぎになったのか』
昨一六日未明、歴史民俗学研究会でご一緒している青木茂雄氏から、拙著『日本人はいつから働きすぎになったのか』の書評が送られてきた。
「勤勉」は、観念か、イデオロギーか、エートスか、といった論争点の摘示を含む、本格的にして厳しい批評である。この論争点については、いずれ詳しく論じたいと思うし、また、青木氏とも、ジックリ議論してみたいと思う。とりあえず以下に、青木氏の書評の全文を、そのまま掲載させていただくことにする。
礫川全次著『日本人はいつから働きすぎになったのか』を読んで 青木茂雄
畏友礫川氏から、新しい本を構想しているということを聞いたのは半年ほど前になるだろうか。同氏が昨年書いた『日本保守思想のアポリア』について私は、短い感想を書いただけで、本格的な批評文がまだ宿題として残されていると感じていたところである。当然前著の延長線上に企画されているものとばかり思っていたが、数カ月前に聞くと、まったく別のものだと言う。正直、戸惑ったというより、肩透かしを食ったというのが、それを聞いたときの率直な感想であった‥。
前著の本格的な批評文をと、鈴木安蔵を始めとする明治憲法に関する研究書を幾冊か古書店で買い求め、シュタインの数少ない翻訳書も何冊か入手し、ロェスラーの英文の原文(Text of the Meiji Constitution acompanied by Herman Roeslers Commentaries)まで上智大学図書館から借りてコピーをして待機していたところであった。
定年退職して基本的に自由の身でありながら、いざ何かまとまったものを研究して書こうとなると、いかんとも大儀である。最近世情がやたらとかまびすしく、身も心もそれに砕いていると無情にも時は過ぎる。それに加齢のせいか、最近時間の経つのが滅法早い。「勤勉」たろうとするが心と身体がついていかない。もっともこれは今に始まったものではなく、物ごころついて以来の自分の習性らしい。そういわけで、とりかかる準備をしている間に数カ月過ぎ、1年が過ぎてしまった。そうしている間に礫川氏から新しい著書が出た。
さて、前著『アポリア』は、「國體」という“観念”(最初は言葉)がどのようにして創案され、明治・大正・昭和の日本人の間にどのように流布されていったかをスリリングな筆致で描いていった好著であるが、近著『日本人はいつから働きすぎになったのか』(以下『働き過ぎ』と略)も一読(二読以上)してみると“勤勉”(表現される言葉は様々であるが)という観念の形成史であることがわかる。その意味でこの2著は近代日本における“観念”の形成史として礫川史学の表裏をなすものと、私は見ている。
『働き過ぎ』の論の骨格は、A江戸中期に「勤勉のエートス」が一部で(浄土真宗門徒の一部に)成立していた。B武士階級の「勤勉のエートス」が明治近代国家の形成に大きな役割を果たした。C明治政権は学校教育を通して「勤勉」のイデオロギーを国民に注入しようとしたが、D「勤勉のエートス」として一般国民の間に広まっていくのは明治30年代以降である。E「勤勉のエートス」は戦時下に「産業戦士」として結実し、それは現在に至るまで持続している。(もとよりこのまとめは筆者が便宜的に行ったものであって正しくはぜひ著書を読んでいただきたい。)
ここで注目したいのはDである。「勤勉のエートス」の定着の時期を明治30年代としたのは、本書の中ではひとつの仮説(仮説7、本書は14の仮説を提示している)とされている。この時期は言うまでもなく、日清戦争から日露戦争へかけての戦間期であり、国内世論が対露強硬派によって主導され、ナショナリズムが異様に盛り上がっていく時期である。同時に学校教育においても小学校の就学率が高まり、小学校教科書も国定化され、祝祭日における「勅語奉読」の儀式も身も心も定着し、それを通じて「國體」イデオロギーが国民の間に広がって行く時期である。そういう時期に「勤勉のエートス」の定着の時期が重なる、ということである。
著者はヴェーバーの説をもとに「勤勉のエートス」という概念を使用しているが、私はむしろこの時期においては“勤勉のイデオロギー”と呼ぶべきではないか、と思っている。そして、これもまったくの仮説なのだが、それこそが「國體」イデオロギーの実相ではなかったのか、と。そうとでも考えない限り、その「勤勉」が戦中の産業戦士の「錬成」へといとも簡単に転化していったことの理由がわからない。そしてそれが「一番美しく」感じられたことの意味もわからない。
そういう観点から本書の第6章「明治時代に日本人は変貌した」の内容を少しく検討してみたい。この章では3つの「仮説」が提示されている。
(仮説5)「明治20年代以降、少なからぬ日本人が、二宮尊徳の勤勉思想から、勤勉のエートスを学び、勤勉化していった。」
(仮説6)「浄土真宗門徒における勤労のエートスは、日本の近代化に積極的な役割を果たした。」
(仮説7)「明治30年代に入ると、日本の農民の多くが勤勉化した。」
著者も述べているように、「勤勉化した」と判定するには資料があまりにも断片的であり、また仮に社会経済史的な統計資料が完備して、総労働時間の推移の算出が可能となっていたにしても、ここで問題とされるべきは“意味関連”であり、必ずしも“量”ではない。
そう考えてみると、國體イデオロギーによる教化を目的として行われている修身教育の中でとりあげられた二宮尊徳の勤勉思想(仮説5)と真宗門徒によるあくまでも自主的な勤勉化(仮説6)とは次元をまったく異にしているのではないか、とまずは思われる。この両者の連関性について著者は直接の言及は避けているが、“教化”が“自主性”に転化するためには媒介する何かが必要である。何がこれを媒介したか。そして、私の用語で言えばいかに“勤勉のイデオロギー”に転化していったか。著者はむしろ仮説6を後続に直接につなげているように見えるのだが。
最後に、“いかにして「勤勉」を超えるか”という著者の最後の問いかけに対して。私は、その課題は“勤勉のイデオロギー”(換言すれば「勤勉」の全体的な意味付け)を対象化していくことによって果たされ得る、と考えている。対象化の素材はこの自分(たち)自身である。
エートスは言わば第2の天性である。しかし、イデオロギーは徹頭徹尾、説明原理である。私がせめてもの救いと考えているのは、日本人の「勤勉」はまだイデオロギーであってエートスとはなりえていないのではないか、ということである。これが私の最後の「仮説」である。
*このブログの人気記事 2014・9・17


















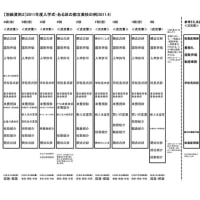
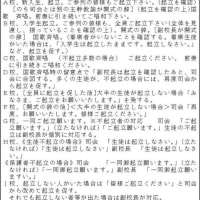








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます