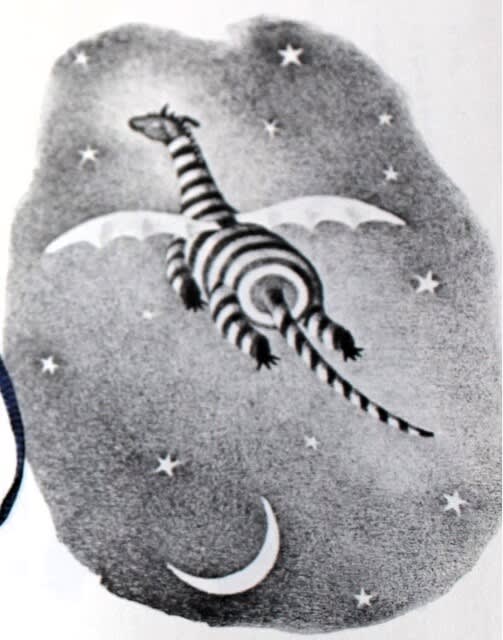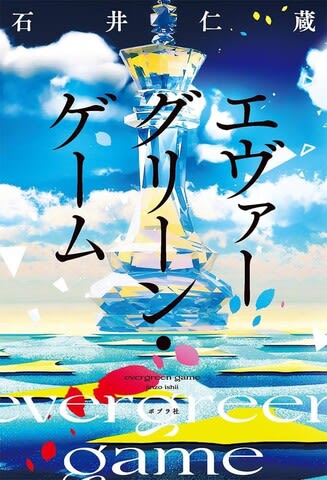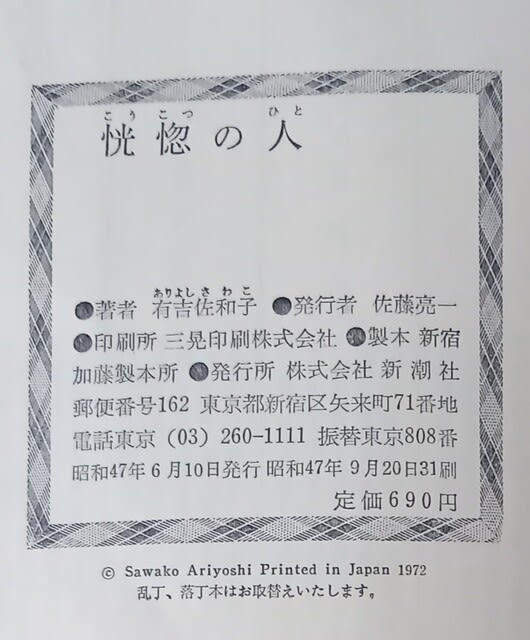「教師が教えない人になれる時間」。
教育の専門書なのに、書名からして面白い。
「教師」という言葉には、「教える人」の意味がある。
その「教師」が「教えない人」になれる、とはどういう意味?
教えることをサボって得しようということか?
…なんて考える人がいてもおかしくはないだろう。
でも、その意味が分かる人は分かるはずだ。
意味が分かる教師は、きっと心ある教師だろうと思う。
ちなみに、帯には次のような方におすすめと書いてある。

本書は、表紙に「15分間の『朝鑑賞』が子どもの自己肯定感を育む」とある。
どういうことかというと、月に1,2度でいいから、15分間の朝学習の時間に、学級で美術作品を鑑賞することによって、子どもたちの力も、教師の力もつけていこうということなのだ。
そのために、「対話型鑑賞」の実施と、教師がファシリテーターに徹するということが求められる。
子どもたちの表現力や思考力は、教師が教え込んでも育つものではない。
では、教師にどのような配慮や役割が求められるのか。
その大切なものが、本書の実践の中に見ることができる。
著者の青木善治氏は、現在滋賀大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)教授である。
その前には、校長など新潟県の公立小学校の経験もある方である。
私も、かつて十数年前に一緒に勤めた経験がある。
物腰も頭脳も柔らかさを感じさせる人だった。
図画工作や美術を専門としていたが、当時よく実践論文などを書いていた方であった。
そのせいか、本書はかたい内容ではなく読みやすく分かりやすいのは、いかにも氏らしい。
「質問を投げかけてから、10秒は待つ」
「否定する言葉を使わない」
「オウム返しや言い換えをする(『〇〇ということですね』など)」
「事実と意見を分ける」
など、教師が「教えない人になる」ために大事なポイントが具体的である。
朝の短い時間の実践によって、
子どもたちに自分の思いを自由に表現する力をつける
みとめ合う力をつける
自己肯定感をつける
などができるということ。
そして何より教師の「子どもを支える力」「子どもの力を引き出す力」が育つことが期待できる。
すでに現職から離れて遠くなってしまったが、読みやすくいい本だと思った。