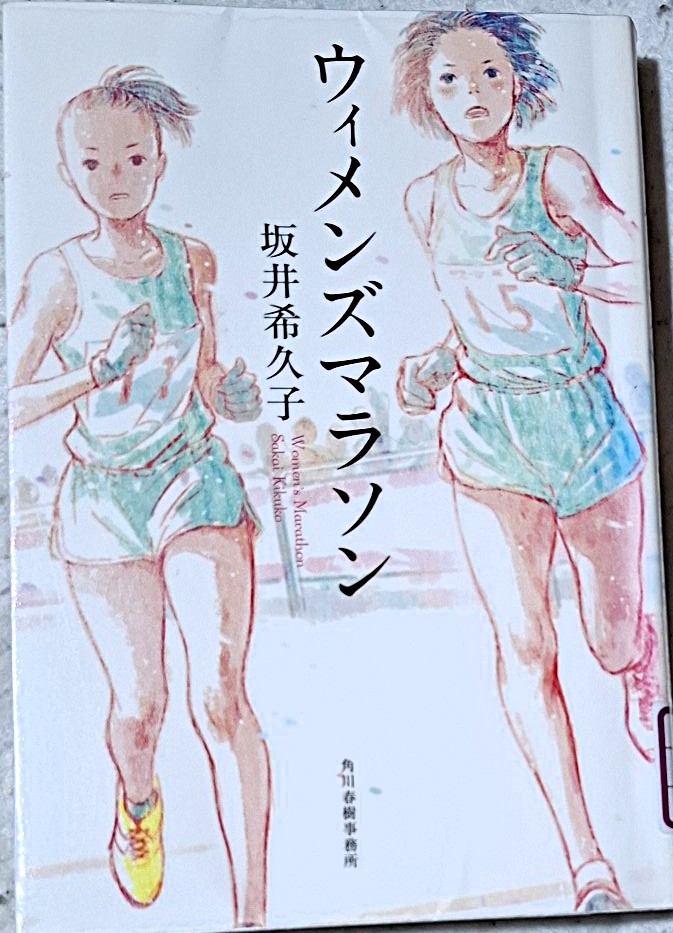「絶対解答可能な理不尽すぎる謎」
魅かれるよね、こんなタイトル見ると。
どんなミステリーなんだろうと思いながら読んでみた。
内容は、6編の連作短編集。
- 小説家 高沢のりお氏の災難
- 映像作家 深沢隆哉氏の誘引
- 公務員 園部芳明氏の困惑
- 評論家 鷺宮聡氏の選択
- 編集者 小野寺司郎氏の失策
- デザイナー 倉崎修一氏の疑惑
どんな事件が起こるのだろう、と読み進んでいったが、すべて人が死なないミステリー。
殺人事件ぽいのは、最初の「小説家 高沢のりお氏の災難」の話だけ。
その話では、密室と残されたダイイングメッセージ(死ななかったけど)の謎を解いていた。
あとの話は、それぞれ事件が起こるのではなく、解かなければならない謎が生じ、それを登場する人物たちが解いていく、というものだ。
ストーリーには、ちょっと私には無理があるぞ、と感じるものがあったが、それぞれの謎解きには、いろいろと専門的な知識を有していなければ解けないものばかりだった。
「映像作家 深沢隆哉氏の誘引」では、暗証番号を解くための映像編集の知識。
「公務員 園部芳明氏の困惑」では、死んでしまった代わりを探すための熱帯魚の知識。
「評論家 鷺宮聡氏の選択」では、プレゼントするためのシャンパンやワインの知識。
「編集者 小野寺司郎氏の失策」では、美しく咲かせるためのバラやその手入れの知識。
それぞれの謎が解かれても、あまりにも専門的で細かい知識が豊富に披露されるので、興味がない人には、何が何やらさっぱりピンとこない展開になる。
ちっとも理詰めに感じない。
普通ミステリーは、誰でもわかる理詰めの謎解きが面白いはずなのだが。
そうか。
すっきりしないそのあたりがきっと、タイトルにあった「理不尽」さに当たるのだな、きっと。
そうではあっても、いずれにしても非常に軽いミステリーとして楽しむことができた。
書かれてあるそれぞれの専門的な知識なんて、「トリビア」ものだったし。
私には、こんな軽いミステリーは初めて読んだように思えて新鮮だったから、それなりに面白かった。
著者の未須本有生氏は、巻末のプロフィールによると、
1963年、長崎県生まれ。
東京大学工学部航空学科卒業後、大手メーカーで航空機の設計に携わる。
1997年より、フリーのデザイナー。
2014年、『推定脅威』で、第21回松本清張賞を受賞。
へえ~、この人も東京大学工学部卒なのか。
以前読んだ「松岡まどか、起業します」を書いた安野貴博氏(先日の参院選挙で当選した)も、東京大学工学部卒だったし、あの本はAIを扱っていたっけ。
工学部出身であっても、2人とも専門的知識が豊富な面白い小説を書いている。
才能豊かなのだなあと感心したよ。
なお、当ブログ「ON MY WAY」は、次のところに引っ越し作業を終えました。
https://s50foxonmyway.hatenablog.com/
当分の間、ここと同じ記事を載せていますが、今後そちらの方を見ていただければと思います。