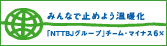| 紅梅 |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
【一口紹介】
◆内容紹介◆
2005年春、癌が発見され、膵臓全摘の手術を受けた吉村昭の、1年半後の壮絶な死までを、作家でもある妻が硬質で冷静な筆で作品化。
◆内容(「BOOK」データベースより)◆
二〇〇五年二月に舌癌の放射線治療を受けてから一年後、よもやの膵臓癌告知。
全摘手術のあと、夫は「いい死に方はないかな」とつぶやくようになった。
退院後は夫婦水入らずの平穏な日々が訪れるも、癌は転移し、夫は自らの死が近づいていることを強く意識する。
一方で締め切りを抱え満足に看病ができない妻は、小説を書く女なんて最低だ、と自分を責める。
そしてある晩自宅のベッドで、夫は突然思いもよらない行動を起こす―一年半にわたる吉村氏の闘病と死を、妻と作家両方の目から見つめ、全身全霊をこめて純文学に昇華させた衝撃作。
◆担当編集者から一言◆
「『文學界』にこの作品が掲載されるときは、心配で夜も眠れなかった」とおっしゃる津村さん。
本作は雑誌発売と同時に大きな反響を呼び、津村さんの不安を吹き飛ばす賞賛の声が相次ぎました。
2005年2月に舌癌と診断された吉村昭氏。
抗がん剤治療や免疫療法を試みる闘病生活、転移から死に至るまでの日々を、妻と作家両方の目から、津村さんが冷静にかつ力強く描ききりました。
5年を経て小説へと昇華された傑作です。
【読んだ理由】
新聞の書評を読んで。
【印象に残った一行】
「針を舌に刺し、膵臓と十二指腸と胃の半分を切除し、今度はカテーテルを静脈から中心静脈まで挿入する手術をする。これほどひどい目に遭わなくてはならない夫は、どんな悪いことをしたというのだろう」
「育子が夫の背中をさすっている時に、残る力をしぼって体を反転させたのは、育子を拒否したのだ、と思う。情の薄い妻に絶望して死んだのである。育子はこの責めを、死ぬまで背負ってゆくのだ」」
【コメント】
素晴らしい夫婦愛だ。