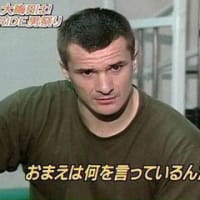カイジ Bet13 「怪物」 ○!
クリスマスナイトに何てもん
放送しやがるんだっ・・・
ケチをつけるのだけど、やっぱし
カイジの声はハギーと完全にシンクロしないなと
今回の悲痛な叫びのシーンで思った。
アカギの飄々とした語りに慣れすぎたからか。
福本漫画のキャラクタってのは抽象度が高い
(下手とはあえていわないw)から
あの独特な演出の「ざわ・・・」とか
「ぐにゃ~」ってのが許容できるのだと思う。
「自分の特性」をよく考えて表現に活かす態度は
素晴らしいものだ。
そして今回はその「演出」のほぼ独壇場の回。
何の心理戦もないのにこの緊張感はある種
福本節の真価をこれでもかと見せつけるための
披露会(それも最低の趣味の)といえるのでは。
まあ、「自分との戦い」は究極の「心理戦」と
言えなくもないけど―
スケッチブック ~full color's~
第13話 「ひとりぼっちの美術部」と
まとめ ◎
ひとりぼっちだけど、そうじゃない気がする
あたりまえのことだけどこの「スケッチブック」
っていうのは必ずしも「フルカラー」ではない
漫画原作だったっていうことがある。
当作品におけるような「日常」を描くようなもの
でも、色が付いてアニメーションする時点で
原作とは違う道をあるきだすことは避けられない
わけで、結論から言うとそのあゆみは大変に
よろしかったと言えたのではなかろうか。
それは「原作」に寄りかかっただけの作品などと
比べて何と幸せな関係であることか。
はじめのほうは空の「ひとり語り」が多かった
このスケッチブックの世界も、友達ができ
先輩を知り、知人が増えていくにつれ
だんだんといろんな人(あるいは猫)の
コトバがあふれる賑やかな世界になっていき
ついには自分の名前でちゃんと自己紹介が
できるようになったという、小さな一歩で
大きな一歩。
そしてその登場人物たちを包む世界は
ぼくたち日本人の「泣かせどころ」(風景)を
丁寧に描くことによって驚くほどの
「安定した世界」を生みだしていたと思う。
こういう「住んでみたい」って思わせる世界を
描くことに関してはハルフィルムは無二だ。
最後、各登場人物を空が素描するシーンは
ベタだけどこれしかないって感じた。
脚本・監督には感謝したいぐらいだ。
そして滅多に色をつけない空があたかも血を
かよわせるようにそれに色をいれる
「この世界はなかなかいいものだ」
っていっているかのように。
げんしけん2 第12話
その先にあるもの…と総括 ◎
「げんしけん」って作品にはいつも
「二面性」あるいは「分裂性」ってのが
ついてまわっていたなあと思い出す。
メンバーはたいがいオタクだけど
ぜんぜんカタギの咲ちゃんがいたり
オタク(自分)嫌いの荻ちんがいたり。
エロゲーだのエロ同人だのやってるくせに
生身の男女関係にはてんで疎かったり。
(高坂は例外)
「くじアン」っていういかにも表層的な
「萌えアニメ」が劇中作のくせに
けっこう生々しい話題や、「笹原の家のゴミ袋」とか
想像力を働かせるような細かい描写があったり。
妄想世界と「現実」をいったりきたりだったり。
まさしくあんばーらんすな世界。
そういうのはまことにいつでもいらんことを
考えてる「オタク」らしくて、しばしばそれが
自分のことのように考えさせられ、苦笑いを
うかべたものだった(え、私だけ?)
「同人活動」や「就職活動」なんかを話しの
軸にまわしていたけど、そのあたりの分裂性のことが
積極的に関わっていて、しかもそれでいて
エンターテインメント分も失っていないのだから
さすがは「現代視覚文化研究」といえよう。
結局、このげんしけんは「オタク」っていう
レッテルの張りやすい人種をつかって
いろいろ笑ったり悩んだり泣いたり恋をしたり
する「ナマの人間」を描き出すことに成功して
いたんだなあと思った。
そういう方法論は決して目新しいものでは
ないかもしれないけれど、ただのパロディでは
なく、光るところのあるオリジナリティを
げんしけんは描けていたと感じた。
クリスマスナイトに何てもん
放送しやがるんだっ・・・
ケチをつけるのだけど、やっぱし
カイジの声はハギーと完全にシンクロしないなと
今回の悲痛な叫びのシーンで思った。
アカギの飄々とした語りに慣れすぎたからか。
福本漫画のキャラクタってのは抽象度が高い
(下手とはあえていわないw)から
あの独特な演出の「ざわ・・・」とか
「ぐにゃ~」ってのが許容できるのだと思う。
「自分の特性」をよく考えて表現に活かす態度は
素晴らしいものだ。
そして今回はその「演出」のほぼ独壇場の回。
何の心理戦もないのにこの緊張感はある種
福本節の真価をこれでもかと見せつけるための
披露会(それも最低の趣味の)といえるのでは。
まあ、「自分との戦い」は究極の「心理戦」と
言えなくもないけど―
スケッチブック ~full color's~
第13話 「ひとりぼっちの美術部」と
まとめ ◎
ひとりぼっちだけど、そうじゃない気がする
あたりまえのことだけどこの「スケッチブック」
っていうのは必ずしも「フルカラー」ではない
漫画原作だったっていうことがある。
当作品におけるような「日常」を描くようなもの
でも、色が付いてアニメーションする時点で
原作とは違う道をあるきだすことは避けられない
わけで、結論から言うとそのあゆみは大変に
よろしかったと言えたのではなかろうか。
それは「原作」に寄りかかっただけの作品などと
比べて何と幸せな関係であることか。
はじめのほうは空の「ひとり語り」が多かった
このスケッチブックの世界も、友達ができ
先輩を知り、知人が増えていくにつれ
だんだんといろんな人(あるいは猫)の
コトバがあふれる賑やかな世界になっていき
ついには自分の名前でちゃんと自己紹介が
できるようになったという、小さな一歩で
大きな一歩。
そしてその登場人物たちを包む世界は
ぼくたち日本人の「泣かせどころ」(風景)を
丁寧に描くことによって驚くほどの
「安定した世界」を生みだしていたと思う。
こういう「住んでみたい」って思わせる世界を
描くことに関してはハルフィルムは無二だ。
最後、各登場人物を空が素描するシーンは
ベタだけどこれしかないって感じた。
脚本・監督には感謝したいぐらいだ。
そして滅多に色をつけない空があたかも血を
かよわせるようにそれに色をいれる
「この世界はなかなかいいものだ」
っていっているかのように。
げんしけん2 第12話
その先にあるもの…と総括 ◎
「げんしけん」って作品にはいつも
「二面性」あるいは「分裂性」ってのが
ついてまわっていたなあと思い出す。
メンバーはたいがいオタクだけど
ぜんぜんカタギの咲ちゃんがいたり
オタク(自分)嫌いの荻ちんがいたり。
エロゲーだのエロ同人だのやってるくせに
生身の男女関係にはてんで疎かったり。
(高坂は例外)
「くじアン」っていういかにも表層的な
「萌えアニメ」が劇中作のくせに
けっこう生々しい話題や、「笹原の家のゴミ袋」とか
想像力を働かせるような細かい描写があったり。
妄想世界と「現実」をいったりきたりだったり。
まさしくあんばーらんすな世界。
そういうのはまことにいつでもいらんことを
考えてる「オタク」らしくて、しばしばそれが
自分のことのように考えさせられ、苦笑いを
うかべたものだった(え、私だけ?)
「同人活動」や「就職活動」なんかを話しの
軸にまわしていたけど、そのあたりの分裂性のことが
積極的に関わっていて、しかもそれでいて
エンターテインメント分も失っていないのだから
さすがは「現代視覚文化研究」といえよう。
結局、このげんしけんは「オタク」っていう
レッテルの張りやすい人種をつかって
いろいろ笑ったり悩んだり泣いたり恋をしたり
する「ナマの人間」を描き出すことに成功して
いたんだなあと思った。
そういう方法論は決して目新しいものでは
ないかもしれないけれど、ただのパロディでは
なく、光るところのあるオリジナリティを
げんしけんは描けていたと感じた。