
ヤマユリの甘く濃厚ときとして きみのようだと俯きていう
■
大阪から滋賀に移り住みなんと鄙びたところかと思っては
みたが、何のことはないこんなに素晴らしい自然と歴史に
包まれた『美まし国、美まし湖』(故友岡和雄の言葉、存
命であれば今年で70歳?)なのだとあらためてその豊饒
さに驚嘆する。
沙沙貴神社
安土周辺の地理を述べたい。近江は〈回廊の国〉とい
われ、都から東国に向かう東海道・東山道・北陸道の
いずれもが近江国を道る。一方、一本の水路が、瀬戸
内・大坂湾から淀川を潮上し琵琶湖・近江国に連した。
東山道が近江から美濃に入る関ケ原ではよく雪が降り、
冬の寒風は伊吹おろしとなり濃尾平野に吹きつけた。
近江の北半分は北陸道に連なる〈裏日本型気候〉の豪
雪地帯で、南半分は〈瀬戸内気候〉である。観音寺山
塊がこの二つの気候帯を分け、この山塊は安上山に連
なる。つまり安土は、山と湖の接点で、大きくは二つ
の気候帯の接点にあった。現在では埋め立てが進み、
昔の面影はないが、安土には「中の湖・伊庭湖・豊浦
湖・常楽寺湖・浅小井湖・白王湖」と呼ばれる琵琶湖
最大の内周群があった。内湖の中に抱えられた安土は、
水陸交通の要衝となる可能性を最初から秘めていた。
この内周群は魚の産卵場所で、周囲には多くの縄文遺
跡があった。
■
安土城下町の形成された常楽寺・下豊浦・上豊浦の地
域は、蒲生郡ではただ1ヵ所〈条理地割りのない世界
〉で、水利の使が悪く、水田ではなく条里制の適応さ
れない〈畑地〉とした。江戸時代にはここに藍や綿、
明治時代以降はネギや人参、桑が植えられた。ここに
常楽寺古墳群や全長162メートルの瓢箪山古墳があ
る。これらの古墳の多くは朝鮮半島系やその類似様式
のもので、弥生文化とは別系統の、非水田稲作系文化
の繁栄を物語っている。この地には「大彦命」の一族
で蒲生郡や神埼郡の大領となった古代豪族「狭狭城山
君」に由来する「沙沙貴神社」が立つ。
■
「狭狭城山君」が若狭の国造「膳臣」と同族なので、
古墳の主は海人族の安曇族だとした。対岸の西近江に
安曇族の活動拠点「安曇川」があり、彼らがこちらの
岸にも上陸したのは自然である。「狭狭城山君」の名
前から「山部」「山守部」との関連が考えられる。そ
れゆえ、この地は「海の民・山の民」の活躍する世界
だった。小島道裕の作った安土城下町の復元図「安土
城下跡要脱」には「景清遊」の南、沙沙貴神社の境内
に接して「鉄砲町」「鍋屋町」があり、少し離れて「
青屋」がある。
■
いつまで遡るかわからないが、神社周辺にはこのよう
な職人たちがある。いつまという自然環境を背景に、
常楽寺の村は〈非農業的要素の強い村〉として中世以
降も存続した。それゆえ、沙沙貴神社の神官出身の国
人領主、木村次郎左衛門尉は、古代の安曇族や「海の
民・山の民」の系譜を引くと思われる(中略)この神
社は、佐々木荘の近江源氏である佐々木氏が近江守護
となった折、氏神化したという。沙沙貴神社の西北の
「慈恵寺」もまた佐々木氏の〈菩提寺〉。沙沙貴神社
の社殿は、守護佐々木氏の氏神化以来、南面化したと
考えられよう。近江の守護佐々木氏は、東山道を挟ん
で神社の東南方向の小脇や観音寺城を根拠地とした。
■
佐々木氏がこの神社を氏神化した時、社殿は南面化し、
常楽寺港との関係は切れたと考えられよう(中略)永
正11(1514)年と天文23(1554)年の年
号のある沙沙貴神社の二つの棟札に「造立奉行」三人、
「修理奉行」二人の後に、「惣官・大神主・大工・同
棟梁」が並び、この「惣官」に「木村左近太夫古銅」
「木村左近太夫高重」とあることを明らかにした。つ
まり木村次郎左衛門尉は代々沙沙貴神社の「惣官」だ
った。「天皇」に対する「院」のように、「惣斜」は
神官の「大神主」に対して神社全体の支配を司ってい
た。沙沙貴神社が職能民を抱えていたとすれば、「惣
官」が彼らを統轄していたと考えられよう。
■
信長上洛後の湖東平野
永禄11年(1568)、信長は上洛に際し、浅井の
勢力圏を愛知川まで、東山道を南下した。一方、六角
承禎・義治親子は、愛知川以西の観音寺城・箕作城・
和田山城など18城に阻止線を築き、信長の行く手を
遮った。信長が9月12日に箕作城を襲撃し、落城さ
せると、六角氏は観音寺城を棄てて伊賀に逃亡した。
翌日信長は観音寺城に本陣を移し、降参者からは人質
を取り、逃散百姓には還往をすすめ、神社仏閣や万民
を安堵し、事実上の領主支配を始めた。22日には
、
かつて足利義晴が「景清遊」に近い桑実寺を御所とし
た故事を踏まえ、義昭を安土の桑実寺に招いた。この
地は安全な味方の地だった。この後、信長は上洛の途
中たびたび常楽寺に立ち寄り、相撲見物などを繰り返
した。信長は上洛前に、琵琶湖の水運管理権を握る湘
南の蘆浦観音寺に接触を試みたが、同様なことを常楽
寺の木村氏にも行なったと思われる。
■
信長は、観音寺城をはじめ、六角氏の直轄地を没収し、
近江の国を事実上制覇しても、支配の正統性までは入
手できなかったのである。10月畿内を平定し、義昭
が将軍になった後、近江で信長が入手したものは大津・
草津の代官職のみである。このことは、当時の物流の
中心地が琵琶湖と京都を結ぶ坂本だったので、経済的
には意味が小さかったが、軍事的には、京都から東山
道・東海道・北陸道への出入口を確保した点に意味が
あった。
■ 「平安楽土」/信長の野望
「平安楽土」/信長の野望
一揆一斉蜂起後の近江 元亀元年(1570)四月の
越前遠征失敗の後、近江全体は鼎が沸く戦乱の時代と
なり、一揆や反乱が起こった。信長はそれを鎮圧し、
やっとのことで千草峠を越えて尾張に帰るが、直前の
五月には宿将を近江各地に配置した。越前遠征前の三
月に森可成を坂本の南「宇佐山城」(志賀郡、現大津
市)に置いたのが初めで、佐久間信盛を東山道と景清
道との分岐点近くの「永原城」(野洲郡、現野洲市)
に、蒲生郡では柴田勝家を「東山道」と「浄厳院道・
八風街道」の交差する武佐「長光寺城」に、中川重政
を琵琶湖水運をにらむ「安土城」に置いた。「東山道
」を通らず領国と京都を結ぶ道を確保することが信長
の至上命令だった。そのため、「ハ風街道」と琵琶湖
への出日常楽寺港の確保が必要だった。この当時、六
角氏は伊賀・甲賀を根拠に「東海道」から北上を狙っ
ており、一方、愛知川以北は浅井氏の勢力圈だった。
観音寺城のある湖東地域は、永禄十一年の上洛の際、
六角氏と戦った場所で、六角氏からの没収地もあり、
各地の国人領主から人質を取っていたので、近江では
大津・草津を除けば、信長の強固な支配地域だった。
それゆえ湖東地域の三城への諸将配置は、京都へのア
クセス、港町常楽寺を通じての琵琶湖の水運、伊勢か
ら琵琶湖に通じる「浄厳院道・ハ風街道」や、両街道
以西の「東山道」「景清道」の確保が目的だった。
■
永原の永原氏は永禄十一年の信長上洛前から信長と連
絡のある国人領主で、この時佐久間氏の寄子になった。
日野の領主蒲生氏は柴田氏の寄子に、常楽寺の領主木
村氏は中川重政の寄子になったと思われる。同年六月
に織田軍が野洲川表で六角軍を破り、対浅井戦も有利
に展開すると、信長は東山道を確保し、木下秀吉を「
横山城」(坂田郡、現長浜市)に、元亀二年二月には
丹羽長秀を「佐和山城」(犬上郡、現彦根市)に配置
し、琵琶湖両岸一帯への宿将配置を完成した。木下・
丹羽両氏の領地は浅井の領国を切り取って形成された
ので、これ以降反乱地域を鎮圧・征服すれば、そこは
各武将の領地になる〈切り取り自由〉体制となった。
第10章 安土市令-大坂並体制の克服
安野眞幸著『楽市論-初期信長の流通政策』
■
『楽市』を考えることで、「琵琶湖/滋賀」の前者として
の世界遺産としての内実の深耕と後者の「政治/社会」の
現在的な内実、分かり安く言えば、広域観光産業の内実の
深耕(MB『富貴桜と狼煙台』の対平安京としてのテーマ・
パーク「戦国絵巻」)にあり、挫けかけたがなんとかたど
り着けた。信長の「楽市楽座」とは、武家集団による専制
体制下での(1)関所の撤廃、座の廃止(フェーデに対抗
するフリーデ)による経済の発展と(2)政教分離による
中世からの脱却、(3)門閥、本籍に拘らない人材登用等
にあり、手段/「天下布武」から目的/「平安楽土」にい
たる道筋を確認した。現在の日本政治課題の地方分権推進
は、肥大化した官僚主義のからの脱却であること。そして、
わが国における『楽市楽座』の内実の模索の契機が、近著
『楽市論-初期信長の流通政策』の偶然的な出逢いであっ
たことに改めて感謝したい。
■
ヤマユリ(山百合、学名:Lilium auratum)とはユリ科ユリ
属の球根植物。日本特産のユリ。草丈は1~1.5m。花期は
7~8月頃。花は、花弁が外に弧を描きながら広がって、1
~10個程度を咲かせる。その重みで全体が傾くほど。花の
色は白色で花弁の内側中心には黄色の筋、紅色の斑点があ
る。花の香りは日本自生の花の中では甘く濃厚でとても強
い。発芽から開花までには少なくとも5年以上かかり、風
貌が豪華で華麗であることから、『ユリの王様』と呼ばれ
る。多糖類の一種であるグルコマンナン(コンニャクにも
多く含まれる)を多量に含み、縄文時代には食用にされた。
■
朝、ユリの薫りを巡り意見がわかれた。濃厚すぎるのも嫌
われるということでふたりとも一致する。1873年、ウィー
ン万博で日本の他のユリと共に紹介され、ヨーロッパで注
目を浴びる。神奈川県の県の花に指定されている大輪の花
「ヤマユリ」。花言葉は「純潔」「荘厳」。
■















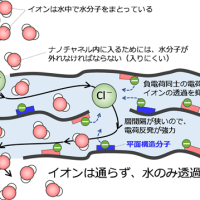













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます