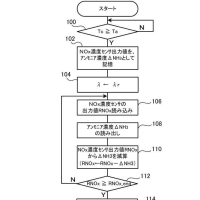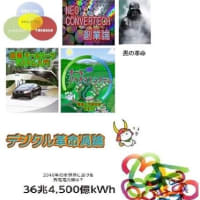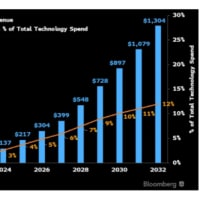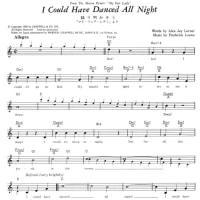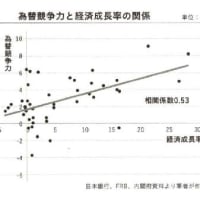世中にたえてさくらのなかりせば春の心ぱのどけからまし 在原業平
花の色はうつりにけりないたづらに我身既にふるながめせしまに 小野小町
ねがはくは花の下にて春死なむそのぎさらぎのもち月の頃 西行
後世は猶今生だにも願はざるわがふところにさくら来てちる 山川登美子
さくらげな陽に泡立つを目守りゐるこの冥き遊星に人と生れて 山中智恵子
さくらさくらいつまで待っても来ぬひとと/死んだひととはおなじさ桜 林あまり
花の奥にさらに花在りわたくしの奥にわれ無く白犬棲むを 水原紫苑
今日は母親を連れだし花見をする予定だったが、体調を悪くしたため急遽取り止め、容態を見舞い、
松原のパン工房、ジュブリルタン(ル・ヴァン・ド・ヴェールはオーナーが健康上の問題で休業中
のためここも急遽変更)で二人でランチ(はじめての「マリネ・チキン」は最高!)をとり、用事
を済ませ、月命日で宗安寺立ち寄る。彦根城周辺はどこも入学式で親子連れやマスク姿の観光客が
目立ったが、寺の敷地内の枝垂れ櫻が美しく咲き、周辺の目抜き通りに櫻吹雪が舞っていた。そん
なこともあり、取り寄せていた、水原紫苑の近著『桜は本当に美しいのか』にめを通した。「桜は
本当に美しいのか。花であるからには、相応に美しいかも知れない。しかし、ここまで人間が傾倒
するほど美しいのか」とまえがきで自問し、「これという結論も得られなかった」とあとがきで返
答している。
●まえがき
桜とは、いったい何だろう。あまりにも多くの人間の思いが、この本の花にこめられている。
しかも、それは、この島国に限っての現象であるらしい。
桜を論じた書物は、一読驚嘆する文語体の、格調高いが非常に国粋的な山田孝雄著『櫻史』
(1941)を始めとして数多いが、「桜は美しいIという大前提に立っているものがほとん
どである。
だが、桜は本当に美しいのか。花であるからには、相応に美しいかも知れない。しかし、こ
こまで人間が傾倒するほど美しいのか。
短歌を本気で始めるまで、私は桜に全く興味がなかった。高校の校門の脇には桜並木があり、
友だちは、学校でお花見ができると喜んでいたが、私にはその気持ちがわからなかった。
はっきりしないピンクの大きな綿菓子のようなかたまりの、いったいどこがいいんだろう。
春の花なら、椿や牡丹や薔薇のほうがずっときれいなのに、と私は思っていた。
一方、歌舞伎はテレビで見ていた子どもの頃から好きだったので、本物を見た時も、吉原の
花魁道中や、白拍子花子の踊りを彩る、舞台の天井からいっぱい吊るされた桜の吊り枝には、
抵抗もなく馴染んだ。舞台装置のひとつ、と感じたのかも知れない。
家の近所には、桜がたくさん植えられた公園があって、花の季節になると、遠くからも見に
来る人たちがいた。それが、癩にさわって、ひどく嫌だった。遠来の花見客は、昼間出られる
中年女性が多い。一人ならまだいいが、数人連れ立って来て、桜の木の下のベンチでお弁当を
広げる。元気に喋りながら、時折ぽかんと目を開けて桜を見上げ、「きれいねえ」などと言い
合っているのを聴くと、「何かそんなにきれいなんですか」と、少女の私は言ってやりたくな
って困ったものだ。
●短歌と桜との出会い
それが、一変してしまったのは、学生時代の終わりである。勉強は残念ながら駄目だったが、
表現の夢が捨てがたく、高校の授業で作った短歌を思い出し、無我夢中で現代短牡の世界に飛
び込んだ。
私の師、春日井建(1938-2004)は前衛短歌と呼ばれた戦後の新しい短歌の流れか
登場した歌人だったが、両親ともに歌人だったこともあって、古典和歌とりわけ藤原定家(1
162-1241)を愛していた。また、前衛歌人の筆頭塚本邦雄(1920-2005)は、
やはり定家を愛し、『新古今和歌集』の美学を自身の歌論に重ね合わせていた。
おのずから、現代短歌だけでなく、古典和歌にも少しずつ近づくことになった。そして出会
ったのが、空恐ろしいほどの桜の歌の集積だった。
なぜ桜にこれほどの情熱が注がれたのか。
私も桜を詠まなければならないという焦燥に似た思いの中で、いつか桜は美しいという結論
が導き出された。花見客はやはり不快だったが、なるべく見ないことにした。そうなると、物
にこだわる気質で、ささやかな庭に三本の桜を植え、純白のトイプードルの仔犬を「さくら」
と名付けて伴侶に決めた。
●桜の素顔
ところが、私の遅咲きの桜信仰が揺らぐ時が来た。2011年3月11日の大震災である。
まだ、桜は咲いていなかった。
しかし、その春の花たちは、みな天地の異変に反応した。椿、董、蒲公英、花の大小にかか
わらず、常よりも色鮮やかに、叫ぶように咲いたのである。
独り、桜だけが尋常だった。猛威を振るった自然の一部としてなのか、何事もなかったよう
に平然と咲いていた。
私は、その桜の姿を美しいと感じることができなかった。あまりにも非情に見えた。
しかし、考えてみれば、非情こそ自然の本来の相である。自然は人間のために存在するわけ
ではないのだ。
まして、桜は、遠い昔には、人知れず山中に咲いていた花である。桜を人間の俗界に招き入
れ、あえかなはなびらに、堪え附ぬほどの重荷を負わせたのは、私たちの罪ではないか。
我に触るるな。
あの春に見た桜は、そう言っていたのかも知れない。
私たちには、桜を、長レ長い人間の欲望の呪縛から、解放すべき時が来てはいないだろうか。
桜を愛するのはいい。だが、桜に肩代わりさせた私たちの本当の望みを、見つめる時が今では
ないだろうか。
●あとがき
桜は本当に美しいのか。その問いから書き始めた、無知蒙昧な一短歌作者の素人読みだが、
迷走のまま、これという結論も得られなかった。私は、桜が、いかなる幻想からも解き放たれ
て原始の不逞な花を咲かせてくれることを望むが、それこそ、借越というもので、春ごとに桜
は、人間の思いなどとは関わりなく、植物の生を全うしているのであろう。
ほとんど妄想のような思い込みで書いたので、読者には文字通り御笑覧の上、御教示御叱責
賜りたい。
桜の通史を書くつもりはさらさらなく、また能力も無いので、自分にとって切実な、『古今
渠』から『新古今集』に至る、国家による桜文化の創造から変容への流れが中心となった。し
かし、また、『新古今集』までは歌が文芸の中心であったということも言えるだろう。
中世からあとは、ほんの拾い読みの形だが、決して革命の起こらないこの国で、桜が負わさ
れてきた役割を、いつかまた改めて考えたい。桜は美しいアヘンだったのか。
近代以降は、桜と天皇制国家と戦争という、とてもこの小論ではとらえきれなかった大問題
がある。今や辺境の文芸となった短歌との関わりを含めて、これこそ自分の残生のテーマだと
思っている。
現代の小説に全くふれることができなかったのは残念だが、21世紀の桜ソングに出会って
、桜文化のしたたかな根強さに驚いた。
平凡社の松井純さんに、何か1冊テーマを決めて書くようにお誘いいただいたのは、もうか
れこれ20年も前である。では、桜論でということに決まったのが10年目くらいで、それでも
書けないまま、また10年が経ってしまった。
今年、急に書く気になったのは、タブレットや新しいパソコンを購入して、手書きより、長
いものが書きやすくなったせいもあるのだが、最終的に背中を押したのは、桜ソングのところ
でも書いた藤圭子の自死である。1959年生まれの私は、社会の記憶が70年から始まって
いる。とりわけ、11月25日の三島由紀夫の自死と、12月31日紅白歌合戦の日本人形の
ような藤圭子のどす黒い歌声は忘れられない。あの呪いは本物だった、振り返れば、三島由紀
夫と藤生子、二人の自死の間を生きてきただけの人生だった、という戦慄の中でひたすら書い
た。
水原紫苑 著『桜は本当に美しいのか』
ここで、2つのことが気になった。その1つは、サクラにまつわる日本人の歴史や風俗観にあり、
明治維新以降の一時的な軍国主義教育(刷り込み)や風俗、習慣への反発、忌避である。このとき
のサクラとは、明治に入り豊島区染井あたりの園芸業者が「吉野桜」という名で商品化(「ソメイ
」+「ヨシノ」、ローン接ぎ木で増植)させた、日本の桜の7~8割を占め瞬く間に日本の春を同
じ色に塗り替えていくソメイヨシノであり、その特徴は、①花だけが一斉に咲き、花つきが多く見
映えがよく、②成長が早く根付きもよく九州南部~北海道中部まで広く分布し日本列島の大部分を
覆うというものであり、それ故に、富国強兵という近代国家形成には迎合されるべき特性だったこ
とを連想させた。

例えば、静岡県三島市の国立遺伝学研究所には日本の各地から集めたサクラが植栽されている。分
かっているだけで218品目。老齢化や密植によるストレスなどで枯死する品種も目立つが、独自の
「挿し木」技術で後継木づくりに取り組んでいる。奈良県葛城市の葛木坐火雷神社(かつらきにい
ますほのいかづちじんじゃ、通称 笛吹神社)のウワミズザクラや宮城県塩釜市にある鹽竈(しお
がま)神社のシオガマザクラ、徳島藩主・蜂須賀茂韶(もちあき)候ゆかりのハチスカザクラの後
継木作成に成功している。一般に、苗を生産方法には、実生苗、接ぎ木苗、組織培養苗、そして挿
し木苗の4方式ある。現在流通しているソメイヨシノのほとんどはオオシマザクラなどの台木接ぎ
木。挿し付けた植物の光合成を活性化させる人工的環境で発根促進技術で、発根率の向上と発根期
間の短縮を図る。例えばソメイヨシノでは、挿し付けた個体の8割以上が4週間で発根。また、挿
し木苗は、ウイルスや菌の侵入路となる接ぎ目がなく、組織培養苗のように遺伝子に変異が入る心
配も少ない。しかし、これらのことを著者はチャンと踏まえた上で問いかけている(例えば、第8
章の「西行と桜の実存」pp.137) 。
もう1つは、サクラのもつ生命活動と人間(日本人)のそれとがシンクリナイズできるように長い
時間をかけ進化してきたのではないかという起想であり、それはあたかもイヌ(オオカミ)の進化
(「人間は犬に飼いならされた?」)、つまり、オオカミの方がわれわれ人間を選んだ可能性が高
いというものに従い、明治以前に生息するサクラの遺伝子戦略、つまり日本人を魅了し、詩歌を詠
わせる能力を身につけたのではないかという奇想天外なものだが、被子植物の種子の散布戦略とし
て(1)他者に散布してもらう(a: 動物による摂食、 b: アリによる運搬、c: 鉤を引っ掛ける、
d: 粘液でくっつく)、(2)風でとぶ(a: 毛、b: 翼、c: 質量がそもそも小さい)、(3)水を
利用する(雨滴、周囲の水に浮く、水中に漂う、沈む)、(4)自力(はじく、土中に種をうめる)
などは既に生命科学で明らかにされている。


さらに、この想いには、『遺伝子の利己性(gene selfishness)』を貫くダーウィンの「最適者生存」
の論理を背景としている-最初は原始地球のスープの中に、偶然にもすこぶる能動的なリプリケー
ター(自己複製子)が出現したのである。おそらくいくつものリプリケーターが競いあっていたの
だろうが、そのなかで最も能動的なリプリケーターが勝ちのこった。それがやがてDNAになった。
この出現自体がドーキンスにいわせれば「最初の自然淘汰」であった。当初のリプリケーターはD
NA配列ではなかった。RNA配列だった。RNAが自分の自己触媒機能を発揮してDNAの自立
を助けた。いわゆる「RNAワールド」の先行だ。やがてその能動的なリプリケーターはDNA配
列の完全コピーという仕事に徹するようになる。DNAはDNAの複製をしつづける。ドーキンス
にとっては、そこからは一瀉千里だ。よく知られているように、DNAはこの4つの塩基のうちの
AとT、GとCという向かい合わせのペア(塩基対)にすることを基本ルールにして、これを二重
螺旋の鎖にしている。鎖はヌクレオチドとよばれる。鎖を二重構造にすることで写真のポジとネガ
の関係のように、2本の鎖のどちらかが損傷したり離ればなれになっても、相補性が保たれるよう
にした。ドーキンスはこれを「不滅のコイル」とよんだ。不滅という意味は、これが生命系におけ
る「新しい安定性」として、これ以降のすべての生物の安定性を保証することになるとみなせるか
らだ」。嫌な言いまわしだが、ドーキンスはこの本のなかで何度も「遺伝子は不死身だ」とか「遺
伝子はダイヤモンドのように永遠だ」と書いている、松岡正剛の書評などを踏まえ、植物のサクラ
と霊長類のヒト(ニホンジン)の共生構図をイメージングさせたものである。
●世阿弥 作『西行桜』
京都は西行の庵室。春になると、美しい桜が咲き、多くの人々が花見に訪れる。しかし、今年、西
行は思うところがあって、花見を禁止した。 一人で桜を愛でていると、例年通り多くの人々がやっ
てきた。桜を愛でていた西行は、遥々やってきた人を追い返す訳にもいかず、招き入れた。西行は
「美しさゆえに人をひきつけるのが桜の罪なところだ」という歌を詠み、夜すがら桜を眺めようと、
木陰に休らう。その夢に老桜の精が現れ、「桜の咎とはなんだ」と聞く。「桜はただ咲くだけのも
ので、咎などあるわけがない。」と言い、「煩わしいと思うのも人の心だ」と西行を諭す。老桜の
精は、桜の名所を西行に教え、舞を舞う。そうこうしているうちに、西行の夢が覚め、老桜の精も
きえ、ただ老木の桜がひっそりと息づいているのだった。
● 西行桜の実存
さて、水原紫苑は「第8章 西行と桜の実存」で、「現代も西行と西行の歌を愛する人は多い。しか
し、西行は、わからない人間であると思う。西行の歌は、平明に見えるが言葉を追ってゆくと迷路
のようでもある。少なくとも、西行さん、とやすやすと親しめるようなものではない。西行は、な
ぜ出家したのか。なぜ歌に志したのか。なぜ花の歌を異常なまでに多く読んだのか。すべてが謎で
ある。ただ、私たちには、歌が残されているだけだ。そして、歌の中でも、花の歌は、異様に生き
生きと匂っている。西行がひそかに思慕を寄せていたと言われる待賢門院の面影を花の歌に見出そ
うとする人もある。たとえば、白洲正子は、『西行』でそのように読んでいた。それが、あながち
当たっていないとは思わない。しかし、それだけでは、西行の花の歌の妖しいまでの生気を説明す
るのはむずかしい」と書いている。その上で次のような短歌を例示し、西行を読み解いていく。
春といへば誰も吉野の花をおもふ心にふかきゆゑやあるらむ
誰かまた花を尋ねてよしの山苔ふみわくる岩つたふらむ
わきて見む老木は花もあはれなり今いくたびか春にあふべき
吉野山梢の花を見し目より心は身にも添はずなりにき
あくがるる心はさても山桜ちりなむ後や身にかへるべき
花みればそのいはれとはなけれども心のうちぞ苦しかりける
身を分けて目こり梢なくつくさばやよろづの山の花の盛を
花にそむ心のいかで残りけむ捨てはててきと思わが身に
白河内在の梢のうぐひすは花の言葉を聞くここちする
ねがはくは花の下にて春死なむそのきさらぎのもち月の頃
仏には桜の花をたてまつれわが後の世を人とぶらはば
わび人の涙に似たる桜かな風身にしめばまづこぼれつつ
吉野山やがて出でじと思ふ身を花ちりなばと人や待つらむ
おぼつかな春は心の花にのみいづれの年かうかれそめけむ
吉野山さくらが枝に雪ちりて花おそげなる年にもあるかな
吉野山こぞのしをりの道かへてまだ見ぬかたの花を尋ねむ
花を待つ心こそなほ昔なれ春にはうとくなりにしものを
あはれわれおほくの春の花を見てそめおく心誰にゆづらむ
吉野山花の散りにし木のもとにとめし心は我を待つらむ
いかでわれ此世の外の思ひ出に風をいとはで花をながめむ
うき世にはとどめおかしと春風のちらすは花を惜しむなりけり
木のもとの死に今宵は埋もれてあかぬ梢を思ひあかさむ
ちる花を惜しむ心やとどまりて又こむ春の誰になるべき
春風の花をちらすと見る夢は覚めても胸のさわぐなりけり
青葉さへみれば心のとまるかな散りにし花の名残と思へば
水原紫苑 著『桜は本当に美しいのか』
そして「西行独特の文体を辿りながら読んでみたが、実に尋常でない花狂いである。恋の歌のよう
でもあるが、恋の歌よりおそろしい。おそろしい理由のひとつは、「花」によって西行の「心」が、
西行いう社会的な人格から外れて、あらわになり、やすやすと「身」から「あくがれ出る」からで
ある。たとえ、出家して世を捨てても、西行は一個の社会的な人格であり、「身」に「心」の具わ
った人間である。だが、その「心」が「身」から解き放たれれば、それはもう、どんな現世の制度
にも屈さない。しかも、西行は、およそ終生この「心]のみをうたったと言ってもいいほどである。
「あくがれ」をうたった歌人は、西行の前にもいた。和泉式部である。しかし、あくがれ出だのは、
「心」ではなく「魂」であり、「花」ゆえではなく、男に忘れられた物思いゆえだったが、西行の
おびただしい花の歌の狂気は、たとえばこ見神一体験のような、社会的な日常を危うくするもので
あるように思われてならない。むしろ、現実に、生きた西行が対峙した、生きた花であるからこそ、
超越的になり得るのだ。これは、生物非生物を問わず霊魂があるとする、アニミズムとは似て非な
るものだと思う。「見神」体験と書いたが、実際それに近い感覚である」といまで言う。ここから
は桜を離れ、西行の「自己」のありようを問いかける。
もの思へば沢のほたるもわが身よりあくがれ出づるたまかとぞ見る
ゆくへなく月に心のすみすみて果はいかにかならむとすらむ
心なき身にも哀はしられけり鴫たつ沢の秋の夕暮
風に靡くふじの煙の空に消えて行方もしらぬわが思ひかな
そして、「死にあくがれ、月に澄みわたる、いかんともしがたいおのれの「心」というものを、あ
りのままに富士の前にさらし、静かに終焉を迎えようとするかに見えるが、最後には、また別種の
劇が待っていた。「ねがはくは花の下にて春死なむそのぎさらぎのもち月の頃」とかつて望んだ通
り、1190年2月16日、73歳の寂滅を遂けるのである。西行への讃仰はいよいよ高まったと
いうが、閉じられた瞼の下には、再び出会う桜の実存があったか、あるいは無か」との自問で結ん
でいる。
以上、美しいと感じるのは自然な情緒なのか、そのように刷り込まれただけではないのか、記紀・万葉あら
桜ソングまで誰も触れえなかった問い(タブー)挑む-との帯のキャッチコピーの通り、今夜は一部のみ読み
解いてみたものの、スリリングな文章に一時魅了されてしまった。