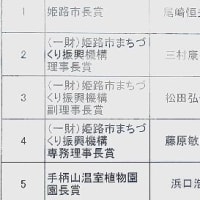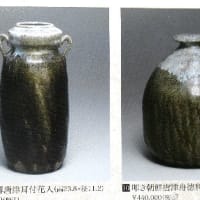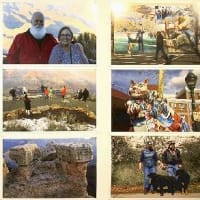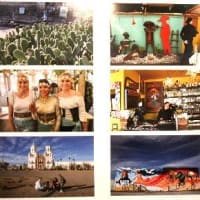6月21日(木)夏至 天気:曇り のち 晴れ 室温:29.2℃
きょうは たつの市揖西町の ”出水(いずみ)の里” を歩いてきました。 「郷土誌ふ
るさと龍野 第六号」 の裏ページの裏に ”7 揖西出水の里コース” が紹介されています。
播磨国風土記によると このあたりには きれいな水が湧き出ることから 出水の里と
呼ばれていました。 第六号のマップを参考に 県道北の恩徳寺にも寄ってきました。
このマップは 「龍野を歩こう」(ドラゴンウォーカーズ)よりの転載だそうです。
きょう歩いたコースは 祝田(はふりた)神社に車を停め 西の小柳の清水から 清江橋
を渡り 照円寺に寄って 清来寺池から 山の南へ回り 佐江山に登って 山から降りて 西
へ行き 上池を見て 南の公民館へ寄って 前池を見て 古子川に沿って 約1km北へ歩
きます。 県道の手前で 東へ曲がり 交番の少し先で 北へ行き 県道を越えて 恩徳寺へ
寄ります。 南へ戻り 中垣内橋を渡り 中垣内川を見ながら 南へ下り 揖西東小学校
の前を東へ。 清水新公園を見て 南へ歩き 祝い田神社へ戻る 約5kmのコースです。


祝田神社は 同じ名前の神社が 姫路市林田町にもありますが 神社について インターネ
ットで 調べた詳細は 参考までに 一番下に載せておきます。 祝田神社へは 以前 訪れた
ことがあり その時のページ : 林田町と揖西町の祝田神社は 2013.12.18 です。
きょうの予報は 曇りで 日が差さないので 歩きやすいかと思いましたが 風がなく
歩き回るには 蒸し暑い日和でした。 下左の写真の低い山の名前を 調べましたが
分からないので 山頂にある三角点の点名:佐江から サエない名前ですが 佐江山という
ことにします。 ある人は 近くのお寺の山号が 栖嵐山なので 栖嵐山かもと・・。



祝田神社は 今から1100年前 平安時代に作られた 「延喜式」 の中には 全国
三千余りの神社の名前が 架かれており 祝田神社のその一つで 農業の神様です。 参
道には 赤い鳥居が並び 本殿の前には キツネの狛犬・狛狐があり 稲荷神社風です。
姫路市林田町にも 同名の神社がありますが どちらが 式内社なのか・・・・。















祝田神社にお参りして 北西にある赤い鳥居の前を 西へ行くと 小柳の清水があります。
小柳の清水は 「播磨十水」の一つで 「播磨國風土記」(奈良時代)には 当時 この
地方は 出水の里と記されている。 室町時代後期 播磨守護・赤松義村が 播磨の国から
十か所の清水を 選定した。 これが 「播磨十水」 である。 播磨鑑 播磨古跡考に
「ききふりし 平井の里の清水をば 誰か名づけん 小屋なきの水」 竹號と記されている。



清江橋を渡り 照円寺へ行きます。 立派なお寺ですが 由緒書きがないので
何も分かりません。 山号は 栖嵐山? 浄土真宗本願寺派。



桝池、清来寺池を見ながら 佐江山の南へ回ります。 出水の里は 湧水が出ると
されていますが この辺りに 溜池が多いのは なぜでしょう? 川の水面より 池の
水面の方が 高いし・・。



佐江山の南から 山へ入ると 草ヤブの中に 水道記念碑があります。 左の竹ヤブに
細い道があるので これを進みます。 しかし ヤブを抜けると 雑木ヤブで 道はありま
せん。 小枝を折りながら 登ると 山頂に きれいな三角点がありました。 四等三角点
は 雑木に隠れているので もう何年も 測量されていないようです。 山頂から 出水の里
が見渡せるかと 思ったのですが まったく展望がありません。



山から降りて 西へ行き 上池と中池を見て 南へ行き 郵便局で 山の名前を
聞きますが 分からず・・。



揖西公民館へ寄って 山の名前を聞きますが ここでも分からず・・。 山の名前は
ないのかも・・。 西の古子川へ出て 橋を渡りますが この橋の名をみわすれました
が 左の大きな池は 前池です。



ここから 北の県道手前まで 古子川に沿って 約1km歩きますが この辺りには
見るものはなく だらだら歩くだけで しんどかった・・。 古子川は 面白い川で
川には 草が茂り 水は ほとんどながれていませんが 川の両側に 幅5、60cm
の水路が設けられていて 水路には 水が 勢いよく流れています。 水路は 川の水面
より高いのに どこから水を引いているのでしょう。



県道の手前で 東へ曲がり 交番を過ぎた少し先で 北へ行き 県道5号線を越え
ると 恩徳寺があります。 ここには 播磨の戦争遺跡の機雷があるので 見に行
きます。 以前 訪れたことがあります。 機雷の脇には 砲弾の玉垣に囲われた
「倶会一処」 の石碑もあります。 これは 戦没者の慰霊碑です。



浄土宗 西山禅林寺派 廣大山恩徳寺は 養老6年(722) 粒穂(揖保)郡矢田部の
出身 得道上人が 父母広大の恩徳を報ぜんため 観世音菩薩を奉り 約千三百年前に 開
基された古刹である。 近くの景雲寺、重蓮寺などの地名は 塔頭の旧跡である。 中世
嘉吉の乱のとき 兵火にかかり 焼失。 森清雲が 元禄元年(1688) 再建した。
廣大の み法も高き 山の端に あらわれ出づる 月のさやけさ



得道上人は 徳道上人だと思いますが なぜ 得 なのか・・。 徳道上人は 西国33か所
霊場を始めた人で また 六地蔵を始めた人でもあります。 恩徳寺には いろいろなアジサイが
咲いています。







県道を渡り 南に戻り 東へ進むと 中垣内川に出ます。 中垣内橋を渡り 南へ。



中垣内川(水無みなし川)は 石龍比古(いわたつひこ)と 石龍比売(いわたつひめ)
の2人の神が 水争いをし 男神は 新宮町へ 女神は 南の出水の里へ流そうとしました。
争いの結果 女神は 地中に桶(水の管)を通して 水を流したので 途中は 水のない川
になってしまったと 『播磨国風土記』 に書かれています。 いまも 川には 土砂が堆積し
草が生え 水面が見えにくくなっています。



揖西東小学校の前を東へ進み はたが森の参道の石碑を見て 清水新公園を見て
南へ下ります。 鳥居をくぐると スタートした祝田神社へ戻ります。



車で一息入れ 景雲寺跡へ行きます。 「郷土誌 ふるさと龍野 第五号」 の19ページ
に そういえば 景雲寺のあったところに 惺窩の石碑がありますよね というくだりがあり
写真もあります。 県道5号線に 景雲寺のバス停があり 信号のある交差点もあります。
藤原惺窩という人が どういう人か知りませんが (三木市生まれの近世儒学の父?)せっ
かくなので 見に行きましょう。 景福寺の信号を北へ突き当たると 山裾に 石碑は ありま
した。 ちょうど 近くに人がおられ 教えていただきました。 これで 本日の行程は 修了。



・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・
・ ・ ・
以下の記述は ネットで ”祝田神社” のページから コピーしました。
このページには 林田町の祝田神社の記述もありますが 削除しています。
【祝田神社】(清水社)・・たつの市揖西町清水
拝殿内に掲げる “式内祝田神社縁起”
「式内祝田神社は 延喜制小社に列する揖保郡七座の一にして、大己貴神の御子・玉帯志比古大稲男神・
玉帯志比売豊稲女神の二柱を祀る。
案ずるに、大己貴神国を占むる時、二神水 無川の水を競ひ、大稲男神は北方越部に流さんと欲し、
豊稲女神は 南方泉村(出水村)に流さんと欲す。 時に男神は 山岑を踰(コ)へて越部村に流したれば、
女神之を見て理に非ずとし、指櫛を以て其の流水を塞ぎ、岑辺より溝を闢(ヒラ)きて 泉村に流したまひぬ。
男神また流を奪ひて 西方桑原村に流したれば、女神遂に之を許さず 密樋を作りて泉村の田頭に流す。
是に於て里人五穀の神として 泉村の田頭に 社殿を営み祀りき。これ当祝田神社なり。
抑も泉村の田頭たるや、往古の出雲往還に当り、水無川の平野が 揖保川の平野に下る傾斜地にして、
水無川の豊富なる伏流は 各所に湧出して 田圃を潤す。 播磨十水・小神の清水と称するも 亦この地にあり。
此の如く当社は 由緒ある地に鎮座し 勧請年極めて古し。 不幸にして 中古社殿荒廃、当初の景観を存せずと
雖も古来ホタノ森(ホタ・ホウタ、ホウタは 祝田・ハフリタの転訛)の社として、神威あらたかに
人々の尊信厚く、遠近人の参拝絶ゆる事なし。
この縁起前段は、風土記揖保郡・美奈志川(水無川)条説話(下記)の祭神名を変えたもので(風土記では、
石龍比古・石龍比売とある)、祭神が 水神と思われることから、在地の人々が 豊穣を願って奉祀したのが
当社の始まりであろう。 ただ、当社創建時期を推測できる記述・史料はない。
◎論社について
この由緒をみるかぎり、由緒・祭神ともに異なり、林田社・清水社のいずれが式内・祝田神社かは 判断できないが、
近世以降の古資料でも同じで、
*播磨鑑(1762)
清水村田地の内に小社有り、延喜式七座の一つ也。 土人ホウダが森と云ふ。
※祭神
林田社--罔象女命(ミズハノメ)・高靇神(タカオカミ)
清水社--石龍比古命(イワタツヒコ)・石龍比売命(イワタツヒメ)・稲倉魂命(ウカノミタマ)
このうち稲倉魂命を除く4座は ともに 水に関係のある神で、
*罔象女命--火の神・カグツチを生んだために火傷を負い病臥したイザナミが生んだ神々の一で、
古事記には 「次に尿(ユマリ)に成りし神の名は 弥都波能売神(ミツハノメ)」とあり、水神という。
*石龍比古・石龍比売については、播磨国風土記・揖保郡条に
・出水の里 この村に冷たい水が出る。 故にその泉によって名とした。
・美奈志川(ミナシ) 美奈志川と呼ぶわけは、伊和大神の御子・石龍比古命と妻の妹・石龍比売命と二人の神が、
川の水を互いに争って、石龍比古命(夫の神)は 北方の越部の村に流したいと思い、石龍比売命(妹の神)は
南方の泉(出水)の村に流したいと思われた。
その時、夫の神は 山の頂を踏みつけて [越部の村の方に]流したもうた。 妹の神は これを見て
無茶なことだと思い、ただちに挿櫛(サシグシ)をもって その流れる水を堰きとめて、頂上のあたりから
溝を切り開いて 泉の村に流して、お互いに争った。
そこで夫の神は出水村の川下に来て川の流れを奪い、西の方の桑原の村に流そうとした。
ここにおいて、妹の神は ついに許さず、密樋(シタビ・地下水路)を作って 泉村の田の頭(ホトリ)に
流し出した。 これによって川の水は 絶えて流れない。 故に无水川(ミナシカワ)と呼ぶ。 とある。
この神の神格は 不詳だが、風土記(東洋文庫版・1969)注では、
「石龍比古命 石立彦または岩戸彦の夫婦神。(説話では)夫は 山の神、妻は 水の神として扱っている。
おそらくは、これも古墳説話の変種で、古墳の周囲を水で囲むことから出た話であろう」 と、
石龍比古を 山の神・比売を 水の神としているが、両神で 水を流す先を争ったことから 両神ともに
水神とみてもいいだろう(山の神は 水神でもある)。
祭神からみて、式内・祝田神社は、林田社・清水社のいずれも、在地の人々が、水神を祀ることで
五穀豊穣即ち豊かな生活を祈願した神社を前身とするといえよう。
なお 清水社縁起・神社覈録に、
玉帯志比古大稲男神(タマタラシヒコオオイナオ)・玉帯志比女豊稲女神(タマタラシヒメトヨイナメ)との
神の名があり、大己貴命の御子というが、記紀等にいう大己貴の御子の中にその名はない。
ただ、播磨国風土記・美嚢郡条に 「高野の里 祝田の社に鎮座する神は、玉帯志比古大稲男神・
玉帯志比女豊稲女神である」 とあり、
その神格について、風土記注に 「玉を垂らした大稲男・大稲女と擬人化されているが、祝(神主)の
奉仕する田に降臨する稲霊(イナタマ)の依り代(ヨリシロ)となる男女をいったものであろう」 とある。
(玉は魂であり、玉帯比古・比売とは稲魂が依り付く巫覡を指す)
【清水社】 祝田神社(清水社)社殿等
周囲は田畑のため見通しよく、遠くからでも朱塗りの大鳥居が見える。
鳥居列入口の左右に“式内祝田神社”との石柱と、“王子八幡宮”と刻した自然石があるように、
祝田神社と八幡宮の2社が 並んで鎮座している。
祝田神社・拝殿前に 「祝田神社 祭神:石龍比古命・石龍比売命・稲倉魂命」との案内が立つ。
社頭の朱塗鳥居列が目立つが、これは 合祀された稲倉魂命(ウカノミタマ・稲荷神)によるもので、
水神信仰というより 稲荷神として 崇敬されているようにみえる。
ただ、水神は 農耕神でもあることから、同じ神格を持つ 稲荷神が合祀されていても 違和感はない。
王子八幡宮拝殿前には 「王子八幡宮 祭神:誉田別大神」との案内が立つのみで、いかなる由緒で
創祀されたかは 不明。
樹木で覆われた境内には 二つの社殿が鎮座し、右側(東側)が 祝田神社で 左が 王子八幡宮。
社殿構成は 両社とも ぼ同じで、前面(南側)に拝殿(入母屋造・瓦葺)が、その奥、弊殿に続いて
本殿(一間社流造・銅板葺)が 面して 鎮座するが、拝殿・弊殿・本殿が連なり、
本殿側面が 板壁で囲われていて 根と背後の結構が見えるのみで 細不明。

。。。。。 。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。
きょうは たつの市揖西町の ”出水(いずみ)の里” を歩いてきました。 「郷土誌ふ
るさと龍野 第六号」 の裏ページの裏に ”7 揖西出水の里コース” が紹介されています。
播磨国風土記によると このあたりには きれいな水が湧き出ることから 出水の里と
呼ばれていました。 第六号のマップを参考に 県道北の恩徳寺にも寄ってきました。
このマップは 「龍野を歩こう」(ドラゴンウォーカーズ)よりの転載だそうです。
きょう歩いたコースは 祝田(はふりた)神社に車を停め 西の小柳の清水から 清江橋
を渡り 照円寺に寄って 清来寺池から 山の南へ回り 佐江山に登って 山から降りて 西
へ行き 上池を見て 南の公民館へ寄って 前池を見て 古子川に沿って 約1km北へ歩
きます。 県道の手前で 東へ曲がり 交番の少し先で 北へ行き 県道を越えて 恩徳寺へ
寄ります。 南へ戻り 中垣内橋を渡り 中垣内川を見ながら 南へ下り 揖西東小学校
の前を東へ。 清水新公園を見て 南へ歩き 祝い田神社へ戻る 約5kmのコースです。


祝田神社は 同じ名前の神社が 姫路市林田町にもありますが 神社について インターネ
ットで 調べた詳細は 参考までに 一番下に載せておきます。 祝田神社へは 以前 訪れた
ことがあり その時のページ : 林田町と揖西町の祝田神社は 2013.12.18 です。
きょうの予報は 曇りで 日が差さないので 歩きやすいかと思いましたが 風がなく
歩き回るには 蒸し暑い日和でした。 下左の写真の低い山の名前を 調べましたが
分からないので 山頂にある三角点の点名:佐江から サエない名前ですが 佐江山という
ことにします。 ある人は 近くのお寺の山号が 栖嵐山なので 栖嵐山かもと・・。



祝田神社は 今から1100年前 平安時代に作られた 「延喜式」 の中には 全国
三千余りの神社の名前が 架かれており 祝田神社のその一つで 農業の神様です。 参
道には 赤い鳥居が並び 本殿の前には キツネの狛犬・狛狐があり 稲荷神社風です。
姫路市林田町にも 同名の神社がありますが どちらが 式内社なのか・・・・。















祝田神社にお参りして 北西にある赤い鳥居の前を 西へ行くと 小柳の清水があります。
小柳の清水は 「播磨十水」の一つで 「播磨國風土記」(奈良時代)には 当時 この
地方は 出水の里と記されている。 室町時代後期 播磨守護・赤松義村が 播磨の国から
十か所の清水を 選定した。 これが 「播磨十水」 である。 播磨鑑 播磨古跡考に
「ききふりし 平井の里の清水をば 誰か名づけん 小屋なきの水」 竹號と記されている。



清江橋を渡り 照円寺へ行きます。 立派なお寺ですが 由緒書きがないので
何も分かりません。 山号は 栖嵐山? 浄土真宗本願寺派。



桝池、清来寺池を見ながら 佐江山の南へ回ります。 出水の里は 湧水が出ると
されていますが この辺りに 溜池が多いのは なぜでしょう? 川の水面より 池の
水面の方が 高いし・・。



佐江山の南から 山へ入ると 草ヤブの中に 水道記念碑があります。 左の竹ヤブに
細い道があるので これを進みます。 しかし ヤブを抜けると 雑木ヤブで 道はありま
せん。 小枝を折りながら 登ると 山頂に きれいな三角点がありました。 四等三角点
は 雑木に隠れているので もう何年も 測量されていないようです。 山頂から 出水の里
が見渡せるかと 思ったのですが まったく展望がありません。



山から降りて 西へ行き 上池と中池を見て 南へ行き 郵便局で 山の名前を
聞きますが 分からず・・。



揖西公民館へ寄って 山の名前を聞きますが ここでも分からず・・。 山の名前は
ないのかも・・。 西の古子川へ出て 橋を渡りますが この橋の名をみわすれました
が 左の大きな池は 前池です。



ここから 北の県道手前まで 古子川に沿って 約1km歩きますが この辺りには
見るものはなく だらだら歩くだけで しんどかった・・。 古子川は 面白い川で
川には 草が茂り 水は ほとんどながれていませんが 川の両側に 幅5、60cm
の水路が設けられていて 水路には 水が 勢いよく流れています。 水路は 川の水面
より高いのに どこから水を引いているのでしょう。



県道の手前で 東へ曲がり 交番を過ぎた少し先で 北へ行き 県道5号線を越え
ると 恩徳寺があります。 ここには 播磨の戦争遺跡の機雷があるので 見に行
きます。 以前 訪れたことがあります。 機雷の脇には 砲弾の玉垣に囲われた
「倶会一処」 の石碑もあります。 これは 戦没者の慰霊碑です。



浄土宗 西山禅林寺派 廣大山恩徳寺は 養老6年(722) 粒穂(揖保)郡矢田部の
出身 得道上人が 父母広大の恩徳を報ぜんため 観世音菩薩を奉り 約千三百年前に 開
基された古刹である。 近くの景雲寺、重蓮寺などの地名は 塔頭の旧跡である。 中世
嘉吉の乱のとき 兵火にかかり 焼失。 森清雲が 元禄元年(1688) 再建した。
廣大の み法も高き 山の端に あらわれ出づる 月のさやけさ



得道上人は 徳道上人だと思いますが なぜ 得 なのか・・。 徳道上人は 西国33か所
霊場を始めた人で また 六地蔵を始めた人でもあります。 恩徳寺には いろいろなアジサイが
咲いています。







県道を渡り 南に戻り 東へ進むと 中垣内川に出ます。 中垣内橋を渡り 南へ。



中垣内川(水無みなし川)は 石龍比古(いわたつひこ)と 石龍比売(いわたつひめ)
の2人の神が 水争いをし 男神は 新宮町へ 女神は 南の出水の里へ流そうとしました。
争いの結果 女神は 地中に桶(水の管)を通して 水を流したので 途中は 水のない川
になってしまったと 『播磨国風土記』 に書かれています。 いまも 川には 土砂が堆積し
草が生え 水面が見えにくくなっています。



揖西東小学校の前を東へ進み はたが森の参道の石碑を見て 清水新公園を見て
南へ下ります。 鳥居をくぐると スタートした祝田神社へ戻ります。



車で一息入れ 景雲寺跡へ行きます。 「郷土誌 ふるさと龍野 第五号」 の19ページ
に そういえば 景雲寺のあったところに 惺窩の石碑がありますよね というくだりがあり
写真もあります。 県道5号線に 景雲寺のバス停があり 信号のある交差点もあります。
藤原惺窩という人が どういう人か知りませんが (三木市生まれの近世儒学の父?)せっ
かくなので 見に行きましょう。 景福寺の信号を北へ突き当たると 山裾に 石碑は ありま
した。 ちょうど 近くに人がおられ 教えていただきました。 これで 本日の行程は 修了。



・ ・ ・ ・
 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・  ・ ・ ・
・ ・ ・以下の記述は ネットで ”祝田神社” のページから コピーしました。
このページには 林田町の祝田神社の記述もありますが 削除しています。
【祝田神社】(清水社)・・たつの市揖西町清水
拝殿内に掲げる “式内祝田神社縁起”
「式内祝田神社は 延喜制小社に列する揖保郡七座の一にして、大己貴神の御子・玉帯志比古大稲男神・
玉帯志比売豊稲女神の二柱を祀る。
案ずるに、大己貴神国を占むる時、二神水 無川の水を競ひ、大稲男神は北方越部に流さんと欲し、
豊稲女神は 南方泉村(出水村)に流さんと欲す。 時に男神は 山岑を踰(コ)へて越部村に流したれば、
女神之を見て理に非ずとし、指櫛を以て其の流水を塞ぎ、岑辺より溝を闢(ヒラ)きて 泉村に流したまひぬ。
男神また流を奪ひて 西方桑原村に流したれば、女神遂に之を許さず 密樋を作りて泉村の田頭に流す。
是に於て里人五穀の神として 泉村の田頭に 社殿を営み祀りき。これ当祝田神社なり。
抑も泉村の田頭たるや、往古の出雲往還に当り、水無川の平野が 揖保川の平野に下る傾斜地にして、
水無川の豊富なる伏流は 各所に湧出して 田圃を潤す。 播磨十水・小神の清水と称するも 亦この地にあり。
此の如く当社は 由緒ある地に鎮座し 勧請年極めて古し。 不幸にして 中古社殿荒廃、当初の景観を存せずと
雖も古来ホタノ森(ホタ・ホウタ、ホウタは 祝田・ハフリタの転訛)の社として、神威あらたかに
人々の尊信厚く、遠近人の参拝絶ゆる事なし。
この縁起前段は、風土記揖保郡・美奈志川(水無川)条説話(下記)の祭神名を変えたもので(風土記では、
石龍比古・石龍比売とある)、祭神が 水神と思われることから、在地の人々が 豊穣を願って奉祀したのが
当社の始まりであろう。 ただ、当社創建時期を推測できる記述・史料はない。
◎論社について
この由緒をみるかぎり、由緒・祭神ともに異なり、林田社・清水社のいずれが式内・祝田神社かは 判断できないが、
近世以降の古資料でも同じで、
*播磨鑑(1762)
清水村田地の内に小社有り、延喜式七座の一つ也。 土人ホウダが森と云ふ。
※祭神
林田社--罔象女命(ミズハノメ)・高靇神(タカオカミ)
清水社--石龍比古命(イワタツヒコ)・石龍比売命(イワタツヒメ)・稲倉魂命(ウカノミタマ)
このうち稲倉魂命を除く4座は ともに 水に関係のある神で、
*罔象女命--火の神・カグツチを生んだために火傷を負い病臥したイザナミが生んだ神々の一で、
古事記には 「次に尿(ユマリ)に成りし神の名は 弥都波能売神(ミツハノメ)」とあり、水神という。
*石龍比古・石龍比売については、播磨国風土記・揖保郡条に
・出水の里 この村に冷たい水が出る。 故にその泉によって名とした。
・美奈志川(ミナシ) 美奈志川と呼ぶわけは、伊和大神の御子・石龍比古命と妻の妹・石龍比売命と二人の神が、
川の水を互いに争って、石龍比古命(夫の神)は 北方の越部の村に流したいと思い、石龍比売命(妹の神)は
南方の泉(出水)の村に流したいと思われた。
その時、夫の神は 山の頂を踏みつけて [越部の村の方に]流したもうた。 妹の神は これを見て
無茶なことだと思い、ただちに挿櫛(サシグシ)をもって その流れる水を堰きとめて、頂上のあたりから
溝を切り開いて 泉の村に流して、お互いに争った。
そこで夫の神は出水村の川下に来て川の流れを奪い、西の方の桑原の村に流そうとした。
ここにおいて、妹の神は ついに許さず、密樋(シタビ・地下水路)を作って 泉村の田の頭(ホトリ)に
流し出した。 これによって川の水は 絶えて流れない。 故に无水川(ミナシカワ)と呼ぶ。 とある。
この神の神格は 不詳だが、風土記(東洋文庫版・1969)注では、
「石龍比古命 石立彦または岩戸彦の夫婦神。(説話では)夫は 山の神、妻は 水の神として扱っている。
おそらくは、これも古墳説話の変種で、古墳の周囲を水で囲むことから出た話であろう」 と、
石龍比古を 山の神・比売を 水の神としているが、両神で 水を流す先を争ったことから 両神ともに
水神とみてもいいだろう(山の神は 水神でもある)。
祭神からみて、式内・祝田神社は、林田社・清水社のいずれも、在地の人々が、水神を祀ることで
五穀豊穣即ち豊かな生活を祈願した神社を前身とするといえよう。
なお 清水社縁起・神社覈録に、
玉帯志比古大稲男神(タマタラシヒコオオイナオ)・玉帯志比女豊稲女神(タマタラシヒメトヨイナメ)との
神の名があり、大己貴命の御子というが、記紀等にいう大己貴の御子の中にその名はない。
ただ、播磨国風土記・美嚢郡条に 「高野の里 祝田の社に鎮座する神は、玉帯志比古大稲男神・
玉帯志比女豊稲女神である」 とあり、
その神格について、風土記注に 「玉を垂らした大稲男・大稲女と擬人化されているが、祝(神主)の
奉仕する田に降臨する稲霊(イナタマ)の依り代(ヨリシロ)となる男女をいったものであろう」 とある。
(玉は魂であり、玉帯比古・比売とは稲魂が依り付く巫覡を指す)
【清水社】 祝田神社(清水社)社殿等
周囲は田畑のため見通しよく、遠くからでも朱塗りの大鳥居が見える。
鳥居列入口の左右に“式内祝田神社”との石柱と、“王子八幡宮”と刻した自然石があるように、
祝田神社と八幡宮の2社が 並んで鎮座している。
祝田神社・拝殿前に 「祝田神社 祭神:石龍比古命・石龍比売命・稲倉魂命」との案内が立つ。
社頭の朱塗鳥居列が目立つが、これは 合祀された稲倉魂命(ウカノミタマ・稲荷神)によるもので、
水神信仰というより 稲荷神として 崇敬されているようにみえる。
ただ、水神は 農耕神でもあることから、同じ神格を持つ 稲荷神が合祀されていても 違和感はない。
王子八幡宮拝殿前には 「王子八幡宮 祭神:誉田別大神」との案内が立つのみで、いかなる由緒で
創祀されたかは 不明。
樹木で覆われた境内には 二つの社殿が鎮座し、右側(東側)が 祝田神社で 左が 王子八幡宮。
社殿構成は 両社とも ぼ同じで、前面(南側)に拝殿(入母屋造・瓦葺)が、その奥、弊殿に続いて
本殿(一間社流造・銅板葺)が 面して 鎮座するが、拝殿・弊殿・本殿が連なり、
本殿側面が 板壁で囲われていて 根と背後の結構が見えるのみで 細不明。

。。。。。
 。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。  。。。。。
。。。。。