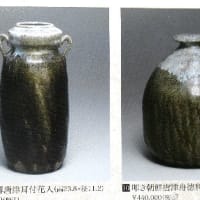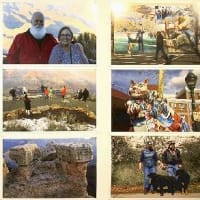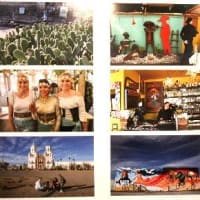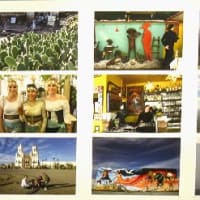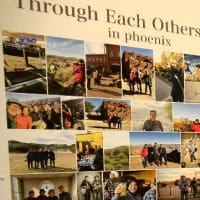5月19日(土) 天気:晴れ 室温:27.1℃
きょうは 出石に行き 有子山に登り 降りてから 但馬の小京都 出石の街を 愛馬ロシナンテ
で 走りまわってきました。 網干で 生まれた ”播州の花神” こと 河野東馬が 長州藩とともに
尊皇攘夷派として 「蛤御門の変」 で 桂小五郎らと 戦いましたが 戦いに敗れ 小五郎は 出石
に潜伏したが 東馬は 逃げる途中 出石藩に 捕らわれの身となったのです。 網干在住の私と
しては 出石藩に 一言 文句を言いたい・・・。 が 言うべき相手が いない・・・・。
出石は 『古事記』や 『日本書紀』にも 登場する古い町です。 但馬開発の祖神「天日槍」が
この地を 拓いたと伝えられています。 室町時代には 山名時氏が 但馬を制圧。 その子 時義
が 此隅山に 本城を構えたことにより 出石は 但馬の中心として 繁栄しました。
注)下の図は 東西南北が 逆になっています。


10:37 山から降りて 車に戻り 折畳み自転車を トランクから出して 10:45 出石散策に
出発。 南東の経王寺へ向かいます。 駐車場の東隣が 市役所の出石支所で 御対面所跡の
表示があります。 この地に 松平忠徳が 建てた 御殿があり 歴代の殿様が 居住したようです。



ちょうど 出石高校の女生徒が 下校中だったので 弘道館や 経王寺を尋ねますが ウソ
ばかり 教えてくれるのも 困ったものです・・。 出石藩の藩校・弘道館跡は 分からず 経王
寺には 裏から 入ってしまいました。 経王寺(きょうおうじ)は 京街道丹波口にあり いざ
戦いになったときは 砦の役割をしたため 櫓のような建物です。 仙石氏の菩提寺で 墓も
あるようです。 沙羅双樹の木もありました。



経王寺の前は 出石高校で 東へ行くと 赤門があります。 旧出石藩のものを 再建。
加藤弘之の生家は 不明。 龍野の街には 道標が整備されていますが 出石は・・。



右に 吉祥寺があり 山門にある仁王像は 極彩色で 立派です。



吉祥寺の前が 石部神社。 御祭神は 天日方奇日方命。 皇大神宮と天満宮が祀られ
ています。 ともあれ ここの御神木・大ケヤキが 有名。 樹齢千年で 樹高30m。 ここに
お参りすると 長生きできる? これで 私も 70までは 生きられる?



高校の前を 戻ると 岩鼻稲荷神社があります。 道路脇には 化粧地蔵が・・。 稲荷神社
は 出石城主・小出大和守吉英公が 有子山山頂より 山麓に移し 城下街づくりに際し 伏
見稲荷より分霊を受け 出石稲荷神社を 建立。 しかし 城内故 町民は 年に一度しか参拝
できなかった。 そこで この地に建立し 町民が いつでも 詣でることができるようになった。
次に 明治館へ行きました。 明治館は 郡役所として 明治20年に建造された 木造擬洋風
建築の貴重な建物。 中に入ると 入館料が 要るようなので 止めました。



路地を入ると 本覚寺。 別名 てっせん寺。 てっせんは 6月が見頃なので 少し 早い。
本覚寺は 浄土真宗 本願寺派のお寺で 本尊は 阿弥陀如来。 住職に なぜ てっせん?
と聞くと てっせんは 陸のハス と言われました。 阿弥陀如来を 拝むよう言われ 本堂に
上げていただきました。 阿弥陀三尊で 日光・月光菩薩もあるのですか? と聞くと 知っ
たかぶりして・・・。 クレマチスは すべて 鉢植えなので 水やり・植え替えなど 手入れは
大変です。 植木鉢は 何百もあります。 本堂の天井のクレマチスの絵は 見事です。
てっせんは クレマチスの原種の一種?







本覚寺を 真っ直ぐ 北へ行くと 出石酒造の酒蔵があります。 長い歳月を経た 赤い土壁の
酒蔵ですが 生憎 日陰で 暗く見えます。 酒蔵の前が 本高寺。 康正元年(1455) 仏性院
日會上人の草創。 一時 全山灰燼に帰すも 小出吉英公、足立一族の外護を得て 慶安三
年 再興。 のち 仙石家の菩提寺になる。 ”仙石騒動”の際 河野瀬兵衛の首を当山に葬る。



本高寺から東へ進み 山裾の坂道を登ると 願成寺があります。 庭園が いいらしいので
すが 建物の中を通らないと 見ることができません・・。



奥が 宗鏡寺(すきょうじ)。 沢庵和尚の遺跡として知られ 本堂東側に 地泉庭園があるそ
うです。 裏山から流れ出る水を 利用した庭園で 細長い池は 鶴の形をし 池の中央に 亀
島を築き 池の対岸にある滝口の傍には 巨石・蓬莱石を立てて・・・。 有料なので 入らず。



坂を下り 街中に戻ると 出石資料館がありますが ここも 有料なので パス。 史料館は
明治時代の豪商 旧福富邸で 仙石騒動の関係資料などが 展示してあるそうです。
この先に 桂小五郎の潜居跡がありますが あまりに ちゃちぃので 通り過ぎてしまいます。
そば屋の隣の 民家の前 2mほどのスペースに 碑がありました。 わざわざ 出石に 来た
のは これを見るのが 主目的だったのですが・・。 出石藩としては 小五郎を 捕えることが
できなかったので 大きくしたくない?
長州藩の桂小五郎は 神道無念流の免許皆伝の使い手でしたが 無益な争いは 避ける
「逃げの小五郎」という異名をとりました。 池田屋襲撃からも 逃れた小五郎は 1864年
「禁門の変」(蛤御門の変)に敗れ この戦で 御所に 弾を撃ち込んだため 朝敵となり
追われる身に・・。 逃げの小五郎は この戦いには 反対で 参加しなかったという噂も・・。
但馬の町人甚助・直蔵兄弟の手引きで 京都を脱出し ここに 隠れ住んだと言われています。
出石には 潜居碑が点在し 転居を繰り返し 京都の芸姑・幾松と暮らした・・・。
後に 小五郎は 薩長連合を結び 倒幕に尽力、幕末を生き抜き 新政府でも 活躍し
西郷隆盛、大久保利通と並んで 維新の三傑 と称されるのです。



山谷川に架かる大橋の袂には おりゅう灯籠(船着場灯籠)があります。 昔の出石川は
川幅が広く 水量も多く 交通運輸は 主として 川筋が利用され 灯籠は 夜間の灯明台と
して使われた。



大橋を渡り 北の見性寺(けんしょうじ)に行きます。 見性寺は 出石城の外堀とみたてた
出石川と堀川が交差する 防衛上の要衝であったため 寺院でありながら 隅櫓のような望楼
形の鐘楼を配し 城下町を守る役目をもった お寺で 戦いになれば 砦として守りを固めた。



大橋を渡り 南へ戻ると 永楽館があります。 永楽館は 明治34年に開館した 近畿最古
の芝居小屋で 歌舞伎などが 上演され 興行のない日は 一般公開され 廻り舞台、奈落な
ど 舞台裏が見学できますが 有料なので パス。 24日 テレビを見ていると 四国の金毘
羅さんの近くにある こんぴら大芝居が 日本で 一番古い芝居小屋 と言っていました。



南へ戻り 内町通りへ。 白壁の塀は 家老屋敷。 長屋門を入ると 人力車が・・。 奥
に 伊藤清永美術館があり 清永画伯の絵画が 多数展示してあるそうですが・・・。
左が 家老屋敷で 出石城内にあった江戸後期の家老・仙石左京の居館です。 左京は
仙石騒動で 森の露と消えた。 ここも 有料だった? 福成寺(ふくしょうじ)は・・。



家老屋敷の前にある 勝林寺へも寄り 車に戻りました。 あっ まだ 辰鼓楼に行って
ない。 駐車場を抜け 辰鼓楼を撮りに 行きました。 辰鼓楼は 明治時代の旧三の丸
大手門脇にある鼓楼で 今は 時計台です。
12:50 やっと 車に戻り 車で 弁当。 こう暑くては 食欲もありません。
13:05 車を出します。 帰路の途中に もう 1ヶ所 寄るところがあります。



家に帰り 駐車場でもらった”出石散策絵図”を見ると 北3kmのところに 出石神社や
此隅山城跡、白糸の滝 などがあるようです。 せっかくなので 行けば 良かった・・・。
県道2号線に出ると 一本道。 伊佐で 円山川に突き当り 右岸を南下。 県道104号
線に入り 道の駅やぶの手前の米地橋を渡り 踏切を越えた先に 西念寺があります。
出石から 19km。 13:28 西念寺に 着きました。



”あいたい兵庫” 春ー夏号 を見ていると 西念寺に 木戸孝允公(桂小五郎)潜伏遺跡の石
碑があるそうなので 見て行きましょう。 西念寺の入口には 古そうな宝篋印塔があります。
西念寺には お墓がたくさんあり 石碑がどこにあるのか 分からず 庫裏へ行って 聞き
ました。 鐘楼の左の木の陰に 石碑がありました。 説明板はなく・・これにも がっかり・・。
桂小五郎は 山陰道を西へ逃れて 城崎温泉の「つたや」に 幾松と身を隠したことは・・・。



話は それますが 歴史秘話を
網干に生まれた河野鉄兜に 作州から安東誠之助が 弟子入りし 鉄兜の鉄と 弟の東馬
の馬から 鉄馬と称した。 歳は 東馬より8歳若く 東馬も 弟のように可愛がっていた。
元治元年 長州藩は 蛤御門の変を勃発。 河野東馬は このとき 安東鉄馬と 行動を共にし
奮戦したが 鉄馬は 銃弾に倒れ・・。 東馬は 逃げる途中 出石藩に捕らわれたのです。
東馬の獄中の期間は 如何ほどであったか 明らかではないが 出石藩の奥女中の手助け
により 逃げることができたのです。 奥女中は 追放となり その後 結婚し 娘を生んだが
短い生涯を 終わったという・・。
網干に 「ふじや」 という料理旅館があり 東馬先生と数人が会食中 そこの仲居さんが
「世が世なれば・・」と話すにつけ 出石藩の奥女中の娘御であることが 分かった。
東馬先生も びっくり仰天。 両手をついて 厚く お礼を申し述べられたという・・。
慶応4年 新政府が樹立し 三条実実公より 民部省判事として 東馬に 召出しの使者が
来たが 応じなかった。 木戸公は 偉いが 伊藤博文は さほどではない・・・。


米地橋を渡り 県道104号線の戻り 南下。 13:56 一本柳の交差点に出て 国道
312号線を 南へ走り 14:03 和田山の料金所を突破し 播但道に入ります。 播但
道をひた走り 神崎南で 山ちゃんの家を見ると 軽トラ?が 停まっていて 山ちゃんは
きょうは 山はなし かと思いましたが・・。 氷ノ山でした・・。
14:42 花田ICを通過し 姫路バイパスに廻り 15:25 家に帰りました。
本日の走行距離は 往路:115.1km 西念寺まで 19km 復路:97.9kmで
計:232kmでした。
。。。。。。。 。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。。。。。。
。。。。。。。
きょうは 出石に行き 有子山に登り 降りてから 但馬の小京都 出石の街を 愛馬ロシナンテ
で 走りまわってきました。 網干で 生まれた ”播州の花神” こと 河野東馬が 長州藩とともに
尊皇攘夷派として 「蛤御門の変」 で 桂小五郎らと 戦いましたが 戦いに敗れ 小五郎は 出石
に潜伏したが 東馬は 逃げる途中 出石藩に 捕らわれの身となったのです。 網干在住の私と
しては 出石藩に 一言 文句を言いたい・・・。 が 言うべき相手が いない・・・・。
出石は 『古事記』や 『日本書紀』にも 登場する古い町です。 但馬開発の祖神「天日槍」が
この地を 拓いたと伝えられています。 室町時代には 山名時氏が 但馬を制圧。 その子 時義
が 此隅山に 本城を構えたことにより 出石は 但馬の中心として 繁栄しました。
注)下の図は 東西南北が 逆になっています。


10:37 山から降りて 車に戻り 折畳み自転車を トランクから出して 10:45 出石散策に
出発。 南東の経王寺へ向かいます。 駐車場の東隣が 市役所の出石支所で 御対面所跡の
表示があります。 この地に 松平忠徳が 建てた 御殿があり 歴代の殿様が 居住したようです。



ちょうど 出石高校の女生徒が 下校中だったので 弘道館や 経王寺を尋ねますが ウソ
ばかり 教えてくれるのも 困ったものです・・。 出石藩の藩校・弘道館跡は 分からず 経王
寺には 裏から 入ってしまいました。 経王寺(きょうおうじ)は 京街道丹波口にあり いざ
戦いになったときは 砦の役割をしたため 櫓のような建物です。 仙石氏の菩提寺で 墓も
あるようです。 沙羅双樹の木もありました。



経王寺の前は 出石高校で 東へ行くと 赤門があります。 旧出石藩のものを 再建。
加藤弘之の生家は 不明。 龍野の街には 道標が整備されていますが 出石は・・。



右に 吉祥寺があり 山門にある仁王像は 極彩色で 立派です。



吉祥寺の前が 石部神社。 御祭神は 天日方奇日方命。 皇大神宮と天満宮が祀られ
ています。 ともあれ ここの御神木・大ケヤキが 有名。 樹齢千年で 樹高30m。 ここに
お参りすると 長生きできる? これで 私も 70までは 生きられる?



高校の前を 戻ると 岩鼻稲荷神社があります。 道路脇には 化粧地蔵が・・。 稲荷神社
は 出石城主・小出大和守吉英公が 有子山山頂より 山麓に移し 城下街づくりに際し 伏
見稲荷より分霊を受け 出石稲荷神社を 建立。 しかし 城内故 町民は 年に一度しか参拝
できなかった。 そこで この地に建立し 町民が いつでも 詣でることができるようになった。
次に 明治館へ行きました。 明治館は 郡役所として 明治20年に建造された 木造擬洋風
建築の貴重な建物。 中に入ると 入館料が 要るようなので 止めました。



路地を入ると 本覚寺。 別名 てっせん寺。 てっせんは 6月が見頃なので 少し 早い。
本覚寺は 浄土真宗 本願寺派のお寺で 本尊は 阿弥陀如来。 住職に なぜ てっせん?
と聞くと てっせんは 陸のハス と言われました。 阿弥陀如来を 拝むよう言われ 本堂に
上げていただきました。 阿弥陀三尊で 日光・月光菩薩もあるのですか? と聞くと 知っ
たかぶりして・・・。 クレマチスは すべて 鉢植えなので 水やり・植え替えなど 手入れは
大変です。 植木鉢は 何百もあります。 本堂の天井のクレマチスの絵は 見事です。
てっせんは クレマチスの原種の一種?







本覚寺を 真っ直ぐ 北へ行くと 出石酒造の酒蔵があります。 長い歳月を経た 赤い土壁の
酒蔵ですが 生憎 日陰で 暗く見えます。 酒蔵の前が 本高寺。 康正元年(1455) 仏性院
日會上人の草創。 一時 全山灰燼に帰すも 小出吉英公、足立一族の外護を得て 慶安三
年 再興。 のち 仙石家の菩提寺になる。 ”仙石騒動”の際 河野瀬兵衛の首を当山に葬る。



本高寺から東へ進み 山裾の坂道を登ると 願成寺があります。 庭園が いいらしいので
すが 建物の中を通らないと 見ることができません・・。



奥が 宗鏡寺(すきょうじ)。 沢庵和尚の遺跡として知られ 本堂東側に 地泉庭園があるそ
うです。 裏山から流れ出る水を 利用した庭園で 細長い池は 鶴の形をし 池の中央に 亀
島を築き 池の対岸にある滝口の傍には 巨石・蓬莱石を立てて・・・。 有料なので 入らず。



坂を下り 街中に戻ると 出石資料館がありますが ここも 有料なので パス。 史料館は
明治時代の豪商 旧福富邸で 仙石騒動の関係資料などが 展示してあるそうです。
この先に 桂小五郎の潜居跡がありますが あまりに ちゃちぃので 通り過ぎてしまいます。
そば屋の隣の 民家の前 2mほどのスペースに 碑がありました。 わざわざ 出石に 来た
のは これを見るのが 主目的だったのですが・・。 出石藩としては 小五郎を 捕えることが
できなかったので 大きくしたくない?
長州藩の桂小五郎は 神道無念流の免許皆伝の使い手でしたが 無益な争いは 避ける
「逃げの小五郎」という異名をとりました。 池田屋襲撃からも 逃れた小五郎は 1864年
「禁門の変」(蛤御門の変)に敗れ この戦で 御所に 弾を撃ち込んだため 朝敵となり
追われる身に・・。 逃げの小五郎は この戦いには 反対で 参加しなかったという噂も・・。
但馬の町人甚助・直蔵兄弟の手引きで 京都を脱出し ここに 隠れ住んだと言われています。
出石には 潜居碑が点在し 転居を繰り返し 京都の芸姑・幾松と暮らした・・・。
後に 小五郎は 薩長連合を結び 倒幕に尽力、幕末を生き抜き 新政府でも 活躍し
西郷隆盛、大久保利通と並んで 維新の三傑 と称されるのです。



山谷川に架かる大橋の袂には おりゅう灯籠(船着場灯籠)があります。 昔の出石川は
川幅が広く 水量も多く 交通運輸は 主として 川筋が利用され 灯籠は 夜間の灯明台と
して使われた。



大橋を渡り 北の見性寺(けんしょうじ)に行きます。 見性寺は 出石城の外堀とみたてた
出石川と堀川が交差する 防衛上の要衝であったため 寺院でありながら 隅櫓のような望楼
形の鐘楼を配し 城下町を守る役目をもった お寺で 戦いになれば 砦として守りを固めた。



大橋を渡り 南へ戻ると 永楽館があります。 永楽館は 明治34年に開館した 近畿最古
の芝居小屋で 歌舞伎などが 上演され 興行のない日は 一般公開され 廻り舞台、奈落な
ど 舞台裏が見学できますが 有料なので パス。 24日 テレビを見ていると 四国の金毘
羅さんの近くにある こんぴら大芝居が 日本で 一番古い芝居小屋 と言っていました。



南へ戻り 内町通りへ。 白壁の塀は 家老屋敷。 長屋門を入ると 人力車が・・。 奥
に 伊藤清永美術館があり 清永画伯の絵画が 多数展示してあるそうですが・・・。
左が 家老屋敷で 出石城内にあった江戸後期の家老・仙石左京の居館です。 左京は
仙石騒動で 森の露と消えた。 ここも 有料だった? 福成寺(ふくしょうじ)は・・。



家老屋敷の前にある 勝林寺へも寄り 車に戻りました。 あっ まだ 辰鼓楼に行って
ない。 駐車場を抜け 辰鼓楼を撮りに 行きました。 辰鼓楼は 明治時代の旧三の丸
大手門脇にある鼓楼で 今は 時計台です。
12:50 やっと 車に戻り 車で 弁当。 こう暑くては 食欲もありません。
13:05 車を出します。 帰路の途中に もう 1ヶ所 寄るところがあります。



家に帰り 駐車場でもらった”出石散策絵図”を見ると 北3kmのところに 出石神社や
此隅山城跡、白糸の滝 などがあるようです。 せっかくなので 行けば 良かった・・・。
県道2号線に出ると 一本道。 伊佐で 円山川に突き当り 右岸を南下。 県道104号
線に入り 道の駅やぶの手前の米地橋を渡り 踏切を越えた先に 西念寺があります。
出石から 19km。 13:28 西念寺に 着きました。



”あいたい兵庫” 春ー夏号 を見ていると 西念寺に 木戸孝允公(桂小五郎)潜伏遺跡の石
碑があるそうなので 見て行きましょう。 西念寺の入口には 古そうな宝篋印塔があります。
西念寺には お墓がたくさんあり 石碑がどこにあるのか 分からず 庫裏へ行って 聞き
ました。 鐘楼の左の木の陰に 石碑がありました。 説明板はなく・・これにも がっかり・・。
桂小五郎は 山陰道を西へ逃れて 城崎温泉の「つたや」に 幾松と身を隠したことは・・・。



話は それますが 歴史秘話を
網干に生まれた河野鉄兜に 作州から安東誠之助が 弟子入りし 鉄兜の鉄と 弟の東馬
の馬から 鉄馬と称した。 歳は 東馬より8歳若く 東馬も 弟のように可愛がっていた。
元治元年 長州藩は 蛤御門の変を勃発。 河野東馬は このとき 安東鉄馬と 行動を共にし
奮戦したが 鉄馬は 銃弾に倒れ・・。 東馬は 逃げる途中 出石藩に捕らわれたのです。
東馬の獄中の期間は 如何ほどであったか 明らかではないが 出石藩の奥女中の手助け
により 逃げることができたのです。 奥女中は 追放となり その後 結婚し 娘を生んだが
短い生涯を 終わったという・・。
網干に 「ふじや」 という料理旅館があり 東馬先生と数人が会食中 そこの仲居さんが
「世が世なれば・・」と話すにつけ 出石藩の奥女中の娘御であることが 分かった。
東馬先生も びっくり仰天。 両手をついて 厚く お礼を申し述べられたという・・。
慶応4年 新政府が樹立し 三条実実公より 民部省判事として 東馬に 召出しの使者が
来たが 応じなかった。 木戸公は 偉いが 伊藤博文は さほどではない・・・。


米地橋を渡り 県道104号線の戻り 南下。 13:56 一本柳の交差点に出て 国道
312号線を 南へ走り 14:03 和田山の料金所を突破し 播但道に入ります。 播但
道をひた走り 神崎南で 山ちゃんの家を見ると 軽トラ?が 停まっていて 山ちゃんは
きょうは 山はなし かと思いましたが・・。 氷ノ山でした・・。
14:42 花田ICを通過し 姫路バイパスに廻り 15:25 家に帰りました。
本日の走行距離は 往路:115.1km 西念寺まで 19km 復路:97.9kmで
計:232kmでした。
。。。。。。。
 。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。
。。  。。。。。。。
。。。。。。。