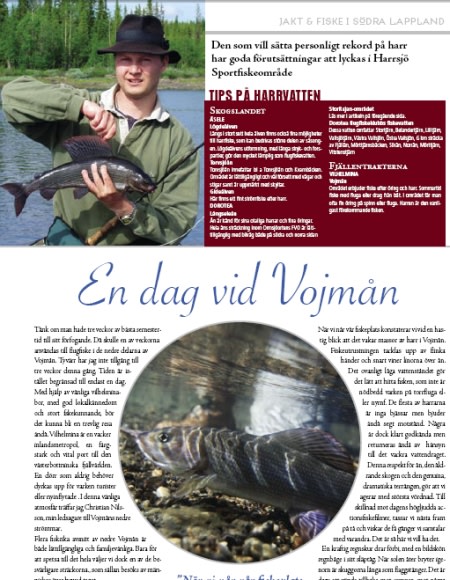2009年が始まり、半年ごとに替わるEUの議長国も新しくなった。2009年上半期にEUをまとめるのはチェコ共和国だ。チェコといえば2004年春にEUに加盟した新参者。もちろん、議長国を務めるのは今回が初めてだ。
しかし、議長国に就いた当初から大きな問題がチェコに重くのしかかった。イスラエルのガザ侵攻、そしてロシアのガス供給問題。
でも、それよりも大きな課題は、チェコの前に議長国を担当した国があまりに大きなインパクトを持っていたので、その影に隠れてしまい、リーダーシップがなかなか発揮できないのではないかという点だ。
その議長国はというと、そう、フランス。フランスが議長国を務めた2008年下半期は、ロシアのグルジア侵攻や金融危機など、いくつかの課題が出現したが、サルコジ大統領が活発に動き回り、外交手腕を発揮した。彼は果たして、EUの議長国の代表としてこれらの活動を行ったのか、それとも、フランス大統領として自国の存在感を世界に誇示しようとしたのか……? 「ドゴールの再来」と呼ぶ政治解説者もいるほどだ。EU首脳部としては、EUが国際舞台において一つにまとまり、影響力を及ぼすことを期待している。だから、一国がワンマンプレーをして自国の威信ばかりを誇示することは嬉しくないはずだ。一方、EUが抱えた様々な課題の解決は、フランスの外交力やサルコジ大統領の手腕のおかげによるところも大きいだろう。
世界各国の外交部は、フランスがEU議長国であった半年の間に、EUの電話番号=(イコール)パリのエリゼ宮殿だと覚えておけばそれで十分、と理解するようになった、なんていうジョークも聞かれる。(エリゼ宮殿はフランス大統領官邸)
いや、ジョークでは済まないかもしれない。年が変わり、EU議長国のバトンがフランスからチェコに移ったのにもかかわらず、ガザをめぐる問題に関してEUと協議するためにイスラエル外相リヴニが向かったのは、実はプラハではなく、パリだったのだ。EUが中東に派遣した外交代表団にも、本来は含まれないはずのフランス外相が加わっていた。それとは別に、サルコジ大統領もイスラエルに足を運んでいる。
とにかく、サルコジが大統領になってから、フランスが外交力を発揮して、国の存在感を誇示するようになってきた。さて、彼は第二のドゴール的存在になるのだろうか。

「サルコジ」と変換しようとするたびに「サル誇示」となるのは単なる偶然だと思いたい
――――――
さて、チェコの次にEU議長国のバトンを受け取るのは、スウェーデンだ。2001年上半期に次いで2度目のお役だ。新参者のチェコには無難に仕事をこなしてもらって、いざスウェーデンがバトンを受け取った後は、EUの代表として、今年12月にデンマーク・コペンハーゲンで開かれる気候変動枠組条約締結国会議(COP15)を成功に導いてもらなわなければならない。
と思ったら、スウェーデンはフライング・スタートして、既に議長国の役割を担い始めているというではないか。
どうしてかというと、チェコには海がない。だから、EU共通政策の一つの柱である「漁業政策」については、知識も経験もあまりない。そのため、漁業政策に限っては、スウェーデンが議長国という立場をチェコから委譲されることになったのだ。正確にいえば、ヨーロッパの海の北半分だけだが。(南半分はフランスに委譲)
つまり、スウェーデンはEUの漁業問題に関しては、一年ものあいだ、そのリーダーシップを発揮することができる。実はあまり知られていないかもしれないが、EUの共通漁業政策には問題が山ほどある。だから、スウェーデンがここでも力を発揮してくれることが期待される。
しかし、議長国に就いた当初から大きな問題がチェコに重くのしかかった。イスラエルのガザ侵攻、そしてロシアのガス供給問題。
でも、それよりも大きな課題は、チェコの前に議長国を担当した国があまりに大きなインパクトを持っていたので、その影に隠れてしまい、リーダーシップがなかなか発揮できないのではないかという点だ。
その議長国はというと、そう、フランス。フランスが議長国を務めた2008年下半期は、ロシアのグルジア侵攻や金融危機など、いくつかの課題が出現したが、サルコジ大統領が活発に動き回り、外交手腕を発揮した。彼は果たして、EUの議長国の代表としてこれらの活動を行ったのか、それとも、フランス大統領として自国の存在感を世界に誇示しようとしたのか……? 「ドゴールの再来」と呼ぶ政治解説者もいるほどだ。EU首脳部としては、EUが国際舞台において一つにまとまり、影響力を及ぼすことを期待している。だから、一国がワンマンプレーをして自国の威信ばかりを誇示することは嬉しくないはずだ。一方、EUが抱えた様々な課題の解決は、フランスの外交力やサルコジ大統領の手腕のおかげによるところも大きいだろう。
世界各国の外交部は、フランスがEU議長国であった半年の間に、EUの電話番号=(イコール)パリのエリゼ宮殿だと覚えておけばそれで十分、と理解するようになった、なんていうジョークも聞かれる。(エリゼ宮殿はフランス大統領官邸)
いや、ジョークでは済まないかもしれない。年が変わり、EU議長国のバトンがフランスからチェコに移ったのにもかかわらず、ガザをめぐる問題に関してEUと協議するためにイスラエル外相リヴニが向かったのは、実はプラハではなく、パリだったのだ。EUが中東に派遣した外交代表団にも、本来は含まれないはずのフランス外相が加わっていた。それとは別に、サルコジ大統領もイスラエルに足を運んでいる。
とにかく、サルコジが大統領になってから、フランスが外交力を発揮して、国の存在感を誇示するようになってきた。さて、彼は第二のドゴール的存在になるのだろうか。

「サルコジ」と変換しようとするたびに「サル誇示」となるのは単なる偶然だと思いたい
――――――
さて、チェコの次にEU議長国のバトンを受け取るのは、スウェーデンだ。2001年上半期に次いで2度目のお役だ。新参者のチェコには無難に仕事をこなしてもらって、いざスウェーデンがバトンを受け取った後は、EUの代表として、今年12月にデンマーク・コペンハーゲンで開かれる気候変動枠組条約締結国会議(COP15)を成功に導いてもらなわなければならない。
と思ったら、スウェーデンはフライング・スタートして、既に議長国の役割を担い始めているというではないか。
どうしてかというと、チェコには海がない。だから、EU共通政策の一つの柱である「漁業政策」については、知識も経験もあまりない。そのため、漁業政策に限っては、スウェーデンが議長国という立場をチェコから委譲されることになったのだ。正確にいえば、ヨーロッパの海の北半分だけだが。(南半分はフランスに委譲)
つまり、スウェーデンはEUの漁業問題に関しては、一年ものあいだ、そのリーダーシップを発揮することができる。実はあまり知られていないかもしれないが、EUの共通漁業政策には問題が山ほどある。だから、スウェーデンがここでも力を発揮してくれることが期待される。