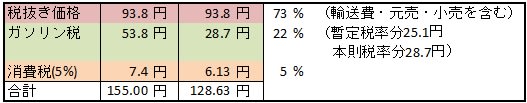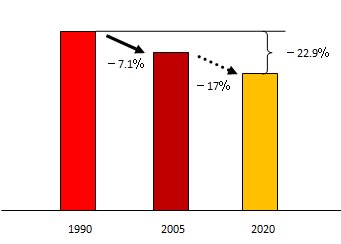カー・コーポラティブやカー・シェアリング、そしてレンタカーに対する需要が伸びている。それは、車の所有をやめ、普段は公共交通を利用しながら、週末など車が必要なときだけ、車を借りて利用する人が少しずつ増えているためのようだ。
とはいっても、そう簡単には車を手放せるものではない。カー・シェアリングなんていっても、その使い勝手がいまいち分からない。車が必要なときに自由に使いたいから、やはり自分の車を手元に置いておきたい。そして、一度乗用車を手にしてしまえば、たとえ公共交通を使えば普段は通勤が可能だと分かっていても、自分の手元にある車を遊ばせておくのはもったいないので、やはり通勤に使ってしまう。
もしくは、カー・シェアリングの使い勝手が良さそうだとは分かっていても、車を取りに行かなければならない。公共交通を使えるとしても、時間がかかるし、運賃もかかるから、やっぱりやめよう、という人もいるかもしれない。
だから、カー・シェアリングやレンタカーなどの利用者を今後も増やして行くためには、公共交通との連携も必要ではないかと思う。
なんて私が考えるよりも、もっと早くそのことに気付いて、積極的に取り組んでいる人たちがいる。例えば、ヨーテボリを中心とする西ヨータランド県の公共交通公社Västtrafikは、<定期券で普段、通勤や通学をしている人を対象に、カー・コーポラティブやカー・シェアリングの無料お試しキャンペーンを今年の3月から実施している。

このキャンペーンは西ヨータランド県の公共交通が、民間のカー・シェアリング会社Sunfleetや協同組合Majornas bilkooperativ(マイヨナ・カー・コーポラティブ)と提携することで実現することになった。カー・シェアリングなどを利用するためには、通常は年会費や拠出金の支払いが必要なのだけれど、お試し期間である3ヶ月間はそういった手続きなしで利用可能で、その使い勝手の良さを公共交通の利用客に実感してもらおう、というものなのだ。
それから私なら、公共交通の利用者であれば、カー・シェアリングの利用料を減額するとか、その逆とか、さらには、カー・シェアリングの車を取りに行くのに公共交通を使えば、運賃がタダになる、なんて制度もいいと思うけど、まだ実際に行われてはいないようだ。
このキャンペーンを推進している担当者の言葉。
「もし、自家用車を持っていれば、どこに出かけるのにも車に乗ることが習慣になってしまうけれど、実際には歩くこともできるし、自転車で行くこともできるし、公共交通を使うことだってできる。自家用車を持つのではなく、カー・シェアリングを利用するようにすれば、出かけようとするたびに、どの交通手段が一番適しているか、積極的な選択を心がけるようになる。」
とはいっても、そう簡単には車を手放せるものではない。カー・シェアリングなんていっても、その使い勝手がいまいち分からない。車が必要なときに自由に使いたいから、やはり自分の車を手元に置いておきたい。そして、一度乗用車を手にしてしまえば、たとえ公共交通を使えば普段は通勤が可能だと分かっていても、自分の手元にある車を遊ばせておくのはもったいないので、やはり通勤に使ってしまう。
もしくは、カー・シェアリングの使い勝手が良さそうだとは分かっていても、車を取りに行かなければならない。公共交通を使えるとしても、時間がかかるし、運賃もかかるから、やっぱりやめよう、という人もいるかもしれない。
だから、カー・シェアリングやレンタカーなどの利用者を今後も増やして行くためには、公共交通との連携も必要ではないかと思う。
なんて私が考えるよりも、もっと早くそのことに気付いて、積極的に取り組んでいる人たちがいる。例えば、ヨーテボリを中心とする西ヨータランド県の公共交通公社Västtrafikは、<定期券で普段、通勤や通学をしている人を対象に、カー・コーポラティブやカー・シェアリングの無料お試しキャンペーンを今年の3月から実施している。

このキャンペーンは西ヨータランド県の公共交通が、民間のカー・シェアリング会社Sunfleetや協同組合Majornas bilkooperativ(マイヨナ・カー・コーポラティブ)と提携することで実現することになった。カー・シェアリングなどを利用するためには、通常は年会費や拠出金の支払いが必要なのだけれど、お試し期間である3ヶ月間はそういった手続きなしで利用可能で、その使い勝手の良さを公共交通の利用客に実感してもらおう、というものなのだ。
それから私なら、公共交通の利用者であれば、カー・シェアリングの利用料を減額するとか、その逆とか、さらには、カー・シェアリングの車を取りに行くのに公共交通を使えば、運賃がタダになる、なんて制度もいいと思うけど、まだ実際に行われてはいないようだ。
このキャンペーンを推進している担当者の言葉。
「もし、自家用車を持っていれば、どこに出かけるのにも車に乗ることが習慣になってしまうけれど、実際には歩くこともできるし、自転車で行くこともできるし、公共交通を使うことだってできる。自家用車を持つのではなく、カー・シェアリングを利用するようにすれば、出かけようとするたびに、どの交通手段が一番適しているか、積極的な選択を心がけるようになる。」