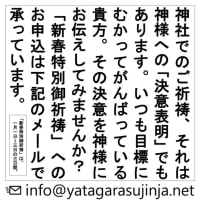6月最後の日曜日、夏越の大祓を斎行いたしました。
当社の氏子様以外の崇敬者様からお預かりした人形(ヒトガタ)11組も当日、恙なくお祓い致しましたことを報告申し上げます(後日お下がりを郵送しました)。
さて、大祓には旧暦と新暦というふたつの捉え方がありまして、当社は新暦を採用していたわけです。
決定的な資料があるわけではないのですが、当社周辺地域(伊那佐地区)には『夏越の大祓』という風習は元々なかったのではないかと感じます。
半面、「夏祭り」という行事は其々のムラ単位で残されていて、当社でも夏祭りだったのが夏越の大祓と習合したのではないかと考えています。
行事の式次第が通常の祭典と同様で、玉串奉奠を伴うことを理由に、あくまでも個人に感想のひとつとして書かせていただいております(汗)。
お預かりした人形(ヒトガタ)は旧暦の夏越の大祓である7月晦日にお焚き上げいたしました。
そして今日。
8月朔日の月次祭を斎行いたしました。
恒例により今月も、大祓詞、月次祭祝詞、武漢肺炎終息祈願祭祝詞、六根清浄太祓を奏上しました。
月次祭斎了後は普段できない社務や雑用、そしてこのブログの下書きをしていました(笑)。

さて、毎日早朝に執り行っている日供祭では携帯性の良さから白紙経本に書き写した祝詞を奏上しています。
このコロナ禍となってから、世の中に事あるごとに、また思いが湧き立つごとに「辞別き」の詞を書き換えてきました。
その度に祝詞の頁はツギハギになります。
今日も「辞別き」の詞を書き換えました。
ともすれば心をふさぎがちになるような世の中の情勢ですが、それに吞まれては禍罪穢れの思うつぼです。
元気出していきましょう。

そういえば今日は「八朔」の日でした。
「八朔」とは「八月朔日」のことで旧暦八月一日あたりは早稲の実がなることから、古くは農家の間でお世話になった人に、その早稲の実を送る習慣があったそうです。
転じて、いつもお世話になっている人に贈り物をする日として地域の風習として残っていったとこのこと。
八朔みかんを頬張って自然の恵みをお裾分けいただくような、そんな月にしたいものです。

元気出していきましょう!

先日、可愛らしいヤタガラスの折り紙のご奉納がありました。
たくさんの方にご覧いただきたいので、拝殿の賽銭箱のうえに展示しています。
よろしければご覧にお参りくださいませ。