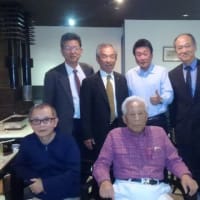漆黒の夜に浮かび上がるサン・マルコ大聖堂、抑制されたライトアップに荘厳さもいや増す。未踏の地に立ち、未知の光景を前にして、感情は昂る。しかし、その高揚は言葉になることもなく、私はただ笑うばかりだった。
海を越えて日本の外に出るのは8年ぶりのことだった。2009年にロンドンを訪れてからというもの、韓国にすら渡っていなかったのだ。
2010年の9月に母が倒れ、それから1年を過ぎた初冬に90年に及んだ天寿を全うし、またしてもそこから3年と少しがたった2015年の1月、もうそろそろ96歳になろうかという父が、体調を崩したかと思いきや、せっかちな性格そのままにそそくさと旅立っていった。このおおよそ5年半にいたる月日の間、私たち夫婦は二人で両親を「看取って」いた。旅行好きにかけては人後に落ちないと自負する私たちであるが、この間の目的地は自ずと「連絡がつき何かあったらすぐに東京に戻れるところ」となり、それを積み重ねた結果、ストレスも少ないけれど刺激も想像の範囲、そんな適度な旅にいつしか充足するようになっていた。ヴェネツィアにたどり着くには、ささやかな「飛躍」が必要だった。
現在の早稲田大学には、学部での共通言語を英語とし、さらに日本語を母語とする学生には1年間の留学を必修とする、国際教養学部という学部がある。昨年の5月くらいのことだろうか、当会奨学生で国際教養学部2年(当時。現在は3年生)に通う二人に軽い世間話のつもりで「どこに留学するのか」と尋ねた。一人は“北京”と答え、もう一人は“ヴェネツィア”と返した。
“それは旅へのいざないだった。それ以外のものではなかった。しかしそれが発作的に現われて、情熱に、いや錯覚にまで高められたのだ。”
“それとわかってみれば至極当然だったとはいうものの、その時はわれ知らず驚きつつ、自分が本来どこへ行くべきであったかを悟ったのである。一夜にして、比類なき幻想的な異国情緒に浸ろうと思うならば、一体どこへ行くべきだったか。それはいわずと知れているではないか。自分は実はあそこへ旅行しようと思っていたのだ。”
トーマス・マンの小説「ヴェニスに死す」(イタリアの名匠ルキノ・ヴィスコンティ監督が1971年に映画化「Death in Venice」)の主人公アッシェンバッハが、旅への憧憬をかきたてられたあげく彼の地が脳裏に浮かび、いても立ってもいられなくなった心情を語る一節である。そういうことなのだ。
予期せず現われた「ヴェネツィア」という地名に、「発作的に」旅への「情熱」は呼び覚まされ、アート・ビエンナーレ開催年にあたることを口実にしながら、後戻りできない「錯覚」にまで発展する。イタリアに行かなければならない!ヴェネツィアが呼んでいる!私は「冒険」を渇望していたのだ!ここまで頭に血が昇ってしまったら、もう手は施せない。「冒険」といっても、実のところは30歳以上離れた女子学生に頼りきることを前提にした、著しく虫のいい「冒険」であるのだが、そんなことに気づきはしない。
とはいえ、自宅からサン・マルコ大聖堂までに要した時間はおよそ21時間、「冒険」と呼ぶにふさわしい長旅だった。羽田からパリのシャルル・ド・ゴール空港へ、ドキドキしながら飛行機を乗り継ぎ、ヴェネツィアのマルコ・ポーロ空港で現地時間20時くらいに迎えに来てくれた後輩と落ち合う。そこから一緒にバスに乗り、車の乗り入れが禁じられている水の都に達してからは水上バス・ヴァポレットに乗り換える。水上から暮れなずむ宵闇の向こうに世界遺産を垣間見つつ、ようやくのことホテルに荷物をおろし、夕食をとるため町に出る。「合図するまで絶対に振り向かないでください」と若い後輩に厳命されるがまま、きょろきょろすることなく従順にサン・マルコ広場を横切り、「はい!」と号令されて微笑ましく回れ右をする。真正面には煌めくサン・マルコ大聖堂。立ち止まったのは広場の中心で、つまりはヴェネツィアの中心。その名の通り広々とした広場の真ん中で、見渡す限り歴史的建造物に囲まれ、感情の昂りを抑えることができないまま、私はただただ笑みを浮かべて「比類なき幻想的な異国情緒に」包まれていた。
ヴェネツィアは、陸地から4キロほど離れたアドリア海のラグーナ(潟)に浮かぶ118の小さな島からなっている。島々の間を道のように運河が縦横に走り、400もの橋がこれをつないでいる。2000年近く前に、無数の杭をラグーナに打ち込んで作った人工的な都市が今にいたるまで存続し、しかも1100年にわたっては『アドリア海の女王』として繁栄を謳歌した都市国家であったということも驚異であり、蜃気楼のように海に浮かぶ都市や運河に映える建築群といった幻想的な景観は誰をも惹きつけてやまない。
そこかしこで見かける傾いた建造物を横目に、乳母車と車椅子以外の車が禁止された(商品の輸送はもちろん船だし、急病人ももちろん船)入り組んだ迷路のような路地を歩いていると、歴史の重みは唐突に姿を現わす。ヴェネツィアは東西約4.5キロ、南北0.5〜2キロと広くはないのだが、教会や同信会館(信徒たちの集まりである同信会の社交場。同信会は名の通ったものだけでも50を超えていたそうだ)が、その小さな町のいたるところに存在する。15世紀から16世紀の名画・名作を擁するそれら歴史的な建造物に流れる空気は、華々しくも厳かで、信者ではない私にとっても「神聖」なものであった。その最たるものがサンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会であったし、それと並ぶサンタ・マリア・グロリオーサ・デイ・フラーリ教会の主祭壇画、天才ティツィアーノの「聖母被昇天」はヴェネツィアを代表する名画だ。信心深さは美術の母体となり、常に美術制作を促す。都市の繁栄とともに同信会(スクオーラ)が競い合い、町には美術品が溢れかえる。一方で、交易都市であるこの町は、繰り返し何度もペストに襲われ、その度に多くの人口を失ってきた。それをやり過ごすための信心と、低く垂れ込めた闇が去った後の絢爛を必要としたのだろう、その記憶が町の隅々に沈潜して今日に至っている。世界に先駆け、アート・ビエンナーレ(2年に一度の国際美術展。現代美術の祭典)を1895年に始めたのも、祝祭空間を必要とするヴェネツィアの特質によるものと思う。
私たちは連れ立ってビエンナーレに2日出向いた。私たちとは、もちろん私たち夫婦と、この夫婦が宿泊していたスキアヴォーニ河岸のホテルからたまたま歩いて20秒のところに住んでいた後輩、そしてビエンナーレを観るために、たまたまこの時ヴェネツィアにやって来たロンドン留学中の彼女の同級生、この4人だ。学生は驚くほどの低料金でEU内を移動でき(その金額を聞いて本当に驚いた)、同級生が各地に散らばる彼らは、その特権を謳歌してお互いを頼りながら行き来し、見聞と交流を蓄積している。もちろん、彼らばかりが学生なのではないから、現地の学生は概ねそうしているのだろう。ヨーロッパで排外主義が結局は蔓延するに至らない理由に触れた気がした。東海道線の鈍行で、一晩かけて東京から大阪に行ったことをなつかしい思い出として語る我が学生時代と比較するとき、「隔世の感」という言葉ひとつで片づけてはならない深慮がそこにはある。兎にも角にも、観光地ゆえに物価が高いヴェネツィアで、厳しい留学生活を送りながらも、様々な国の友人たちと苦楽を共にしながら成長している後輩の様子は、眩しく喜ばしいものだった。
ビエンナーレに話を戻そう。会場はヴェネツィアの東のはずれにある市立公園(ジャルディーニ)と国営造船所(アルセナーレ)の2箇所。国ごとのパビリオンや展示場が立ち並び、金獅子賞をかけて競う形式を維持しているため、国の財力や政治力が介入する余地を残すあり方に今日では批判も多く、歴史的使命は終わったという人もいる。だが、私たちは「優劣」に興味はなかったし(金獅子賞受賞作品も、それとも気づかずにチラっと見ただけだった)、刺激的な作品に出会いたいだけだったし、2日もかけているのに全てを見きれなかったその規模に満足した。せっかくだから例をあげると、当時の印刷物と自身の家族の写真を並べただけで、近現代史を雄弁に俯瞰した韓国館の展示はパワフルだったし、野蛮な人間存在を隠すことなく荒々しいパフォーマンスで提示したドイツ館の作品にはかき乱されたし(しかも作者はクラブの用心棒をしていたこともある女性だという)、「価値観」を変えられずにいまだ混乱したまま前にのめる国の光景を、暑苦しい労力で表現していたロシア館もおもしろかった。つまり、とても楽しかったのだ。
陽が高い時間帯、国際的観光地ヴェネツィアは人でごった返している。おしなべてTシャツに短パンのアメリカ人、大きな帽子をかぶって笑い声絶えない韓国のおばさんたち、一族郎党でがなりたてる中国人、考えうる限りの団体さんがひしめく。とりわけ人気スポットであるサン・マルコ広場やリアルト橋周辺は、それぞれ京都の清水寺や浅草の仲見世通りに倍の輪をかけた人口密度。それにひきかえビエンナーレ会場は広くてゆったりしている。そもそも興味を共有する人達しかいない。イタリアらしくスタッフも大らかで、楽しそうにおしゃべりに興じていたり、大声を発することに躊躇なく携帯電話に出て歩き回っていたり、我関せずとゆっくり本を読む人もいた。なのに、一線を超えそうな鑑賞者がいると、「NO!」とすごい剣幕で仕事をする。私たち夫婦は、日中はこうしたところに身を置き、早朝や陽が陰ってから人気スポットへ足を向けていた。つまり、とても快適でもあったのだ。
また、ビエンナーレ開催期間中は会場だけではなく、町中各所で連動した企画が催される。中でも英国人ダミアン・ハーストの個展「Treasures from the WRECK of the Unbelievable」は圧巻で、バジェットも含めたその規模たるや想像を絶していた。かつての「海の税関」を安藤忠雄が改装した美術館プンタ・デッラ・ドッガーナと、18世紀のバロック建築グラッシ宮、この離れた2会場を占拠した作品はタイトル通り「難破船アンビリーバブル号から引き揚げられた財宝」。それはあまりにも巨大で、驚くほどの物量で、そしてあからさまに「虚構」だった。風化しているように作られた「新品」で語られる「ニセ」物語そのものこそが「作品」で、そこからは“常識を疑え、「歴史」だって怪しいぜ”と下品にほくそ笑む彼の声が聞こえてくる。ヴェネツィアは、過去の栄光を物語る歴史遺産、そして最先端の現代美術、それらすべてを融合させて町の魅力としてきた。溢れかえる美術品と、杭の上に乗っているという町の成り立ちとがあいまって、現実でありながら虚構に身を置いているテーマパークのような世界を作り上げてきた。賛否渦巻くスターアーティストの個展は、この町でしか成立しなかった。
この旅行中、片道2時間ほど電車に揺られ、ルネサンスの聖地でメディチ家の都、フィレンツェにも1泊2日で行ってきている。当たり前のことだが、同じ古都とはいえ両者はまるで違う。ミケランジェロも観たし、ダヴィンチの前にも立った。これまた心躍る旅だったが、長くなるのでフィレンツェについてはまたの機会があればということにしたい。ただ、わかりやすく違いを際立てるために、食事について触れておこう。乱暴に言ってしまえば、ヴェネツィアは海鮮で、内陸のフィレンツェは肉なのだ。ヴェネツィアは魚やスカンピ(手長エビ)のグリルおよびフリットが売りだが、フィレンツェはビステッカと呼ぶ牛肉のステーキやトリッパ(ハチノス)の煮込みが名物、フリットもうさぎ。すべからく美味しい。マンマが仕切る食堂で食べたヴェネツィアの海鮮スパゲッティは忘れられない。ぶっきらぼうな親父に供されたフィレンツェのポルチーニ茸のパスタも同様だ。明日は日本に帰るという晩にヴェネツィアで恐る恐る注文した謎の料理「カニと黒人の麺」も絶品だった。その店の日本語メニューにそう記載されていたのだが、実態は「蟹肉とイカ墨のスパゲッティ」だった。自動翻訳ソフト、まだまだである。
妻への賞賛を込めて「食」にまつわるエピソードをもうひとつ。「必ずやジェラートを食べる。しかもイタリア語で注文して。」この旅に臨む妻の野望のひとつだった。たくさんあるジェラートの中からどれをチョイスするのか、それをカップにいれてもらうのかコーンに載せてもらうのか、コーンを選ぶとしたらプレーンなのかチョココーティングにするのか、日本で画一的なソフトクリームを買うのとはわけが違い、イタリアでジェラートを注文するには自身の「選択」を細密に表明しなければならない。国際教養学部4年で、昨年までヴェネツィアに留学していたもう一人の後輩に、美味しいジェラート屋さん、リアルト橋近くの人気店「SUSO」を教えてもらっていた。狭い路地にあるSUSOは観光客で溢れている。私たちの前に並んでいた人たちは戸惑ったり、指差したりしながら時間がかかっていた。店員が肩をすくめながら妻に目で語りかける。「決まっているなら言ってみたら」と。妻は堂々と彼女に返した、「ウン コーノ ピスタチオ(ピスタチオのジェラートをプレーンのコーンに載っけてちょうだい)」。意志的できっぱりとした発語に、店員は「このシニョーラはイタリア語で注文したわよ!」と喝采し、狭い店内が歓喜に包まれた。すぐ後ろに並んでいた関西からの若いお父さんに、多大なプレッシャーをかけてしまったのは申し訳なかったが(奥さんが「あんた、この子たちの分まで大丈夫やろなぁ」と詰めていたのが聞こえた)、ジェラートは青臭くて、とても爽やかだった。
6月2日の昼下がり、カナル グランデ(大運河)のシンボル、リアルト橋からマルコ・ポーロ空港行きの船に乗り、私たちはヴェネツィアを後にした。暑かった6泊8日の旅も終わろうとしていた。後輩は船着場まで見送ってくれた。彼女も留学を終え、9月には東京に帰ってくる。ヴェネツィアは満ち干を繰り返すラグーナの潮とともに今日も日を送っている。じきに沈むから、早く観に行った方がいいという人もいる。ロシアの文豪ツルゲーネフは、「ヴェネツィアを訪れると、幸福な人はますます幸福になり、不幸な人はさらに不幸を感じる。」と書いたそうだ。旅を終えしばらく経った。現地で撮った写真の整理は終えたが、友人たちと顔を合わすごとに、土産話の披露はまだまだ続きそうだ。この文章を綴ることもその一環ではあった。その度に、旅の愉悦が思い起こされ、行って帰ってきたばかりなのに「再訪」という情熱がじりじりと錯覚へと湧き返る。そう感じることができるのは、私が「幸福な人」だからか?だとしたら、それは照れ臭くも嬉しいことだ。
朴魯善