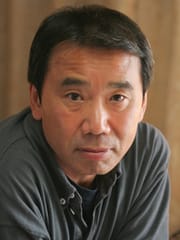村上春樹の短編集「女のいない男たち」を読んだ。

自分には面白い小説だった。結婚しない男あるいは妻に逃げられた男、浮気された男といろいろと出てくる。
この小説は若者が読むよりも、中年男性が読む方が楽しめると思う。それなりの人生経験を踏んだほうがこれらのストーリーにすんなり入っていけるかもしれない。
短編小説について吉行淳之介がこんなことを言っている。
「長い棒があるとしますね。長編は左から右まで棒の全体を書く。短編は短く切って切り口で全体をみせる。あるいは、短い草がはえていて、すぐ抜けるのと根がはっているのとがある。地上の短い部分を書いて根まで想像させるものがあれば、いくら短いものでもよいと思う。」
名言だ。
今回の村上春樹の短編集で、「シェエラザード」と「木野」は吉行淳之介の言う「地上の短い部分を書いて根まで想像させる」という匂いを感じた。両方とも決して超短いわけではないが、読者に想像させる行為を起こさせる。

「シェエラザード」の大意を追っていく。
この小説は「女のいない男」よりもその「面倒を見る女性」がクローズアップされる。
シェエラザードとは千夜に渡って毎夜王に話をしては気を紛らわさせた「千夜一夜物語」の王妃である。

(大意:文章より引用)
羽原は北関東の地方小都市にある「ハウス」に送られ、近くに住む彼女(シェエラザード)が「連絡係」として世話をすることになった。シェエラザードは35歳。。。身体のあちこちに贅肉が付着し始めた地方都市在住の主婦で、見るところ中年の領域に着実に歩を進めつつあった。羽原がそこに落ち着いた翌週から、ほとんど自明のこととして彼をベッドに誘った。シェエラザードは週に二度のペースで「ハウス」を訪れた。彼女は近所のスーパーマーケットで食品の買い物をし、それを車に積んでやってきた。時計の針が4時半を指すと。。ベッドを出て、床に散らばった服を集めて着こみ、帰り支度をした。
「十代の頃だけど」とある日、シェエラザードはベッドの中で打ち明けるように言った。
「私はときどきよその家に空き巣に入っていたの」
シェラザードが初めて他人の家に侵入したのは、高校二年生の時だった。彼女は地元の公立高校の、同じクラスの男の子に恋をしていた。。。しかし、それは女子高校生の多くがおおかたそうであるように、報われない恋だった。でも彼女はどうしてもその男の子をあきらめることができなかった。なんとかしないとそのままでは頭がおかしくなってしまいそうだった。
ある日シェエラザードは無断で学校を休み、その男の子の家に行った。彼の家には父親がいない。母親は隣の市の公立中学校で国語の教師をしていた。玄関のドアにはもちろん鍵がかかっていた。シェエラザードはためしに玄関のマットの下を探してみた。鍵はそこに見つかった。応答がないのを確かめ、また近所の人の目がないことを確認してから、シェエラザードは鍵を使って中へ入った。
彼の部屋は思った通り二階にあった。部屋の中はきれいに片づけられ、整頓されている。シェエラザードは勉強机の椅子に腰をおろし、しばらくそこでじっと座っていた。それから机の抽斗をひとつひとつ開けて、中に入っているものを細かく調べた。

「私は彼の持ちものがなにか欲しかった。だから彼の鉛筆を1本だけ盗むことにした。」
「そのかわりに、そこにしるしとして後に残していこうと思った。。。仕方ないからタンポンを一つ置いていくことにした。それを彼の机の一番下の抽斗の、いちばん奥の、見つかりにくいところにおいていく事にした。。。たぶんあまりに興奮したからだと思うけど、そのあとすぐに生理が始まってしまった」
「それから一週間ばかり、私はこれまでになく満ち足りた気持ちで日々を送ることができた」とシェエラザードは言った。
「彼の鉛筆を使ってノートにあてもなく字を書いた。その匂いを嗅いだり、それにキスしたり、頬をつけたり、指でこすったりした。。。」
「私は頭がまともに働かない状態になっていたのだろうと思う。」
彼女は十日後に再び学校を休み、彼の家に足を向けた。午前十一時。前と同じように玄関マットの下から鍵を取り出し、家の中へ入った。今回、半時間ばかりその部屋の中にいた。彼のノートを抽斗から出して一通り目を通した。彼の書いた読書感想文も読んだ。夏目漱石の「こころ」について書いたものだ。それからシェラザードは洋服ダンスの抽斗を開け、中に入っているものを順番に見ていった。どれも清潔に整頓されている。彼女は毎日彼のためにそういうことができる母親に、強い嫉妬を覚えた。無地のグレーのシャツを1枚抽斗から取り出し、それを広げ、顔をつけた。彼女はそれを手に入れたいと思った。
結局そのシャツを持って行くことをあきらめた。今回は鉛筆のほかに、抽斗の奥に見つけたサッカーボールをかたどった小さなバッジを持っていくことにした。ついでに、いちばん下の抽斗の奥に隠しておいたタンポンがまだあるかどうか、確かめてみた。それはまだそこにあった。
今回シェエラザードは二つ目のしるしとして、自分の髪を三本おいていく事にした。抽斗の中の古い数学のノートの間にはさんだ。彼女はそこを出て、その足で学校へ行き、昼休みのあとの授業に出席した。そして、その後の十日ばかりを、また満ち足りた気持ちで過ごした。彼のより多くの部分が自分のものになったような気がした。
空き巣に入るようになってから、学校の勉強にはほとんど身が入らなかった。シェエラザードはもともと成績は悪くなかった。だから彼女が授業中に指名されてほとんど何も答えられないとき、教師たちは怒るより前に怪訝そうな顔をした。
「私は定期的に彼の家に空き巣に入らないではいられないようになってしまった。」とシェエラザードは言った。
「二度目の<訪問>の十日後、私の足はまた自然に彼の家に向ってしまった。そうしないことには頭がおかしくなってしまいそうだったの。」
「私はまた玄関マットの下から鍵を取り、ドアを開けて中に入った。なぜかいつにも増して家の中はしんとしていた。。。途中で一度、電話のベルが鳴り出した。大きく響きわたる耳障りな音で、私の心臓はほとんど止まってしまいそうになった。。。十回ばかり鳴ってから止んだ。ベルが鳴り止んだあと、沈黙は前よりも深くなった」
浴室の脱衣場に洗濯かごをみつけ、その蓋を開けてみた。そこには彼と母親と妹と三人分の洗濯物が入っていた。シェエラザードはその中から男物のシャツを1枚見つけた。そのシャツを持って二階に上がり、もう一度彼のベッドに横になった。。。そしてシャツに顔を埋め、その汗の匂いを飽きることなく嗅ぎ続けた。。。とにかくその汗を吸い込んシャツを持ち帰ることにした。。。彼女は自分の下着を置いていくことを考えた。。。しかし、脱いでみると、実際にその股の部分が暖かく湿っていることがわかった。私の性欲のせいだ。しかし、そんな風に性欲で汚れてしまったものを、彼の部屋に残していくわけにはいかない。さて、何を置いていけばいいだろう。
シェラザードは黙り込んだ。「ねえ、羽原さん、もう一度私のことを抱けるかな?」と彼女は言った。
「できると思うけど」と羽原は言った。。。。この女は実際に時間を遡り、十七歳の自分自身に戻ってしまったのだ。。。そして二人はこれまでになく激しく交わった。。。
「それで結局、彼のシャツの代わりに何を置いていったの?」と羽原は沈黙を破って尋ねた。。。。。
この後転換点を迎える。
それは読んでのお楽しみだが、村上春樹は吉行の言う「根を想像させる」という読者の楽しみを残していく。
狂っていくシェエラザードの心理状況を実にうまく描写している。実際にありそうな話に聞こえる。出来心で忍び込んだあと、徐々にヒートアップしていく。その心理状況を彼女が語る形で表現していく。当然その話を聞いての主人公の心の動きも伝わるが、ここでは特筆すべきことではない。
1.2人の素性はわからない。
主人公はなんで北関東のある町にある「ハウス」にいるのか?全く語られない。宗教法人の特殊な工作員なのかもしれないし、犯罪に関わり匿ってもらっている男なのかもしれない。謎である。
彼女も名前がない。普通の主婦であることは明らかだが、どういう生活をしているかわからない。村上春樹らしい。
2.恋する惑星
この映画でフェイ・ウォン演じる女の子が香港島のヒルサイドエスカレーター横にあるトニーレオン扮する警官のアパートに忍び込む。ひょんなことから以前店の常連だったトニーレオンの自宅の鍵をフェイウォンが手に入れる。忍び込んで部屋の模様替えをするフェイウォンの姿が脳裏に浮かぶ。でもシェエラザードはそんな大胆なことはしない。自分が侵入しているという証拠を少しは残すがあからさまにそうだという形にしない。全然ちがうのだが、女の子が片思いの男の部屋に忍び込むという設定はこの2つくらいしか知らない。

3.美貌の女性としない設定
この短編集に出てくる女性は美女ではない。「ドライブマイカー」の女性運転手は「彼女はおそらくはどのような見地から見ても、美人とは言えなかった」としている。「独立器官」の主人公が好きになった女性も「彼女より容貌の優れた女性。。。とつき合ったことがあります。でもそんな比較は何の意味も持ちません。なぜなら彼女は私にとって特別な存在なのです。」と言う。ブスではないかもしれないが、美人ではなさそうだ。「木野」でも「美人という範疇に入るか微妙なところだが、髪がまっすぐで長く、鼻が短く、人目を惹く独特の雰囲気があった。」どぎつい謎があった。
これらの言葉にすごく自分は魅かれる。美人でなくても独特の吸引力があるということなのであろう。
「1Q84」に出てくる主人公と交わりあった中年女性も「ノルウェーの森」で一緒にギターをひいた女性もその系統である。
4.謎をつくる。
「転換点」をむかえた後、その時点からしばらく経ったあとの近未来物語があるという。
それが語られたら面白いなあと思う場面でストーリーは終末を迎える。主人公もシェエラザードが語るであろうストーリーを知りたがっていたのにと思っていた。研修で芥川龍之介「藪の中」を読んで、グループワークで事実を推定せよというのをやったことがある。近未来物語がどうなるのか?想像するとわくわくする。
「ネタばれあり」の別ブログを読むと、この作品についてすごい推理があります。
ネットで検索されることをお勧めします。

自分には面白い小説だった。結婚しない男あるいは妻に逃げられた男、浮気された男といろいろと出てくる。
この小説は若者が読むよりも、中年男性が読む方が楽しめると思う。それなりの人生経験を踏んだほうがこれらのストーリーにすんなり入っていけるかもしれない。
短編小説について吉行淳之介がこんなことを言っている。
「長い棒があるとしますね。長編は左から右まで棒の全体を書く。短編は短く切って切り口で全体をみせる。あるいは、短い草がはえていて、すぐ抜けるのと根がはっているのとがある。地上の短い部分を書いて根まで想像させるものがあれば、いくら短いものでもよいと思う。」
名言だ。
今回の村上春樹の短編集で、「シェエラザード」と「木野」は吉行淳之介の言う「地上の短い部分を書いて根まで想像させる」という匂いを感じた。両方とも決して超短いわけではないが、読者に想像させる行為を起こさせる。

「シェエラザード」の大意を追っていく。
この小説は「女のいない男」よりもその「面倒を見る女性」がクローズアップされる。
シェエラザードとは千夜に渡って毎夜王に話をしては気を紛らわさせた「千夜一夜物語」の王妃である。

(大意:文章より引用)
羽原は北関東の地方小都市にある「ハウス」に送られ、近くに住む彼女(シェエラザード)が「連絡係」として世話をすることになった。シェエラザードは35歳。。。身体のあちこちに贅肉が付着し始めた地方都市在住の主婦で、見るところ中年の領域に着実に歩を進めつつあった。羽原がそこに落ち着いた翌週から、ほとんど自明のこととして彼をベッドに誘った。シェエラザードは週に二度のペースで「ハウス」を訪れた。彼女は近所のスーパーマーケットで食品の買い物をし、それを車に積んでやってきた。時計の針が4時半を指すと。。ベッドを出て、床に散らばった服を集めて着こみ、帰り支度をした。
「十代の頃だけど」とある日、シェエラザードはベッドの中で打ち明けるように言った。
「私はときどきよその家に空き巣に入っていたの」
シェラザードが初めて他人の家に侵入したのは、高校二年生の時だった。彼女は地元の公立高校の、同じクラスの男の子に恋をしていた。。。しかし、それは女子高校生の多くがおおかたそうであるように、報われない恋だった。でも彼女はどうしてもその男の子をあきらめることができなかった。なんとかしないとそのままでは頭がおかしくなってしまいそうだった。
ある日シェエラザードは無断で学校を休み、その男の子の家に行った。彼の家には父親がいない。母親は隣の市の公立中学校で国語の教師をしていた。玄関のドアにはもちろん鍵がかかっていた。シェエラザードはためしに玄関のマットの下を探してみた。鍵はそこに見つかった。応答がないのを確かめ、また近所の人の目がないことを確認してから、シェエラザードは鍵を使って中へ入った。
彼の部屋は思った通り二階にあった。部屋の中はきれいに片づけられ、整頓されている。シェエラザードは勉強机の椅子に腰をおろし、しばらくそこでじっと座っていた。それから机の抽斗をひとつひとつ開けて、中に入っているものを細かく調べた。

「私は彼の持ちものがなにか欲しかった。だから彼の鉛筆を1本だけ盗むことにした。」
「そのかわりに、そこにしるしとして後に残していこうと思った。。。仕方ないからタンポンを一つ置いていくことにした。それを彼の机の一番下の抽斗の、いちばん奥の、見つかりにくいところにおいていく事にした。。。たぶんあまりに興奮したからだと思うけど、そのあとすぐに生理が始まってしまった」
「それから一週間ばかり、私はこれまでになく満ち足りた気持ちで日々を送ることができた」とシェエラザードは言った。
「彼の鉛筆を使ってノートにあてもなく字を書いた。その匂いを嗅いだり、それにキスしたり、頬をつけたり、指でこすったりした。。。」
「私は頭がまともに働かない状態になっていたのだろうと思う。」
彼女は十日後に再び学校を休み、彼の家に足を向けた。午前十一時。前と同じように玄関マットの下から鍵を取り出し、家の中へ入った。今回、半時間ばかりその部屋の中にいた。彼のノートを抽斗から出して一通り目を通した。彼の書いた読書感想文も読んだ。夏目漱石の「こころ」について書いたものだ。それからシェラザードは洋服ダンスの抽斗を開け、中に入っているものを順番に見ていった。どれも清潔に整頓されている。彼女は毎日彼のためにそういうことができる母親に、強い嫉妬を覚えた。無地のグレーのシャツを1枚抽斗から取り出し、それを広げ、顔をつけた。彼女はそれを手に入れたいと思った。
結局そのシャツを持って行くことをあきらめた。今回は鉛筆のほかに、抽斗の奥に見つけたサッカーボールをかたどった小さなバッジを持っていくことにした。ついでに、いちばん下の抽斗の奥に隠しておいたタンポンがまだあるかどうか、確かめてみた。それはまだそこにあった。
今回シェエラザードは二つ目のしるしとして、自分の髪を三本おいていく事にした。抽斗の中の古い数学のノートの間にはさんだ。彼女はそこを出て、その足で学校へ行き、昼休みのあとの授業に出席した。そして、その後の十日ばかりを、また満ち足りた気持ちで過ごした。彼のより多くの部分が自分のものになったような気がした。
空き巣に入るようになってから、学校の勉強にはほとんど身が入らなかった。シェエラザードはもともと成績は悪くなかった。だから彼女が授業中に指名されてほとんど何も答えられないとき、教師たちは怒るより前に怪訝そうな顔をした。
「私は定期的に彼の家に空き巣に入らないではいられないようになってしまった。」とシェエラザードは言った。
「二度目の<訪問>の十日後、私の足はまた自然に彼の家に向ってしまった。そうしないことには頭がおかしくなってしまいそうだったの。」
「私はまた玄関マットの下から鍵を取り、ドアを開けて中に入った。なぜかいつにも増して家の中はしんとしていた。。。途中で一度、電話のベルが鳴り出した。大きく響きわたる耳障りな音で、私の心臓はほとんど止まってしまいそうになった。。。十回ばかり鳴ってから止んだ。ベルが鳴り止んだあと、沈黙は前よりも深くなった」
浴室の脱衣場に洗濯かごをみつけ、その蓋を開けてみた。そこには彼と母親と妹と三人分の洗濯物が入っていた。シェエラザードはその中から男物のシャツを1枚見つけた。そのシャツを持って二階に上がり、もう一度彼のベッドに横になった。。。そしてシャツに顔を埋め、その汗の匂いを飽きることなく嗅ぎ続けた。。。とにかくその汗を吸い込んシャツを持ち帰ることにした。。。彼女は自分の下着を置いていくことを考えた。。。しかし、脱いでみると、実際にその股の部分が暖かく湿っていることがわかった。私の性欲のせいだ。しかし、そんな風に性欲で汚れてしまったものを、彼の部屋に残していくわけにはいかない。さて、何を置いていけばいいだろう。
シェラザードは黙り込んだ。「ねえ、羽原さん、もう一度私のことを抱けるかな?」と彼女は言った。
「できると思うけど」と羽原は言った。。。。この女は実際に時間を遡り、十七歳の自分自身に戻ってしまったのだ。。。そして二人はこれまでになく激しく交わった。。。
「それで結局、彼のシャツの代わりに何を置いていったの?」と羽原は沈黙を破って尋ねた。。。。。
この後転換点を迎える。
それは読んでのお楽しみだが、村上春樹は吉行の言う「根を想像させる」という読者の楽しみを残していく。
狂っていくシェエラザードの心理状況を実にうまく描写している。実際にありそうな話に聞こえる。出来心で忍び込んだあと、徐々にヒートアップしていく。その心理状況を彼女が語る形で表現していく。当然その話を聞いての主人公の心の動きも伝わるが、ここでは特筆すべきことではない。
1.2人の素性はわからない。
主人公はなんで北関東のある町にある「ハウス」にいるのか?全く語られない。宗教法人の特殊な工作員なのかもしれないし、犯罪に関わり匿ってもらっている男なのかもしれない。謎である。
彼女も名前がない。普通の主婦であることは明らかだが、どういう生活をしているかわからない。村上春樹らしい。
2.恋する惑星
この映画でフェイ・ウォン演じる女の子が香港島のヒルサイドエスカレーター横にあるトニーレオン扮する警官のアパートに忍び込む。ひょんなことから以前店の常連だったトニーレオンの自宅の鍵をフェイウォンが手に入れる。忍び込んで部屋の模様替えをするフェイウォンの姿が脳裏に浮かぶ。でもシェエラザードはそんな大胆なことはしない。自分が侵入しているという証拠を少しは残すがあからさまにそうだという形にしない。全然ちがうのだが、女の子が片思いの男の部屋に忍び込むという設定はこの2つくらいしか知らない。

3.美貌の女性としない設定
この短編集に出てくる女性は美女ではない。「ドライブマイカー」の女性運転手は「彼女はおそらくはどのような見地から見ても、美人とは言えなかった」としている。「独立器官」の主人公が好きになった女性も「彼女より容貌の優れた女性。。。とつき合ったことがあります。でもそんな比較は何の意味も持ちません。なぜなら彼女は私にとって特別な存在なのです。」と言う。ブスではないかもしれないが、美人ではなさそうだ。「木野」でも「美人という範疇に入るか微妙なところだが、髪がまっすぐで長く、鼻が短く、人目を惹く独特の雰囲気があった。」どぎつい謎があった。
これらの言葉にすごく自分は魅かれる。美人でなくても独特の吸引力があるということなのであろう。
「1Q84」に出てくる主人公と交わりあった中年女性も「ノルウェーの森」で一緒にギターをひいた女性もその系統である。
4.謎をつくる。
「転換点」をむかえた後、その時点からしばらく経ったあとの近未来物語があるという。
それが語られたら面白いなあと思う場面でストーリーは終末を迎える。主人公もシェエラザードが語るであろうストーリーを知りたがっていたのにと思っていた。研修で芥川龍之介「藪の中」を読んで、グループワークで事実を推定せよというのをやったことがある。近未来物語がどうなるのか?想像するとわくわくする。
「ネタばれあり」の別ブログを読むと、この作品についてすごい推理があります。
ネットで検索されることをお勧めします。