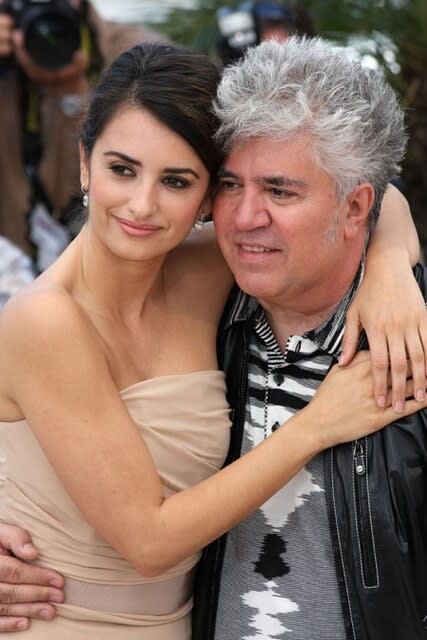映画「ミセス・クルナスvs.ジョージ・W・ブッシュ」を映画館で観てきました。

映画「ミセス・クルナスvs.ジョージ・W・ブッシュ」はドイツ映画。ドイツ居住のトルコ移民の男がタリバンの疑いをうけて強制収容所に留置されているのを救出しようと試みる母親と弁護士の物語である。アンドレアス・ドレーゼン監督による実話をもとにした人間ドラマだ。。肝っ玉母さんを演じたを演じたメルテム・カプタンは第72回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(主演俳優賞)を受賞した。太ったオバサンの振る舞いが気になる。
2001年10月、ドイツ・ブレーメン。トルコ移民のクルナス一家の母ラビエ(メルテム・カプタン)は、19歳の長男ムラートから、パキスタンのカラチへ旅行するという電話を受ける。ムラートはパキスタンでタリバンではないかと逮捕され、翌年2月、キューバの米軍グアンタナモ収容所に移送されていることがわかる。

警察も行政も動いてくれず、息子の無実を信じるラビエは、電話帳で見つけた人権派弁護士ベルンハルト・ドッケ(アレクサンダー・シェアー)の事務所に乗り込み無理やり協力を依頼する。そこでアメリカ政府を訴える集団訴訟に加わることを提案され、2人でワシントンD.C.へ向かう。
母親の奮闘ぶりは理解するが、ちょっと苦手なキャラクター
テロリストと疑われ、米軍のグアンタナモ収容所に収容された無実の息子を救おうと母が奮闘する。一家はトルコ出身でドイツに暮らす移民だ。主人公の夫はメルセデスベンツに勤めて、自分もベンツを乗り回す。3人の息子を育てるひと昔前の大阪のオバちゃんを連想させる猛烈なキャラだ。
正直こういう自分勝手で、自分の都合だけで振る舞うおばさんは苦手だ。弁護士事務所にも予約なしで乗り込んでいくし,運転すると一方通行路は逆走するし、信号無視もしょっちゅうだ。コンプライアンスの概念は皆無。からだ中に貴金属やアクセサリーをつけまくっているので,空港の手荷物検査場もなかなか通過できない。その強烈さで笑いを取ろうとするのがこの映画だが,自分は好感を持てなかった。一方で人権派弁護士は長身でやせていて、主人公と対照的。そのコントラストはいい。題名にあるジョージブッシュはまったく出てこない。

米軍のグアンタナモ収容所はいくつかの映画で取り上げられている。キューバ海上にある無法地帯のエリアだ。ジョディフォスター主演「モーリタニアン 黒塗りの記録」では、同じくテロの嫌疑のある男の弁護の話だった。そこでの拷問シーンは想像を超える酷いものだ。拘束されたムラートも無実なのに疑いを持たれたということになっている。当地では拷問を受けているようだ。ここではそのシーンはない。ただ、あの911テロ事件の直後にイスラム信仰のためとはいえ、疑いを持たれる渡航をするのは自業自得だ。

リベラル派はアメリカの残虐な囚人への仕打ちを糾弾するが、一方ではあのテロに関わった可能性で当然の処置とも考えられる。今のイスラエル問題同様意見がわかれる論点だ。平和な日本で良かったと感じる。

映画「ミセス・クルナスvs.ジョージ・W・ブッシュ」はドイツ映画。ドイツ居住のトルコ移民の男がタリバンの疑いをうけて強制収容所に留置されているのを救出しようと試みる母親と弁護士の物語である。アンドレアス・ドレーゼン監督による実話をもとにした人間ドラマだ。。肝っ玉母さんを演じたを演じたメルテム・カプタンは第72回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(主演俳優賞)を受賞した。太ったオバサンの振る舞いが気になる。
2001年10月、ドイツ・ブレーメン。トルコ移民のクルナス一家の母ラビエ(メルテム・カプタン)は、19歳の長男ムラートから、パキスタンのカラチへ旅行するという電話を受ける。ムラートはパキスタンでタリバンではないかと逮捕され、翌年2月、キューバの米軍グアンタナモ収容所に移送されていることがわかる。

警察も行政も動いてくれず、息子の無実を信じるラビエは、電話帳で見つけた人権派弁護士ベルンハルト・ドッケ(アレクサンダー・シェアー)の事務所に乗り込み無理やり協力を依頼する。そこでアメリカ政府を訴える集団訴訟に加わることを提案され、2人でワシントンD.C.へ向かう。
母親の奮闘ぶりは理解するが、ちょっと苦手なキャラクター
テロリストと疑われ、米軍のグアンタナモ収容所に収容された無実の息子を救おうと母が奮闘する。一家はトルコ出身でドイツに暮らす移民だ。主人公の夫はメルセデスベンツに勤めて、自分もベンツを乗り回す。3人の息子を育てるひと昔前の大阪のオバちゃんを連想させる猛烈なキャラだ。
正直こういう自分勝手で、自分の都合だけで振る舞うおばさんは苦手だ。弁護士事務所にも予約なしで乗り込んでいくし,運転すると一方通行路は逆走するし、信号無視もしょっちゅうだ。コンプライアンスの概念は皆無。からだ中に貴金属やアクセサリーをつけまくっているので,空港の手荷物検査場もなかなか通過できない。その強烈さで笑いを取ろうとするのがこの映画だが,自分は好感を持てなかった。一方で人権派弁護士は長身でやせていて、主人公と対照的。そのコントラストはいい。題名にあるジョージブッシュはまったく出てこない。

米軍のグアンタナモ収容所はいくつかの映画で取り上げられている。キューバ海上にある無法地帯のエリアだ。ジョディフォスター主演「モーリタニアン 黒塗りの記録」では、同じくテロの嫌疑のある男の弁護の話だった。そこでの拷問シーンは想像を超える酷いものだ。拘束されたムラートも無実なのに疑いを持たれたということになっている。当地では拷問を受けているようだ。ここではそのシーンはない。ただ、あの911テロ事件の直後にイスラム信仰のためとはいえ、疑いを持たれる渡航をするのは自業自得だ。

リベラル派はアメリカの残虐な囚人への仕打ちを糾弾するが、一方ではあのテロに関わった可能性で当然の処置とも考えられる。今のイスラエル問題同様意見がわかれる論点だ。平和な日本で良かったと感じる。