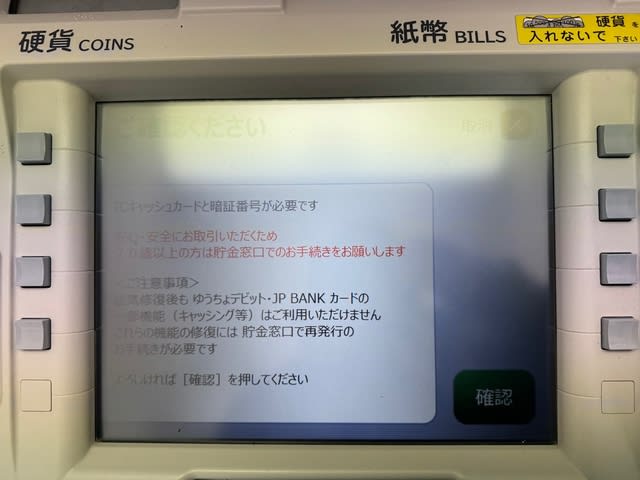温泉保養施設の通路に並べてある観葉植物のパキラに見慣れないモノがあった。
パキラという名前も同行の連れから教えてもらったものだけれど、それより枝に雫が付いていて興味を覚えた。
直前に霧吹きなどで水遣りをしたようにも見えなくて、触ってみると、雫のまま固まっていたり、ネバネバしていたり、水滴状だったりとさまざま。
これは聞いたことも観たこともないけれど、密に違いないと思い、舐めてみた。
案の定、甘い蜜だったので、検索すると、蟻(アリ)を誘き寄せ、害虫や害虫の産み付けた卵などを退治させる仕掛けなのだという。
それを取って舐めたらダメでしょう、と連れにたしなめられたのだが、なかなかの甘さだった。
室内に飾る中南米原産の観葉植物なので、わがニホンミツバチがその蜜にありつくことはないのだろうと何だか残念な気もした。