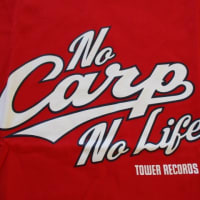今でも、ラジオが大好きです。
朝も夜もラジオ。
テレビは、ニュース以外はほとんど見なくなった今、BGMならぬバック・グラウンド・ラジオが空気のような存在になっています。
ラジオには、AM、FM、短波といった種類があるのですが、商売をしている人やタクシーの運転手さんはAM派、音楽好きはFM派、株や競馬をする人は短波というイメージです。
小職の場合は、FM派。音楽を中心にしたプログラムは、本を読みながら、仕事をしながらでも聴くことができ、気楽な雰囲気を醸し出してくれます。
特に、J-WAVEの登場後、各局の番組構成も変わってきており、少人数で運営されているラジオ局の手腕が手を取るように分かります。
最近では、インターネットで全国のラジオ局を聴けたり、文字放送もある見えるラジオという技術進化も続いています。
しかしながら、若い世代、特に中高生や大学生はラジオという媒体自体に興味がないようです。
数十年前にわたしが勤めていた広告代理店にもラテ局(ラジオ・テレビ局)があり、当時の広告扱いではテレビ、新聞、雑誌に続く第四の広告メディアとしての存在感がありました(今では、インターネット広告が新聞を凌ぐ勢いで伸びています)。
QR(文化放送)、LF(ニッポン放送)、エフエム東京の営業の方々はとてもフレンドリーで、ちょっとタカビーなテレビ局の営業の人たちよりも、よく飲みに行っていた記憶があります。
思い起こせば、ラジオとの出会いは小学生高学年の頃。
「オールナイトニッポン」「セイヤング」といった深夜放送を知った頃からだと思います。
親に隠れて布団の中でイヤフォンで聴いていた深夜放送。
翌日、悪友と、その他愛もない話をするのが大人の入口のような感じでした。
「オレは、走れ歌謡曲まで聞いたぞ・・・」と自慢するヤツ(この番組は午前3時からオンエア)、「リクエスト葉書を読んでもらった」と誇るヤツ・・・。
結構楽しんでいたように思います。
落合恵子さん、谷村新司さん、せんだみつおさん、ビートたけしさんなどなど、その後の若者のオピニオンリーダーはラジオから生まれてきたといっても過言ではないと思います。
当時は、AMの全盛時代。
FMはNHK中心であり、民放FM局では夕刻のゴールデンタイムに通信高校講座をやっていました。
しかしながら、FMの高音質、ステレオ放送は魅力的で、当時、「FMファン」や「FMステーション」といったFMの番組雑誌が書店で複数発売されていました。
このころが、ちょうどラジカセが普及し始めた時代。
ラジカセとは、AM、FMのチューナーと録音機能つきのカセットレコーダーが一体化したもので、当初はスピーカーが一つしかないモノラル版。
その後、SONYを皮切りにステレオのラジカセが登場しました。
そのラジカセでラジオ番組やそこで流れる好きな音楽を録音することを「エア・チェック」などと称していました。
本当にアナログな世界です。
チューブの歌にもある「渚のカセット・・・好きな歌だけ詰め込んで・・・」若い人には理解できないと思います(笑)。
また、ラジオ好きの中には、海外の放送を聴くオタクも存在しており、英国BBC、米国VOA、オーストラリアなどの放送局の電波を受信していました。
国際郵便を出すと海外の放送局から届く、確か「ベリカード」と呼んでいたと思うのですが、ネットがない当時、世界とつながるための道具の一つがラジオだったのです。
SONYのスカイセンサーや松下電器のジャイロなど、親に無理を言えば買ってもらえる価格帯の高級ラジオは友人とコミュニケーションを取るためのツールだったのです。
画像なしの音のみの世界。
それが想像力をかきたてるということ・・・それがラジオの魅力だと思います。
当時、「ながら族」という言葉がありましたが、ラジオを聴きながら勉強する受験生のことを指していました。
孤独の中で、DJや好きな音楽を聴きながら一人深夜に勉強する・・・。
そんな彼彼女をラジオが支え続けたのだと思います。
さらに悩み相談や恋愛話などもリクエスト葉書という媒体を通じてオンエアされ、リスナーの連帯感を醸成していたように思います。
今のwebでは、そんなアナログ的な部分がとても少ないように思います。
フィーリングからロジカルへ、アナログからデジタルへ・・・時代は変わりました。
そして、ラジオの最大の魅力は、ドキドキ感だと思います。
聴覚だけで想像を働かせる・・・結構広がりを感じさせる時間です。
年とともに薄れゆくドキドキ感。
媒体としては晩年期、衰退期にあるラジオを使って、再び取り戻そうと思っています。