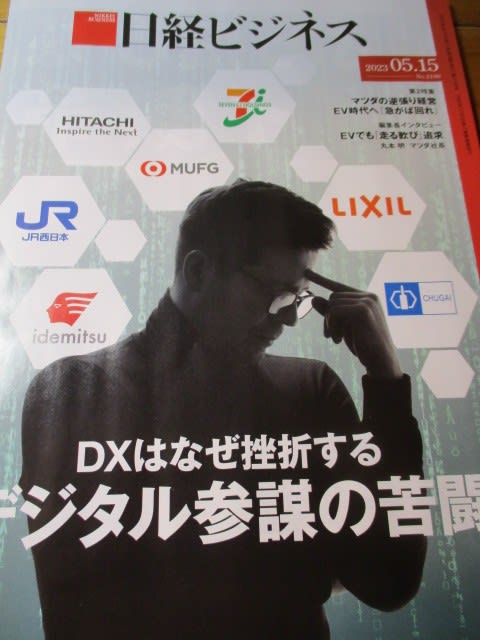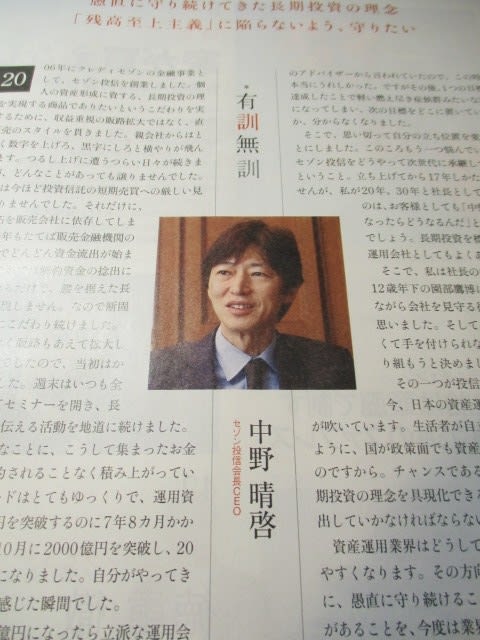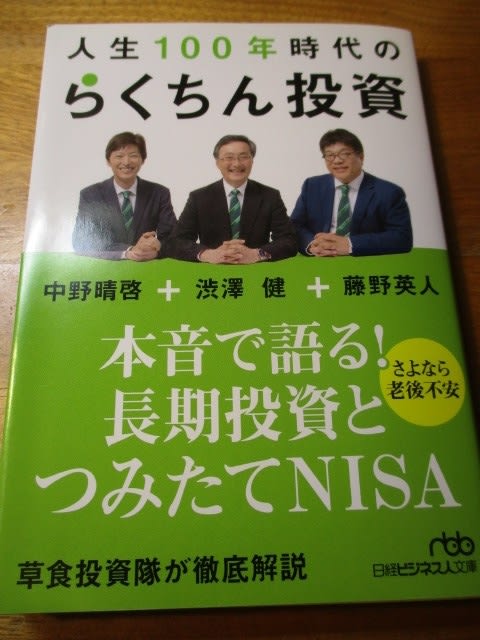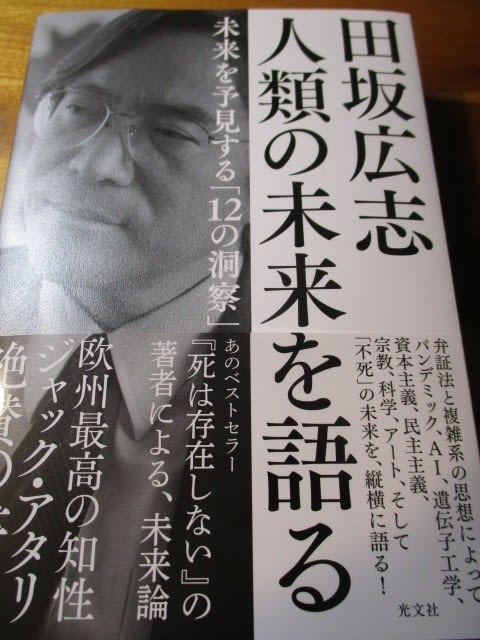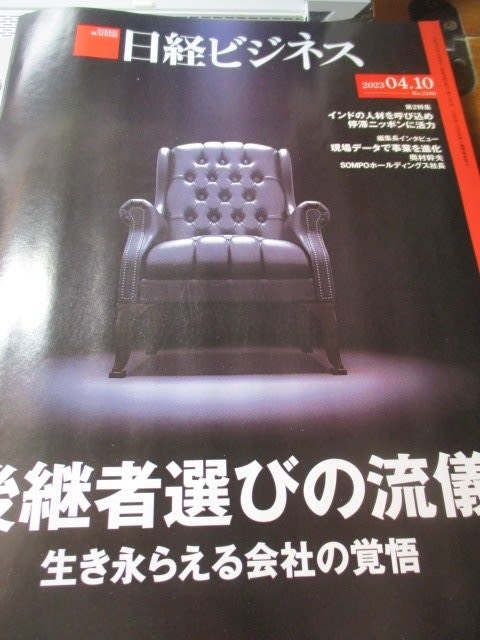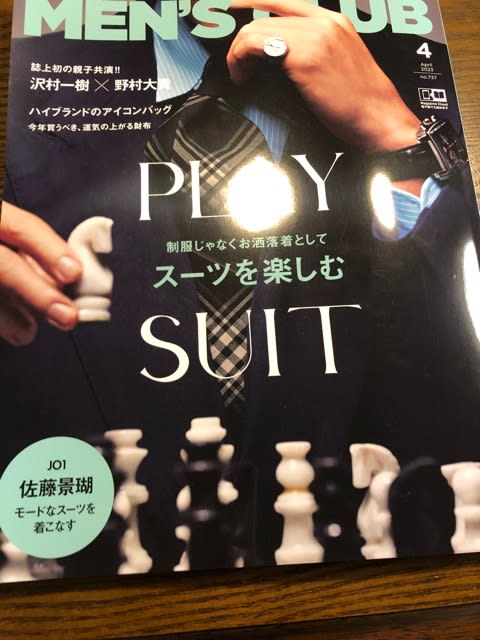企業のバックグラウンドで営まれている健康保険組合。
組合健保と呼ばれています。
国が運営する協会けんぽと共に日本の皆保険制度を支えています。
その健保組合の8割が赤字とのこと・・・ショッキングな事実です。
高齢化、少子化、人口減少が背景にあると思うのですが、それにしても、ここまで酷いとは思いませんでした。

日経ビジネス2023.5.29号の特集は、「健保沈没 人的資本経営の急所」。
健康経営、人的資本経営がトレンドワードになっている今、組合健保のサバイバルの重要性を指摘しています。
最近では、コカ・コーラボトラーズ健保組合、国際自動車健保組合などが解散。
健保組合危機は、時間とともにそのリスクを高めています。
Contents
Part1 赤字組合は8割 解散ラッシュの予想
Part2 現役世代の健康 財政改善のカギに
Part3 医療費膨張招いた40年の失策 健康への無関心 経営者に回るツケ
Part4 健保組合と経済界 国、医師会に声あげよ
最近では、政府が打ち出した異次元の少子化対策の財源を社会保険料から徴収しようという動きもあります。
この10年で高齢者医療費4300億円を健保組合が負担、今年の4月からは出産育児一時金負担が増加・・・。
何でもかんでも社会保険料・・・何だかなあ!?と言う感じです。

大赤字の健保組合が解散したとしても、受け皿となるのは国。
結局は、血税によって支えることになります。
年金、健保・・・社会保険制度自体が、少子高齢化、人口減少に耐えられない状況になっていると思います。
社会全体、国民全体で応分に負担していなければ、国民皆保険も崩壊することになるでしょう。
小手先、パッチワーク的な改善レベルでは効果性はないと思います。
企業としては、健康経営、人的資本経営というコンセプトと結びつけていくマネジメントをしていかなければなりません。
そして、最終的には、働く現役世代も高齢者も全体バランスをとって負担増していくしか方法論はないのではないかと思います。