てとてと作業所やグループホームを運営するNPO法人なかまとの井澤泉理事長のお話を伺った。
なかまと(孤独にならず)手と手と(双方向で)をたずさえて歩もう、との願いから法人名、事業所名をつけたそうだ。
自分が聞きたかった話しであるが、せっかくなのでいろんな人にきてもらって勉強会形式にした。
勉強会にはいろんな立場の方、25人くらいの方が参加してくださった。
なかまとは平成13年にグループホームを白樺の家の業務委託により運営開始。
もともと白樺の家という自閉症者生活施設を運営る信濃の郷による業務委託からはじまった。
しかし親の会の活動は自分の子供の指定席のために頑張って活動し、親としては指定席を買ったつもりになる。
結果、新たに加わる人には寄付をもとめたりということになりがち。
市民社会では当事者を抜きに周囲だけきめてはならない。
そういうしがらみとは無縁でやりたいと、平成15年にNPOとして独立したそうだ。
そしてさらにグループホームを2カ所開設。
宅幼老所や、認知症対応型グループホーム、はたらき支援センターなども次々と開設し事業展開している。
今では約40名の職員。
グループホームは知的と精神あわせて計4カ所で、定員は19人(知的15人、精神4人)
作業所は2カ所あわせて60名を受け入れている。
グループホームを開設する際には世話人を全国に募集をしてIターンの夫婦に来てもらったりするそうだ。
まったくの素人だったりするようだが、世話人会を毎月開き燃え尽きないようにしているようだ。
グループホームも万能ではない。
グループホームでは施設のような大きな管理はないが、小さな決まり事やルールなどの管理は多い。
そして小さな雑事は多い。
メンバーの相性などもありなかなか大変なようだ。
今回はNPOで事業を展開するにあたってのお役所との交渉のコツをいくつか教えていただいた。
前例に従うのが役所だから前例を作る。
単純な間違いをあえて挿入し、ご指導をあおぎ労をねぎらう。
などなどがポイント。
しかし役所の縦割り行政や硬直化した姿勢、不作為にはまったく不満だという。
社会福祉法人は優遇されてNPOは同じことをやっていても課税されるなどおかしなことがたくさんある。

(てとてと松川共同作業所)
作業所での就労に関しては、工賃の高い物は下請けに出さず安い物を下請けに出すために工賃倍増は構造的に難しい。
こんなのやってられないと言う気持ちが一般就労へのモチベーションになると半ば自嘲的に言う。
障害者雇用としては法定雇用率として55人に1人は障害者を雇わなければならないという制度があるがなかなか推進されない。
現制度で上手くいっていないのだから一般就労が難しければ就労の場を作っていく必要がある。
大企業に関しては特例子会社という制度があるが、中小企業に関しては各企業が出資して会社をつくりそこで障害者を雇用するというのがいいのではないかと主張。
自立支援法から障がい者総合福祉法へとあらたな福祉の仕組みが検討されている今こそ主張しないとまた困った仕組みができてしまう。
いわなくっちゃあ、世の中変わらない。
まったくその通り。声を上げ行動していこう。
なかまと(孤独にならず)手と手と(双方向で)をたずさえて歩もう、との願いから法人名、事業所名をつけたそうだ。
自分が聞きたかった話しであるが、せっかくなのでいろんな人にきてもらって勉強会形式にした。
勉強会にはいろんな立場の方、25人くらいの方が参加してくださった。
なかまとは平成13年にグループホームを白樺の家の業務委託により運営開始。
もともと白樺の家という自閉症者生活施設を運営る信濃の郷による業務委託からはじまった。
しかし親の会の活動は自分の子供の指定席のために頑張って活動し、親としては指定席を買ったつもりになる。
結果、新たに加わる人には寄付をもとめたりということになりがち。
市民社会では当事者を抜きに周囲だけきめてはならない。
そういうしがらみとは無縁でやりたいと、平成15年にNPOとして独立したそうだ。
そしてさらにグループホームを2カ所開設。
宅幼老所や、認知症対応型グループホーム、はたらき支援センターなども次々と開設し事業展開している。
今では約40名の職員。
グループホームは知的と精神あわせて計4カ所で、定員は19人(知的15人、精神4人)
作業所は2カ所あわせて60名を受け入れている。
グループホームを開設する際には世話人を全国に募集をしてIターンの夫婦に来てもらったりするそうだ。
まったくの素人だったりするようだが、世話人会を毎月開き燃え尽きないようにしているようだ。
グループホームも万能ではない。
グループホームでは施設のような大きな管理はないが、小さな決まり事やルールなどの管理は多い。
そして小さな雑事は多い。
メンバーの相性などもありなかなか大変なようだ。
今回はNPOで事業を展開するにあたってのお役所との交渉のコツをいくつか教えていただいた。
前例に従うのが役所だから前例を作る。
単純な間違いをあえて挿入し、ご指導をあおぎ労をねぎらう。
などなどがポイント。
しかし役所の縦割り行政や硬直化した姿勢、不作為にはまったく不満だという。
社会福祉法人は優遇されてNPOは同じことをやっていても課税されるなどおかしなことがたくさんある。

(てとてと松川共同作業所)
作業所での就労に関しては、工賃の高い物は下請けに出さず安い物を下請けに出すために工賃倍増は構造的に難しい。
こんなのやってられないと言う気持ちが一般就労へのモチベーションになると半ば自嘲的に言う。
障害者雇用としては法定雇用率として55人に1人は障害者を雇わなければならないという制度があるがなかなか推進されない。
現制度で上手くいっていないのだから一般就労が難しければ就労の場を作っていく必要がある。
大企業に関しては特例子会社という制度があるが、中小企業に関しては各企業が出資して会社をつくりそこで障害者を雇用するというのがいいのではないかと主張。
自立支援法から障がい者総合福祉法へとあらたな福祉の仕組みが検討されている今こそ主張しないとまた困った仕組みができてしまう。
いわなくっちゃあ、世の中変わらない。
まったくその通り。声を上げ行動していこう。










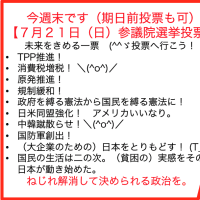
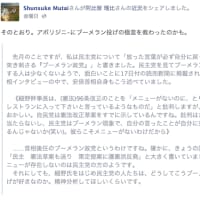




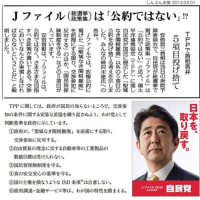

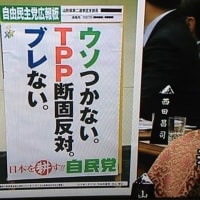

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます