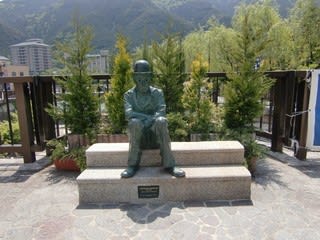旧益田郡萩原町(はぎわらちょう)は岐阜県中部・飛騨地方の南部に位置した町です。益田郡小坂町、下呂町、馬瀬村、大野郡宮村、久々野町に隣接。南飛騨総鎮守町の中央を飛騨川が流れ、周囲は1000メートル級の山に囲まれており、昔から益田郡の政治・文化の中心地として栄えてきました。町内には天下十刹(じっせつ)の一宇「禅昌寺」や、南飛騨総鎮守「久津(くづ)八幡宮」を擁し、また下呂総合庁舎や下呂警察署などの機関も置かれています。「町の木:イチイ」「町の花:萩」を制定。

この町に「高山本線:上呂(じょうろ)駅」があると聞いて、物好きにも確かめにきた二人。で、「上呂」「下呂」とあるのだから、真ん中の「中呂」という地名もあるのかなと思って調べたら、下呂の北方に本当に中呂(ちゅうろ)という地区がありました😲

明治22年(1889)、町村制の施行により、益田郡三郷村・宮田村・川西村、大野郡山之口村が発足。
1897年、三郷村・宮田村が合併、益田郡萩原村が発足。同年10月、町制を施行し益田郡萩原町(初代)となる。
1956年、益田郡川西村、大野郡山之口村と合併、益田郡萩原町(2代)が発足。
2004年、益田郡下呂町、小坂町、金山町、馬瀬村と合併、下呂市萩原となりました。
マンホールには、「降り注ぐ太陽の下、山とビルを背景に飛騨川で遊ぶ子供たち」がデザインされています。

農業集落排水のマンホールには、「飛騨はぎわら」の文字を中心に、「飛騨川で遊ぶ子供達」がデザインされています。

昭和35年7月1日制定の町章は「「ハギ」を端的に図案化し、「信義」・「勤労」・「友愛」を印象付けて円満平和を近代的総会に表したものです。昭和31年8月に制定されていたものを、再制定しました。」合併協議会資料より


撮影日:2012年5月16日