福井市(ふくいし)は福井県北部(嶺北)に位置する市です。2006年2月1日に、足羽郡美山町、丹生郡越廼村・清水町を編入合併。勝山市、大野市、越前市、鯖江市、坂井市、今立郡池田町、吉田郡永平寺町、丹生郡越前町に隣接。福井県の県庁所在地及び県内では人口最多(県人口の約34%)の自治体で、中核市に指定。『柴田勝家』の北ノ庄城時代から城下町として都市形成が成され、江戸時代には石高68万石を数える日本屈指の大城下町として発展。朝倉氏滅亡後に一乗谷から移転した文化人の影響もあり華やかな文化や行事が行われてきました。市域の約半分が山林で、海岸部を除く全域が九頭竜川水系流域。本流を含む三大河川が合流する地点から東側の南北に平野が広がり、その中例外として市中心部のすぐ南側に足羽山(117m)、兎越山(89m)、八幡山(139m)の足羽三山が連なります。南東部には足羽川及びその支流に沿った谷間の小盆地・一乗谷などが点在。東端付近には市最高地点の飯降山(884m)がそびえます。

昭和20年(1945)の福井大空襲、昭和23年(1948)の福井地震(1か月後に集中豪雨で九頭竜川堤防決壊)とわずか3年の間にそれぞれ人口の1〜2%を失う大災厄に2度も見舞われるという、近現代日本の都市としては唯一ともいえる経験を経ながら、当時の倍以上の人口にまで復興したことから不死鳥を街のシンボルとしています。「市の木:松」「市の花:紫陽花」を制定。
キャッチフレーズは「人、街、自然、文化の『交・響・楽・彩 ふくい』(まじわり・ひびきあい・たのしみ・いろどるまち)」

明治22年(1889)、市町村制の施行により、足羽郡福井城下及び石場畑方の区域をもって、福井市が発足。
足羽郡東安居村・和田村・木田村・東安居村・社村・麻生津村・酒生村・一乗谷村・上文殊村・下文殊村・六条村・東郷村・殿下村・下宇坂村・上宇坂村が発足。
吉田郡円山東村・円山西村・西藤島村・中藤島村・河合村・藤岡村・森村が発足。
丹生郡西安居村・天津村・三方村・志津村が発足。
坂井郡大安寺村・国見村・殿下村・鶉村・本郷村・棗村・鷹巣村が発足。
大野郡芦見村・羽生村・上味見村・下味見村が発足。
1931年、足羽郡東安居村三橋区域を編入。
1935年、吉田郡森田村が町制を施行、吉田郡森田町となる。
1936年、足羽郡和田村、木田村を編入。1939年、足羽郡東安居村を編入。
1941年、吉田郡円山東村を編入。1942年、吉田郡円山西村を編入。
1948年、吉田郡西藤島村田原下及び牧の島区域を編入。
1949年、足羽郡社村小山谷区域を編入。1951年、吉田郡西藤島村を編入。
1954年、 足羽郡社村、丹生郡西安居村、吉田郡中藤島村を編入。
1955年、坂井郡鶉村、本郷村、棗村、鷹巣村が合併、坂井郡川西町が発足。
足羽郡酒生村、一乗谷村、上文殊村、下文殊村六条村が合併、足羽村が発足。同年、足羽村が東郷村を編入。
大野郡芦見村、羽生村、上味見村、下味見村、足羽郡下宇坂村、上宇坂村が合併、足羽郡美山村が発足。
丹生郡天津村、三方村、志津村が合併、丹生郡清水町が発足。
1956年、足羽郡足羽村大町別所・大町・江端・大島・下荒井区域。足羽郡麻生津村を編入。
1957年、坂井郡大安寺村南楢原・北楢原・田ノ谷・四十谷・岸水・天菅生区域を編入。吉田郡河合村、丹生郡国見村を編入。
1960年、足羽村が町制を施行、足羽町となる。
1961年、吉田郡藤岡村を編入。1963年、丹生郡殿下村を編入。
1964年、足羽郡美山村が町制を施行、足羽郡美山町となる
1967年、坂井郡川西町を編入、吉田郡森田町を編入。1971年、足羽郡足羽町を編入する。
2006年、足羽郡美山町、丹生郡清水町、越廼村を編入。
マンホールには福井市のシンボル、二羽の不死鳥(フェニックス)がデザインされています。




親子タイプマンホール(中)

親子タイプマンホール(小)

満開の桜の下、一乗谷朝倉遺跡の唐門から顔を覗かせる「朝倉ゆめまる」がデザインされたマンホール。

集落排水用マンホールには、市章を中心に「市の花:紫陽花」がデザインされています。

大正14年(1925)9月28日制定の市章は「 福井城内にあった「福ノ井」の. 井げたに、福井の旧称「北ノ庄」. の北を組み合わせ、古きを生かし、. 新しい時代への発展と繁栄を図案. 化したものである」公式HPより
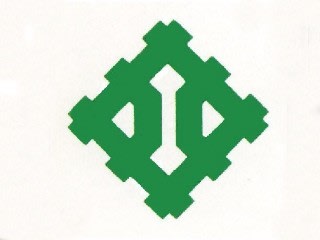


市章付き耐スリップマンホール

市章付き排水弁

市章付き防火貯水槽


市章付き消火栓


市章付き仕切弁


市章付き空気弁

市章付きガスバルブ

市章付きガス

市章付き電防

市章付き側溝蓋


朝倉氏遺跡の象徴:唐門を兜にした、福井市宣伝隊長『朝倉ゆめまる』は一乗谷朝倉氏遺跡に住む妖精。出会った人に「一乗谷朝倉氏遺跡の素晴らしさを日本全国に広めることが夢なんだ♪」と言っております。

撮影日:年月日&2017年9月30日&2018年10月15日
------------------------00----------------------
旧丹生郡越廼村・清水町は未訪問のため、マンホール画像はありません。











































































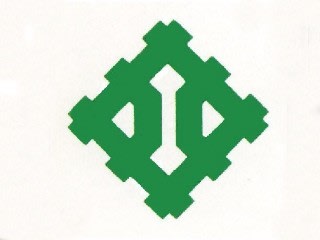




















 、
、





































































