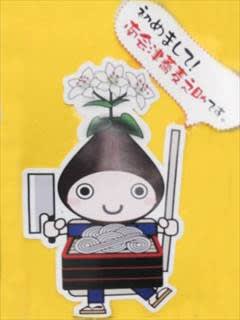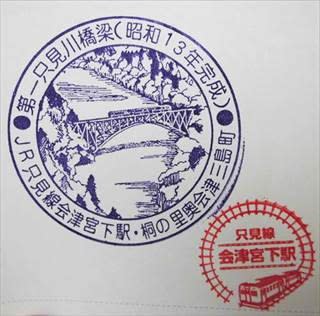白河市(しらかわし)は福島県中通り南部に位置する市です。岩瀬郡天栄村、西白河郡矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、東白川郡棚倉町、石川郡石川町、浅川町、さらに県を跨いで栃木県那須町に隣接。古代より、白河は奥州の要として重要視され、白河の関が置かれて以来、みちのくの玄関口として知られるようになりました。「市の木:赤松」「市の花:梅」「市の鳥:ホオジロ」を制定。
キャッチフレーズは「しらかわいいし」
明治22年(1889)、町村制の施行により西白河郡白河町・大沼村・白坂村・小田川村・五箇村・表郷村・大信村・東村が発足。
1949年、白河町が大沼村と合併、市制を施行し白河市が発足。
1954年、白坂村、小田川村を編入。
1955年、五箇村を編入。表郷村関辺地区及び旗宿地区を編入。
2005年11月7日、 旧白河市、西白河郡表郷村、東村、大信村の合併により新たに白河市となりました。
マンホールは旧大信町デザインで「村の村:木スギ」「村の花:ヤマユリ」「村の鳥:キジ」、下に「しらかわし」の文字があります。

2005年11月7日制定の市章は「白河市の「白」の字を図案化し、中心の楕円は輝き集う市民の活力を、外側の楕円の濃い青は豊かな大地と清らかな水を、淡い青はさわやかな青い空を、上部はこれまで育まれてきた歴史と文化を表し、全体の右上がりのデザインは、これらが調和し、「白河市」が未来へ向け限りなく躍進していくことを表しています。」公式HPより


------------------------00----------------------
旧西白河郡大信村(たいしんむら)は福島県の南部に位置した村です。白河市、泉崎村、矢吹町、西郷村、岩瀬郡天栄村に隣接。「村の木:杉」「村の花:山百合」「村の鳥:雉」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により西白河郡大屋村・信夫村が発足。
1955年、大屋村、信夫村が合併、西白河郡大信村が発足。
2005年、(旧)白河市・表郷村・東村と合併、白河市となりました。
マンホールには「村の木:杉」「村の花:山百合」「村の鳥:雉」がデザインされていますが、自治体名が新白石市に変更されていました。

昭和38年(1963)9月制定の村章は「村人の融和と発展を円により力強く表現し、それらを支える行政が常に安定し建設的であるように不動の山で象徴している。また、進歩、堅実、正義を三角各々の先端に配している。」合併協議会資料より



撮影日:2015年7月3日
帰路の道で目に付いた白河市のマンホール、紹介できる他の画像も満足に無いのに、見つけてしまうと無視できない因果な性分なのです😓
------------------------00----------------------
マンホールカード、頂きました。
2017年4月3日、第4弾として全国42自治体で50種類(累計151自治体170種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「白河市」のマンホールカードは、「白河観光物産協会」でいただけます。
1992年に設置開始されたマンホールには「南湖公園」と「小峰城復元三重櫓」がデザインされています。

「南湖公園の千世の堤からの眺望を背景に、小峰城の三重櫓(やぐら)を描いたデザイン蓋です。 南湖は享和元年(1801年)、武士と民衆が共に楽しめる庭園として、当時の白河藩主・松平定信が築上したもので、現代の公園の先駆けとして知られています。 一方の小峰城は寛永6年(1632年)、初代白河藩主の丹波長重によって大改修され、本丸や二の丸が総石垣造りに生まれ変わるなど、名城としての風格をまといました。 その後、戊辰戦争「白河口の戦い」で大半を消失しましたが、1991年に三重櫓、1994年に前御門が木造で復元され、今では観光の見どころとなっています。 本デザインは、三重櫓の復元を機に制作しました。」