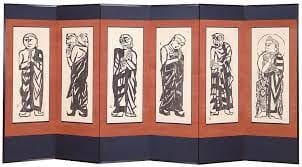木下闇に鳥の目ヒッチコックの眼 有馬ひろこ
なんという感性と表意だろう
木下闇から自分をじっと見ている
鳥とヒッチコックとは
不気味な感じはほんの少しで納得させられる
(小林たけし)
【木下闇】 こしたやみ
◇「木下闇」(このしたやみ) ◇「下闇」 ◇「青葉闇」 ◇「木の晩」(このくれ) ◇「木暮」(こぐれ) ◇「木暗し」(こぐらし)
夏の木立の枝葉が茂って日を遮り、昼間でも暗いさまをいう。「下闇」「青葉闇」などともいう。「緑陰」が木洩れ日のある明るい木陰であるのに対し、「木下闇」は鬱蒼とした暗い様子を指す。明るい所から急にそうした中に入った時など、特にその感が強い。
例句 作者
人形の素魂の棲める木下闇 栗林千津
充電を終えて出てくる木下闇 尾崎竹詩
夢で蹴った女はかなし青葉闇 田山嘉容
少年の嘘のひろがる木下闇 杉浦圭祐
戻って見たい気になる声よ木下闇 山口石鳴
指のない掌のざわめき木下闇 曾根毅
木下闇からだを拭けば赤くなり 大石雄鬼
人形の素魂の棲める木下闇 栗林千津
充電を終えて出てくる木下闇 尾崎竹詩
夢で蹴った女はかなし青葉闇 田山嘉容
少年の嘘のひろがる木下闇 杉浦圭祐
戻って見たい気になる声よ木下闇 山口石鳴
指のない掌のざわめき木下闇 曾根毅
木下闇からだを拭けば赤くなり 大石雄鬼