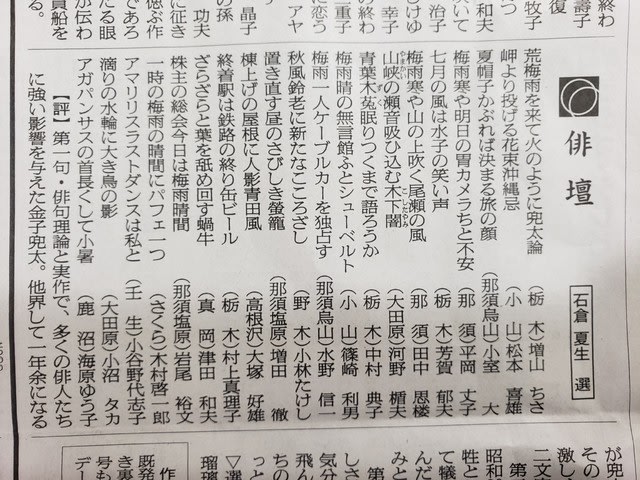山ばかりつづくしこ名や草相撲 門司玄洋人
山ばかりつづくしこ名や草相撲 門司玄洋人
相撲は秋の季語。桓武天皇の時代から、宮中での相撲節会が、陰暦七月の終わり頃に行われてきたことによる。ところで、相撲の句というと、ひいきの力士が勝負に負けた哀感や、老いた相撲取りの姿などを詠むことが多い。力勝負の世界では、弱者のほうが絵になりやすいからだ。そんななかで、この句はあっけらかんと異色である。下手くそで弱いくせに、出てくる奴はみな「……山」と強そうな名前ばかり。鼻白んでいるのではなく、作者はむしろ呆れている。しかし、それが草相撲の楽しさであるとも言っている。いまの大相撲でも「武双山」「旭鷲山」「雅山」「千代天山」など「山」のつく力士は多く、やはり動かざること山のごとし、というイメージにこだわった結果なのか。反対に、最近影が薄いのは「川」の名だろう。「海」はあるが、「川」はほとんど見られなくなった。私が好きだった上手投げの名人「清水川」の頃には、「川」を名乗った力士は沢山いたけれど、現在の幕内には一人もいない。川は抒情的に過ぎるからだろうか、それとも水質汚染のせいで嫌われるのか。しこ名にも、流行があるようだ。(清水哲男)
相撲】 すもう(スマフ)
◇「九月場所」(くがつばしょ) ◇「角力」 ◇「宮相撲」 ◇「草相撲」 ◇「相撲取」 ◇「土俵」
宮廷では初秋の行事として、相撲節会(すまいのせちえ)が行われたため、秋の季語。年の豊凶を占う神事であったが、その後職業相撲が発達、興行化された。現在は東京国技館で9月中の15日間に開かれる相撲を「秋場所」といい、これも季語とする。
例句 作者
少年の白きししむら宮相撲 伊藤 妙
負まじき角力を寝ものがたり哉 蕪村
やはらかに人わけゆくや勝角力 几菫
相撲取ならぶや秋のからにしき 嵐雪
秋場所や退かぬ暑さの人いきれ 久保田万太郎
二日まけて老といはれる角力取 松瀬青々
秋場所や霧の中なる幟数 山田土偶
みやこにも住みまじりけり相撲取 去来
宿の子をかりのひいきや草相撲 久保より江