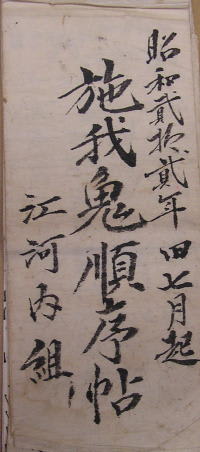4年前からお盆のお参りは全て
新命和尚にお願いしています。
4年目の新命和尚は
クタクタで戻って来ます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
檀家さんは和尚さんのお参りが
済むと仏間でお茶とお菓子を用意してくれます。
4年目の新命和尚は檀家さんのお気持ちを
無碍にしてはならないと用意された
お茶やお菓子を全て頂くようです。
現在は「冷えたゼリー」が多いらしく、
「今日は12個頂いてお腹がパンパンです」と
話していました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
私が子どもの頃は「カルピス」が全体の7割で
ヨーグルトが1割でした。
カルピスはビン入りでヨーグルトは一升ビン
に入っていました。
薄める飲み物(粉ジュースも含め)が多かったです。
当時のお婆さんたちは「カルピス」の適度が分からず
水のようなカルピスも随分頂きました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
お盆は檀家さんからお土産もたくさん頂きます。
地元の方は畑を作っていますから
「なすび・キュウリ・カボチャ・トウモロコシ・オクラ・シシトウ・ピーマン」
などなど大量に頂きます。
これ全てお供えとしていただきます。
昔からお盆の飾り付けは「施餓鬼棚」で
乾物や野菜が供えられます。
檀家さんの仏壇にも「トウモロコシ・スイカ・なすび・キュウリ」などが
お盆の時期には上がっています。
※お供えした野菜を細かくしてお墓に撒くのを「水の花」と云います。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
これから大量の野菜がお土産となって典座に置かれていきます。
野菜は12日に本堂と位牌堂へ移してお供えします。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
今日は珍しいお供え物を新命が頂いて来ました。

まくわうり(真桑瓜)です。
昔はあちこちでたくさん作っていましたが、
最近は見なくなったフルーツです。

専業農家の檀家さん から頂きました。
※専業農家さんはログインしないとダメかも!
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
昔はカルピスでしたが今は「栄養ドリンク」がお茶の
代わりだそうです。
でも、一日1本しか飲めません。
新命和尚にお願いしています。
4年目の新命和尚は
クタクタで戻って来ます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
檀家さんは和尚さんのお参りが
済むと仏間でお茶とお菓子を用意してくれます。
4年目の新命和尚は檀家さんのお気持ちを
無碍にしてはならないと用意された
お茶やお菓子を全て頂くようです。
現在は「冷えたゼリー」が多いらしく、
「今日は12個頂いてお腹がパンパンです」と
話していました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
私が子どもの頃は「カルピス」が全体の7割で
ヨーグルトが1割でした。
カルピスはビン入りでヨーグルトは一升ビン
に入っていました。
薄める飲み物(粉ジュースも含め)が多かったです。
当時のお婆さんたちは「カルピス」の適度が分からず
水のようなカルピスも随分頂きました。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
お盆は檀家さんからお土産もたくさん頂きます。
地元の方は畑を作っていますから
「なすび・キュウリ・カボチャ・トウモロコシ・オクラ・シシトウ・ピーマン」
などなど大量に頂きます。
これ全てお供えとしていただきます。
昔からお盆の飾り付けは「施餓鬼棚」で
乾物や野菜が供えられます。
檀家さんの仏壇にも「トウモロコシ・スイカ・なすび・キュウリ」などが
お盆の時期には上がっています。
※お供えした野菜を細かくしてお墓に撒くのを「水の花」と云います。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
これから大量の野菜がお土産となって典座に置かれていきます。
野菜は12日に本堂と位牌堂へ移してお供えします。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
今日は珍しいお供え物を新命が頂いて来ました。

まくわうり(真桑瓜)です。
昔はあちこちでたくさん作っていましたが、
最近は見なくなったフルーツです。

専業農家の檀家さん から頂きました。
※専業農家さんはログインしないとダメかも!
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
昔はカルピスでしたが今は「栄養ドリンク」がお茶の
代わりだそうです。
でも、一日1本しか飲めません。