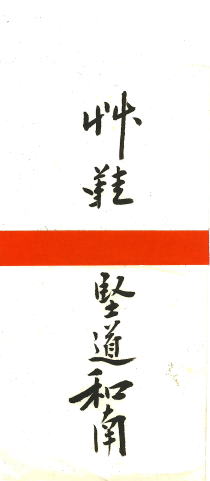たくさんの方々から東日本大震災花園会員見舞金が
寄せられました。
一年前の平成24年6月20日の報告では、被災された7340戸の
花園会員さまに見舞金が届き、全体目標額の56%が全国の
花園会員から義援されたと聞きました。
義援金の期日は今年度中で、寄せられ義援金は
「臨済宗妙心寺派東日本大震災特別災害対策本部」を通じて
被災地に届けられます。
「妙心寺からの義援袋」


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
義援金を納めるときに被災現場や被災者の顔が思い浮かんだのでしょうか、
義援封筒の中に「お願い致します」とか「頑張ってください」などの
一筆書きの手紙が入っているものもありました。
多くの檀家さんは、会社・行政・個人ですでに震災直後から
たくさんの義援金を喜捨していると思います。
中には「お寺の都合なのがいやだ」とか
「和尚が使うお金だろう」・「被災者に届くのか」などの
意見が3人ほどからあったと聞きます。
※上記の意見は、いずれも私ども僧侶による
平素の行いによる不徳と考えています。
有り難い事に、その不徳を足して頂き、
全員の義援を賜ることができました。
世話人さんが檀徒さんに頭を下げて、丁寧な説明をして
互助の気持ちを伝えていたことを
地域の檀家さんや花園会役員さんから聞かされました。
地区世話人さまには
本当にご足労をおかけ致しました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
正定寺の檀家さんで5月12日に15歳になった女の子がいます。
その子が幼稚園の頃おばあちゃんと一緒にお参りした
妙心寺を描いた絵が下の写真です。

屋根に龍がいて中には和尚さんが絡子を掛けて数珠を持った様子が描かれています。
法堂の天井にある龍と説明する和尚さんが印象的だったのでしょう。
この妙心寺を本山とする花園会員の互助として、
いち早く復興支援や被災見舞いに全国の花園会員が名乗りを上げました。
被災した妙心寺派の子供たちの中には、上の絵のように妙心寺の思いでを
持っている子もあるのではないでしょうか。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
全国の花園会員の皆さまより、2年遅れですけどたくさんの方が
義援金を喜捨してくれました。
又、個別の領収や預かり証がないので、ご芳名をもって会計受け取り
の証とさせて頂きます。
尚、芳名削除希望の方はご連絡を下さい。
同様に7月下旬発行の寺報でも掲載されます。
正定寺檀徒中
甲斐辰己 ・ 小野美智治 ・ 久保田嘉博 ・ 柳井百人 ・ 宮下 與
甲斐龍太 ・ 石川栄子 ・ 久保田英治 ・ 安藤智公 ・ 矢野照雄
山本源義 ・ 曽根田千鳥 ・ 久保田美津江 ・ 柳井清浩 ・ 山内一平
木下保治郎 ・ 小野潔 ・ 久保田 忍 ・ 柳井 淳 ・ 山内正明
戸高浅生 ・ 小野道夫 ・ 久保田綾子 ・ 安藤金喜 ・ 安藤秀明
戸高直人 ・ 植田純市 ・ 下川雅秀 ・ 野村浩史 ・ 安藤廣美
小野邦彦 ・ 小野泰雄 ・ 戸高小恵子 ・ 伊東好文 ・ 安藤道紀
小野恒存 ・ 志賀 満 ・ 三浦一人 ・ 岩崎政徳 ・ 安藤哲也
小野秀喜 ・ 野々下博 ・ 三浦日出男 ・ 宇戸ミヤ子 ・ 簀戸功吉
戸高勝馬 ・ 林 亀 ・ 三浦幸一 ・ 川野久美子 ・ 安藤義博
戸高 忠 ・ 古矢長生 ・ 平井健吾 ・ 川野登志郎 ・ 小野広太
山元 都 ・ 近藤正視 ・ 小野 寛 ・ 広瀬豊喜 ・ 小野哲生
戸高由美子 ・ 小野浩伸 ・ 小野 力 ・ 広瀬正也 ・ 柴田 弘
御手洗 堅 ・ 御手洗晴視 ・ 川股憲明 ・ 御手洗欣也 ・ 大司八郎
小野幾夫 ・ 小田木聖孝 ・ 大竹正男 ・ 川野貴重 ・ 飛田幸平
小野征夫 ・ 井崎敏行 ・ 大竹良一 ・ 岩佐昭一 ・ 飛田茂子
佐脇廣栄 ・ 小野二三雄 ・ 安藤康正 ・ 後藤保代 ・ 星野喜三男
戸高恒喜 ・ 長田小太郎 ・ 足立米壽 ・ 染矢信子 ・ 柳井みはる
飛田 郁 ・ 御手洗麗子 ・ 尾形利勝 ・ 高橋忠男 ・ 矢野 薫
飛田和政 ・ 柳井順一郎 ・ 尾形一彦 ・ 安藤美喜 ・ 渡辺昭子
飛田幸幾 ・ 柳井孝義 ・ 甲斐朝美 ・ 後藤武士 ・ 竹下 裕
御手洗 哲 ・ 小野勇一 ・ 甲斐マツ代 ・ 後藤時子 ・ 大畑利春
飛田清馬 ・ 染矢豊喜 ・ 甲斐律男 ・ 染矢朝子 ・ 竹中裕子
御手洗正人 ・ 岡田喜敏 ・ 鴨尾利夫 ・ 立箱和人 ・ 竹元タマエ
飛田芳海 ・ 小野哲夫 ・ 武田敏秋 ・ 広瀬謙治 ・ 吉田禮子
柳井正道 ・ 小野富生 ・ 村西栄二 ・ 広瀬広美 ・ 御手洗基茂
加藤隆美 ・ 志賀健一郎 ・ 小野和行 ・ 柳井昌之 ・ 甲斐照光
桜井洋紀 ・ 染矢フサエ ・ 甲斐興宣 ・ 廣瀬芳見 ・ 小野永生
桜井有一 ・ 染矢春江 ・ 甲斐一男 ・ 広瀬茂弘 ・ 小野一人
櫻井米士 ・ 鉄山宗始 ・ 染矢邦正 ・ 安藤アヤ子 ・ 甲斐典昭
簀戸 健 ・ 橋迫寿生 ・ 染矢節子 ・ 安藤健辞 ・ 河野 林
簀戸寅夫 ・ 林 裕人 ・ 森下 修 ・ 安藤哲也 ・ 吉内良金
簀戸サヨ子 ・ 林 美春 ・ 武田 博 ・ 安藤鉄也 ・ 吉内耕二
簀戸茂一 ・ 山口直哉 ・ 武田雄二 ・ 安藤久男 ・ 吉内達也
戸高壽生 ・ 山下冨美江 ・ 立箱貞夫 ・ 後藤富士夫 ・ 吉田 勇
羽明忠夫 ・ 久保田和博 ・ 平井カズエ ・ 広瀬精治 ・ 甲斐久仁子
松井文生 ・ 三浦伸一 ・ 松田昭治 ・ 安藤慶喜 ・ 木下善吉
御手洗貞子 ・ 大久保保美 ・ 平井均和 ・ 井道則 ・ 冨高和夫
山畑 実 ・ 大竹琴美 ・ 森下モキ ・ 山内文男 ・ 鳴海 勇
桜井孝平 ・ 川野恵美 ・ 柳井律子 ・ 高橋慶太 ・ 鳴海勝也
鳴海健二 ・ 鳴海達男 ・ 鳴海雄二郎 ・ 山本伊勢治 ・ 鳴海 龍
鳴海信吾 ・ 鳴海トキ子 ・ 山本春男 ・ 鳴海由久 ・ 小野二三子
鳴海隆子 ・ 鳴海三好 ・ 山田桂子 ・ 吉田源蔵 ・ 安藤愛子
後藤政子 ・ 広瀬伊久生 ・ 安藤征一 ・ 柴田スミ子 ・ 小原勿子
(敬称略)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
世話人さまがいない地域では、お盆・秋彼岸の行事に合わせてご依頼の
通知をさせて頂きます。
又、今回の募金中に旅行やお仕事で世話人さまへ義援金を渡すことが
出来なかった檀家さんは、ご都合の良いときにでも正定寺へ直接か、
村西会計さん・総代さんにご持参ください。
本当にありがとうございました。