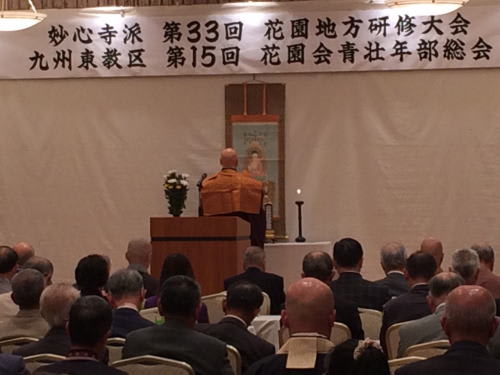9月29日に右副腎に癌が転移して手術をしました。
術後の痛みが有り、10月23日に行われた法類寺院(本匠因尾瑞祥寺)の
先々住職の五十回忌にはお参り出来ませんでした。
10月27日には右後頭葉に転移性がんが見つかり放射線治療を行いました。
11月に入ると手術の痛みも取れ、日常の生活を行えるようになりました。
11月9日に神奈川県伊勢原市の耕雲寺で晋山式があり、
一人では電車や飛行機の乗り降りが出来ないので、
介添えに女房が随行してくれました。
交通機関を利用すれば、荷物や移動が大変なので自家用車で
神奈川まで行くことにしました。
家内が運転者で私は助手席に座っているだけです。
そこで、以前から行って見たかった処へも足を延ばす事にしました。
行程距離は2.000㎞を越えたのではないでしょうか。
その一つが「出雲大社」です。

今年の本山参りで「伊勢神宮」にはお参りしているので、
次は高千穂か出雲と決めていました。
二つ目が石川県金沢にある西田幾多郎と鈴木大拙記念館に行くことでした。
11月11日は鈴木大拙の生誕日でした、お陰で両記念館の入場券が半額になりました。

鈴木大拙の生誕地

記念館

西田幾多郎記念館ではたまたま西田幾多郎書斎「骨清窟」が公開されていました。

西田幾多郎哲学記念館の館内

最終は四国に渡ってフェリーで九州へ。
松山では正岡子規記念館へ

充実した旅行でした。
充分に歩くことも出来ませんでしたが、術後の痛みもなく無事に帰ってこれました。
四国に渡ったので真言宗開祖空海の父である佐伯善通を開基として創建され空海生誕地の善通寺に
お参りして来ました。
術後の痛みが有り、10月23日に行われた法類寺院(本匠因尾瑞祥寺)の
先々住職の五十回忌にはお参り出来ませんでした。
10月27日には右後頭葉に転移性がんが見つかり放射線治療を行いました。
11月に入ると手術の痛みも取れ、日常の生活を行えるようになりました。
11月9日に神奈川県伊勢原市の耕雲寺で晋山式があり、
一人では電車や飛行機の乗り降りが出来ないので、
介添えに女房が随行してくれました。
交通機関を利用すれば、荷物や移動が大変なので自家用車で
神奈川まで行くことにしました。
家内が運転者で私は助手席に座っているだけです。
そこで、以前から行って見たかった処へも足を延ばす事にしました。
行程距離は2.000㎞を越えたのではないでしょうか。
その一つが「出雲大社」です。

今年の本山参りで「伊勢神宮」にはお参りしているので、
次は高千穂か出雲と決めていました。
二つ目が石川県金沢にある西田幾多郎と鈴木大拙記念館に行くことでした。
11月11日は鈴木大拙の生誕日でした、お陰で両記念館の入場券が半額になりました。

鈴木大拙の生誕地

記念館

西田幾多郎記念館ではたまたま西田幾多郎書斎「骨清窟」が公開されていました。

西田幾多郎哲学記念館の館内

最終は四国に渡ってフェリーで九州へ。
松山では正岡子規記念館へ

充実した旅行でした。
充分に歩くことも出来ませんでしたが、術後の痛みもなく無事に帰ってこれました。
四国に渡ったので真言宗開祖空海の父である佐伯善通を開基として創建され空海生誕地の善通寺に
お参りして来ました。