現在の体重が96㎏です。病気を患って16㎏も
太ってしまいました。
「和尚さん体重を少し落とすように」と毎月の
内科検診で近藤先生から言われます。
太った和尚さんは怠け者しか見えません。
女房と顔を合わせては「痩せるぞ!」と
あるときは合い言葉のように
又、あるときは慰め合うように言葉にしています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
しかし、
いくら太っていても痩せていても
成仏すると骨壺に入るだけの身になってしまいます。
お釈迦さまの遺骨は仏舎利と言います。
仏舎利は細かく粉砕しひと粒ひと粒に分け8万の
寺院に収められたとも言います。
この写真は佐伯市弥生江良の洞明寺と言う
大きなお寺の「佛器書上」と題された佛具などの
什物を記した帳面です。
※何故か帳面は正定寺に保管されています。

最初に「佛舎利 二粒」と書かれています。
お釈迦さまの遺骨が佐伯市に在った事になっています。
※現在は不明との事です。
同じように「佛舎利」が在った記録が養賢寺にも残っています。
養賢寺の古文書には「三粒」となっていて京都から拝受した由来が
細かく記されたものだそうです。
※3粒がどの寺院に配られたか、
それとも養賢寺に在るのか謎です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
今回は「佛舎利」ではなく、その記録の最後にある
洞明寺檀徒総代(檀中惣代) 近藤元恭さんに興味がありました。

この近藤家は代々医師で佐伯藩藩医のようです。
その近藤家から正定寺に第九世として住持した
「寂水志堪和尚」がいます。
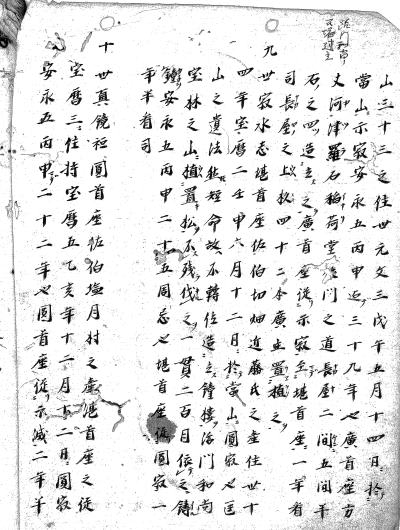
九世 寂水志堪首座 佐伯切畑 近藤氏之産 住世十四年
宝暦二壬申六月十二日於當山圓寂也
匡山之遺法 然短命故不轉位 造立鐘楼
活門和尚宝林之山植置松不残伐之 一貫二百目依之鋳鐘
安永五丙申二十五周忌也 堪首座従圓寂一年半看司
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
貧乏な正定寺の住職になって苦労しながら「梵鐘」を
鋳造しました。
詳しくはこちらです。
寂水和尚は養賢寺の第10世匡山和尚の遺言により
養賢寺を嗣ぐように言われていたのですが、
正定寺での苦労がたたったのか若くして亡くなったようです。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
白衣の前身頃がきつくなっている体型に
寂水和尚の末裔でもある近藤先生の
「少し痩せるように」のお言葉が
心に深くしみます。
次回の検診でいかされるように努力します。
太ってしまいました。
「和尚さん体重を少し落とすように」と毎月の
内科検診で近藤先生から言われます。
太った和尚さんは怠け者しか見えません。
女房と顔を合わせては「痩せるぞ!」と
あるときは合い言葉のように
又、あるときは慰め合うように言葉にしています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
しかし、
いくら太っていても痩せていても
成仏すると骨壺に入るだけの身になってしまいます。
お釈迦さまの遺骨は仏舎利と言います。
仏舎利は細かく粉砕しひと粒ひと粒に分け8万の
寺院に収められたとも言います。
この写真は佐伯市弥生江良の洞明寺と言う
大きなお寺の「佛器書上」と題された佛具などの
什物を記した帳面です。
※何故か帳面は正定寺に保管されています。

最初に「佛舎利 二粒」と書かれています。
お釈迦さまの遺骨が佐伯市に在った事になっています。
※現在は不明との事です。
同じように「佛舎利」が在った記録が養賢寺にも残っています。
養賢寺の古文書には「三粒」となっていて京都から拝受した由来が
細かく記されたものだそうです。
※3粒がどの寺院に配られたか、
それとも養賢寺に在るのか謎です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
今回は「佛舎利」ではなく、その記録の最後にある
洞明寺檀徒総代(檀中惣代) 近藤元恭さんに興味がありました。

この近藤家は代々医師で佐伯藩藩医のようです。
その近藤家から正定寺に第九世として住持した
「寂水志堪和尚」がいます。
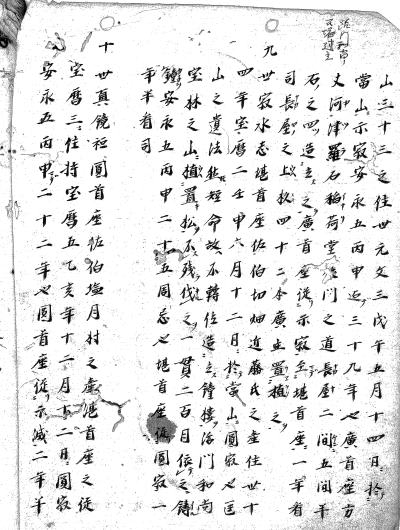
九世 寂水志堪首座 佐伯切畑 近藤氏之産 住世十四年
宝暦二壬申六月十二日於當山圓寂也
匡山之遺法 然短命故不轉位 造立鐘楼
活門和尚宝林之山植置松不残伐之 一貫二百目依之鋳鐘
安永五丙申二十五周忌也 堪首座従圓寂一年半看司
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
貧乏な正定寺の住職になって苦労しながら「梵鐘」を
鋳造しました。
詳しくはこちらです。
寂水和尚は養賢寺の第10世匡山和尚の遺言により
養賢寺を嗣ぐように言われていたのですが、
正定寺での苦労がたたったのか若くして亡くなったようです。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
白衣の前身頃がきつくなっている体型に
寂水和尚の末裔でもある近藤先生の
「少し痩せるように」のお言葉が
心に深くしみます。
次回の検診でいかされるように努力します。































































