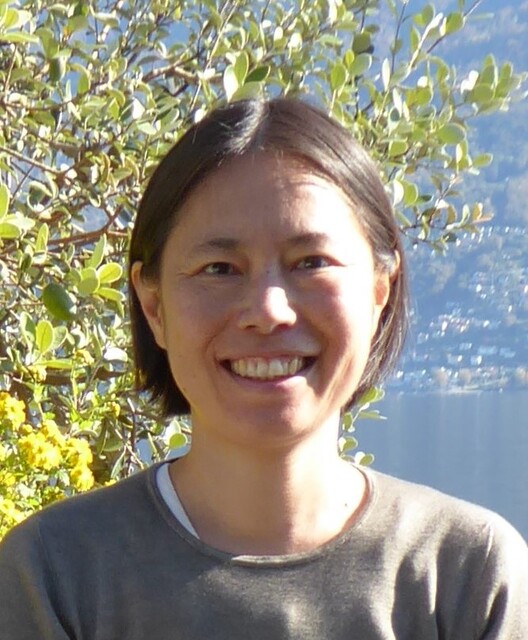Quelle: Minergie® クリステン邸
● ミネルギー・P建築、全国830棟
スイスには12年前に導入された「ミネルギー」という省エネ建築の認証基準があります。
誰でも知っていると言っていいくらい知名度が高い基準で、そこから人々が思い浮かべるイメージは、分厚い断熱材やコンフォート換気(熱回収型の機械換気設備)のある快適住宅といったとこでしょうか。住宅だけでなく、学校やオフィス、店舗など、様々な建物があります。
ミネルギーの中には数種類の認証基準があります。
省エネルギー性能に関しては、普及型の「ミネルギー基準」。こちらは新築市場の20%を占め、合計1.8万棟が既に建てられています。「ミネルギー基準」は今や珍しい存在ではありません。
対して、次世代型の基準が「ミネルギー・P」。こちらは新築市場でのシェアはまだ僅かで、現在830棟の建物が認証を受けています。
また、省エネ性能に加えて、建物の健康性と環境性を配慮する建物のための「ミネルギー・エコ」、「ミネルギー・P・エコ」基準というのもあります。
「ミネルギー・P」はドイツの「パッシブハウス基準」に相当するスイスの基準です。普及版のミネルギー基準には法規の規制基準が追いつきつつあるため、数年以内に、ミネルギーはミネルギー・Pに格上げされると言われています。というわけで、スイスの新築で目指すべき省エネレベルはミネルギー・Pなのです。
● ベルン州で100棟目、クリステン邸
さて、昨11月に人口100万人のベルン州で100棟目のミネルギー・P建築が認証を受けて、話題を呼びました。認証を受けたのは、エヴィラルド村にある4人家族クリステン家の木造一戸建て住宅です。11月中旬の時点で、入居2ヶ月目。ご主人のグレゴール・クリステンさんは、建物の快適性についてこう述べます。*
「私たちの住いの質は本当に期待通りのもので、部分的には上回っています。たとえば室内気候は思っていた以上に良好です。」*と、ミネルギー・Pの温熱環境と機械換気による新鮮な空気に、非常に満足されているご様子。また11月中旬まで、3日間を除いては暖房要らずで、外気が零度近くになっても、南側の大窓からの日射獲得と室内からの排熱で十分に建物を温かく保つことができたそうです。
クリステンさんは、高気密・高断熱な躯体のおかげで、11月に「夜の間も0.5度くらいしか気温が下がらない」*と語っています。夏の過熱防止対策として、窓面はしっかりと日除けできるようになっています。また、夏には建物の上部に排気口を用いて夜間通気し、室内を自然に冷却することができます。
● ペレットストーブ一台で全館暖かく
クリステン家では、暖房が必要な季節には159㎡の住いを、居間に据えられた一台の小さなペレットストーブだけで快適な温度に暖房できます。これはスイスの気候下では驚くべきこと、というか高度な省エネ建築ミネルギー・Pならではのことです。暖房熱は100%ペレットストーブ、給湯は通年すると80%を太陽熱温水器で、20%をペレットストーブからの熱でまかないます。
スイスでは全館温水暖房が一般的ですが、高度な省エネ建築のミネルギー・Pの一戸建てでは、居間の薪ストーブやペレットストーブで全館を暖める建物が少なくありません。そのような場合、給湯はソーラー温水器で行なう例が多いようです。グレゴール・クリステンさんも、自宅計画時にそのような事例を多数調査し、ソーラー温水器とペレットストーブの組み合わせで行ける、と納得したそうです。
● ミネルギー・P化への追加コストは+3%
気になるコストは、クリステンさんよると、「ミネルギー・P基準を達成するための追加コストは総コストで約3%」*だそうです。これはクリステン邸を規制基準で建てた場合と、ミネルギー・P基準で建てた場合の比較です。この追加コストは比較的少ないケースと思われます。お施主さんも、このコスト追加分は中期的に暖房費がかからないことで回収できる、と述べます。さらに、クリステン家はベルン州のエネルギー・建設・交通局から、この家の建設に際して2.5万フラン(約210万円)もの助成金を得ています。
● 人気スポーツ選手のミネルギー&プラスエネルギー住宅
スイス人の女性シモーネ・ニッグリ・ルーダーさんは、オリエンテーリング競技で17回の世界優勝記録を持つ、国民的人気を誇るスポーツ選手です。彼女は生物学者ということもあって、環境活動に熱心で、有機栽培の食品メーカの広告なんかに出ていたりします。
その彼女の一家の自宅が、昨10月、ベルン州のミュンジンゲン町に竣工しました。こちらはミネルギー&プラスエネルギー住宅です。木造プレファブ工法のおしゃれなデザインの躯体には、環境や健康に負担の少ない建材が用いられ、ミネルギー認証を受けています。それに屋根材一体型の太陽光発電8.85kWを設置して、暖房・給湯・換気・家電に消費するエネルギー量の110~130%を生産するコンセプトになっています。


Quelle: Minergie® ニッグリ・ルーダー邸
ニッグリ夫妻と子供の住まう建物は、住職一体型、広さは240㎡、トレーニングルームなんてのもあります。外から見ると箱ですが、南側の大窓と、室内の遊び心のある空間デザインが魅力的です。 間取りや室内の写真は下記のサイトで見られます。 http://www.minergie.ch/tl_files/download/Plusenergiehaus_luchliweg_objektdoku.pdf
● エコ建材づくし
この家を設計した建築家Dieter Aeberhard Devauxさんの資料によると、木造建築に蓄熱容量を与えるために、室内には石灰砂岩の
蓄熱壁を設けています。冬には南側の大窓から入ってくる日射がそれを暖めます。夏には、この大窓は庇と日除けスクリーンで守られています。また灰色のトウヒ材外壁には、背面通気層が設けられ、ファザードが熱くなるのを妨いでいます。
断熱材はスイス製のウール。U値は外壁が0.12(断熱材34㎝)、屋根0.15(断熱材27㎝)、窓全体0.85~1.1、床0.14(断熱材24cm)です。気密性0.4h-1。建物の表面積に占める窓の割合27.1% 使用した木材は国産材で、スイス国内で2分以内に育つ量だそうです。さらに室内には粘土塗量、漆喰塗壁などを用い、空気を汚さず、湿度を自然に調整できる建材を選んでいます。
● エネルギー消費量は約6000kWh、生産量は7400kWh
暖房と給湯は空気ヒートポンプ(通年パフォーマンス値JAZ3.47※)で行なっています。ですが電気を食うヒートポンプの負荷を減らすために、居間には薪ストーブがすえられています。熱交換式の機械換気設備には、夜間・昼間に使う部屋に応じて、ゾーン別スイッチがついており、熱損失を減らしているそうです。
このルーダー家の一年のエネルギー消費量は:
暖房 2025kWh
給湯 1119kWh
換気 340kWh
家電と照明 2500kWh(目標値)
合計 5984kWh
エネルギー生産量 7400kWh
というわけで、「計算上」はネット・プラスエネルギーです。もちろん住み手の室内温度の設定や家電の使い方によって、プラスエネルギー度は計算よりも上がったり、下がったりします。
● プラスエネルギー化への追加コストは+5~10%
建築家によると、ニッグリ邸がプラスエネルギーを達成するのに必要な追加コストは、+5~10%だったそうです。比較されているのは、この家をミネルギー基準で建てた場合と、ミネルギー基準をプラスエネルギー化した場合のコストです。普通の建物(規制基準)をミネルギー&プラスエネルギー化した場合との比較ではありません。
ただこのニッグリ邸は、建物の省エネ性能的にはミネルギー・Pには到らないようです。ここまでやるなら、模範生としてミネルギー・P・エコ認証を目指してもらいたかった、と勝手ながら思います。
(参照)ミネルギー連盟プレスリリース、* 出典:ミネルギー連盟プレスリリース
※ ヒートポンプ暖房の年間パフォーマンス値JAZ:
年間パフォーマンス値JAZは、ヒートポンプ暖房を一年の気候変化の下での運転した場合に、周辺機器(地下水ポンプや地熱ポンプなど、空気弁)も含めた、システム全体でのパフォーマンスを表す値です(1kWhの電気で・・kWhの利用熱を作る)。対してCOPは、メーカーがヒートポンプ部分のみを水準化されたラボ条件でテストしたパフォーマンス値。前者は、ドイツ語ではJahresarbeitzahlでJAZ。英語ではSeasonal/Annual Performance Index (SPI/API)というそうです。スイスでは省エネ建築の資料ではヒートポンプ暖房システムの効率はJAZで表記されています。通常3~4.5。
参照:http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpenheizung