
★シューベルト:ピアノ作品集
(演奏:ギルバート・シュフター)
※シューベルトのピアノ作品12枚組
(1970年代録音)
これでいい。
シューベルトのピアノ曲集は数多あれども、資料的にも演奏的にもこれがあればいい。(^^;)
もちろん変ロ長調ソナタはじめ、それぞれの曲にそれぞれの演奏家の思いの詰まった名演奏に迷演奏、快演奏に怪演奏、洗練されたのからイモいものまでいっぱいあってよいし、それはそれで楽しい。
中にはシフのように演奏は洗練の極みなのにもかかわらずジャケットはイモいとか・・・まぁ私のは彼のもソナタ全集であるからして、ひとつのイモいグリーンのケースに宝物がいっぱい詰まっているみたいなものだけど。
さて、このセット。
シューベルトのピアノ曲全集と謳われているものの、本当に全曲かどうかは専門家じゃないからわからない。
漏れもあるだろうし、ピアニストとて共感できないものは外しているに違いないと思うのだが、何せ31歳までしか生きていなかった人であること、他にもシンフォニーも歌曲も室内楽も霊感吐き出しまくりみたいに作り倒した人でもあることから、流石に12枚分も録音したらフラグメントとかを除けばだいたい入っちゃってるんじゃないか・・・とか。
要するにわからない。(^^;)
中には他愛もなく聴こえる曲から、ホントに30歳ぐらいで死んじゃった人が書いたのかといわんばかりの晦渋な曲まで明るいの暗いの、長いの短いの・・・あらゆる楽曲が収められている。
例外なく言えるのは、このシュフターというピアニストがシューベルトに心の底からの共感をいだいてこれらを演奏しているということである。
そしてそれが余りにも自然であり、気負いのないものであるために、聴き手である私も知らず知らずそのシューベルトの世界に引き込まれ同化しているような錯覚に陥っている・・・ことに気づく。
音量の大きな箇所であっても決して居丈高になることなく、必要な箇所で絶妙なピアノの音の芯の輝きを伴った周りの気配が、私に心を開くよう促してくるのである。
ネコにマタタビを嗅がせたようなもの・・・かな!?
どんな小品に至るまで、ピアニストは肩に力を入れずにさりげなく提示してくれる。
当方は決してワクワクドキドキするようなこともないかわりに、注意を殺がれることもない・・・非常に理想的な弾き手と聴き手の間合いが、時間を忘れて引き込んでくれるのである。
フレージングは自然ではあるが、決して作為的な工夫がないわけではない。
呼吸が絶妙なので気にならないばかりか、旨味、妙味に感じてしまうのだ。
これがなければ、シューベルトの曲を弾いた場合、多くは冗長ダラダラ演奏でいつ終わるとも知れず・・・という感想になってしまうに違いない。
その点、このピアニストにとって最早自分の血肉となっているこのシューベルトの全体感は、彼が今いま楽しんで弾いていることをもってして、聴き手にもその瞬間ごとの楽しみを与えずにはおかない。
とても幸せな全集である。
そして、もうひとつ感じるのは『隙間』である。
ピアノの音の繊細な軽い輝き、微温的でありながら悲しみさえ湛えていそうな音色、フレージングの自然さにはこれらのファクターも重要な要素を占めているだろう。
こんな分析的なことをいっても詮無い事ではあるけれど・・・。
ただ、これがアナログ録音であるということを考えるとき、その最良の部分がこの聴感に影響しているのではないかということを思わずにはいられない。
すべての隙間が1か0で埋め尽くされているように感じられる、高品位なデジタルな音では考えられないぐらい風通しの良い音・・・翻って言えばすかすかな音であるのかもしれないが・・・が、私の体を鮮やかに通り抜けていくような感がある。
アナログの音ではなく「アナログな音」とでもいうべき、このサウンドにただただ身を任せているとき、いろんな名手のシューベルトの演奏のうちの、もっとも人懐っこい部分だけを取り出して作曲者の意図している世界へ誘ってくれているのが感じられる。
ただただ黙って聴く・・・考えることも忘れて聴く・・・眠っちゃってもいいから聴いているという状態で今を過ごせることが、無上の喜びであると思える全集である。
12枚・・・どの曲がどうだ・・・ではなく、それなりにバリエーションはあるが、それなりに彼独特の規則性も特長もあるシューベルトの世界に遊ぶ。。。
還って来れなくなりそうなトリップである。
幻想ソナタや変ロ長調ソナタの冒頭・・・自力か他力かわからない音がただ在る状態を、ちゃんと音を鳴らしているのに静かさが際立つところなどは、この演奏にしかない白眉といえよう。
そんな温さはまさに今の時期にちょうどいい。
(演奏:ギルバート・シュフター)
※シューベルトのピアノ作品12枚組
(1970年代録音)
これでいい。
シューベルトのピアノ曲集は数多あれども、資料的にも演奏的にもこれがあればいい。(^^;)
もちろん変ロ長調ソナタはじめ、それぞれの曲にそれぞれの演奏家の思いの詰まった名演奏に迷演奏、快演奏に怪演奏、洗練されたのからイモいものまでいっぱいあってよいし、それはそれで楽しい。
中にはシフのように演奏は洗練の極みなのにもかかわらずジャケットはイモいとか・・・まぁ私のは彼のもソナタ全集であるからして、ひとつのイモいグリーンのケースに宝物がいっぱい詰まっているみたいなものだけど。
さて、このセット。
シューベルトのピアノ曲全集と謳われているものの、本当に全曲かどうかは専門家じゃないからわからない。
漏れもあるだろうし、ピアニストとて共感できないものは外しているに違いないと思うのだが、何せ31歳までしか生きていなかった人であること、他にもシンフォニーも歌曲も室内楽も霊感吐き出しまくりみたいに作り倒した人でもあることから、流石に12枚分も録音したらフラグメントとかを除けばだいたい入っちゃってるんじゃないか・・・とか。
要するにわからない。(^^;)
中には他愛もなく聴こえる曲から、ホントに30歳ぐらいで死んじゃった人が書いたのかといわんばかりの晦渋な曲まで明るいの暗いの、長いの短いの・・・あらゆる楽曲が収められている。
例外なく言えるのは、このシュフターというピアニストがシューベルトに心の底からの共感をいだいてこれらを演奏しているということである。
そしてそれが余りにも自然であり、気負いのないものであるために、聴き手である私も知らず知らずそのシューベルトの世界に引き込まれ同化しているような錯覚に陥っている・・・ことに気づく。
音量の大きな箇所であっても決して居丈高になることなく、必要な箇所で絶妙なピアノの音の芯の輝きを伴った周りの気配が、私に心を開くよう促してくるのである。
ネコにマタタビを嗅がせたようなもの・・・かな!?
どんな小品に至るまで、ピアニストは肩に力を入れずにさりげなく提示してくれる。
当方は決してワクワクドキドキするようなこともないかわりに、注意を殺がれることもない・・・非常に理想的な弾き手と聴き手の間合いが、時間を忘れて引き込んでくれるのである。
フレージングは自然ではあるが、決して作為的な工夫がないわけではない。
呼吸が絶妙なので気にならないばかりか、旨味、妙味に感じてしまうのだ。
これがなければ、シューベルトの曲を弾いた場合、多くは冗長ダラダラ演奏でいつ終わるとも知れず・・・という感想になってしまうに違いない。
その点、このピアニストにとって最早自分の血肉となっているこのシューベルトの全体感は、彼が今いま楽しんで弾いていることをもってして、聴き手にもその瞬間ごとの楽しみを与えずにはおかない。
とても幸せな全集である。
そして、もうひとつ感じるのは『隙間』である。
ピアノの音の繊細な軽い輝き、微温的でありながら悲しみさえ湛えていそうな音色、フレージングの自然さにはこれらのファクターも重要な要素を占めているだろう。
こんな分析的なことをいっても詮無い事ではあるけれど・・・。
ただ、これがアナログ録音であるということを考えるとき、その最良の部分がこの聴感に影響しているのではないかということを思わずにはいられない。
すべての隙間が1か0で埋め尽くされているように感じられる、高品位なデジタルな音では考えられないぐらい風通しの良い音・・・翻って言えばすかすかな音であるのかもしれないが・・・が、私の体を鮮やかに通り抜けていくような感がある。
アナログの音ではなく「アナログな音」とでもいうべき、このサウンドにただただ身を任せているとき、いろんな名手のシューベルトの演奏のうちの、もっとも人懐っこい部分だけを取り出して作曲者の意図している世界へ誘ってくれているのが感じられる。
ただただ黙って聴く・・・考えることも忘れて聴く・・・眠っちゃってもいいから聴いているという状態で今を過ごせることが、無上の喜びであると思える全集である。
12枚・・・どの曲がどうだ・・・ではなく、それなりにバリエーションはあるが、それなりに彼独特の規則性も特長もあるシューベルトの世界に遊ぶ。。。
還って来れなくなりそうなトリップである。
幻想ソナタや変ロ長調ソナタの冒頭・・・自力か他力かわからない音がただ在る状態を、ちゃんと音を鳴らしているのに静かさが際立つところなどは、この演奏にしかない白眉といえよう。
そんな温さはまさに今の時期にちょうどいい。











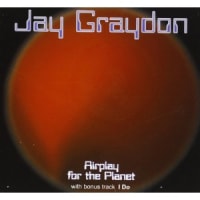
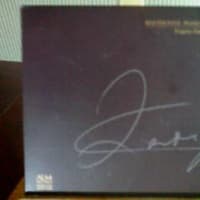
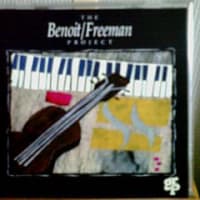
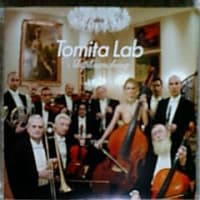
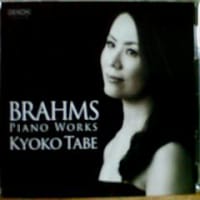

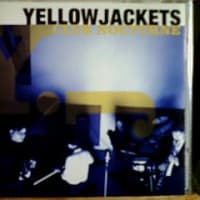


確かにデジタルで色彩のある演奏がいいとは言えないし、シューベルトは広げようがない。子供でも弾けるし。30で常人がシューベルトの境地に行き着くには、超ハードに仕事したとか、病気したとか、まあそれなりに等身大の琴線を得ることは出来るかもしれませんが、美しい歌に辿り着いた彼はやはり孤高の天才であったのかも知れませんね。
出張でレスが遅くなりスミマセン。
時代も国も違う我々が彼の生き様死に様がどうだったかをうかがい知ることは最早、出来ないのかもしれません。
仰るようなシューベルトの歌、ドレミを用いてこの世ではない世界をも紹介してくれる彼を孤高の天才ということは、適切な表現の一つだと思いますです。
彼はその世界を滔々と、天国的な長さをもって表現してくれるので、その世界に遊ぶためには生の音、あるいはアナログの音のほうが自然であることはいえると思います。
少なくとも、デジタル臭い録音ではストレスフリーに彼の世界に遊ぶことは難しいのではないでしょうか?(^^;)