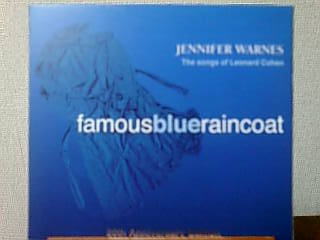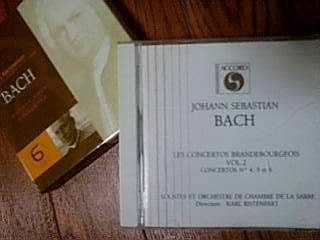★フェイマス・ブルー・レインコート
(ジェニファー・ウォーンズ、レナード・コーエンを歌う)
(演奏:ジェニファー・ウォーンズ)
1.ファースト・ウィ・テイク・マンハッタン
2.電線の鳥
3.すてきな青いレインコート
4.ジャンヌ・ダルク
5.美を求めて遠くまで来た
6.エイント・ノー・キュアー・フォー・ラヴ
7.あなたの胸に
8.ソング・オブ・バーナデッド
9.歌手は死ななければならない
(1986年)
思えばこのブログを始めた当初、オーディオの記事が書かれるページだと認識されていたような気がする。
躍起になって、「音楽全般のブログなんだ」と騒いだ・・・んだったっけ?
・・・・・・してみると、今回のテーマは久しぶりに出るべくして出た記事と言えるかもしれない。
ジェニファー・ウォーンズ・・・
確かに『愛と青春の旅立ち』におけるジョー・コッカーとのデュエット、そして『ダーティ・ダンシング』でのビル・メドレーとの“タイム・オブ・マイ・ライフ”のデュエットという2曲のサウンドトラックからのナンバーワン・ヒットを彼女のキャリアの頂点と考えてもなんら差し支えないかもしれない。
でも、本人はこれらのヒットによって自分の商売はやりやすくなっただろうとはいえ、また、いずれの曲をも大事なレパートリーと認識しているであろうことは想像に難くないとはいえ、2曲のアカデミー受賞曲よりも誇りに思っているキャリアがあると思う。
それは彼女の本当に数少ない(厳選された)ソロ活動になるディスクではないか?
最新作とされる“ザ・ウェル”もDSDレコーディングの威力が炸裂した名作であり、私は今までにパフォーマンス、録音の両面において感動し、何度も何度も傾聴させられ続けている。
そして“ザ・ハンター”。
これは彼女のいささかポップな面を強調したディスクであり、プロのシンガーの技を楽しく聞かせる内容だと思われる。
CDレコードのフォーマットのなかでは、今でも優秀録音としていろんな場所で試聴されているディスクの座を譲っていないんじゃないだろうか。
しかし、私はそれらのディスクよりもこの1986年、私が社会人になった年に制作・発表されたこの“Famous Blue Raincoat”こそが、彼女のキャリアの頂点だと信じるものである。
それはレナード・コーエンの作品集という統一されたコンセプトを実現する手堅いバックのムードの統一。
その中にスティーヴィー・レイ・ヴォーンのE.ギターやテヴィッド・リンドレーのラップ・スティールなど、アクセントの効いたパフォーマンスが躍る。。。
そして主役のジェニファー・ウォーンズという歌手はとてつもなく気高い。
そして、その存在感とテクニックには本当に舌を巻くしかない・・・・・・例えば、ジャンヌ・ダルクでのひとり2重唱ではプリンシプルのメロディーを太く猛く、否、崇高に歌いながら、オブリガードでは軽く触れただけで崩れ落ちそうなほど危うい、あるいははじけそうなシャボンのように2面性を表現してみせる。
かつてここまで劇的に表現仕分けた歌手を知らない・・・そう言って差し支えないだろう。
終始、このディスクのパフォーマンスには敬服して、以後当然のように虜となってしまった。
オーディオファイルと呼ばれる人の中に、いや、少しくそのような心得のある方の中にこそ、このディスクは浸透しているのだろうと思う。
というのも、私がこのディスクに出逢ったのは、オーディオ評論家の傅信幸(ふうのぶゆき)先生による絶賛コメントと幾多の試聴記事により入手したことが始まりである。
傅先生の現在までのご活躍を見るとき、その支持基盤となっている同病筋のなかに、きっと私同様にジェニファー・ウォーンズに目覚めさせられた人はすこぶる多いと確信できる。
傅信幸先生からは、このほかにもダイアー・ストレイツ、リンダ・ロンシュタット、アマンダ・マクブルーム、エンヤなどの再発見と、ウィンダム・ヒルからショーンヘルツ&スコットを発見させてもらったなど、大きな影響を受けた。
何を隠そう、私が最初に購入したオーディオ・セットはとある雑誌で先生が組んだ元気よく鳴る組合せそのものであるというほどだから・・・
CDトランスポートがケンウッド、マランツの4ビッドのDAC内臓プリメイン、そしてビクターのバルプコーンのスピーカー。。。
トランスポートとアンプが殆どおそろいのブラック・フェイスで、音質も申し分なくご満悦だったのが懐かしく思い出される。。。
さて、このディスクは“サイプレス・レコーズ”(CYPRESS RECORDS)というレーベルから発売されていた。
このレーベルの作品は演奏それ自体のハイ・パフォーマンスとともに、録音も良いということで評判だったものだ。
ただ、いくつか購入した記憶があるこのレーベルのディスクで今でも愛聴しているのはこれと、ゲイリー・ライトの“フー・アイ・アム”という傅先生を紹介するようなタイトルのディスクの2銘柄だけ・・・ではあるが。
ジェニファー・ウォーンズの“FAMOUS BLUE RAINCOAT”に戻るが、この録音、表記はされていないが多分アナログ録音であり、現在でも高重量のアナログ・レコードにもプレスされたものが珍重されているようだから、このディスクの録音コンテンツのポテンシャルは相当高いものだったのだろう。
ある雑誌でイギリスのオーディオファイルが、このディスクのアナログ・レコードををその棚に飾っているのを見たことがあるから、本作品の名声はわが国だけに留まるものではないということも知っている・・・。
本当にリッパな業績なのだと思う。
ただ、月日が流れるにつれてさすがにこの録音も、平面的とかカタイという評が雑誌等に並ぶようになったのを見つけてはいた。
しかし、しかしだ・・・
リマスタリングによって、活き活きした音質で生まれかわったのを聴く事ができることになって喜んでいる。
やはりこのディスクを心から愛する人は、プロフェッショナルの中にもいたのだと・・・
現在屈指の音質に匹敵すると言ってよい響がスピーカーからあふれてくると、録音テープを丹念にあたっただろうトーンマイスターの仕事ぶりにも、自然と感謝の念があふれてくるというものである。
★BEST
(演奏:ジェニファー・ウォーンズ)

1.ファースト・ウィ・テイク・マンハッタン
2.ザ・ハンター
3.愛と青春の旅立ち (デュエット;ジョー・コッカー)
4.ロック・ユー・ジェントリー
5.ショット・スルー・ザ・ハート
6.ドント・メイク・ミー・オーヴァー
7.エイント・ノー・キュアー・フォー・ラヴ
8.サムホェア・サムボディ
9.バード・オン・ア・ワイアー
10.ジャンヌ・ダルク
11.ウェイ・ダウン・ディープ
12.アイ・ノウ・ア・ハートエィク・ホェン・アイ・シー・ワン
13.ホェン・ザ・フィーリング・カムズ・アラウンド
14.カム・トゥ・ミー
15.バラッド・オヴ・ザ・ランナウェイ・ホース
16.フェイマス・ブルー・レインコート
17.ハード・タイムズ,カム・アゲィン・ノー・モア
(2000年)
これはドイツの“ZOUNDS”なるレーベルが著名アーティストの録音を集めてきて、独自にリマスタリングを施してベスト盤をプロデュースした一環の作品。
このコンセプトにジェニファー・ウォーンズの名前を外さなかったスタッフの慧眼に敬意を表したい。
ヴォルフガング・フェルド氏を筆頭としたリマスタリング・チームの仕事は、鮮烈な音をこれらの録音から引き出してくれており、とても驚かされたし、嬉しく思ったものである。
このレーベルの作品は他に、ジェフ・ベックのものが秀逸だった。
ワイルドさは後退したかもしれないが、何より先鋭さが増した・・・・・したがって、違う魅力が感じられるようになったと評してよいと思った次第。。。
パット・ベネターやスティーヴ・ウィンウッド、ビル・ウィザースも確かに良い音になったけれど、私の好みかといわれると・・・・・この作業もなかなか難しいものだ。
しかし、ジェニファー・ウォーンズのこのディスクに関しては大成功。
ただし、ベスト盤にしているために個性が取り混ぜになっている気がする。
その個性には、彼女のパフォーマンスや曲調、ことに何年ものスパンに1枚しか発表しない彼女のこと・・・・・ディスクごとに肌合いの違う曲が収められているわけで、それをガチャガチャポンすれば当然にアルバム1曲ごとのつぎはぎは感じられてしまう。
ジェニファー・ウォーンズという強烈な個性が一本、芯として貫かれているではないかと言われればそのとおりではあるが。。。
★フェイマス・ブルー・レインコート・・・20th アニヴァーサリー・エディション
(ジェニファー・ウォーンズ、レナード・コーエンを歌う)
(演奏:ジェニファー・ウォーンズ)
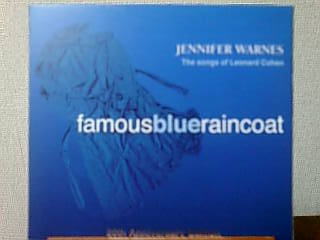
1.ファースト・ウィ・テイク・マンハッタン
2.バード・オン・ア・ワィアー
3.フェイマス・ブルー・レインコート
4.ジャンヌ・ダルク
5.エイント・ノー・キュアー・フォー・ラヴ
6.カミング・バック・トゥ・ユー
7.ソング・オブ・バーナデッド
8.ア・シンガー・マスト・ダイ
9.ケイム・ソー・ファー・フォー・ビューティ
10.ナイト・カムズ・オン
11.バラッド・オブ・ザ・ランナウエイ・ホース
12.イフ・イット・ビー・ユー・ウィル
13.ジャンヌ・ダルク (アントワープに於けるライヴ録音)
(2007年)
そしてこの“20周年記念エディション”である。
装丁にはレナード・コーエンによる讃辞のシールが貼られていた。
ジェニファー・ウォーンズ、レナード・コーエンを歌う
未発表曲4曲所収
オリジナル・アナログ・テープより復刻(リマスター)を施す
「彼女の歌声はカリフォルニアの気候を思わせる。陽光に満ち溢れているのだが、その背後に地震が覆い隠されているのだ」
コーエンは、彼女の歌声をやはり的確に捉えている。
力強さも脆さも・・・
そしてそれはこのディスクを聴くと非常によくわかる。
これを聴いてしまっては、サイプレスから発表された当初のディスクは平面的だと評されても仕方あるまい。
“ZOUNDS”に比べるとピントがどぎつくなくて、あくまでも自然に気配まで感じ取れるような録音になっている。
我が家のスピーカーが「高性能」タイプではなく、長時間聴いてても疲れないタイプであるのと、そのスピーカーのコーン紙自体が相当疲れているのでここらの違いははっきりとは聞き取れないのだが、聴き比べたときのテイストの差は確かにある。
“ZOUNDS”レーベルによるものがアクセントやメリハリがハッキリしているのに対して、“シャウト・ファクトリー・レーベル”による『20周年記念盤』は自然さが売り物である。
クレジットによるとリマスター作業はバーニー・グランドマン氏が行っているようだが、ミキシングに関してはかのジョージ・マッセンバーグを始め何人もの手によるものである。
でも、作品としての一貫性は見事に保たれている。
ちなみに4曲の未発表曲は、確かにひとつひとつはステキな出来映えだけれども、冒頭のディスクに収められなかった理由は分かるような気がする。
はっきり言えば、毛色が合わない・・・それだけの理由なのだろう。
もっとも、20年聴き馴染んだ楽曲に、同じ時に録音されたとはいえここ何日か聴きまくっただけの新しい録音を聴いたのでは、毛色の違いを感じないほうがウソだというもの。
とにかく聞けて良かったと思っておけばよいことである・・・。
そして収録曲“バラッド・オブ・ア・ランナウエイ・ホース”についても一言触れねばなるまい。
この曲の初出はベーシストのロブ・ワッサーマン“デュエッツ”というアルバムである。
これも傅先生の紹介で入手して、ワッサーマンのベース一本とデュエットして比較的長い時間なのにまったく飽きさせないジェニファー・ウォーンズの歌唱に唸らされたもの・・・。
そして“ZOUNDS”に収められているのはこのヴァージョンのリマスターであり、ここでも鮮明な音に生まれかわっていたものであるが。。。
しかしこの“アニヴァーサリー・エディション”に入っているものは、ベースのアレンジこそ同じだと思われるが、パーソネルも編成も違う・・・。
確かにベース一本に乗っていく歌唱のコンセプトは一緒だが、ごくごく控えめに添えられたそれ以外の音、そして最後後奏と言ってよい合奏のテイストはどことなくイギリスのフォークソングやカントリーミュージックを思わせるものでなかなかに興味深かった。
この曲の演奏史にこんな経過があったことを知ることができたのも、楽しく贅沢なことである。
このアルバムのライナーには“JENNY SINGS LENNY”と題された絵が掲げられており、丁寧な装丁で各曲のパーソネルや手紙の類が夥しい写真と共に振り返られている。
当然にこの2人は音楽上、非常に幸福なよい関係をそのキャリアの中で築いてきたのだと知れる・・・
20年経って・・・
落穂ひろいを少し加えてなんと見事な総括がなされたことではないか・・・。
だとすれば・・・
どうして『レナード・コーエンを歌う』の続編を期待してはいけないのだろう?
やはりこの作品が、自他共に認める最高傑作に収まるのか?
非常に気になり、期待するところである。(^^;)