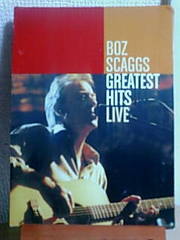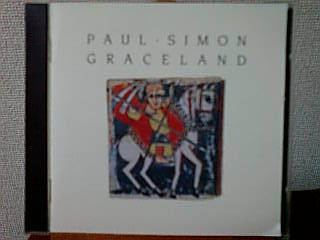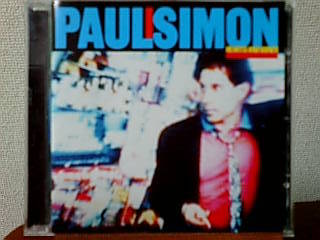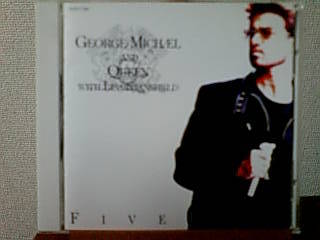★オアシス
(演奏:ロバータ・フラック)
1.オアシス
2.オール・コウト・アップ
3.ルック・アウト
4.ショック・トゥ・マイ・システム
5.フー・ユー・ブロウト・ミ・ラヴ
6.サムシング・マジック
7.アンド・ソー・イット・ゴーズ
8.ユー・ノウ・ホワット・イッツ・ライク
9.アンド・ソー・イット・ゴーズ(リプライズ)
10.マイ・サムワン・トゥ・ラヴ
11.ブラジル
(1988年)
昨年の10月23日にこのブログを開始しました。
思うところあって、1年(ホントは一定期間ということで時期を1年と決めたのは半年ぐらい前であります)は絶対継続するという誓いを立てて、アヤシイところはあるもののなんとかかんとかその日付の記事は書き込み続けることができました。
もちろんこのブログはやめませんよ。(^^;)
でも、毎日投稿するのは流石にしんどいものがあります。
メインステージの仕事が忙しくなったとかそういうことでもないんですが、アウトプットすることは結構この一年で書き込んだんじゃないかなという充足感はかなりあります。
インプットするための時間もほしいし、記事のためのディスクの視聴というのもなかったわけではないし・・・本当は、全部の所有ディスクにリスペクトの意味を込めて記事をつけようと想っていた時期もあるのですが、とてもそれは難しいなということで折り合いをつけることにしたしだいです。
今後はトピックがあったり、本当にこれはと思うディスクがあったときに記事を書いていきたいと思います。
もちろん、書きたいと想うディスクはまだまだいっぱい手許にありますが・・・これは書くべき内容をしっかり吟味して納得できる記事にしてから提示していきたい・・・そんな風に思っています。
ことしの正月には「きりぎりす宣言」で行くという誓願を立てたのですが、概ね実現されています。
唯一このブログの運営だけは「ギリギリす状態」でありましたが・・・。(^^;)
あと、何が変わったかというと体重が15キロ近く落とせていることでしょうか。
私個人としては、過去1年の記事が残ったことでしょうかね。
このとき、何があって、どのように感じていたのかはよく判ります。日記をつけてらっしゃるみなさんは、この感覚をずっと持ち続けてらっしゃるんだということがよくわかりました。
過去の自分の垂れ流し状態から、とりあえず網にかけてすくいあげて後から見ることができるようになっていることは、かくも違うことであるというのは大発見でしたね。
それと、本を読むようになったかな。(^^;)
本当に充実した1年だったと振り返ることが出来ます。勝手に始めたといいながら、やはりアクセスいただいている皆さんの存在が励みになっていて、続けさせていただいていたという側面はおおいにあります。
改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。(^^)/
今日から比較的長期の出張なので、しばらくここでクールダウンしたいと思います。
次回からといっても、新装もなにもしませんし、字数制限を基本的に2000字以上という制約もかけてきたんですが、これも取っ払って好きなように書き綴って生きたいと想いますので、よければまたお越しくださいね。(^^;)
ロバータ・フラックのアルバムを選んだのは、もちろん『オアシス』という単語を意識してというだけの意味合いです。
大歌手でありながら、とても伸びやかな歌声でありながら、どことなく硬く初々しさが漂う彼女のフィーリングを2年目のこのバックステージの運営にも取り入れていきたいと思います。
でもしばらくは書けませんのであしからず・・・。
★ピュア・シューア
(演奏:ダイアン・シューア)

1.ノウバディ・ダズ・ミー
2.オール・コート・アップ・イン・ラヴ
3.ディード・アイ・ドゥ
4.縁は異なもの
5.タッチ
6.ベイビー・ユー・ゴット・ホワット・イット・テイクス
7.アンフォゲッタブル
8.アイ・クッド・ゲット・ユースト・トゥ・ディス
9.ユー・ドント・リメンバー・ミー
10.ホールド・アウト
11.ウィ・キャン・オンリー・トライ
(1990年)
さて、素晴らしい歌唱力を誇るダイアン・シューアのこのアルバムもあわせてご紹介します。
理由は、収録曲の“オール・コート・アップ・イン・ラヴ”(邦題は違いますが双方とも2曲目に収められています)が共通で、そのききくらべが興味深いからです。
ともすれば歌唱力の豊かな人はそれをひけらかすような歌い方に堕することがあるところ、シューアはすごいと思わせながら誠実さがあるのでそのような危惧はありません。
いまほど久しぶりに堪能して、とてもリラックスした楽しみを味わいました。
やはりここは私にとってのオアシスなのです。(^^)v
(演奏:ロバータ・フラック)
1.オアシス
2.オール・コウト・アップ
3.ルック・アウト
4.ショック・トゥ・マイ・システム
5.フー・ユー・ブロウト・ミ・ラヴ
6.サムシング・マジック
7.アンド・ソー・イット・ゴーズ
8.ユー・ノウ・ホワット・イッツ・ライク
9.アンド・ソー・イット・ゴーズ(リプライズ)
10.マイ・サムワン・トゥ・ラヴ
11.ブラジル
(1988年)
昨年の10月23日にこのブログを開始しました。
思うところあって、1年(ホントは一定期間ということで時期を1年と決めたのは半年ぐらい前であります)は絶対継続するという誓いを立てて、アヤシイところはあるもののなんとかかんとかその日付の記事は書き込み続けることができました。
もちろんこのブログはやめませんよ。(^^;)
でも、毎日投稿するのは流石にしんどいものがあります。
メインステージの仕事が忙しくなったとかそういうことでもないんですが、アウトプットすることは結構この一年で書き込んだんじゃないかなという充足感はかなりあります。
インプットするための時間もほしいし、記事のためのディスクの視聴というのもなかったわけではないし・・・本当は、全部の所有ディスクにリスペクトの意味を込めて記事をつけようと想っていた時期もあるのですが、とてもそれは難しいなということで折り合いをつけることにしたしだいです。
今後はトピックがあったり、本当にこれはと思うディスクがあったときに記事を書いていきたいと思います。
もちろん、書きたいと想うディスクはまだまだいっぱい手許にありますが・・・これは書くべき内容をしっかり吟味して納得できる記事にしてから提示していきたい・・・そんな風に思っています。
ことしの正月には「きりぎりす宣言」で行くという誓願を立てたのですが、概ね実現されています。
唯一このブログの運営だけは「ギリギリす状態」でありましたが・・・。(^^;)
あと、何が変わったかというと体重が15キロ近く落とせていることでしょうか。
私個人としては、過去1年の記事が残ったことでしょうかね。
このとき、何があって、どのように感じていたのかはよく判ります。日記をつけてらっしゃるみなさんは、この感覚をずっと持ち続けてらっしゃるんだということがよくわかりました。
過去の自分の垂れ流し状態から、とりあえず網にかけてすくいあげて後から見ることができるようになっていることは、かくも違うことであるというのは大発見でしたね。
それと、本を読むようになったかな。(^^;)
本当に充実した1年だったと振り返ることが出来ます。勝手に始めたといいながら、やはりアクセスいただいている皆さんの存在が励みになっていて、続けさせていただいていたという側面はおおいにあります。
改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。(^^)/
今日から比較的長期の出張なので、しばらくここでクールダウンしたいと思います。
次回からといっても、新装もなにもしませんし、字数制限を基本的に2000字以上という制約もかけてきたんですが、これも取っ払って好きなように書き綴って生きたいと想いますので、よければまたお越しくださいね。(^^;)
ロバータ・フラックのアルバムを選んだのは、もちろん『オアシス』という単語を意識してというだけの意味合いです。
大歌手でありながら、とても伸びやかな歌声でありながら、どことなく硬く初々しさが漂う彼女のフィーリングを2年目のこのバックステージの運営にも取り入れていきたいと思います。
でもしばらくは書けませんのであしからず・・・。
★ピュア・シューア
(演奏:ダイアン・シューア)

1.ノウバディ・ダズ・ミー
2.オール・コート・アップ・イン・ラヴ
3.ディード・アイ・ドゥ
4.縁は異なもの
5.タッチ
6.ベイビー・ユー・ゴット・ホワット・イット・テイクス
7.アンフォゲッタブル
8.アイ・クッド・ゲット・ユースト・トゥ・ディス
9.ユー・ドント・リメンバー・ミー
10.ホールド・アウト
11.ウィ・キャン・オンリー・トライ
(1990年)
さて、素晴らしい歌唱力を誇るダイアン・シューアのこのアルバムもあわせてご紹介します。
理由は、収録曲の“オール・コート・アップ・イン・ラヴ”(邦題は違いますが双方とも2曲目に収められています)が共通で、そのききくらべが興味深いからです。
ともすれば歌唱力の豊かな人はそれをひけらかすような歌い方に堕することがあるところ、シューアはすごいと思わせながら誠実さがあるのでそのような危惧はありません。
いまほど久しぶりに堪能して、とてもリラックスした楽しみを味わいました。
やはりここは私にとってのオアシスなのです。(^^)v