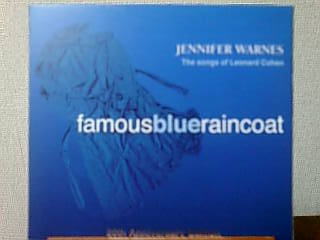★高橋多佳子 ~ピアノ リサイタル~ at MUSE CUBE HALL
《前半》
1.スカルラッティ:ソナタ ホ長調 K.380/L.23
2.モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330
3.ショパン:ワルツ 第5番 変イ長調 作品42 《大円舞曲》
4.ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47
《後半》
5.ラヴェル:夜のガスパール (ベルトランの詩、朗読付き)
6.リスト:巡礼の年報 第2年《イタリア》S.161より 「ダンテを読んで―ソナタ風幻想曲」
《アンコール》
7.シューベルト/リスト:ウィーンの夜会 第6番
8.ショパン:12の練習曲より第3番 作品10の3 《別れの曲》
(2008年9月21日 所沢市民文化センター ミューズ キューブホール)
所沢市民文化センター・ミューズで開催された高橋多佳子さんのリサイタルを聴いた。
毎度のことではあるが、私にとっては『待望の』という修飾語が付くイベントであり、これまた毎度のことであるが、その演奏にはすこぶる付きの充足感を味わって帰途に着くことが約束されている・・・そんなイベントでもある。
果たして本日もそうだった。(^^)v
早速、個々の演奏についての感想文を・・・(^^;)
冒頭のスカルラッティのソナタを多佳子さんから聴くのは初めてではない。
逆にスカルラッティの曲で聴いたことがあるのはこの曲だけ・・・ともいえる。
結論をいえば、右手のニュアンスの多彩さが生かされること、その冒頭部“♪~ ちゃんちゃちゃちゃっちゃっ・ちゃんちゃっちゃぁ~~~~”とリズミックなトゥッティ(?)との対比が楽しいことなどの点で、555曲あるソナタのうちもっとも多佳子さんに合ったレパートリーと思われる。
それだけでなく中間部のニュアンスの付け方には、多佳子さんからしか聴けないあの感覚が確かにあったし、ニュアンスといえば装飾音がめっぽう品が良かったことも耳の娯楽としてはゼイタクなことだった。
「装飾音」についての専門知識はないけれど、とてもやんごとなき女性の手になるもの・・・王女様のために作曲されたものだからそれは望ましいことだろう・・・のように感じられて、私にはとても好ましかった。
続いて、モーツァルトのK.330ハ長調のピアノ・ソナタ。
モーツァルトのピアノ・ソナタって、私はそれと聞くだけでいささか金縛りにあうような気がする。。。(^^;)
多佳子さんの演奏は、多分まったく模範的であったであろうし、足りないものは何一つ思いつかない。
音色、表情、しなやかで見通しの良い非の打ちどころのない表現・・・多分に愉悦的に弾かれたのはなかろうかとも思うには思う。
ではあるのだが、聴いてるほうにモーツァルトのソナタを愉悦的に(楽しく?)聞くための遺伝子というか抗体というか素養が不足していたのかもしれない。(-“-;)
もしかしたら本日の演奏の中で最も「演奏自体の完成度」が高い、立派な演奏だったかもしれない・・・ことを思いながらも、私はいまいち乗り切れなかった。
理由ははっきりしない・・・。
が、先にも述べたようにきっと聴く側の事情によるのだろう。
生まれてからこのかたの時間の使い方の中で、私のモーツァルト理解がこの曲を聴いたときに自分のものにできるレベルまで持ち上がっていなかった・・・・・
おおかたそんなところだろう。
前半の最後は、ショパンの変イ長調の2作品である。
これまでの多佳子さんとの会話の中で、彼女がショパンの「変イ長調」作品の素晴らしさに注目されていることは知っていた。
確か、以前同じホールでりかりんさんと“デュオ・グレース”として弾かれているはず。
そのときソロ・パートで演奏された2曲・・・“即興曲第1番 作品29”、“練習曲 作品24-1《エオリアン・ハープ》”・・・もまた、変イ長調であったことをすら忘れていなかったエラい“私”・・・。(^^;)
そのほかにも多佳子さんに“変イ長調”と言われたときチェックしていたために“英雄ポロネーズ”、“幻想ポロネーズ”、“華麗なる円舞曲(作品34-1)”、“別れのワルツ”・・・などなど、この調性のかずかずの名曲はすぐに思い浮かべることができるのだ。(^^)v
そんな中、今回多佳子さんが選んだ2曲、作品42の“大円舞曲”と“バラード第3番”は実演では初めて聴くレパートリーであった。
やはり多佳子さんのショパンは彼女にとっても、あるいは聴き手である私のいずれにとってもホームグラウンドなんだろうな・・・。
いずれの曲も100%多佳子さんと一体化しているようにさえ思えた。。。
そればかりではない!
聴き手がいることに配慮してなのか・・・・・ややたっぷりとられたフレージングの呼吸に乗っかると、あら不思議、私も自然にチューニングが合うかのごとく、すんなりショパンの世界に誘われてしまった。
これはライヴじゃないと味わえない感覚、思わず頬が緩む。(^^)/
これは“多佳子さん自身がショパン”であり“ショパンの曲そのもの”だからこそ、そんな感覚を味わわせてくれることができる・・・そうであるに違いない。
そしていささか自慢めいて言わせてもらえるならば、私の「受信感度」、これだってまんざらじゃないからだよね・・・とも言えよう。(^^;)
“大円舞曲”、この曲の出だしとしては異例なほどファンタジックにスケール大きく始まったように思う。
いや、これから後の楽曲とその演奏にはファンタジー(幻想)というコンセプトが一貫していた。
軽妙で雄弁な右手の旋律、表情も音色も高橋多佳子節。
そして左手のバス音の小股の切れ上がったとでもいうありかた・・・これも多佳子さん演奏の得難い特徴、「これを聴くためにリサイタルに来たのよね」って感じで幸せであった。
“バラード第3番”では、これもギリギリまで表現意欲を積極的に顕した演奏だった。
特に録音されたものを聞くともっと抑えた演奏が多いように思うけれど、「ここまで行っちゃってでも音楽的にも芸術的にも踏みとどまって楽しませてくれるのが多佳子さんなんだよね~」とここでも大いに納得。

後半はラヴェルの“夜のガズパール”から・・・。
安曇野でも試みられた、各曲の前にベルトランの詩を朗読するという趣向。
今回は照明を工夫してとの前触れどおり、スポットライトの中で起立しての朗読、そして演奏にはいるとステージの情報の白亜の壁に幻想的なライティング・・・オンディーヌは青、絞首台は赤~橙、スカルボは緑を基調・・・が当たって視覚的にも判りやすいという凝った仕掛けがあった。
この後に弾かれるリサイタル形式を編み出し暗譜云々の呪縛を考案したリスト先生が見たら、この視覚効果について何と言うだろうか?
私には面白い試みだと思われたけれど・・・。(^^;)
それはライティングが単色ではなく、赤に緑を混ぜて橙にしてみたり、緑の効果もライティングされている基の光の色そのものではない・・・空間で交じり合ううちに微妙にテイストの変わる色になる・・・ことが興味深かったから。
そして、ラヴェルの後にリストを演奏されたときも、断りはなかったけれど実は地面のライティングの光量を強くして、ダンテの世界を密かに演出していたことに気づいていたから。
その昔・・・
多佳子さんや私が子供の頃、いわゆる歌謡曲全盛時代にはこのようなライティングの演出は斯界では当たり前のことであり、大いに成果を挙げていた。
それを大胆にリサイタルに導入したというのは、発想からすると別に自然かもしれないけれど、実はピアニスト業界にあってはたいへんなことなのかもしれないと思っている。
そうであるならば、応援しなきゃね。。。
そんな気持ちにもなろうというものである。(^^;)
そして、多佳子さんの詩の朗読はこれは安曇野よりも格段に進歩されている。
ピアノがどれほど上手になられたかは、今のブルーレイの性能がどれだけ最新のDVDのそれを凌駕しているかというぐらいハイスペックな部分での話なので、私にはとんとわからないけれど、朗読の巧拙であるならばはっきりその違いはわかろうというもの。
同じことばを繰り返すときなど、どっちのことばにアクセントを置くか、また語尾をハッキリさせるかどうするか・・・
こんなことを楽譜を解釈するときさながらに、しっかりと準備されたんだろうなと思う。
ところで終演後、ご父君にお話を伺った際に聞いたのだが多佳子さんは学生時代に銀河鉄道999のメーテルの声優をしたことがあるらしい・・・。
それ自体は、多佳子さんの「ピアノの森」はもとより「北斗の拳」にまで至るアニメへの傾倒振りを思えばなんら不思議ではない。
しかし、その際、今や押しも押されぬ俳優としての座を揺ぎ無いものにしているT.K.氏と一緒にやっていたという情報には驚いた。
今日、多佳子さんに終演後サインしていただいたシン・ドンイルの『虹色の世界』のディスクでのナレーションの妙も納得というものである。(^^;)
なんとなく照明と朗読へのコメントが、演奏の感想より長くなった気がするけど・・・・・・。
次は肝心の“夜のガスパール”の演奏から・・・・・・・だったっけ?
「悪かろうはずがない!!」
・・・・・のひとことで終わらせるわけにも行かないか・・・。(^^;)
冒頭の“オンディーヌ”だが、私はこの演奏を多佳子さんが演奏会にかけて真剣に弾いたのであれば、最早どのように弾かれたとしても鳥肌が立つほど感動するのを禁じ得ないと確信している。
ショパンが生涯最後の演奏会をパリで実施したとき、“舟歌”の演奏を強弱などかなり楽譜の表記と違えて表現したが、聴衆はたいへんな感銘を受けたとされている。
それはもちろん最高の作曲家であり、最高の自作の演奏家であったショパンが“そのとき”の感興に任せて最高と信じる表現をしたわけであるから、観客の感銘は当然だ・・・という理解でよいのだと思う。
翻って、多佳子さんのショパンの多くの曲の奏楽はもちろんその域にあるのだが、ラヴェルにあってもこの“オンディーヌ”に関しては間違いなくそのレベルにある・・・
それを確信したのだ!
それは、去年のヤマハ立川店に於ける何年ぶりかの披露に続き、ピアノを安曇野のベーゼン、そしてスタインウェイと替えながらもどんどん深化していくその表現を、私が実体験として目の当たりにした実績から経験的に断言できること。
繰り返して言えば、どのように弾かれたとしても高橋多佳子の演奏する“オンディーヌ”は、驚くべきことに“そのとき”その観衆の前でそのピアノを遣ったときの最高の表現を約束してくれるのだ。
具体的には、最初の雫の音型を粒ぞろいに弾いたとしても、敢えてそろえることに拘泥しないで表現したとしても・・・
その後の旋律を歌いこんでもそうでなくても、交差した手の左手旋律を強調しようとも両手のメロディーのユニゾンに意識が向けられていても・・・
それらはどのように弾かれても、それが“そのとき”における最高の解釈であり、多佳子さんの感性はそれを的確に探り当てることができる・・・・・・そこまで曲を血肉と化した境涯に至っているのだという確信なのである。
そして“スカルボ”も考えうる限りの試行錯誤は経て、当初思い切り弾けていたときの魅力とはまた別の円熟した味わいというべきものを醸し出していた。
どこをどうしたら制動が利くのか、どんな節回しで行けばどのような効果が現われるのかとことん検討しつくした思われる。
炸裂する音響の中にあってすら表現の幅、ニュアンスの豊かさが格段に違っていたから、遠からず“オンディーヌ”の演奏の域にまで達するに違いあるまい。
もしかしたら多佳子さんにとって、最もこの曲の難物は“絞首台”かもしれない。
尋常じゃない集中力を継続させラヴェルが小節1つずつを積上げて作曲していったのをトレースするがごとく、慎重に音を積み重ねておられるのはよ~く聴き取れた。
和音を伴う旋律の生々しさにおいて、今回の演奏に匹敵する演奏はディスクでは聞いたことがない・・・そりゃ生だからかもしれない・・・けれど、野ざらしの骸にしては死体が新しい気もした。(^^;)
もっと鄙びてるってもんだよね・・・って感じだろうか?
そしてこの曲の要は終始鳴らされる鐘の音・・・これが素っ気なく、でも実在感を持って演奏されねばならないと思うのだが・・・。
多佳子さんはペダルを巧みに遣って音を合成していた・・・
きっとハーフペダルのテクニックであの2つ目の引っかかるような音をこしらえているんだろうな・・・な~んて思いながら聞いていた。
私見だが、この鐘の音の連打のアゴーギグ・デュナーミクはある意味一定でありながら必ずしも一定でないと思っている。
うまく言えないが、これをメトロノーム代わりにテンポキープする、そういうあり方ではいけないのではないだろうか?
思えば多佳子さんからは、これまでにも“展覧会の絵のキエフの大門”、“ラ・カンパネラ”、そしてこの後に演奏される“ダンテ・ソナタ”などなど・・・いろんな鐘の音の表現を聴かせてもらってきたが、「幸せな鐘」、「けたたましい鐘」の表現のほうが『執拗な鐘』のそれよりもお似合いかもしれないな・・・とチラと思った。
それにしてもこの曲・・・“夜のガスパール”。
納得がいくまで弾き込まれた暁には、なんとか録音してもらえないかなぁ~。
切実なお願い。m(_ _)m
プログラム最後の曲目、リストの“ダンテを読んで”は本邦初公開だそう・・・。
安曇野でこの曲を手がけると伺っていたので楽しみにしていたが、想像通り多佳子さんに合ったレパートリーだった。
まず、最初のオクターブの和音が左手で奏されているのに驚いた。
右手が加わったところ、その中音域の雄弁なことといえばこれも多佳子さんならでは・・・。
激するところと、中間部の甘美なところの弾き分けも鮮やかに最後まで緊張感を切らさずに聴くことができて、自分を誉めてあげたい。(^^;)
もちろん全編“ブラヴォーな演奏”であったことこの上ない・・・・・。
“スカルボ”から連続しての演奏、聴くほうも結構その展開を追いきるのはけっこうハードだったなぁ~。(^^;)

そして、アンコール・・・
“ウィーンの夜会 第6番”は、最初アフターアワーズのリラックスした雰囲気で始まっていい感じ・・・・・と思っていたのだが、どこからともなく途中ですごく感極まって表現が真剣そのものになったように聞こえたのはなぜだろう?
なんかいきなり聖域(ゾーン)に入り込んじゃったような集中度合いに聞こえた・・・。
だからどうだということはないのだが、最後の走句にせよ白眉ともいえる音色美、旋律美が聴かれてゾクゾクだった。。。
いつ、どこから、なぜにあんなに気合が入っちゃったんだろう・・・?
中盤以降の美音はいまも耳の奥に残っているけれど、猫なで声というか神経を麻痺させられそうな必殺の響きだったと改めて感じている。
“別れの曲”もたっぷり歌いこまれて、「これぞライブだね」。(^^)/
今回もまた期待通り、いや、いつもながら期待以上に充足したリサイタルだったなぁ~。(^^;)
最後に、多佳子さんの演奏姿が心なしか大人びた・・・自然体で大家チックなオーラをかもしてた・・・ように思えたんだけど気のせいかなぁ~?
アップの髪にカチューシャをしていなかったから・・・・・という訳ではないと思うんだけど。。。
とにもかくにも、余は満足ぢゃ!(^^)v
《前半》
1.スカルラッティ:ソナタ ホ長調 K.380/L.23
2.モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330
3.ショパン:ワルツ 第5番 変イ長調 作品42 《大円舞曲》
4.ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47
《後半》
5.ラヴェル:夜のガスパール (ベルトランの詩、朗読付き)
6.リスト:巡礼の年報 第2年《イタリア》S.161より 「ダンテを読んで―ソナタ風幻想曲」
《アンコール》
7.シューベルト/リスト:ウィーンの夜会 第6番
8.ショパン:12の練習曲より第3番 作品10の3 《別れの曲》
(2008年9月21日 所沢市民文化センター ミューズ キューブホール)
所沢市民文化センター・ミューズで開催された高橋多佳子さんのリサイタルを聴いた。
毎度のことではあるが、私にとっては『待望の』という修飾語が付くイベントであり、これまた毎度のことであるが、その演奏にはすこぶる付きの充足感を味わって帰途に着くことが約束されている・・・そんなイベントでもある。
果たして本日もそうだった。(^^)v
早速、個々の演奏についての感想文を・・・(^^;)
冒頭のスカルラッティのソナタを多佳子さんから聴くのは初めてではない。
逆にスカルラッティの曲で聴いたことがあるのはこの曲だけ・・・ともいえる。
結論をいえば、右手のニュアンスの多彩さが生かされること、その冒頭部“♪~ ちゃんちゃちゃちゃっちゃっ・ちゃんちゃっちゃぁ~~~~”とリズミックなトゥッティ(?)との対比が楽しいことなどの点で、555曲あるソナタのうちもっとも多佳子さんに合ったレパートリーと思われる。
それだけでなく中間部のニュアンスの付け方には、多佳子さんからしか聴けないあの感覚が確かにあったし、ニュアンスといえば装飾音がめっぽう品が良かったことも耳の娯楽としてはゼイタクなことだった。
「装飾音」についての専門知識はないけれど、とてもやんごとなき女性の手になるもの・・・王女様のために作曲されたものだからそれは望ましいことだろう・・・のように感じられて、私にはとても好ましかった。
続いて、モーツァルトのK.330ハ長調のピアノ・ソナタ。
モーツァルトのピアノ・ソナタって、私はそれと聞くだけでいささか金縛りにあうような気がする。。。(^^;)
多佳子さんの演奏は、多分まったく模範的であったであろうし、足りないものは何一つ思いつかない。
音色、表情、しなやかで見通しの良い非の打ちどころのない表現・・・多分に愉悦的に弾かれたのはなかろうかとも思うには思う。
ではあるのだが、聴いてるほうにモーツァルトのソナタを愉悦的に(楽しく?)聞くための遺伝子というか抗体というか素養が不足していたのかもしれない。(-“-;)
もしかしたら本日の演奏の中で最も「演奏自体の完成度」が高い、立派な演奏だったかもしれない・・・ことを思いながらも、私はいまいち乗り切れなかった。
理由ははっきりしない・・・。
が、先にも述べたようにきっと聴く側の事情によるのだろう。
生まれてからこのかたの時間の使い方の中で、私のモーツァルト理解がこの曲を聴いたときに自分のものにできるレベルまで持ち上がっていなかった・・・・・
おおかたそんなところだろう。
前半の最後は、ショパンの変イ長調の2作品である。
これまでの多佳子さんとの会話の中で、彼女がショパンの「変イ長調」作品の素晴らしさに注目されていることは知っていた。
確か、以前同じホールでりかりんさんと“デュオ・グレース”として弾かれているはず。
そのときソロ・パートで演奏された2曲・・・“即興曲第1番 作品29”、“練習曲 作品24-1《エオリアン・ハープ》”・・・もまた、変イ長調であったことをすら忘れていなかったエラい“私”・・・。(^^;)
そのほかにも多佳子さんに“変イ長調”と言われたときチェックしていたために“英雄ポロネーズ”、“幻想ポロネーズ”、“華麗なる円舞曲(作品34-1)”、“別れのワルツ”・・・などなど、この調性のかずかずの名曲はすぐに思い浮かべることができるのだ。(^^)v
そんな中、今回多佳子さんが選んだ2曲、作品42の“大円舞曲”と“バラード第3番”は実演では初めて聴くレパートリーであった。
やはり多佳子さんのショパンは彼女にとっても、あるいは聴き手である私のいずれにとってもホームグラウンドなんだろうな・・・。
いずれの曲も100%多佳子さんと一体化しているようにさえ思えた。。。
そればかりではない!
聴き手がいることに配慮してなのか・・・・・ややたっぷりとられたフレージングの呼吸に乗っかると、あら不思議、私も自然にチューニングが合うかのごとく、すんなりショパンの世界に誘われてしまった。
これはライヴじゃないと味わえない感覚、思わず頬が緩む。(^^)/
これは“多佳子さん自身がショパン”であり“ショパンの曲そのもの”だからこそ、そんな感覚を味わわせてくれることができる・・・そうであるに違いない。
そしていささか自慢めいて言わせてもらえるならば、私の「受信感度」、これだってまんざらじゃないからだよね・・・とも言えよう。(^^;)
“大円舞曲”、この曲の出だしとしては異例なほどファンタジックにスケール大きく始まったように思う。
いや、これから後の楽曲とその演奏にはファンタジー(幻想)というコンセプトが一貫していた。
軽妙で雄弁な右手の旋律、表情も音色も高橋多佳子節。
そして左手のバス音の小股の切れ上がったとでもいうありかた・・・これも多佳子さん演奏の得難い特徴、「これを聴くためにリサイタルに来たのよね」って感じで幸せであった。
“バラード第3番”では、これもギリギリまで表現意欲を積極的に顕した演奏だった。
特に録音されたものを聞くともっと抑えた演奏が多いように思うけれど、「ここまで行っちゃってでも音楽的にも芸術的にも踏みとどまって楽しませてくれるのが多佳子さんなんだよね~」とここでも大いに納得。

後半はラヴェルの“夜のガズパール”から・・・。
安曇野でも試みられた、各曲の前にベルトランの詩を朗読するという趣向。
今回は照明を工夫してとの前触れどおり、スポットライトの中で起立しての朗読、そして演奏にはいるとステージの情報の白亜の壁に幻想的なライティング・・・オンディーヌは青、絞首台は赤~橙、スカルボは緑を基調・・・が当たって視覚的にも判りやすいという凝った仕掛けがあった。
この後に弾かれるリサイタル形式を編み出し暗譜云々の呪縛を考案したリスト先生が見たら、この視覚効果について何と言うだろうか?
私には面白い試みだと思われたけれど・・・。(^^;)
それはライティングが単色ではなく、赤に緑を混ぜて橙にしてみたり、緑の効果もライティングされている基の光の色そのものではない・・・空間で交じり合ううちに微妙にテイストの変わる色になる・・・ことが興味深かったから。
そして、ラヴェルの後にリストを演奏されたときも、断りはなかったけれど実は地面のライティングの光量を強くして、ダンテの世界を密かに演出していたことに気づいていたから。
その昔・・・
多佳子さんや私が子供の頃、いわゆる歌謡曲全盛時代にはこのようなライティングの演出は斯界では当たり前のことであり、大いに成果を挙げていた。
それを大胆にリサイタルに導入したというのは、発想からすると別に自然かもしれないけれど、実はピアニスト業界にあってはたいへんなことなのかもしれないと思っている。
そうであるならば、応援しなきゃね。。。
そんな気持ちにもなろうというものである。(^^;)
そして、多佳子さんの詩の朗読はこれは安曇野よりも格段に進歩されている。
ピアノがどれほど上手になられたかは、今のブルーレイの性能がどれだけ最新のDVDのそれを凌駕しているかというぐらいハイスペックな部分での話なので、私にはとんとわからないけれど、朗読の巧拙であるならばはっきりその違いはわかろうというもの。
同じことばを繰り返すときなど、どっちのことばにアクセントを置くか、また語尾をハッキリさせるかどうするか・・・
こんなことを楽譜を解釈するときさながらに、しっかりと準備されたんだろうなと思う。
ところで終演後、ご父君にお話を伺った際に聞いたのだが多佳子さんは学生時代に銀河鉄道999のメーテルの声優をしたことがあるらしい・・・。
それ自体は、多佳子さんの「ピアノの森」はもとより「北斗の拳」にまで至るアニメへの傾倒振りを思えばなんら不思議ではない。
しかし、その際、今や押しも押されぬ俳優としての座を揺ぎ無いものにしているT.K.氏と一緒にやっていたという情報には驚いた。
今日、多佳子さんに終演後サインしていただいたシン・ドンイルの『虹色の世界』のディスクでのナレーションの妙も納得というものである。(^^;)
なんとなく照明と朗読へのコメントが、演奏の感想より長くなった気がするけど・・・・・・。
次は肝心の“夜のガスパール”の演奏から・・・・・・・だったっけ?
「悪かろうはずがない!!」
・・・・・のひとことで終わらせるわけにも行かないか・・・。(^^;)
冒頭の“オンディーヌ”だが、私はこの演奏を多佳子さんが演奏会にかけて真剣に弾いたのであれば、最早どのように弾かれたとしても鳥肌が立つほど感動するのを禁じ得ないと確信している。
ショパンが生涯最後の演奏会をパリで実施したとき、“舟歌”の演奏を強弱などかなり楽譜の表記と違えて表現したが、聴衆はたいへんな感銘を受けたとされている。
それはもちろん最高の作曲家であり、最高の自作の演奏家であったショパンが“そのとき”の感興に任せて最高と信じる表現をしたわけであるから、観客の感銘は当然だ・・・という理解でよいのだと思う。
翻って、多佳子さんのショパンの多くの曲の奏楽はもちろんその域にあるのだが、ラヴェルにあってもこの“オンディーヌ”に関しては間違いなくそのレベルにある・・・
それを確信したのだ!
それは、去年のヤマハ立川店に於ける何年ぶりかの披露に続き、ピアノを安曇野のベーゼン、そしてスタインウェイと替えながらもどんどん深化していくその表現を、私が実体験として目の当たりにした実績から経験的に断言できること。
繰り返して言えば、どのように弾かれたとしても高橋多佳子の演奏する“オンディーヌ”は、驚くべきことに“そのとき”その観衆の前でそのピアノを遣ったときの最高の表現を約束してくれるのだ。
具体的には、最初の雫の音型を粒ぞろいに弾いたとしても、敢えてそろえることに拘泥しないで表現したとしても・・・
その後の旋律を歌いこんでもそうでなくても、交差した手の左手旋律を強調しようとも両手のメロディーのユニゾンに意識が向けられていても・・・
それらはどのように弾かれても、それが“そのとき”における最高の解釈であり、多佳子さんの感性はそれを的確に探り当てることができる・・・・・・そこまで曲を血肉と化した境涯に至っているのだという確信なのである。
そして“スカルボ”も考えうる限りの試行錯誤は経て、当初思い切り弾けていたときの魅力とはまた別の円熟した味わいというべきものを醸し出していた。
どこをどうしたら制動が利くのか、どんな節回しで行けばどのような効果が現われるのかとことん検討しつくした思われる。
炸裂する音響の中にあってすら表現の幅、ニュアンスの豊かさが格段に違っていたから、遠からず“オンディーヌ”の演奏の域にまで達するに違いあるまい。
もしかしたら多佳子さんにとって、最もこの曲の難物は“絞首台”かもしれない。
尋常じゃない集中力を継続させラヴェルが小節1つずつを積上げて作曲していったのをトレースするがごとく、慎重に音を積み重ねておられるのはよ~く聴き取れた。
和音を伴う旋律の生々しさにおいて、今回の演奏に匹敵する演奏はディスクでは聞いたことがない・・・そりゃ生だからかもしれない・・・けれど、野ざらしの骸にしては死体が新しい気もした。(^^;)
もっと鄙びてるってもんだよね・・・って感じだろうか?
そしてこの曲の要は終始鳴らされる鐘の音・・・これが素っ気なく、でも実在感を持って演奏されねばならないと思うのだが・・・。
多佳子さんはペダルを巧みに遣って音を合成していた・・・
きっとハーフペダルのテクニックであの2つ目の引っかかるような音をこしらえているんだろうな・・・な~んて思いながら聞いていた。
私見だが、この鐘の音の連打のアゴーギグ・デュナーミクはある意味一定でありながら必ずしも一定でないと思っている。
うまく言えないが、これをメトロノーム代わりにテンポキープする、そういうあり方ではいけないのではないだろうか?
思えば多佳子さんからは、これまでにも“展覧会の絵のキエフの大門”、“ラ・カンパネラ”、そしてこの後に演奏される“ダンテ・ソナタ”などなど・・・いろんな鐘の音の表現を聴かせてもらってきたが、「幸せな鐘」、「けたたましい鐘」の表現のほうが『執拗な鐘』のそれよりもお似合いかもしれないな・・・とチラと思った。
それにしてもこの曲・・・“夜のガスパール”。
納得がいくまで弾き込まれた暁には、なんとか録音してもらえないかなぁ~。
切実なお願い。m(_ _)m
プログラム最後の曲目、リストの“ダンテを読んで”は本邦初公開だそう・・・。
安曇野でこの曲を手がけると伺っていたので楽しみにしていたが、想像通り多佳子さんに合ったレパートリーだった。
まず、最初のオクターブの和音が左手で奏されているのに驚いた。
右手が加わったところ、その中音域の雄弁なことといえばこれも多佳子さんならでは・・・。
激するところと、中間部の甘美なところの弾き分けも鮮やかに最後まで緊張感を切らさずに聴くことができて、自分を誉めてあげたい。(^^;)
もちろん全編“ブラヴォーな演奏”であったことこの上ない・・・・・。
“スカルボ”から連続しての演奏、聴くほうも結構その展開を追いきるのはけっこうハードだったなぁ~。(^^;)

そして、アンコール・・・
“ウィーンの夜会 第6番”は、最初アフターアワーズのリラックスした雰囲気で始まっていい感じ・・・・・と思っていたのだが、どこからともなく途中ですごく感極まって表現が真剣そのものになったように聞こえたのはなぜだろう?
なんかいきなり聖域(ゾーン)に入り込んじゃったような集中度合いに聞こえた・・・。
だからどうだということはないのだが、最後の走句にせよ白眉ともいえる音色美、旋律美が聴かれてゾクゾクだった。。。
いつ、どこから、なぜにあんなに気合が入っちゃったんだろう・・・?
中盤以降の美音はいまも耳の奥に残っているけれど、猫なで声というか神経を麻痺させられそうな必殺の響きだったと改めて感じている。
“別れの曲”もたっぷり歌いこまれて、「これぞライブだね」。(^^)/
今回もまた期待通り、いや、いつもながら期待以上に充足したリサイタルだったなぁ~。(^^;)
最後に、多佳子さんの演奏姿が心なしか大人びた・・・自然体で大家チックなオーラをかもしてた・・・ように思えたんだけど気のせいかなぁ~?
アップの髪にカチューシャをしていなかったから・・・・・という訳ではないと思うんだけど。。。
とにもかくにも、余は満足ぢゃ!(^^)v