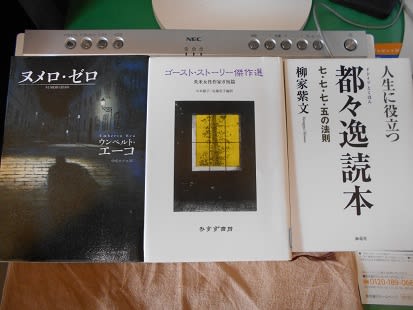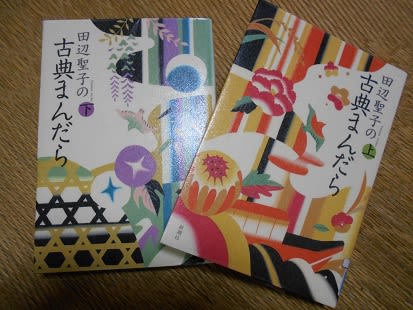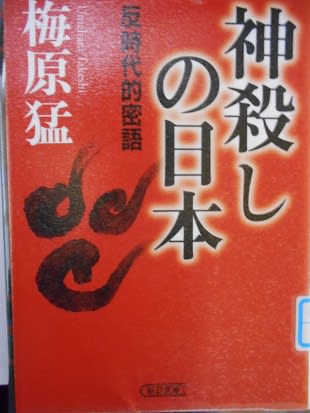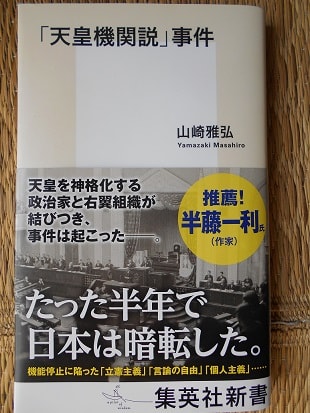この頃詩を読むことが多くなった。
字が大きい、従って字数が少ない、ページに余白が多いし目も疲れない。
だが、今回は少し厚手の読み物を借りてきた。

「世界の終わりの天文台」リリー・ブルックス・ダルトン(著)佐田千織(訳)2018.1東京創元社(刊)
地球からの連絡がまったく途絶えてしまった宇宙船の乗組員と、本部との通信が途絶え北極の天文台に一人取り残された研究者の別々の物語が同時進行する。
二つの物語の接点はアイリスという不思議な少女の行動。
地球の運命も、二つの物語の主人公達の運命もまったく謎のままに物語は終わる。
さて、お次は・・。

「議会に死体」ヘンリー・ウエイド(著)武藤崇恵(訳)2007.2原書房(刊)
人物像や背景を丁寧に描いていく本格ミステリー。
スピード感ありユーモアあり、エスプリも効いている。
ちょっと辛口の社会批評もいい。
今回の2冊は、読み応えがあった。
★★★を贈呈したい。

にほんブログ村
字が大きい、従って字数が少ない、ページに余白が多いし目も疲れない。
だが、今回は少し厚手の読み物を借りてきた。

「世界の終わりの天文台」リリー・ブルックス・ダルトン(著)佐田千織(訳)2018.1東京創元社(刊)
地球からの連絡がまったく途絶えてしまった宇宙船の乗組員と、本部との通信が途絶え北極の天文台に一人取り残された研究者の別々の物語が同時進行する。
二つの物語の接点はアイリスという不思議な少女の行動。
地球の運命も、二つの物語の主人公達の運命もまったく謎のままに物語は終わる。
さて、お次は・・。

「議会に死体」ヘンリー・ウエイド(著)武藤崇恵(訳)2007.2原書房(刊)
人物像や背景を丁寧に描いていく本格ミステリー。
スピード感ありユーモアあり、エスプリも効いている。
ちょっと辛口の社会批評もいい。
今回の2冊は、読み応えがあった。
★★★を贈呈したい。
にほんブログ村