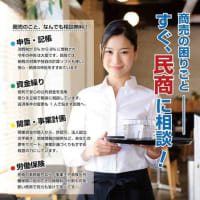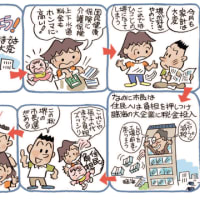300年以上も前から今なお、その存在をアピールしている茅葺き屋根の家。世界遺産となっている岐阜県白川郷には113棟の合掌造りと呼ばれる茅葺きの家が建ち並ぶ。この合掌造りは江戸時代後期から明治の初めにかけて建てられた茅葺き家で屋根がちょうど人が手を合わせたような形をしている事から、そのように呼ばれている。茅葺き家の特徴の1つである屋根裏の広い構造は古く養蚕業を営んでいたからでもある。
茅葺き屋根は寄棟造りが広く一般的であるが近畿地方では入母屋造りが多い。茅とは葉が細長く屋根を葺くのに適した「すすき」や「ちがや」等を言い、これらの他に「稲藁」も屋根葺きの材料に使われた。茅は高温多湿な日本の気候に優れており、葉に含まれている油が水を弾く防水の役目を果たす。また茅は音を吸収するため外からの防音の役割をして家の中は静かで、しかも、草を材料にしているので風通しが良く、夏は涼しい。
正に日本人の暮らしに適している家屋と言える。
茅葺き屋根のてっぺんの部分を芝棟と言うが月日を重ねるに連れ、そこに草が生い茂る。中には木々でさえ生える芝棟もある。この芝棟は反り上がった屋根を繋ぎ支える箇所であり、茅葺き作業では1番重要な仕上げの部分でもある。だから棟は昔から家の顔と言われて来た。一般的には棟を竹で編んだ竹簀巻きが多いが山間部の家は木を交差して作る置千木、また花魁の髪型をなぞったような笄棟も有名である。
筑波山の麓、茨城県石岡市にも100棟を超える茅葺き家がある。茅葺き屋根の棟の両端をキリビキと言うが、ここにはその地方・地方の風習になぞらえた文字が刻み込まれている。石岡市のキリビキには「龍」や「水」の1文字が目に付く。昔から龍は海の中や地中、天空に住み、雲や雨を自在に操り、水を呼ぶと言われ火災避けを意図してキリトビに龍が刻み込まれた。茅葺き家にとっては火事が1番、怖いからだ。その他、松竹梅などもキリトビには印されている。
また、茅葺き家は屋根裏にも特徴がある。茅の重さは屋根の大きさにもよるが概ね、数トンにもなる。この屋根を「さす組み」で受け止める。さす組みには屋根裏の横方向に真竹が使われる。竹は柔軟で強度がある。縦方向には丸太が使われ、ヒノキや松が用いられる。この真竹と丸太を縦横に網の目に結び括って行く。結びには縄が使われ「いぼ結び」と言う独特の方法で仕上げていく。この方法で結んだ「さす組み」は針金よりも頑丈になると言う。そして囲炉裏で燻らす生木の煙に含まれる有機化合物がいぼ結びの結び目を更に強くする。しかも、煤が茅に付着して防虫剤の効果も果たす。
時代の変化と共に、新しい様式を取り入れる事も必要だが、このように茅葺き屋根の建物は日本古来の生活様式にマッチングした家屋と言える。そして、その時代やその地方の人間社会の生活模様がそこに映し出されてくる。ここには日本の歴史と伝統が脈々と流れ、日本の風土に息づいている。茅葺き屋根は日本が日本である事の証明を見事にしていると言えよう。
世界に誇れる日本の財産…例えば、「日本国憲法9条」も茅葺き屋根のように大切にしていかなければならない!
茅葺き屋根は寄棟造りが広く一般的であるが近畿地方では入母屋造りが多い。茅とは葉が細長く屋根を葺くのに適した「すすき」や「ちがや」等を言い、これらの他に「稲藁」も屋根葺きの材料に使われた。茅は高温多湿な日本の気候に優れており、葉に含まれている油が水を弾く防水の役目を果たす。また茅は音を吸収するため外からの防音の役割をして家の中は静かで、しかも、草を材料にしているので風通しが良く、夏は涼しい。
正に日本人の暮らしに適している家屋と言える。
茅葺き屋根のてっぺんの部分を芝棟と言うが月日を重ねるに連れ、そこに草が生い茂る。中には木々でさえ生える芝棟もある。この芝棟は反り上がった屋根を繋ぎ支える箇所であり、茅葺き作業では1番重要な仕上げの部分でもある。だから棟は昔から家の顔と言われて来た。一般的には棟を竹で編んだ竹簀巻きが多いが山間部の家は木を交差して作る置千木、また花魁の髪型をなぞったような笄棟も有名である。
筑波山の麓、茨城県石岡市にも100棟を超える茅葺き家がある。茅葺き屋根の棟の両端をキリビキと言うが、ここにはその地方・地方の風習になぞらえた文字が刻み込まれている。石岡市のキリビキには「龍」や「水」の1文字が目に付く。昔から龍は海の中や地中、天空に住み、雲や雨を自在に操り、水を呼ぶと言われ火災避けを意図してキリトビに龍が刻み込まれた。茅葺き家にとっては火事が1番、怖いからだ。その他、松竹梅などもキリトビには印されている。
また、茅葺き家は屋根裏にも特徴がある。茅の重さは屋根の大きさにもよるが概ね、数トンにもなる。この屋根を「さす組み」で受け止める。さす組みには屋根裏の横方向に真竹が使われる。竹は柔軟で強度がある。縦方向には丸太が使われ、ヒノキや松が用いられる。この真竹と丸太を縦横に網の目に結び括って行く。結びには縄が使われ「いぼ結び」と言う独特の方法で仕上げていく。この方法で結んだ「さす組み」は針金よりも頑丈になると言う。そして囲炉裏で燻らす生木の煙に含まれる有機化合物がいぼ結びの結び目を更に強くする。しかも、煤が茅に付着して防虫剤の効果も果たす。
時代の変化と共に、新しい様式を取り入れる事も必要だが、このように茅葺き屋根の建物は日本古来の生活様式にマッチングした家屋と言える。そして、その時代やその地方の人間社会の生活模様がそこに映し出されてくる。ここには日本の歴史と伝統が脈々と流れ、日本の風土に息づいている。茅葺き屋根は日本が日本である事の証明を見事にしていると言えよう。
世界に誇れる日本の財産…例えば、「日本国憲法9条」も茅葺き屋根のように大切にしていかなければならない!