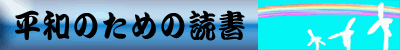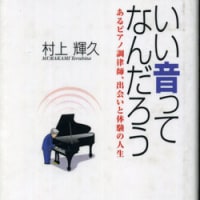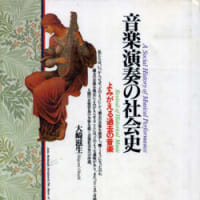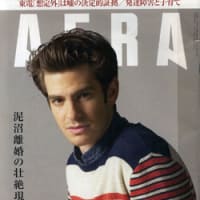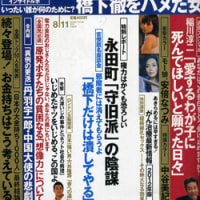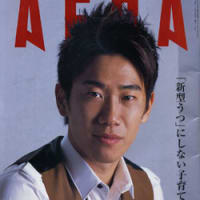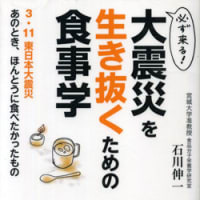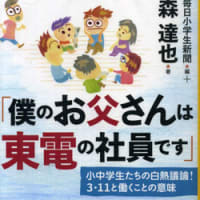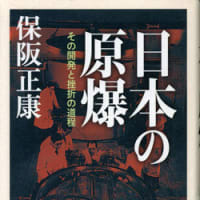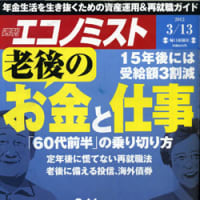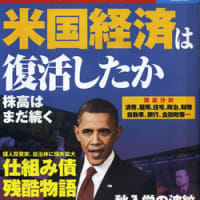『国民教育と軍隊-日本軍国主義教育の成立と展開-』
大江志乃夫・著/新日本出版社1974年
軍国主義も、時代によって変化していったようである……。

明治の「教育再改革」と昭和の軍国主義復活。下「」引用。
「「明治中期の教育再改革」は、「緊迫した内外の情勢」、すなわち世界史的段階としての帝国主義段階への移行と、それにともなう中国の植民地的分割から再分割への動きを中心とする東アジア情勢の緊張、そして、これにともなう「富国強兵の国策」、すなちわ日本資本主義の確立とその帝国主義への転化、強大な帝国主義軍事力の建設と軍国主義支配体制への確立にむけて、これらの「国策に協力する」学校教育体制の改編確立であった。-略-いいかえれば、自己の労働をひたすら国家と独占資本への奉仕としてささげ、いっさいの権利を放棄してもっぱら支配体制に対する義務と責任をのみ負い、積極的に軍服を着て銃をとり戦場におもむく労働者・市民・兵士を「育成」することをねらいとしたものである。それは、明治の「富国強兵」に現在の日本独占資本の経済大国主義と日米軍事体制下の四次防を対応させたうえ、日本の帝国主義・軍国主義復活過程の現段階に即応させた教育制度の改編構想であるといえよう。」
中教審のモデルとした明治。下「」引用。
「このうよな中教審の教育改革構想の正確とその帰着するものを具体的にとらえるためには、あたかも中教審答申がその目的にてらしてモデルとした「明治中期の教育再改革」の構想と、その具体的な展開・既決をとらえることが、相当に大きな有効性をもつと考えられる。もちろん、明治憲法体制として表現される天皇制国家と、高度に発展した独占資本主義国でありながら決定的な対米軍事従属体制にある現在の日本とでは、一口に帝国主義・軍国主義の確立あるいは復活といっても、大きな条件の違いがある。この点を前提としての歴史的考察である。-略-」
京大の新設など。下「」引用。
「大学では一八九七(明治三○)年六月勅令第二百八号による京都帝国大学の新設、教員養成に関しては、同年十月勅令第三百四十六号をもってする師範学校令の排しと師範教育令の制定、私立学校に関しては一八九九年八月の私立学校令(勅令第三百五十九号)制定、小学校では一九○○(明治三三)年八月の小学校令改正(勅令第三百四十四号)、一九○三年の再改正(勅令第七十四号)による教科書国定化など、一連の学校制度整備の法令の制定、改正が行われた。」
日露戦争時の就学率と出席率。下「」引用。
「長野県においてはね日露戦時下における就学率の減少という結果となってあらわれたのであった。日露戦時下の就学率は、全国的にはなお上昇傾向をしめしている。しかし、全国的な就学率の上昇は、戦時体制下における権力主導の就学督励による表面的現象であったことは、全国平均で、就学率の数字の増大とは逆に就学児童の出席率が異常に低率であり、しかも戦時下にはその出席率が低下傾向をしめしていることからも知ることができる。-略-」
出席率は75%前後。
「軍隊主義教育」と教育本来の目的。木下尚江の批判。下「」引用。
「「軍隊主義」なるものが教育本来の目的と絶対にあいいれることができない思想であることを力説している。-略-この「軍隊主義教育」の目的とするところは何か。木下は主張している。「彼等は常に外国との戦争を予想し、又た之を夢望す、彼等は戦争を以て人生の最大事業にして、又た最高事業となす、特に日本が、日露戦争に依りて世界の驚愕を買ひ得たりとの自信は、日本の光栄は一に懸りて『戦争』に在りと盲信するに至らしめき、彼等が常義常道を忘れて、人生の奥義開発の学校を以て、物食ふ剣銃の製作場となさんと欲して怪まざる所以のもの、実にこゝに在り」と。「軍隊主義教育」の目的が、日露戦争を画期とする日本軍国主義の確立にあることを、木下は的確にも指摘しているのである。」
矛盾をおさえつづけた……。下「」引用。
「日露戦争でともかくも戦勝国となった日本は、帝国主義列強の一員として、世界的な帝国主義争覇戦に、みずから身を投じていった。しかも、最初の本格的な帝国主義戦争下で、さまざまな新しい矛盾の展開、もしくは在来する矛盾の深化と様相の変化に直面しなければならなかった日本資本主義とその上部構造である天皇制国家は、このさまざまな矛盾を強引におさえつつ、日露戦争体制の延長と恒久化のうえにたって、支配体制の帝国主義的編成がえを強行しなければならなかった。-略-」
「2 義務教育延長にともなう諸問題と財政」下「」引用。
「一九○七年三月二十一日、勅令第五十二号をもって小学校令が改正され、義務教育である尋常科は六年に延長され、尋常科六年卒業をもって一方では中学校・高等女学校・甲種実業学校に直結し、他方では従来の高等科三・四年を一・二年とする高等科二年の制度が併存することになった。同年三月二十五日、文部省は、小学校令および同施行規則の改正について、同省訓令第一号をもって、次のように解説した。」
大学教育=特権集団の養成の場。下「」引用。
「大学の門徒の拡大は、天皇制官僚という特権集団の養成の場である帝国大学の権威の低下をもたらし、この特権の城塞をブルジョアジーに開放することによって、天皇制官僚機構のブルジョアジーに対する独自性確保の有力なよりどころのひとつが失われることになる。-略-」
天皇の肩入れ。下「」引用。
「一八八○年代後半以後、対外戦備の充実拡大に力をそそぎはじめた政府は、いわゆる松方財政の名でよばれる大増税政策のもとに軍備拡張を強行してきたが、帝国議会開設以後は、とくに「天皇の軍隊」に対する天皇の財政的肩入れを武器として、議会に対抗してきた。一八九三(明治二六)年の第四議会における軍事予算大削減に対し、六年間毎年三○万円の内廷費を軍備にさくから議会も協力せよという勅令をもって議会の軍事予算削減権を凍結してしまった事件は、その好例であった。-略-」
 index
index
 index
index
 もくじ
もくじ
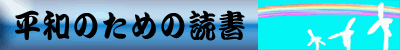


大江志乃夫・著/新日本出版社1974年
軍国主義も、時代によって変化していったようである……。

明治の「教育再改革」と昭和の軍国主義復活。下「」引用。
「「明治中期の教育再改革」は、「緊迫した内外の情勢」、すなわち世界史的段階としての帝国主義段階への移行と、それにともなう中国の植民地的分割から再分割への動きを中心とする東アジア情勢の緊張、そして、これにともなう「富国強兵の国策」、すなちわ日本資本主義の確立とその帝国主義への転化、強大な帝国主義軍事力の建設と軍国主義支配体制への確立にむけて、これらの「国策に協力する」学校教育体制の改編確立であった。-略-いいかえれば、自己の労働をひたすら国家と独占資本への奉仕としてささげ、いっさいの権利を放棄してもっぱら支配体制に対する義務と責任をのみ負い、積極的に軍服を着て銃をとり戦場におもむく労働者・市民・兵士を「育成」することをねらいとしたものである。それは、明治の「富国強兵」に現在の日本独占資本の経済大国主義と日米軍事体制下の四次防を対応させたうえ、日本の帝国主義・軍国主義復活過程の現段階に即応させた教育制度の改編構想であるといえよう。」
中教審のモデルとした明治。下「」引用。
「このうよな中教審の教育改革構想の正確とその帰着するものを具体的にとらえるためには、あたかも中教審答申がその目的にてらしてモデルとした「明治中期の教育再改革」の構想と、その具体的な展開・既決をとらえることが、相当に大きな有効性をもつと考えられる。もちろん、明治憲法体制として表現される天皇制国家と、高度に発展した独占資本主義国でありながら決定的な対米軍事従属体制にある現在の日本とでは、一口に帝国主義・軍国主義の確立あるいは復活といっても、大きな条件の違いがある。この点を前提としての歴史的考察である。-略-」
京大の新設など。下「」引用。
「大学では一八九七(明治三○)年六月勅令第二百八号による京都帝国大学の新設、教員養成に関しては、同年十月勅令第三百四十六号をもってする師範学校令の排しと師範教育令の制定、私立学校に関しては一八九九年八月の私立学校令(勅令第三百五十九号)制定、小学校では一九○○(明治三三)年八月の小学校令改正(勅令第三百四十四号)、一九○三年の再改正(勅令第七十四号)による教科書国定化など、一連の学校制度整備の法令の制定、改正が行われた。」
日露戦争時の就学率と出席率。下「」引用。
「長野県においてはね日露戦時下における就学率の減少という結果となってあらわれたのであった。日露戦時下の就学率は、全国的にはなお上昇傾向をしめしている。しかし、全国的な就学率の上昇は、戦時体制下における権力主導の就学督励による表面的現象であったことは、全国平均で、就学率の数字の増大とは逆に就学児童の出席率が異常に低率であり、しかも戦時下にはその出席率が低下傾向をしめしていることからも知ることができる。-略-」
出席率は75%前後。
「軍隊主義教育」と教育本来の目的。木下尚江の批判。下「」引用。
「「軍隊主義」なるものが教育本来の目的と絶対にあいいれることができない思想であることを力説している。-略-この「軍隊主義教育」の目的とするところは何か。木下は主張している。「彼等は常に外国との戦争を予想し、又た之を夢望す、彼等は戦争を以て人生の最大事業にして、又た最高事業となす、特に日本が、日露戦争に依りて世界の驚愕を買ひ得たりとの自信は、日本の光栄は一に懸りて『戦争』に在りと盲信するに至らしめき、彼等が常義常道を忘れて、人生の奥義開発の学校を以て、物食ふ剣銃の製作場となさんと欲して怪まざる所以のもの、実にこゝに在り」と。「軍隊主義教育」の目的が、日露戦争を画期とする日本軍国主義の確立にあることを、木下は的確にも指摘しているのである。」
矛盾をおさえつづけた……。下「」引用。
「日露戦争でともかくも戦勝国となった日本は、帝国主義列強の一員として、世界的な帝国主義争覇戦に、みずから身を投じていった。しかも、最初の本格的な帝国主義戦争下で、さまざまな新しい矛盾の展開、もしくは在来する矛盾の深化と様相の変化に直面しなければならなかった日本資本主義とその上部構造である天皇制国家は、このさまざまな矛盾を強引におさえつつ、日露戦争体制の延長と恒久化のうえにたって、支配体制の帝国主義的編成がえを強行しなければならなかった。-略-」
「2 義務教育延長にともなう諸問題と財政」下「」引用。
「一九○七年三月二十一日、勅令第五十二号をもって小学校令が改正され、義務教育である尋常科は六年に延長され、尋常科六年卒業をもって一方では中学校・高等女学校・甲種実業学校に直結し、他方では従来の高等科三・四年を一・二年とする高等科二年の制度が併存することになった。同年三月二十五日、文部省は、小学校令および同施行規則の改正について、同省訓令第一号をもって、次のように解説した。」
大学教育=特権集団の養成の場。下「」引用。
「大学の門徒の拡大は、天皇制官僚という特権集団の養成の場である帝国大学の権威の低下をもたらし、この特権の城塞をブルジョアジーに開放することによって、天皇制官僚機構のブルジョアジーに対する独自性確保の有力なよりどころのひとつが失われることになる。-略-」
天皇の肩入れ。下「」引用。
「一八八○年代後半以後、対外戦備の充実拡大に力をそそぎはじめた政府は、いわゆる松方財政の名でよばれる大増税政策のもとに軍備拡張を強行してきたが、帝国議会開設以後は、とくに「天皇の軍隊」に対する天皇の財政的肩入れを武器として、議会に対抗してきた。一八九三(明治二六)年の第四議会における軍事予算大削減に対し、六年間毎年三○万円の内廷費を軍備にさくから議会も協力せよという勅令をもって議会の軍事予算削減権を凍結してしまった事件は、その好例であった。-略-」
 index
index index
index もくじ
もくじ