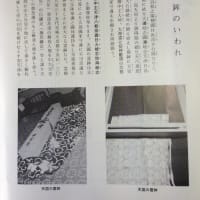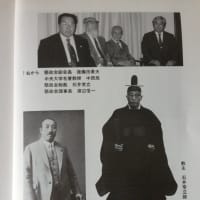東京大学名誉教授・小堀桂一郎さんが言う。
◎戦後70年に思う 「終戦の詔書」に残る深い傷痕
『昭和天皇陛下がラジオを通じて日本国民に直接語りかけられた終戦の詔勅の原文は、「義命の存することろ 耐えがたきを耐え 忍びがたきを忍び」であったが、閣議で「時運の趨むくところ 〜 〜 」へと改変されたという。当時の閣僚の見識の無さ、日和見主義、行き当たりばったり、長いものに巻かれろ主義に暗澹とする。』
先帝陛下の「終戦の詔書」を奉戴してより満70年の記念日が近づいて来る。この詔書を斯かる題で呼ぶのは〈吾等は…日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり〉とのポツダム宣言の冒頭句を受けた形で陛下が戦争を終結する手続に着手せよ、との勅命を政府に下し給うたと見る故に名づけた事である。
◎国民の耳に達した玉音放送
元来詔勅とは〈詔(みことのり)を承けては必ず謹しめ〉と上宮太子の仰せられた上古の昔から文字通りに唯奉戴服膺(ふくよう)すべきものであつて、その内容を批判的に論(あげつら)つたり字句の由来を穿鑿(せんさく)したりすべきものではなかつた。然(しか)し近代になると、五箇条の御誓文、軍人勅諭、教育勅語等を日本精神史上の重要文献と見て、その成立の由来や制定・発布の経過等に文献学的分析を施し、聖旨が歴史の展開に齎(もたら)した意味を考究し評価を下すといふ作業が、謹直な意図に発する史料研究の一種として承認される様になつた。畏れ多い話ではあるがこれも時代の要請の必然といふ事であらう。
さういふわけで、例へば昭和16年12月8日の米英両国に対する宣戦の詔書にも当時の指導的言論人であつた徳富蘇峰により『宣戦の大詔』と題する「謹解」の一書が直ちに著述・刊行されもした。
昭和20年8月14日付で戦争終結を御下命になつた詔書についても同様の「謹解」の役割を果すべき識者による解説への要望は夙(つと)に存したであらう。殊にこの場合、詔書の本文は8月15日正午の所謂(いはゆる)玉音放送を通じて一応全国民の耳に達してはゐたが、録音や再生装置の不備もあつて、陛下のお聲(こえ)だけは確かに拝聴したが、内容はどうもよく理解できなかつたといふ人々が多かつたからである。
「終戦の詔書」の解題役として逸速(いちはや)く名乗を挙げたのは鈴木貫太郎内閣で内閣書記官長を務めた迫水久常氏である。迫水氏は詔勅の起草には慥(たし)かに一役を買つた人であるが、自負心の強い秀才官僚の型に属してゐた。本来ならば軽々しく口にすべきではない、重大な詔勅の成立過程に関して、自分の知り得た裏話を公けの場で語る事についての抑制のたしなみを全く持ち合せてゐなかつた。
◎最大の眼目は何だったか
詔勅の起草時に実はその第一稿を執筆した漢学者の川田瑞穂氏、詔勅の文体上の彫琢・完成に重大な役割を果した安岡正篤氏の様に迫水氏の誇らしげな内情の打ち明け話を不謹慎と感じ自らは固く沈黙を守つた人々も周囲には居た。然しともかくも迫水氏の積極的姿勢のおかげで、天皇御親(おんみづか)らのお聲を以て全国に放送された詔勅といへども、その本文は何人かの臣下の者が知恵を寄せ集めて作成した一篇の合作文書であるといふ内実を国民は知らされたわけである。
「終戦の詔書」の文章上の完成度について最も重要な寄与をなしたのは、当時大東亜省の顧問として首相官邸に出入してゐた安岡氏である。安岡氏は詔書の成立に自分が関与した度合については、既に世間に種々取沙汰される様になつてからも長く沈黙を守つてゐたが、昭和37年になつて初めて公開の席上で語る事をした。
安岡氏によれば、この詔書全文中の最大の山場はその第3段落に当る部分で、天皇はそこで、大東亜戦争の名分に共鳴し東亜の解放のために共に戦つてくれたアジアの諸盟邦に対し、業半ばにしての帝国の挫折につき深い遺憾の意を表され、次いでこの戦争で非命に斃(たふ)れた多数の殃死(あうし)者とその遺族に向けての深甚の哀悼の言葉を贈られ、又戦禍により家業を失つた者の厚生について懇ろな御軫念(しんねん)の程を披瀝(ひれき)される。次いで戦後復興の事業の前途多難を慮(おもんばか)つて激励の辞を述べられた後、この詔書の最大の眼目をなすべきお言葉が来る。
◎「義命」知らぬ戦後政治
安岡氏の胸裡(きょうり)に生じた文案は〈爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ義命ノ存スル所堪ヘ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ万世ノ為ニ太平ヲ開カント欲ス〉といふ至高の格調を具へた一節だつた。
ところがこの詔勅文案が8月14日午後、詔書正文を決定する最後の閣議にかけられた段階で〈義命〉といふのは辞書に載つてゐない難しい語だとの苦情が出て削除され、代つて現行本文の如く〈朕ハ時運ノ趨(おもむ)ク所…〉といふ表現に替へられ、〈万世の為に太平を開く〉といふ究極の字眼はその大前提を失つて宙に浮いてしまつた。
事情を知つた安岡氏は〈学問のない人にはかなひません〉と長大息したが後の祭だつた。以上の経緯は最近安岡氏の門弟筋の関西師友協会が編纂した『安岡正篤と終戦の詔勅』(PHP研究所刊)に詳しい記述があるので正確な理解を期したい向は参照されたい。いづれにせよ、この字句の改変によつて先哲の苦心の修辞は台無しになつてしまひ、戦後の政治は〈義命ノ存スル所〉には関心を向けること無く専ら〈時運ノ趨ク所〉に追随して流されるがままになつてしまつた。安岡氏の嗟嘆(さたん)は筆者も心中深く共有するところである。