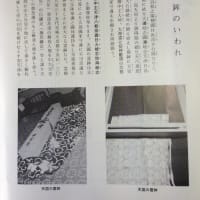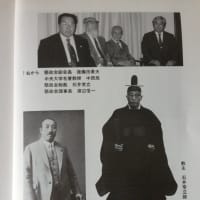◎納豆とナットウキナーゼの違いについて教えて下さい。
納豆とは、煮た大豆に納豆菌をふりかけて発酵させることにより作られる食品であり、ナットウキナーゼとはその発酵過程において、納豆菌が生産する酵素です。
◎ナットウキナーゼの効果・効用についてわかり易く教えて下さい。
ナットウキナーゼは血栓を直接溶かす働きのほか、体内が持つプラスミンやウロキナーゼという線溶酵素を活性化することもわかっています。また、体内のPAI-1という物質を減らすことも確認されています。
◎納豆をどの位の量を食べればナットウキナーゼと同じ効果を得られることができますか?
当協会が推奨するナットウキナーゼ摂取量は1日2000FUです。
納豆には1パック50gとして、平均1500FUのナットウキナーゼ活性がございます。そのため、単純に計算すると1~2パック程度の摂取を必要としています。ただし、納豆によってはナットウキナーゼ活性の少ないものや1パックの内容量が少ないものがあったり、賞味期限間近のものは活性が少なくなります。また、ナットウキナーゼはサプリメントとしてソフトカプセル状で摂取される場合が多いですが、その場合は胃酸の影響を受けにくくなります。一方、納豆の場合は胃酸により影響を受けます。
◎血栓症とは?
血栓症とは、血管が血栓で詰まることにより臓器に血流が流れなくなることを言います。
その結果、末梢臓器の細胞が死ぬことを梗塞と言い、血栓が詰まる場所により、脳梗塞や心筋梗塞と分類されます。飛行機に乗っている際、狭い機内で長時間同じ姿勢でいることによって起こる深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)も血栓症の一つです。
◎実は身近な血栓症!
この血栓症、35歳以上の方は特に注意が必要です。平成20年患者調査(厚生労働省)によると、35歳以上で発症者数が急増しています。
また、現在、日本人の死因の第1位はがん(30.1%)ですが、第2位は心筋梗塞などの心疾患(15.8%)、第3位は脳梗塞などの脳血管疾患(10.7%)になっています。(平成21年厚生労働省 人口動態統計より)つまり、日本人の約3割が 「血管がつまる・破裂する」ことにより死亡しているのです。
◎常日頃からの予防が必要です。
食生活や生活習慣の変化により、現代人は高齢者に限らず若年層でも血液成分のバランスが崩れ、コレステロールや中性脂肪値の多いドロドロ血が増えています。不健康な血液では、血栓ができやすく、血栓を溶かす“線溶系”の働きも弱まります。つまり、現代人は血栓ができやすく、しかもできてしまった血栓が溶けにくい体質になっているのです。
心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症は、血液中にできた血栓が血管を詰まらせることにより引きおこされる病気です。血栓症は、多くの場合、自覚症状の無いまま突然発症し、発症にともない症状は急速に悪化。たとえ命を取り留めたとしても再発の恐れや重大な障害をもたらします。
ある日突然襲ってくる血栓症に対し、何よりも大切なのが「予防」です。血栓を作らず、できてしまった血栓を溶かす体質になるためには、運動や食事による生活習慣の改善が必要です。
◎血栓ができやすい血管とは?
正常な血管では、血管内で血液が固まらず、ケガをして血液が血管の外に出ると固まります。血栓ができやすい血管は、この働きに異常が出ており、19世紀の病理学者Virchow(ウィルヒョウ)によると、それには、「血液」、「血管」、「血流」の3つの因子が関わると提唱されています
◎血液の変化
よく「血液サラサラ」という言葉が使われますが、その逆の「ドロドロ」とはどのような状態なのでしょうか?血栓症のリスクという観点からは、血小板や凝固系が活性化されやすいこと、線溶系に異常をきたしている可能性が考えられます。
血小板とは出血した際に止血のために働く成分です。つまり、血小板が活性化されると血液が凝固しやすくなりますが、例えば精神的なストレスが大きい場合は、その傾向が強くなります。
また、そもそも血栓とは、フィブリンというタンパク質の糸のようなもので構成されていますが、血液の中では、最終的にフィブリンが生成される前段階の成分であるいくつもの凝固因子が存在しています。凝固系とは、この凝固因子の集団であり、この内フィブリノーゲンが増えることは血栓症の大きなリスクとなります。
逆に、血栓を溶解する線溶因子の集団は線溶系と呼ばれます。線溶系は、プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1型(PAI-1)という阻害因子が増加すると、その働きが弱まり、血液の中で血栓は溶けにくい状態になります。
◎血管の変化
血管内で血液が固まりにくい状態を保つために働くのが血管内皮(血管の最も内側の層)細胞です。そのため、この細胞が炎症を起こしたり動脈硬化により障害されると血液が固まりやすくなります。
動脈硬化の内、動脈の内膜にコレステロールなどの脂肪からなるドロドロの粥状物質がたまってプラークができ、次第に肥厚することで動脈の内腔を狭めるタイプでは、プラークが破綻した際に凝固系が一気に活性化されます。これは、急性心筋梗塞や梗塞範囲の大きい脳梗塞を引き起こします。
◎血流の変化
血流が速いと赤血球はバラバラになり血液粘性は低下し、遅いと赤血球同士が凝集して粘性が増します。つまり、血流が遅いと血栓症を起こしやすくなりますが、この流速の変化はどうやって起こるのでしょうか?
血液が流れる速度は、心臓が血液を送り出す力や細い動脈で生じる抵抗によって変わりますが、静脈ではふくらはぎの筋肉が収縮することや呼吸運動による力も大きく関わっています。そのため、例えば、狭い飛行機の座席で長時間動かないことや、被災時に狭い乗用車の中で眠ることで、静脈に血栓が生じることもあります。
◎納豆のネバネバに含まれるナットウキナーゼ
長年、わが国の健康を支えてきた伝統食品である「納豆」。この納豆のネバネバ部分に含まれるタンパク質分解酵素がナットウキナーゼです。
納豆は、煮大豆を納豆菌が発酵させることでできる食品ですが、この発酵過程でナットウキナーゼをはじめとする多様な栄養素が生成されます。1925年、北海道帝国大学の大島先生によりその精製および性質について報告がなされており、その後様々な研究報告がなされ、1980年代にフィブリン(血栓の素となるタンパク質)を分解(溶解)する酵素が「ナットウキナーゼ」として命名されました。
◎ナットウキナーゼのはたらき
ナットウキナーゼには、血栓の主成分であるフィブリンに直接働きかけ分解(溶解)する作用、身体の中の血栓溶解酵素であるウロキナーゼの前駆体プロウロキナーゼを活性化する作用、さらに血栓溶解酵素プラスミンを作り出す組織プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)量を増大させる作用があります。
さらに、最近の研究で、ナットウキナーゼには血栓を溶けにくくする血栓溶解阻害物質PAI-1を分解する作用、オイグロブリン溶解時間の短縮作用があり、血栓溶解活性の増強作用があることがわかってきました。
このように血栓を色んな角度から溶解するのがナットウキナーゼの特長です。そのため、よく消費者の方からナットウキナーゼを摂取し過ぎると血が止まらなくなるのでは?、という質問がありますが、ナットウキナーゼは各種の安全性試験をクリアしていますので、安心してお召し上がりいただけます。
◎血液凝固を促進するビタミンK2を除去
食品としての納豆には、血栓溶解を促す成分「ナットウキナーゼ」が含まれている反面、血液凝固を促進する「ビタミンK2」も含まれています。そのため、ビタミンK2の除去されたナットウキナーゼの方が、納豆に比べ優れた血栓溶解作用を持っています。
また、血栓症患者などに処方される血液を固まりにくくする医薬品、「ワルファリン(商品名:ワーファリン等)」を服用されている方は、「ビタミンK2の拮抗作用」により効果が減弱されるため、納豆などのビタミンK2を多く含む食品の摂取は医師により制限されています。そのため、折角の納豆の血栓溶解作用を活かすことが出来ませんでした。しかし、ナットウキナーゼならその様な方でも安心して摂取することが可能です。