男の『超』一流品図鑑 (第2回)
1970年代から80年代にかけて中高校生の間で巻き起こった世界中からのラジオ放送を受信するBCLブーム。10kHz直読ダイヤルを搭載したスカイセンサー5900は、まだ手探り受信が主流だった全世界のラジオ受信マニアに衝撃をもたらし登場した。
BCLブームの火付け役となり100万台以上を販売、大ヒットしたスカイセンサー5800や、ジャイロアンテナ搭載でデザイン性にも優れたクーガ115で多くの中高校生は海外からの短波放送受信に熱中していた。

1975年(昭和50年)10月、ソニーはスカイセンサー5800の後継機としてスカイセンサー5900 (ICF-5900)を発表した。それまでのラジオは、シングルスーパであったため15MHz以上のハイバンドでは感度が低く、周波数表示も大雑把でズレが大きく、受信したい放送局の周波数を手探りで選局しなければならないため実用上不便だった。
そこでスカイセンサー5900は、短波帯で高感度受信が可能なダブルスーパーヘテロダイン(1stIF:10.7MHz、2ndIF:455kHz)の回路構成を採用、さらに250kHzステップのクリスタルマーカーと±130kHz可変のスプレッドダイアルの組み合わせにより、受信周波数を10kHzの単位まで指定することのできる画期的な機能をもち、27,800円の価格で発売された。クーガ115の定価が26,900円だったことを考えると、ユーザーにとってどれほど大きなインパクトであったか推し量ることは容易である。

かってのスカイセンサー・シリーズのアイデンティティであるブラックからメタリック・ブラウンのボディカラーへ変更し、正面中央に位置するスプレッド・ダイヤル、右上のメイン・チューニングダイヤル、その他パーツのレイアウトとデザインがラジオ受信マニアの心をくすぐる絶妙なバランスだ。
ちなみにスカイセンサー5900には前期型/後期型の2種類のモデルがある。前期モデルはサブダイヤルの目盛りが1パターンで照明がなく、後期モデルはサブダイヤル目盛が4パターンと照明が付く。

前期型(左)/後期型(右)のサブダイヤル
デジタル周波数表示のラジオなんて夢の時代にあって、マーカーとスプレッドダイヤルで周波数を正確に読みとり、待ち受け受信のできる画期的なラジオであった。
スプレッドダイヤルが「0」になる位置でクリスタルマーカーのスイッチをONにすると、250KHzごとにピーという発信音が出るので、チューニングメーターの値が10になり、発振音が一瞬消える位置(ゼロビート)にメインダイヤルを調整すると、その前後125KHzの範囲が10Hz単位で周波数設定ができる仕組みだ。

このように選局性能の向上は特筆に値するが、各バンドともメインダイヤルの目盛りずれがかなりあり、サブダイヤルでチューニングを行なうと可変端が1stIFフィルタの帯域端になるため、+方向の感度低下が見うけられた。
また周波数安定度は従来のラジオと変わらないため、ある時間毎に周波数の微調整をする必要があった。しかしこれらの問題は、民生用短波ラジオとして安価に提供するためには仕方なかったと考えられる。それどころか、この価格帯で実用的な短波ラジオを提供できる回路方式を考案したソニー設計陣の功績の方が遙かに大きい。
周波数安定度に優れ、デジタル表示も可能なPLLシンセサイザ技術が登場したためスプレッドダイヤルを使った「直読ダイヤル」の技術発展は無かったが、30年を経た今でもオークションでは2万円以上の高値で取引されている。それほど当時のBCL少年にとっては熱い思いを注いだ、あるいは憧れのラジオであり続けた名機だと言える。
スカイセンサー5900/ICF-5900は、元ラジオ少年にとって、30年前の夢を今に育む、時代を超えた「男の『超』一流品」なのである。
1970年代から80年代にかけて中高校生の間で巻き起こった世界中からのラジオ放送を受信するBCLブーム。10kHz直読ダイヤルを搭載したスカイセンサー5900は、まだ手探り受信が主流だった全世界のラジオ受信マニアに衝撃をもたらし登場した。
BCLブームの火付け役となり100万台以上を販売、大ヒットしたスカイセンサー5800や、ジャイロアンテナ搭載でデザイン性にも優れたクーガ115で多くの中高校生は海外からの短波放送受信に熱中していた。

1975年(昭和50年)10月、ソニーはスカイセンサー5800の後継機としてスカイセンサー5900 (ICF-5900)を発表した。それまでのラジオは、シングルスーパであったため15MHz以上のハイバンドでは感度が低く、周波数表示も大雑把でズレが大きく、受信したい放送局の周波数を手探りで選局しなければならないため実用上不便だった。
そこでスカイセンサー5900は、短波帯で高感度受信が可能なダブルスーパーヘテロダイン(1stIF:10.7MHz、2ndIF:455kHz)の回路構成を採用、さらに250kHzステップのクリスタルマーカーと±130kHz可変のスプレッドダイアルの組み合わせにより、受信周波数を10kHzの単位まで指定することのできる画期的な機能をもち、27,800円の価格で発売された。クーガ115の定価が26,900円だったことを考えると、ユーザーにとってどれほど大きなインパクトであったか推し量ることは容易である。

かってのスカイセンサー・シリーズのアイデンティティであるブラックからメタリック・ブラウンのボディカラーへ変更し、正面中央に位置するスプレッド・ダイヤル、右上のメイン・チューニングダイヤル、その他パーツのレイアウトとデザインがラジオ受信マニアの心をくすぐる絶妙なバランスだ。
ちなみにスカイセンサー5900には前期型/後期型の2種類のモデルがある。前期モデルはサブダイヤルの目盛りが1パターンで照明がなく、後期モデルはサブダイヤル目盛が4パターンと照明が付く。

前期型(左)/後期型(右)のサブダイヤル
デジタル周波数表示のラジオなんて夢の時代にあって、マーカーとスプレッドダイヤルで周波数を正確に読みとり、待ち受け受信のできる画期的なラジオであった。
スプレッドダイヤルが「0」になる位置でクリスタルマーカーのスイッチをONにすると、250KHzごとにピーという発信音が出るので、チューニングメーターの値が10になり、発振音が一瞬消える位置(ゼロビート)にメインダイヤルを調整すると、その前後125KHzの範囲が10Hz単位で周波数設定ができる仕組みだ。

このように選局性能の向上は特筆に値するが、各バンドともメインダイヤルの目盛りずれがかなりあり、サブダイヤルでチューニングを行なうと可変端が1stIFフィルタの帯域端になるため、+方向の感度低下が見うけられた。
また周波数安定度は従来のラジオと変わらないため、ある時間毎に周波数の微調整をする必要があった。しかしこれらの問題は、民生用短波ラジオとして安価に提供するためには仕方なかったと考えられる。それどころか、この価格帯で実用的な短波ラジオを提供できる回路方式を考案したソニー設計陣の功績の方が遙かに大きい。
周波数安定度に優れ、デジタル表示も可能なPLLシンセサイザ技術が登場したためスプレッドダイヤルを使った「直読ダイヤル」の技術発展は無かったが、30年を経た今でもオークションでは2万円以上の高値で取引されている。それほど当時のBCL少年にとっては熱い思いを注いだ、あるいは憧れのラジオであり続けた名機だと言える。
スカイセンサー5900/ICF-5900は、元ラジオ少年にとって、30年前の夢を今に育む、時代を超えた「男の『超』一流品」なのである。










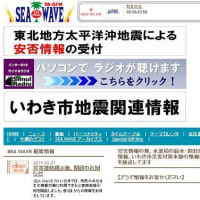









その 1年後に こいつ(5900) は現れた!
あまりの ショックに 僕は BCL をやめてしまいました。
それからは ひたすら ギター少年の道を 歩みました。
30年後、この憎き 5900 を手に入れましたが、、、
やはり、5800 の方が好きですね。
5900 嫌い ・゜゜・(>_<)・゜゜・
でもギターに転向されて正解♪
先週の土曜、UZさんのCDを約500万のYAMAHA C-Ⅰ+自作真空管アンプ+JBLのシステムで聞かせてもらいました。オーディオシステムのオーナー曰く、「これだけの作品を打ち込みで作られたのなら、ギターをもう少し前面に出したミキシングの方がいいのに・・・。控えめな人柄なんでしょうね」と感心しておられましたぜ。