『日本人の英語』ピーターセンの新著を紐解いて: シリーズ 日本人の英語
マーク・ピーターセン著、『日本人の英語はなぜ間違うのか』が集英社発行されました。「英語本」というと、タイトルだけで、読まれたり、嫌われたりするようで、一見この本もそういうふうに見なされるのではないかと思います。
しかし、私はピーターセンの言うことはよく聞いた方がよいですよ、と周囲の方に申し上げています。彼だけではなく、ミントン、バーナード、トム・ガリーたち、日本で英語を教えている人たちの意見には、耳を傾けるべきだと思います。英語を教えていると言っても、母国語なら自分でも教えられるさという気分のインストラクターではなく、実際に母国語を、日本語を母国語とする人にぶつけて生じるさまざまな問題を考えている人たちのことです。
しかし、どうも、現場の先生であれ、文部省の役人や政治家など予算を決めるひとたちであれ、ピーターセンたちの述べている意見には関心がないように思えるのです。「意見を聞く」とういのは、「そうだ、そうだ」と相槌を打つことではありません。意見を述べる人がなぜそういうのか吟味し、現実の問題を解決するために役に立てるということです。
先日、この本を買い、まだ最初の方しか読んでいません。(ブログもお休みする忙しさで、少数のブログの読者の方には失礼をしました。) しかし、最初の章で提起されたいくつかの問題は、曖昧さを含まない明確な問題群です。しかも、私には致命的に重要な事柄だと思います。
ピーターセンは、ある中学校の英語の教科書の一部を取り上げています。ここで、再引用させてもらいましょう。p.10
Many years ago, there were wonderful elephants at the Ueno Zoo. The elephants were John, Tonkey, and Wanly. They could do tricks. Visitors to the zoo lived to see their tricks.
Japan was at war then. Little by little the situation was getting worse. Bombs were dropped on Tokyo every day.
If bombs hit the zoo, dangerous animals will get away and harm the people of Tokyo. So the Army ordered the zoo to kill the dangerous animals such as lions, tigers, and bears.
以下は、ピーターセンの書き換え例です(この書き換え例の前に、中間段階の書き換え例があります。(p.12)
Many years ago, there were three wonderful elephants at the Ueno Zoo: John, Tonky, and Wanly. They could do tricks, and visitors to the zoo loved to watch them.
Japan was at war then, and little by little the situation was getting worse. Bombs were dropped on Tokyo every day.
If bombs hit the zoo, dangerous animals might have got away and hurt people, so the Army ordered the zoo to kill all its dangerous animals, such as lions, tigers, and bears. (p.13 - p.14)
いくつか大きな問題が扱われているのですが、ここでは以下の部分に注目します。
原文:
If bombs hit the zoo, dangerous animals will get away and harm the people of Tokyo.
書き換えられた文:
If bombs hit the zoo, dangerous animals might have got away and hurt people,
この箇所を訳せば、「もし爆弾が動物園を直撃したら、危険な動物が逃げ出し、東京の人々を傷つけたことでしょう。」というところでしょう。実際は、ここでは典型的な反実仮定法ではありません。現実性の乏しい推測、という方がよいのでしょう。
が、教科書のように書き換えてしまう背景には、would have / might haveのような仮定法的な表現が中学段階で出てこないので、過去の話なのに、むりやりwillを使ってしまったという事情がありそうです。(日本語では直説法と仮定法の区別がない、ということは、英語を教える場合、強く意識する必要があります。)
文部省が示す指導の指針に中学段階では仮定法を扱わない、という規則があるから仮定法を使わず書く、という杓子定規な発想があるのでしょうか。たしかに、小学校の国語教育では、各学年ごとに習得すべき漢字は決まっているので、その前の学年で、習っていない漢字を使う漢字熟語ができたら、たとえば、「じゅく語」というような「分かち書き」にしなければならないことになっています。それと同じように、英語でも、中学では習わないことになっているから、いかに実際の英語とは違っていても、その表現を使わないということがあるのではないかと推察されます。
しかし、しかしです。英語という教科は国語とは性質が違うのです。国語なら、常に無数の経験にさらされるるわけですから、ほどなく、「じゅく語」は脳裏から消え、「熟語」が定着するでしょう。しかし、英語は、インプットされる情報量が国語より圧倒的に少ないのですから、最初に習った形が一生にわたって定着してしまう可能性が極めて高いのです。実際に、英語学校や玉大の「和文英訳添削」で私が日々経験していることでもあります。
英語の先生、またはディレクターの地位にある人、教科書の編纂者はそのことに気がつかないのでしょうか。もし指導要領を厳守するというなら、仮定法の出ないような物語にすべきです。そんなに難しいことではありません。話がつまらなくなっても、一生にわたって間違って英語を定着させてしまうよりずっと罪に軽いことです。それとも、どうしても平和教育を英語の時間にしたいとでも言うのでしょうか。
気がつかなかったのか、故意なのか分かりませんが、なぜそうなるのか、と考えてみると、深い問題が潜んでいることがほの見えてきます。
つまり、上記の人たちにとっては、外国語は存在しないのです。いや、これは彼らだけではなく日本人の大衆心理に潜んでいる気分だと思います。外国語はその国の人たちが使っているものであって、我々がどうこうできるものではありません。日本人が日本人の都合で、どうこうできると思い込むほどばかばかしいことはありません。
さらに推測を推し進めましょう。たしかに「大衆心理」などという粗雑な言い方はしない方がよいのかもしれませんが、どうも、日本人には、他者というものの怖さが分かっていない...、そこまで言っては言い過ぎでしたら、他者の存在に対する意識が希薄なのではないか、と思えてきます。その意識が、英語教育にまつわるさまざな「議論」だけではなく、ここ百年の対外国の諸問題の根底に横たわっているように私には思えるのです。皆さんはどうお考えでしょう。
■■










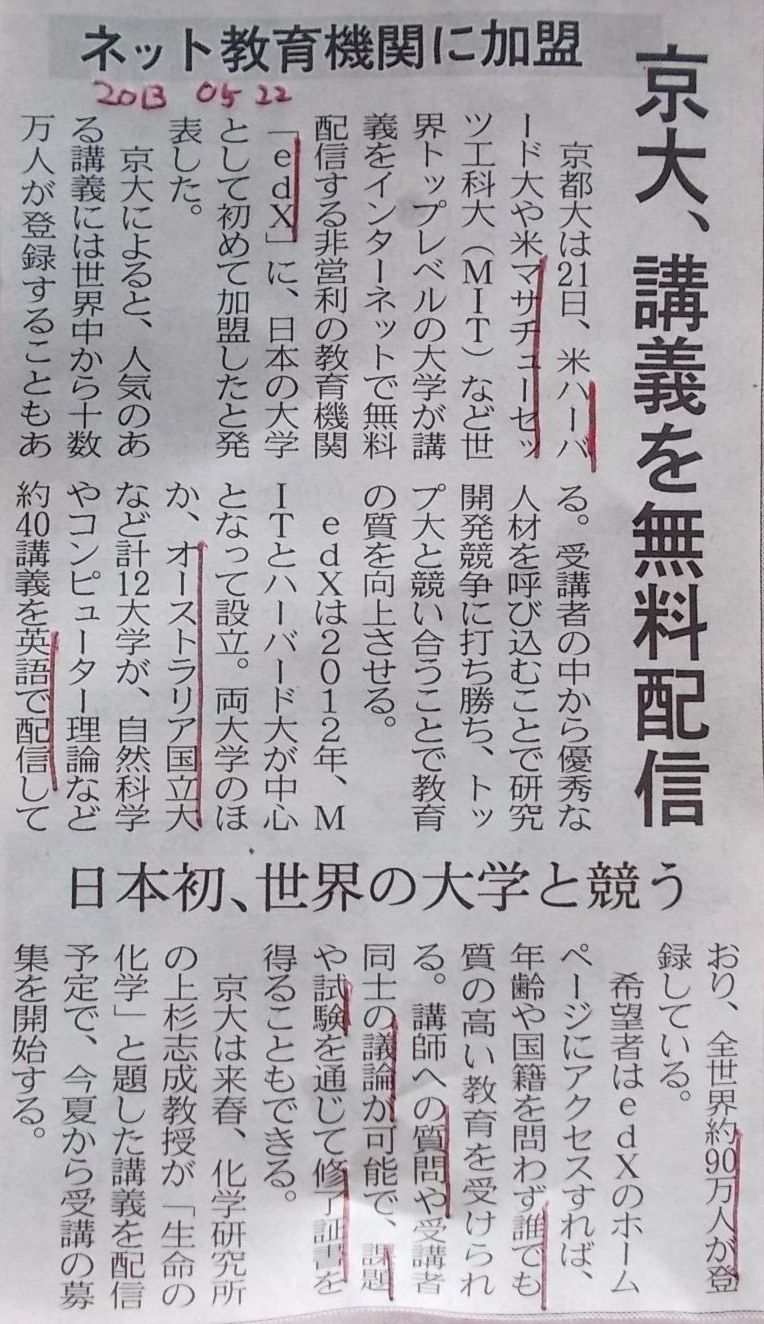 しれません。「日本人の英語もここまできたな」、とか「日本人離れした英語」という言葉が聞こえてきそうです。
しれません。「日本人の英語もここまできたな」、とか「日本人離れした英語」という言葉が聞こえてきそうです。